キャプテンの2度目の夏
連載『そんなこと言うんだ』は、日常の中でふと耳にした言葉を毎回1つ取り上げて、その言葉を聞き流せなかった理由を大切に考えていくエッセイです。#17では、自分の人生を、そして他者の人生を尊重することについて。

■ぼろぼろふわふわ
目が覚めると執刀医が第一声「あれ、足動くね」と呟いた。
なんとも呑気な調子で気が抜けた。何にせよその言葉で、どうやら下半身不随の予定だったこと、それをぎりぎり回避したことを同時に知った。
その診断を受けて、右足全体を覆うギプスの隙間からわずかに見えている薬指が、どうにか自分の意思で動かせることを確認した。こんな状態を「動く」と言っていいのか気が引けるけれど、少なくとも足を動かす神経は死んでいないようだった。とはいえ体中あちこち管を繋がれギプスで固められボルトで留められて、それでどうにか命をこの世に縛りつけているような有様。自力で息すらできない、笑っちゃうくらいの重症だ。
20歳の誕生日を迎えた週の終わり、ふっと大怪我をした。
全身の骨がずいぶんまんべんなく折れた。本当に突然だった。事態を飲み込めないまま麻酔漬けの生活が始まり意識も朦朧として、閉塞的な救命病棟には感情に起伏を起こすような刺激もない。
だから体中ぼろぼろで常に痛みや出血にさいなまれながらも、不思議と心はずっとふわふわしていた。
このあと1年近く続いた入院生活は、あまりにも突然で、非現実的で、どこか他人事で、長い長い放心状態のような時間だった。
■よぼよぼきらきら
ぼろぼろの体にふわふわした頭で半年間過ごしていると、どうにか骨が繋がってきた。
となると、また座ったり立ったり歩いたりするためのリハビリが始まるので、救命救急センターからリバビリを専門におこなう病院へ引っ越しすることになった。
転院先に到着すると、わざわざ出迎えに来た院長は
「うちの病院始まって以来、たぶん初めての40代以下の入院患者だ」
となんだか浮き足立った様子で言った。
この病院の入院患者の平均年齢は70代、ほとんどが認知症かつ車椅子で、コミュニケーションの難しい人が大半を占めているそうだった。看護師たちも口々にはばからず「うちは会話の成り立つ患者さんがまずいないから」とカラッと言ってのけながら、レアキャラの「会話ができる患者」に連日うれしそうに話しかけにきた。
代わる代わる病室へ迎えに来る看護師に車椅子を押されて、リハビリ室に毎日通った。松葉杖をついて歩く訓練から始めて、慣れてきたらエアロバイクで筋力を取り戻して、徐々に杖無しで歩く訓練に切り替えていく。担当の理学療法士が立てた計画を一歩一歩進めていった。
リハビリ室の光景は、若さを自覚すらしていないほど若かった当時の自分には衝撃だった。「よぼよぼ」というのは擬態語だと思っていたけれど、そういう音がはっきり聞こえる気がするほどに、みんながみんな本当に本当によぼよぼだった。リハビリをまともにこなせている人がほとんどいない。
同室の金子さんは院内で2番目に若い50代で、でもすでに認知症で意思疎通が難しい。マットの上で寝返りの練習をしている途中、疲れてそのまま眠ってしまう。
また別の人は、脳の活性化のために指を規則正しく動かす訓練を毎日一生懸命やっているけれど、何分かおきに自分が何をしている誰なのかわからなくなって首を傾げている。
その隣には、誰もいない空中に向かって楽しげに話しかけている人がいる。しばらく「いない人」との会話を続けた末、驚いて腰を抜かして立てなくなっていた。「いない人」に何を言われたんだろう。
そこから少し離れたところには、足腰のリハビリのためにスクワットに励む別の老人がいる。自分を鼓舞するように、天に向かって何かを叫び続けている。スクワットといっても膝を5°ほど曲げては伸ばす程度の運動で、それでもきつそうに全身を震わせ、歯を食いしばって全身全霊で挑んでいる。
この老人たちが5年も前にはそれぞれの勤め先でそれなりに偉い人だったんだと思うと混乱した。
リハビリ室で老人たちは毎朝必ず、看護師の歌う「きらきら星」に合わせて体操をする。まるで幼稚園のお遊戯会だ。
かつての地位も威厳も関係ない。生きることに精一杯の弱々しい体を童謡に合わせて真剣に曲げ伸ばしする。
最初の頃は選曲からしていくらなんでも失礼なんじゃないかと思ったし、不気味さも感じた。けれど、老いが一周して幼児退行している人も多くて、慣れてくると自分自身が老人たちを赤ちゃんのように感じてしまう瞬間が多々あった。どう接するべきだったのかは今でもよくわからない。
こんな調子で、風邪を引いた日の夢みたいにちぐはぐで現実味のない日常風景の中で、若い盛りの時期を過ごした。
■虎と目が合って気づいたこと
時間が経過するにつれ、老人たちと赤ちゃんとの決定的な違いに気づきはじめる。赤ちゃんはどんどん成長するが、老人はそうはいかないということ。
自分は若さもあってか猛スピードで回復していった。心はいまだここにあらずな状態でありながら、体がこんなにも生きたがっているのがなんだか恥ずかしく思えた。まだ外の世界で生活を再スタートしていく心の準備がまったくできていないのに、体はてきぱきと傷を塞ぎ、骨を繋げて、筋肉を取り戻し血をつくる。
ただ、他の入院患者は違う。あの人は今日も天に向かって何かを叫びながら、スクワットとは呼びにくいあの膝の微細な曲げ伸ばしを続けている。
エアロバイクを漕ぎながら、おじいちゃんおばあちゃんたちはだいたい何カ月くらいで退院するんですか、と担当の理学療法士に訊ねると、
「いや、他の人たちは基本ずっとうちにいるよ」
と答えたあと、訂正するように続ける。
「ずっとではないけど。そんなに長くいられるわけでも、っていうか、まあ、うん」
言葉を濁したのを聞いてようやく理解した。ああ、あの人たちの大半は、ここで天寿を全うするのか!
老いというものが改めて怖くなった。それでも、ぼろぼろとはいえ20歳の体の持ち主にはまだまだ他人事だった。なんとか老人たちの立場をシミュレーションしようと考えを巡らせていると、傍らで金子さんがリハビリ台から転落しかけているのが目に入った。あっと声が出て冷や汗をかいたけれど、理学療法士が間一髪でTシャツの裾を掴んで、金子さんをフローリングに軟着陸させた。
「この仕事してると、こんなことはよくあるからね」
と理学療法士が頼もしい調子で言った。言いながら金子さんをリハビリ台に引き上げる。ほっとして金子さんに目をやると、めくれ上がった裾の下にいた虎と目が合った。虎?
それは背中一面に彫られた立派な虎の刺青で、前足の先端はおむつで隠れて見えなかった。虎の刺青とおむつが同居する金子さんの後ろ姿は、それそのものが詩として機能するような鮮烈なコントラストだった。
顔を青くして虎から目を背けると、目を背けた先で理学療法士と目が合った。
「そうなのよ、金子さんはねえ、元そっちの人」
説明してくれた。そして、「そっち」だけでは伝わらないかもと思ったのか、一拍遅れて頬のあたりの空気を人差し指で引っ掻くジェスチャーを添えた。
「そっちの人」を目の前にしてそんなジェスチャーをしたらたぶん半殺しにされるだろう。でも今の金子さんにその体力と気力はない。金子さんは相変わらず虚ろな目をしてまどろんでいる。
一部始終を受けて、世界がひっくり返るような感覚に陥った。
あの弱々しい、一人ではとても生きていけない赤ちゃんみたいな金子さんは、元々「そっちの人」だった。「そっち」のことはよくわからないけれど、金子さんもカチコミとかシノギとかドスとかチャカとか、そういう日常を過ごした末にここへ来たのだ。
そのとき初めて、自分がさも老人たちを生まれたときからずっと今みたいな状態だったように扱っていたことに気づいた。ものすごく一面的な見方をしていた。
彼らそれぞれの、この病院へ来るまでの人生のドラマをまったく見ようとしていなかった。なんだかいやな感じだ。ぼんやり過ごしている中で、当たり前のことに目がいっていなかった。自分の態度が傲慢に思えた。

■彼はキャプテン
そう思うようになってからは、これまで見えていなかったものに目を凝らして、聞こえていなかったものに耳を澄ますようになった。たとえばエアロバイクを漕いでいる間中BGMのように聞こえていた、あのスクワット老人が天に向かって叫んでいる言葉だ。
これまで彼が叫んでいる「何か」が何なのか考える発想すらなく、理解を放棄していた。
改めて聞き耳を立ててみると、少なくとも叫び声には規則性があった。1つの言葉をずっと繰り返し叫んでいる。
「あの人、なんて言ってるんでしょうね」
理学療法士に話を振ってみると、
「キャプテンのこと?」
と返事がきた。
「え、そんなあだ名だったんですかあの人」
「僕らはみんなキャプテンって呼んでるよ。あの人は高校時代に野球の名門校のキャプテンだったんだって。で今、彼はその頃に意識が退行して、自分のことを高校球児だと思ってるわけ」
それを聞いてハッとして、彼がなんと言っているのか突然はっきりわかった。
実家の近所をランニングしていた野球部が叫んでいた言葉と一緒だ!
「もうそろそろ人生が終わるってタイミングで、あのおじいちゃんはまたキャプテンでいたかったんだよね。だから僕たち職員はキャプテンって呼んであげなきゃ」
認知症老人をケアする仕事に従事する者としての矜持を示すように、噛み締めながら言った。かっこいいなと思った。理学療法士たちは、彼をキャプテンと呼ぶことによって彼をまたキャプテンに任命している。
自分にもキャプテンみたいに戻っていける黄金時代があるだろうか、と考えた。
高校時代は本当に楽しかったけれど、キャプテンみたいに友達と一緒に共通の目標へ向かっていくような、何か成し遂げたと胸を張れることがない。
退院してからそういう時間を作るしかないな、と思ったら、ずっとふわふわしていた心がようやく地に足ついて歩きはじめた。
もうキャプテンの声ははっきりと聞き取れた。
彼は人生の最終幕を迎えてまた、一番輝いていた18歳の夏の熱狂の中にいる。あの夏に一番多く声に出したであろう言葉をまた彼は叫んでいる。
「帝京ファイト!」










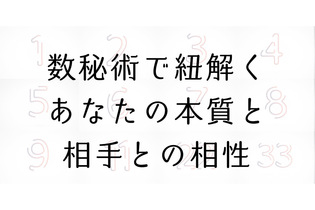










ライター/編集者