人生で一番ウケた日、爆弾が落っこちる時
連載『そんなこと言うんだ』は、日常の中でふと耳にした言葉を毎回1つ取り上げて、その言葉を聞き流せなかった理由を大切に考えていくエッセイです。#8では、誰かの心に一生消えない傷をつけてしまうことについて、筆者自身が口にした言葉から考えていきます。

■ボンボンライオット
都内の中高一貫の私立校に通っていた。
都内と言っても東京の外れの寂れた駅からバスで30分以上走った辺鄙なところ。
世はゆとり教育まっただ中で、公立校は週休2日だったけれど、あの学校は土曜日も毎週授業があった。反比例して部活動は圧縮され、運動部でも週2〜3日。教員は狂気じみた情熱で途方もなく無意味な校則を強いる憲兵だった。男子は髪が耳に触れる長さになってはいけなかったし、女子はキャミソールの色を指定されていた。おぞましい。
裕福な家庭でスポイルされて育ったボンボンどもがこんな抑圧的な環境に放り込まれると、当然ストレスでどうにかなってしまう。日々溜まり続けるフラストレーションは爆発する場所を求めて血走っていた。ぶちまけられるならどこでもいい。
そのしわ寄せのいった先が、中学1年の頃の地理の授業だった。わかりやすく学級崩壊していた。
■人間が仲良く暮らす方法
その授業を受け持っていた新任の教員はひょろっと細長くて、いつ見てもおどおどした表情。声もか細くまるで覇気がない。そんな彼をクラスの全生徒が着任早々になめくさった。本当に早々に、初日から。全力で、それも全スクールカーストが、階級や民族の違いを問わずクラス一丸となって彼をなめくさった。人間は人間扱いしなくていい人間を、共用のサンドバッグを見つけると、みんな仲良く暮らせるのだ。最低だ。
今思えば、あの大騒ぎはある種の狂気を孕んでいたように思う。あの閉鎖的な環境で滞留した行き場のないエネルギーを、この50分で! 出しきらないと!おれたちどうにかなってしまう! そういう悲痛さがあった。だから許されるべきというのではなく、環境が悪魔を生む仕組みはごく日常的なところに存在するという話だ。
そんな生徒たちを前に、彼も最初の頃はか細い声で「静かに」と窘めの言葉を口にしたけれど、騒ぎが常態化してからは「こういうもんなんだろう」と思ってしまったのか、一切注意せず、まるで生徒が誰一人として机の上に乗って大声で喚いてなんかいないみたいに"普通に"授業をするようになった。授業内容はほとんど聞き取れなかった。
彼が不憫でならなかった。甘やかされてきたであろうモラルのないボンボンどもに、教員としての最低限の尊厳すら認められていない。あまりにも不憫だ。
ただ筆者はそれ以上に怒りを覚えていた。
何をお前慣れてるんだ。仕事をしろ。何かしら理想の教員像を持ってこの業界に来たんだろう。それがどんなものか検討もつかないし興味もないけれど、今のこの姿が彼の理想にかすってもいないことは間違いない。何もしないことにしてる場合じゃないだろう。もちろん罰されるべきは大騒ぎしている生徒たちなのだけれど、この状況に大人として責任を負えるのは彼しかいない。
この底辺の教室にも騒ぎに加担したくない生徒はわずかにいて、筆者もそのうちの1人だった。単純にまともに授業が受けられないと困るし、こうやってサンドバッグを殴ることでいい気になってる同級生たちが見るに耐えなかった。だからこの授業中は校舎を抜け出していることが多くなった。
通っていた学校に”ヤンキーとかではないんだけどなんかちょくちょく教員と揉める奴”がいなかっただろうか。筆者もそれだった。生まれてこのかたただの一度も教員に気を許したことがない。毎日まじめに授業を受けてはいるけれど、教員への不満が閾値に達すると授業中に出ていったり、1時間教員を睨み続けて呼び出されたり、逆に教員を呼び出したり、筆者は筆者で存分にライオットしていた。
そういったこともあって、あの新任教員に同情する気にはとてもならなかった。
今思えば教員を嫌いすぎというより、教員に期待しすぎだったのかもしれない。教員全員何かしらの理由で絶対に許せなかった。そんな感じだったので、彼のことも相当軽蔑していた。授業中目が合うと申し訳なさそうに会釈するのにまた一層腹が立った。今思えば、あの会釈はSOSだったのかもしれない。
■爆弾が落っこちる時
そんなある日、彼は前触れなく弾けた。
「クソガキども、いい加減にしろ」
後ろに”!”をいくつ付けても足りない怒号だった。それも、大声を出して萎縮させて従わせようとかそういう戦略で発されたものではない。怒鳴った後の生徒との関係修復には一切意識がいっていない。純粋に怒りが爆発したのだ。人が臨界点に達するところを初めて見てしまった。
彼自身も今日こうなるとは思っていなかっただろう。予期せず今、限界が来てしまった。ぷつんと糸が切れて、ちょっと後戻りできない類の声色と形相になってしまっている。もう彼がこのあと何をしでかしても不思議ではない。あの覇気のない彼が、背筋の凍るような狂気の表情で教室をゆっくりと見渡して、一人ひとりの顔を順に眺めていく。まずい。
教室は水を打ったように静まり返った。全員の顔に「ああ、とんでもないことをしてしまった」と恐怖が浮かんでいた。子供ながら、人生をなめくさったクソガキながら、ようやく自分たちのしてきたことの愚かさを理解できたようだった。
調子に乗りすぎたのだ。怒らせてはいけない人を怒らせてしまった。彼は怒り慣れていない。今アンガーマネジメントがまったくできていない。何をするかわからない緊張感があった。下手をしたらどんな凶行に走るかわからない。そのことは何より、彼に散々ひどい仕打ちをしてきたクソガキども自身がいちばんよくわかってる。
そんな中筆者は心の底から感動して鳥肌が立っていた。目の前の光景があんまり美しくて笑みが溢れていた。
あの彼が、あのにっちもさっちもいかない彼が、ようやく怒っていいんだと自分を許せた! 自分が今後ようやくちゃんとした学習環境を手に入れられることもうれしかったが、それが二の次になるほど、彼への祝福の気持ちでいっぱいだった。今日から彼は変わるのだ!
今日から彼は、毎週決まった時間に絶望しなくて済む。彼が壊れてしまう前に、自分自身で現状を打破できた。ここからだ。ここからあんたは教師になるんだ。今日が教師としてのあんたの1日目だ。随分上からものを言うようだがなんのことはない、筆者もれっきとしたクソガキの1人なのだ。なんにせよ、彼のこれからを思うと胸がいっぱいになった。そして気持ちは思わず口に出た。考えてることをそのまま言ってしまうときってあるでしょう、それがこのときだった。教室は静まり返っていたので、筆者の言葉は全員の耳へ鮮明に行き届いた。
「成長したな……」
教室内の全生徒に死ぬほどウケた。
■「成長したな」
今回のテーマである忘れられない言葉がこの「成長したな」だ。
普段から冗談ばかり言ってる。それなりに試行錯誤を重ねてやってきた。でもあの瞬間ほどウケたことはその後10年以上生きてきてまだ一度もない。
緊張が高まりきったところにあまりにも素っ頓狂な言葉が飛び込んできて、一気に場が弛緩した。しかもその言葉は底意地の悪いニュアンスに変換されて認識され、サンドバックから突然の反撃を受けたクソガキたちの溜飲を下げ、ツボにドハマりしたのだった。
空間にいる(自分と教員以外の)全員が自分の言葉で発狂するほど笑い転げてる様は気が変になるほどの快感で、足元がぐらつくような多幸感の中、脳内麻薬ってこれのことか! と”理解”した。今でもはっきりと体が覚えてる。
もしもこれがウケを狙って狙い通りにウケた笑いだったら、間違いなくその後お笑い芸人を目指していたと断言できる。それほどまでに強烈な手応えが全身を満たした。
でもあの一言は決してウケ狙いではなかった。口にするつもりもなかった。感動のあまり口をついて出てしまっただけだ。こういうことが、感動で節度のコントロールがバカになることが間々ある。やってしまった。
でも、意図なく出たあの言葉が最上級のボケに化けたことは、口に出た瞬間に自分でもわかった。だからこそ、なんて取り返しのつかないことを言ってしまったんだ。
筆者の一言を受けて、教室内は残酷なほどあっさりとまたさっきまでの騒がしさに逆戻りした。台無しだ。クラスの誰より静かになった教室を祝福していたのに。
あの怒号を機にようやく彼の教師人生が始まるはずだった。それをこんなクソしょうもないクソガキその1に台無しにされてしまった。
教壇の上に呆然と浮かぶ顔は見られなかった。彼は筆者を殺したいほど憎かったはずだから。

■殺されてもしょうがない憎悪を植え付けながら
今回初めて、この連載で自分の言葉を取り上げた。これまでに野外フェスでたまたま見かけたある母親の宣言、サイゼリヤで出会ったギャルの謝罪、サークルの友達の何気ない一言、ある俳優の好きなタイプなどをテーマに文章を書いてきたけれど、そろそろ自分の言葉も、と考えたときに、まず最初にこの一言を避けて通るのは嘘になると思った。
筆者はこの一言を通して、1人の人間の脳におそらく一生消えない憎悪の種を植えつけたはずだ。今、自分のしてしまったことを客観的に見て、極めて冷静に「殺されてもしょうがない」と思ってしまった。
あの一件以降の彼の授業がどんなふうだったかは、本当にごっそり記憶が抜け落ちていて思い出せない。おそらく逆戻りしっぱなしで、悲惨なまま続いていっただろう。あの件の翌年、彼が我々の学年を受け持たなかったことは、彼にとって僥倖だっただろうし、筆者としても負い目から幾分遠ざかれて好都合だったのだと思う。
そしてさらに数年して、あの教員はキャリアを積んで担任のクラスを持てるようになり、休み時間にはおとなしめのグループの子たちが群がって話しかけにくるような人気者になった。その様子を教室移動の際に見かけるのが、筆者にとって何よりの救いだった。そうでなかったら、あの「成長したな」のときに彼が折れてしまっていたら、筆者は今以上にあのことに苛まれていただろう。
そして今書いていて気づいたけれど、”折れてしまっていたら”なんて随分他人事じゃないか。違う、”折ってしまっていたら”だ。筆者がとどめを刺していた可能性は十分にあったのだ。
そしてきっとこれ以外にも、誰かに一生残る傷をつけている。今生きているのはたまたまだ。相手も、筆者も、今これを読んでいるあなたも、もしかしたら。
このことを文章にすることで懺悔をしたいわけじゃない。ただ、こういうことをなるべく少なくしていきたい。










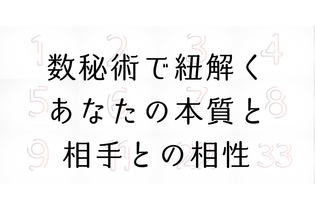










ライター/編集者