「野球強いから」あの子の志望校
『そんなこと言うんだ』は、日常の中でふと耳にした言葉を1つ取り上げて、その言葉を聞き流せなかった理由を大切に考えていくエッセイです。#14では、小学生の頃、同じ塾に通っていた友人の言葉にどう返すことが正解だったのか、大人になった今考えてみます。なお、本稿に登場する人物の名前は仮名です。

■西暦2000年、東京の外れ、快晴
シルクロードの時代、この街はそのシルクロードを渡る絹織物の生産で栄えていたらしい。
街の経済を支えた養蚕家も、今となっては去年の社会科見学でお邪魔したお宅を含めて2軒だけ。僕が大人になる頃、2010年か2020年くらいにはもう1軒もなくなっているだろう。
今のここは、特に都会でも別に田舎でもないただの街だ。
こんな街でも駅の北口側にだけはそこそこ高いビルが立ち並んでいて、駅前ロータリーにかぶさる歩道橋からそれぞれのビルへ渡っていける。塾のある方へ下りていく、その道すがら顔を上げると、視線の先にはこんな街のくせに生意気にも大型ヴィジョンがある。
大型ヴィジョンといっても渋谷の交差点にあるような華やかな映像は一切映らない。流れる映像の種類はだいたい3種類だけだ。
こんな街でも一応東京なんだと自分を奮い立たせるような執拗さで東京の天気予報を流し、今週のヒットチャートの第10位から第1位までを何周も何周も流し、そしてふっと、「いい話」の映像が流れる。
家族のありがたみとか、思いやりの大切さとか、そういうことにはたと気づかせるような短い「いい話」の映像だ。不意打ちのように始まって、これは保険会社なのか電力会社なのか、なんのCMだろうと眺めていると、最後の最後によく知った新興宗教の名前が画面に浮かび上がる。ああなんだ、またあそこのCMか。
この街で強い地盤を持つ新興宗教だ。
クラスにもあそこの宗教のおうちの子が何人かいる。
たぶん僕みたいな子供でもみんな、なんとなく誰と誰と誰のおうちが”そう”だ、ということは把握している。その上で親から「あの子にそういう話をふっかけてはいけない」と言いつけられている子も多いだろう。そうでなくとも暗黙の了解で、わざわざその話題に触れることは子供だってしない。この街で生まれ育つということはそういうことだから。
■独身貴族と特別な子供たち
塾は好きだ。学校以外にも友達がいるのがうれしい。
それに、学校の教員は全員嫌いだけど、塾の先生たちはみんな好きだ。
職員室には先生たちがクレーンゲームで獲ってきたぬいぐるみ、大人買いした食玩のフィギュア、ペプシコーラのボトルキャップが並べてある。
大人のことはよくわからないけれど、先生たち本人がよく「ここじゃないと働けないようなダメ人間ばっかり」だと口々に言っている。お迎えに来た友達のお母さんは「ここの塾の先生は独身貴族の集まりだね」と言っていた。その言葉はなんだか特別な称号のように思える。
確かに先生たちは他の大人とはちょっと違う。きっと大人としてちゃんとしてない人たちなんだけど、みんなそれなりに頭がよくて、それなりにお金に余裕があって、夕方スタートの仕事だってことにかこつけて毎晩夜ふかしして趣味を楽しんで、休み時間には僕ら生徒と自前のゲームボーイを繋いで通信対戦する。大人げなく本気で勝ちにくる。
でも対等なのがうれしい。ここに通う子供はみんなそういう、半分大人の仲間入りをさせてもらえているような優越感があって、自分を特別な子供だと思っていると思う。僕も和樹もその1人だ。
■あの子の志望校
同じ塾に通う和樹は、僕にとって一番長い付き合いの友達だ。
親の仕事と人格の都合で引っ越しが多くて、僕は今の小学校に転校する前に学区が1つ隣の小学校に通っていた。駅の北口から南口、徒歩20分の至近距離の引っ越しだけど、通う学校は変えなければならなかった。
前の小学校で同じクラスになったのが和樹との出会いだ。そして初登校の日の放課後、初めて行った塾にも和樹がいた。この塾には今の学校に転校した後も通い続けているから、引っ越す前も後もずっと毎週3回塾で顔を合わせている。
和樹は人見知りだけど仲良くなるとずっとふざけて絡んできて、いつだってニコニコしている奴だ。病弱で頻繁に授業を休むくせに、塾に来られる日はいつも教室を走り回る。
2年生のときに出会った和樹と毎週3回顔を合わせる日々が3年続いて、僕たちは今5年生になった。高学年にもなると、塾の先生たちはもうほとんど大人と話すときと変わらない態度で僕たちに接してくるようになる。その他にも、声変わりの時期に差し掛かって声が出にくくなったりといった体の変化もあって、大人になるための準備期間に入ったのだ、ということを生活のいろんな場面で感じている。決定的だったのは、先週塾で配られた志望校調査票だ。
そうだ、漠然と中学受験コースに通っていたけれど、自分はクラスで1人だけ違う中学に行くのだ。いよいよ初めての人生の岐路、受験が現実味を帯びはじめてきた。

そして今日。志望校調査票の提出日だ。先週いっぱい各自親と話し合って志望校を決めることになっていた。
僕には元々特に行きたい学校はない。受験をさせたい親のエゴに付き合って、及第点以上の偏差値の中学に入るのが自分の役目だというだけだった。だからそういう学校を3つ見繕って書き込んだ。
他の子供もそんなもんだろうと、雑談中なんの気なしに和樹に「そういえば志望校どこにした?」と聞く。すると和樹はぴたりとニコニコを止めた。黙って調査票を取り出して、こちらに見えるように傾ける。
和樹の第一志望の中学校は、あの大型ヴィジョンの新興宗教が経営する中高一貫校だった。
そこで思い出した。そうだ、和樹も”あそこの子”だった。
油断した。忘れていた。この街で生きていく上で踏まないようにしなきゃいけないところをなんの心の準備もせず踏み抜いた。
この話を早く通り過ぎよう。どう反応したものか頭をフル回転させている途中、不用意な言葉が自分の口から聞こえた。「そこにしたんだね」。間が持てなくなって無意識に出た言葉だった。なんだか自分の声じゃないみたいだったのは、声変わりの過程の時期だからだろうか。
「そこにしたんだね」。まずい。含みがありそうな言い方になってしまった。
和樹に「お前って”あの”家の子だもんな」というニュアンスで伝わってしまってはいけない。でも、”あそこの子”は敏感に感じ取る。その件について触れるようなニュアンスがあればすぐに防御を堅める。でも、すすんで触れられたくないのは当然だ。
”あそこの子”が事故的にその件について触れられてしまう現場に出くわしたことが何度かあるけれど、いつだってとんでもない空気になった。
自分が慣れ親しんだものが世間では一般的なものじゃないと理解したときの顔、あるいは世間からの印象を知っていて極力触れられないようにしてきたことをおおっぴらに暴露されたときの顔、あるいは自分がずっと違和感を抱えてきたものが世間でどう受け止められているかを知って辻褄が合ったときの顔、その他それぞれに置かれた環境は少しずつ違うだろうけれど、どの表情も思い出すたび冷や汗をかく。
だからこそ、和樹にとって波風を立てない存在でいたかったのに。
少しの沈黙の後、僕の不躾な言葉に、和樹はこう返答した。
「うん、野球強いからさ」
■「野球強いからさ」
今回取り上げる忘れられない一言が、この「野球強いからさ」だ。この言葉を聞いて、何も返答できなかった。大人になった今もまだ、何が最適解かわからないままだ。
あんな悲しい苦しい言い訳を10歳の子供にさせている環境を思うと胸が潰れそうになる。
確かにその学校は野球が強い。高等部の野球部は何年かおきに甲子園へ行っていたと思う。
ただ、和樹は野球をやっていない。お父さんがプロ野球好きで、一緒に中継を観ることはあると言っていたけれど、和樹本人が特別野球好きなわけではなかった。そもそも持病があるので激しい運動はできない。
それに、成績の面でも和樹では到底受からない偏差値の学校で、レベルも合っていなかった。勝手な推測を並べ立てるのは大概にしておきたいけれど、親の意向でその学校を勧められたんだろうということは子供の自分にも想像ができた。そういう子はあの街にたくさんいた。
自分の意思で学校を選んでいない受験生はたくさんいるだろう。筆者だってそうだった。だからこそ和樹が置かれた状況はいたたまれなかったし、和樹の場合、滑り止めの学校に受かってもなんの意味もない。落ちたら何を思うんだろう。自分だったらきっと、親に対して申し訳ない気持ちでいっぱいになる。そんなふうに感じるいわれはないはずなのに。
先生たちは雑談中ふいに和樹の志望校を知ると、まるで大人みたいに神妙な顔つきで「和樹の成績だとまだ難しいから、これからがんばらなきゃね」といった大人のコメントをしていた。あの先生たちが、大人ぶって、大人みたいな距離をとって。
それが正解なのか? それが大人なのか? こんなときこそいつもの子供みたいな振る舞いで踏み込んで、寄り添うこともできたんじゃないか?
でも、あのときあの場に自分が大人としていたら何が言えたかと考えると、やっぱりこれといって思い浮かばない。
当時いっちょまえに大人への階段を登りはじめた気になっていた子供にとって、あの事件は大きなショックだった。なんだよ、ぜんぜんうまく立ち回れてないじゃないか。自分は悲しいくらいに子供で、大人だって何かできるわけでもなかった。
■あの子たちのこと
「新興宗教二世」という言葉を知ったのは大人になってからで、日常のふとした瞬間に思い出すたび、とりとめもなく文献を読み漁っている。
あのとき何か、何かは言いたかった。
「そんなこと言わなくていいんだよ」
と言えたら、言った上でその先のサポートができたらどんなによかっただろう。
でも子供には到底無理な話だし、そこまで踏み込むべきかもわからない。
これまでに何人かの二世と出会った。
出会うと必ずこのときの話をする。そして少しずつ、当事者として思うことを聞かせてもらっている。
話を聞くにつけ思うのが、教団自体の是非とはまた別の「自分の意志で選択できなかった」ということのアンフェアさだ。
あの”志望理由”を聞いたとき以外にも、教団の話題に触れそうになるとき、和樹はいつも消え入りそうな顔で言葉を濁した。
教団にどれくらい、どんな帰属意識があるのか、もしくはないのか。わからないけれど、少なくとも当時は胸を張って誰にでも言えることではないと思っていて、おそらく教団に対する態度を決めかねているところのように見えた(重ね重ねになるが、勝手な推測であることは重々承知の上だ)。
先生たちの反応は、あの一時においては正解だったのかもしれない。和樹を気まずい空気から逃がしてやるためにそれ以上踏み込まない。和樹自身それを望んでいたかもしれないが、根本的なところで和樹が報われるには、また違う言葉や行動が必要だったように思う。
相手は新興宗教二世に限らず、こういうふうに差し出せなかった手がたくさん、たくさんある。
あれが転んでできた痣だったと今でも本気で思う?
あのときの「大丈夫」は本当に「大丈夫」だったか?
あそこで追いかけなかったのは何を守りたかったから?
何人かとのいくつかの場面を思い出す。
定期的に思い出して忘れずにいることを誠実さだと感じているのだとしたら、あまり健康的じゃない気もする。










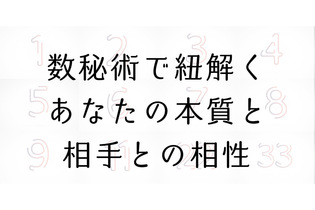










ライター/編集者