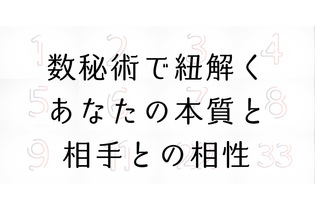「もちろん、ある男と女とが、愛し合うまでには、双方ともある程度まで理解しあうのが普通でしょうが、愛しあい信じあうと同時に、二人の人間が、どこまでも同化して、一つの生活を営もうと努力するのが、現在の普通の状態のように思います。
私は、こんなものが真の恋愛だと信ずることはできません。こんな恋愛に破滅がくるのは少しも不思議なことではないと思います」
『定本 伊藤野枝全集』第三巻「自由母権の方へ」伊藤野枝著,171頁
私も、あなたも、わがままでいい。伊藤野枝が求めた自由 3/3
■どうしたって、人はひとつになれないのだから
恋愛については以下のように述べている。
好きな人と親密になったり、体を重ね合わせたりすれば、まるで心身が同化していくような、甘い感覚を覚えることもある。結婚すれば、男性が女性を所有するような感覚を覚えることもあるだろう。でも、本来、人は一人ひとり違うのだ。交際の約束をしても、結婚したとしても、好きな人は自分のものにはならないし、思い通りにはならない。
私は彼女のこの考え方が好きだ。約100年の月日が経ち、男女の権利差は小さくなってはいるけれど、私は「俺の女」と言われるのは好きではないし、恋人を「私の男」と言う気もない。どんなに好きな人でも、恋人でも、配偶者でも、子どもでも、それぞれに人格があり、自由に変わりゆく意思がある。これが個人の自由を保障する考え方であり、多様性の礎なのだと思う。
■子育ては迷惑をかけるものだ
伊藤野枝は大杉と暮らすようになった1916年から1923年までの7年間に、子どもを5人出産する。その前に辻との子をふたり産んでいるので、合計7人の子どもがいた。18歳から28歳までの10年間、ずっと妊娠・出産・育児をしていたと言っていいだろう。その間に恋愛をしたり、小説やエッセイを書いたり、『青鞜』の編集長を務めたり、社会運動をしたり……。信じられないくらい情熱的でパワフルだ。
彼女がわがままだったから可能だったとも言えるし、この状況ではわがままにならざるをえなかったとも言えるだろう。育児もけっこう適当だったようだ。赤ちゃんを職場に連れて行き、みんなに子守をしてもらい、ウンチをしたら青鞜社の庭に投げる(臭いので他の人が掃除をしていた)。布おむつも面倒なのであまり洗わない(子が可哀想なので大杉や同居人が洗っていたようだ)。
ずぼらな私は、おお、こういう感じでも何とかなるのか、とこっそり勇気をもらってしまう。「子どもを産んだら自己責任で、他人に迷惑をかけずに育てなくてはいけない。それができないなら産んではいけない」という声も散見されるが、私はもっと適当でいいし、多少の迷惑は仕方がないように思う(もちろんウンチはゴミとして捨てた方がいいし、今なら紙おむつを選べばいいだろうが)。もっと縛りの少ない、助け合える世の中になるといいのにな。
■いつ死んでも幸福だったと思ってくれ
1923年9月1日、関東大震災が起きる。この混乱の中で朝鮮半島にルーツを持つ人々が大量に虐殺された話は有名だが、もうひとつ事件があった。9月16日、甘粕正彦大尉の率いる憲兵隊に、無政府主義者として運動を展開していた大杉栄(38歳)、伊藤野枝(28歳)、大杉の甥・宗一(6歳)が虐殺された事件(甘粕事件)である。野枝は男の子を出産して約1カ月後だった。
こうして彼女は28年間の生涯を、国家権力に首を締められて終えることになる。野枝の妹は、号外で報道される前にこの事実を知ったが、
「ああ、やっぱりかと思っただけで、それほどびっくりしもせず、急には悲しくもならなかったものです。家の両親たちもそうだったといっていました」
『美は乱調にあり』瀬戸内寂聴著,岩波現代文庫,2017年,46頁
と語っている。それは彼女がよくこのように語っていたからだという。
「どうせ、あたしたちは畳の上でまともな死に方なんてしやしない。きっと思いがけない殺され方をするだろう。その時になっても、決してあわてたり悲しんだりしてくれないように。あたしたちはいつだって好きなことを信じてやって死んでいったんだから、本人は幸福だったと思ってくれ」
『美は乱調にあり』瀬戸内寂聴著,岩波現代文庫,2017年,46頁
どんな主義主張があったにせよ、若者にこんな覚悟をさせなくてはいけない社会がおかしかったと思うので、単に美談にする気はない。ただ、これを読んでからというもの、彼女のこの言葉、「いつだって好きなことを信じてやって死んでいったんだから、本人は幸福だったと思ってくれ」を言えるかどうか、ということは私の人生の道しるべとなっている。
人生は選択の積み重ねだ。迷ったとき、誰かの決めたルールや道徳、倫理、モデルコース、そういうものに従えば、ひとまずは褒めてもらえるかもしれない。それが楽ならそれでもいいだろう。でも、自分の欲望以外のものに選択を委ねると、後悔が発生しかねない。あのときああすれば、こうすれば……。私はそれがイヤなのだ。
いつだって、自分の好きなことを信じて選択していれば、あとでマズいことになっても、誰かに怒られても、最悪の場合に死んだとしても、「あのときに自分が最高だと思って決めたんだから、仕方ないな」と思えるだろう。
伊藤野枝が生きた時代とはずいぶん違うけれど、今でもさまざまな道徳や倫理があるし、隙あらばそれらを振りかざし、人の選択や恋愛、セックスを勝手に裁こうとする人がいる。でも、誰かが勝手に決めた道徳が、倫理が、どれほどのものだろう。
それよりも今、自分が好きなことを信じて生きる。だから、いつ死んだとしても、私は幸福だったと思ってくれ。そう言えるように日々を過ごしていきたいな。私も、あなたも、もっと、わがままでいい。
Text/雨あがりの少女(@ameagari_girl)
Illust/野出木彩
参考文献
『美は乱調にあり』瀬戸内寂聴,岩波現代文庫,2017年
『村に火をつけ、白痴になれ』栗原康著,岩波書店,2016年
『『青鞜』女性解放論集』堀場清子編,岩波文庫,1991年