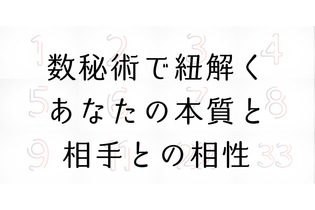『35歳――希望の在処』第五話
「希望は未来にしかない」のだと気づいた葉子は……。作家・南綾子さんが描く「35歳×離婚」をテーマにした全5回の短編小説、最終回です。

涼太は胡坐を組んだ足の上に右ひじをたてた姿勢のまま、石になったように固まった。
急に、鼓動がはやくなった。「うん、俺たち戻ろうか」と涼太が言ったら。今。もし。わたしはどうするだろう。今になって急にわからなくなった。わたしはそれを望んでいるのだろうか。
そのとき、隙をついたように、遥がパチンと音を立てて駒をおいた。
同時に、涼太が「うわー」と声をあげて頭をかかえた。「お前、いつそんな技を覚えた! ちょっと、それはマズい。時間がほしい。え? どうしよう待って」
「3分だけ待ってあげる」
「いや、明日の昼ぐらいまで待って。一晩考えたい」
一瞬の間をおいて、遥がウヒャヒャと大笑いしはじめた。「一晩って、長すぎ」などと言いながら、ラッコみたいに床にひっくり返っている。よほどツボにはまったらしい。葉子と涼太はあっけにとられ、思わず見つめ合った。
あれ、この人、こんな間の抜けた顔をしてたっけ、と思った。
と同時に、頭の中で何かがひらめくのを感じた。
そうか、この人は、何にも決められない人だったんだ。ずっと、昔からずっと、最初から。
たとえ遥が明日の昼まで待っても次の一手を決められないだろうし、29歳で結婚をせまらず、33歳まで待ったところで、やっぱり何も決められなかっただろう。決められないから流される。でもそんな自分が情けなくて嫌だから、全部わたしのせいにして安心しているだけなのだ。そういう、ずるい男。
「マンションの契約書に判子をついたのは、自分のくせに。わたしが無理やり押させたんじゃない」
葉子は無意識のうちに口に出していた。
涼太は驚いたように目を見開き、まったく知らない人を見るような顔になった。
涼太の姉が葉子に渡したいものは見合い写真だった。
「いい話よね? どう? 会ってみない?」
「やめときます」
葉子が即答すると、涼太の姉はあからさまに不機嫌そうな顔になった。
「この方、国立大卒の医者よ? バツイチでちょっと背が低いけど、いい人なんだから」
「今はゆっくりやりたいんです」
「ゆっくりって……もうアラフォーよ、あなた。ゆっくりとか言ってる場合じゃないし、高望みしている歳でもないのよ?」
そのとき、ソファに寝そべっていた遥が「あー!」と急に大きな声を出した。「やだやだ、マジで歳とりたくないっ」「やめなさい」と母親にたしなめられ、遥は口をとがらせた。寝不足のせいか少しむくんでいるその顔に視線を投げつつ、あの頃、自分も遥と同じような気持ちでいただろうかと葉子は考える。
あの頃。19歳。確かに若い若いとチヤホヤされた。けれど、このままでいたい、時間がとまってほしいなんて、考えたこともなかった。
なぜなら、やりたいことがありすぎるぐらいあったからだ。まず、お金をためて一人で海外旅行をしてみたかった。1カ月ぐらいの長い旅。パリやウイーンでおいしいお菓子をたらふく食べる旅。菓子メーカーに就職して商品開発をするのが何よりの夢だった。
未来に希望がたくさんあった。だから、歳をとるのが嫌だなんて少しも思わなかった。
それは今だって同じじゃないだろうか。歳をとりたくないと未来に背を向けるのは、希望を捨てることと同じことかもしれない。だって、希望は未来にしかないのだから。過去にあるのは思い出だけ。
いつからか、何歳までにこれをしてあれをして、と年齢のことばかり考えてしまうようになった。たくさんあったやりたいことも、もう遅い、と片付けてしまうようになった。
「もう、いきますね」
見合い写真を突き返し、葉子は1人で家を出た。
午後の空はやけに白かった。風が強い。隣の家の洗濯物が、今にもどこかに飛んでいきそうなぐらい大きくはためいている。
小走りで庭を駆け抜け、ぴょんとジャンプして道路に出た。結婚相談所の入会金にしようと思っていたお金で、海外旅行にいこう、と思いつく。はじめて、1人で。我ながらなかなかいいアイディアだ。素敵な出会いがあるかもしれないし。そうだ、35歳だから、誰からも愛されないなんて大間違いだ。わたしはなんてばかばかしいことを考えていたのだろう。
今のこの決意を忘れないようにしたい。葉子はスマホを出し、涼太につながる全ての情報をその場で消した。
(完)