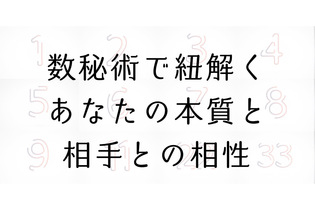『35歳――希望の在処』第一話
30歳になる直前、結婚の「け」の字も言わない恋人に「30歳で独身は絶対に嫌だから、結婚相談所に登録する」と宣言し、結婚にこぎつけた葉子。しかし、新婚生活半年で夫が家を出て、早5年。作家・南綾子さんが描く「35歳×離婚」をテーマにした短編小説を全5回でお届けします。

「長い間、お世話になりました」
目の前に、かわいらしくラッピングされた手作りのクッキーが差し出された。牧野葉子はデスクを片付ける手を止めて、顔をあげた。
「そっか。美由紀ちゃん、今日までだっけ」
「はいっ」と27歳の派遣社員は、輝くような笑顔で頷いた。比喩ではなく、本当に彼女の顔からは光が発せられていて、葉子はまぶしさに思わず目をそらした。
「葉子さんには、何から何まで相談にのってもらって、本当にありがとうございました」美由紀はまだ何もついていない左手の薬指を、無意識のしぐさで右手で触っている。
「葉子さんの言うとおりにして、本当に正解でした。あのまま待ってたら、30歳になっても何も起こらなかった気がします」
「おめでとう、末永くお幸せに」
美由紀は何度もこちらを振り返り、そのたびに小さく手を振りながら去っていった。
1人になったあと、葉子は心の中で繰り返す。
末永く、お幸せに。
「付き合って3年もたつのに、彼が結婚してくれないんです」
そう美由紀から相談を持ち掛けられたのは、ちょうど1年前の春、一緒に会社の近所にある讃岐うどん屋でランチをとっていたときのことだ。合コンで知り合った2歳上の彼氏は、広告代理店勤務の元ラガーマン。美由紀は出会ったときから結婚を意識していたのに、彼からは一向に、“あの言葉”が聞こえてこない。
友達や派遣仲間には、「まだ若いんだからそんなに焦る必要もないんじゃない?」「彼がプロポーズしたくなるまで待つべきだよ」などと言われるが、本当に待っているだけでいいのか、不安でたまらないのだという。
「どうしても彼と結婚したいなら、『結婚するか別れるか決めて』って言うべきだよ」
そんな美由紀に、葉子はきっぱりと断言した。
「3年付き合ってプロポーズしない彼氏は、5年後も10年後もしない。そういう彼氏に結婚を決意させるには、妊娠や別れなどの突発的なイベントが必要なんだよ」
続けて、葉子はそう主張した。
実際、自分が20代の頃に、女性の先輩社員から言われた言葉だった。
「わたしも同じようなことを言って、大学時代から付き合ってた夫に決意させたから」
それから半年後、美由紀は元ラガーマンの口から、「じゃあ、結婚しようか」という言葉を苦心の末、ひきだした。
葉子が結婚したのは、29歳と11カ月の、夏の終わりのことだった。
本当は、25〜26歳で結婚して、30歳になるまでに、子どもを2人産みたいと思っていた。東京の有名女子大を出て、大手菓子メーカーに就職。そこまでは完璧。あとは結婚して、若くて綺麗なワーキングマザーになること。学生の頃はいろいろとぼんやりした夢を抱いていたが、社会人になってからは、それだけが目標だった。
大学3年のときからの付き合いの、1つ年上の涼太とは、もともとはアメフト部の選手とマネージャーの関係だった。さわやかで、頼りがいがあって、みんなの憧れ。3年にわたる片思いの末、交際がはじまった。涼太の彼女でいられることが誇らしくてしかなかった。涼太は大学卒業後、父親と同じ消防士になった。
交際中、2人の間で、結婚について話し合ったことはほどんとない。が、真面目な彼のことだから、真剣に考えてくれているはずだと信じていた。きっと、2人が付き合い始めたクリスマスイブに、プロポーズしてくれるはず。そう期待していた。しかし、25歳のイブも26歳のイブも、27歳と28歳のイブも、何事もなく通りすぎた。
そして29歳のイブ、「仕事が忙しい」という理由で、会うことすら叶わなかった。
年が明け、最初のデートは、涼太の都合で1月下旬までずれこんだ。2人の行きつけのカフェで顔を合わせるなり、葉子は「30歳で独身は絶対に嫌だから、結婚相談所に登録する」と宣言した。
そのときの涼太の顔を、今でもはっきり覚えている。ほんの一瞬、まったく知らない人を見るような顔になった。
その次のデートで、涼太は新築マンションのパンフレットを持ってきた。それが、彼の答えなのだと思った。
そこからは、すべてが流れるように進んだ。翌月には両親に挨拶をすませた。涼太の父親の勧めもあり、すぐにマンションを買った。葉子はいらないといったのに、涼太は80万円の婚約指輪を用意してくれた。
29歳と11カ月の夏の終わり、無事に挙式と披露宴を済ませた。新婚旅行先は涼太の希望でマレーシアになった。
ところか年が明けて2月、涼太はふいに家を出ていった。