やがて幻になるこの街で 「よろ星のもとに生まれて」
めまぐるしいスピードで開発が進み、日々変化していく大阪の街。 いま目の前にあるわたしたちの街が徐々に幻になっていく光景を、リアルなのに少し不思議な物語で描く。 小説家・磯貝依里による大阪を舞台にした読み切り短編小説連載です。

まるで全身の皮膚をナイフで削がれるかのように強烈だった寒さがようやくほころびを迎えはじめた。と、誰しもに思わせるような三月初旬のとある午後。
新世界は通天閣のふもとに佇む〈喫茶ドレミ〉の窓際席。
ガラス窓のすぐ向こうでは、まろやかな陽光をたたえた雨上がりの水たまりがそこらじゅうに点々と散らばっていた。
「じゃ、そろそろいいですか」と、コンパクト三脚にカパリとはめたソニーのデジカメをテーブルの角にセッティングすると、向かいでぶ厚いホットケーキに夢中になっているインタビュー対象の女が、あっ、すごい。iPhoneちゃうんや。と、大げさに驚いてみせた。
「iPhoneでも撮れますけど、iPhoneのほうがいいですか?」
わたしの問いに女はフルフルと首を振り、んーん、そっちのほうがいい! てかそれがいいかな。
「スマホで撮影するほうが緊張しないってパターンもありますけど」
んーん、んーん。せっかくやしこっちがいい。てかさ、YouTuberって実際こんな感じやねんね。スマホでも撮れんねんな。ふーん。なんせうち初めてやからさ、こうゆうのん。ぜんぶ珍しいわぜんぶ。
あっ、すいません、すいません。YouTuberちゃうくて小説書いてるんですよね。すいません(笑)
Iさんの連載ちゃんとぜんぶ読んでますよ。
ネットで、ぜんぶタダで読めるんほんまに便利ですよね。
連載してはる小説、ぜんぶ大阪舞台にしててめっちゃ身近やし、あ、うちの出身のトコはまだ出てきてへんけど。ていうか、やから今日うちが呼ばれたんですよね(笑) すいませんフザけてて。あ、コーヒーフロート、溶けた。右、右に汁が垂れた。そっち。あ、ごめん、Iさんから見たら左やわ。左です。
新しいお手拭きもらってきます? あ、そう、それで、それでうちが呼ばれたんですよねってトコまで。
うちが今から話すことぜんぶ映像に残して、それをもとに小説にするんですよね。
録音だけのインタビューはNGで映像でお願いしますとか、ワガママ言っちゃってごめんね。
やっぱほら、声だけやとほんまに誰なんかわからんやないですか。
声紋? とかそういう? たぶんそういうの調べたら誰かとかわかると思うけどまあ無理やから、やからまあせめて誰にでもわかる証拠っていうか。動画やったら、まあうちにとっても、良い思い出の記録になるんちゃうかなっていうか。
Iさん、うちと真逆の雰囲気で最初会った時は緊張したけど、齢近くて安心した。『カードキャプターさくら』とか『神風怪盗ジャンヌ』とか、あと五歳くらいの頃、日曜日の朝に『ママレードボーイ』観て、なんかエッチでドキドキしてたとかぜんぶ一緒やもん、やっぱ同世代ってええなあって思う。
ねえ、幼稚園でやってたセーラームーンごっこ何役?
ジュピター? えーうそー、マーキュリーやと思った! 真面目そうやし青色着てはるし。髪ボブやし。うちより学歴賢しこやし。
でもジュピターってのもわかるけど。なんか、人気低そうな余り物いつももらっちゃいそうな雰囲気っていうか。優しそうっていうか。気、弱そうで強そうっていうか。やからぜんぶ、話せるっていうか。
ちなみにうち何役やったと思う?
うちはねー、いっつもルナPボール役。

生まれは東大阪の布施。駅でいうと布施と俊徳道のちょうどあいだくらいに家があって、けっこう古い町。
ぼろの長屋と狭い路地ばっかりでできた町で、布施のほうは駅前に行けばえべっさんもあるし商店街もあるし、イオンとか居酒屋街とかヒバリヤ書店とかもあるけど、うちは俊徳寄りやったからほんとに、東大阪ののっぺりした地に這う、入り組んだ路地の住宅ゾーンっていう感じだった。
通っていた幼稚園は規模は小さいのにやたらと園児が多くって、やからセーラームーンごっこの役も、毎回めちゃくちゃ取り合いの喧嘩になってしまう。
セーラームーンとかちびうさとか、プリンセスセレニティとか、ビーナスとか、そういう人気の役はリーダーの子が「文句ないやんな」って恐い顔で(やけどブリっ子して)容赦なく取ってくし、そうこうするうちに役の種類がもうぜんぜんなくなっちゃって、どうしようこのまんまやったら仲間はずれにされてまうって焦って、焦って、焦って、ほんで、あ! って思いついたのがちびうさが相棒にしてるルナPボール。
それで「うち、ルナPボール」って手挙げたら最初はみんなキョトンとしとったけど、でもまあいっか、って受け入れてくれて、ルナPボールはアニメのなかでもいつもちびうさのそばに居られるし、役を手に入れて無事にみんなと遊べるようになったんはええんやけど、ごっこ仲間の、ブリっ子のくせして気強いやつが最悪で。
ごっこ中、別の銀河の惑星に旅立って敵と戦うってなって、うちが「バリア!」って叫んで両手をばばっと広げたら、隣に立ってたうさぎ役のブリっ子が、
「ルナPボールは道具やからしゃべられへんし、手、ないで」
ってすかさず睨んできて、それからはもううち、幼稚園では一生猫の形のボールの道具。
道具やからしゃべられへんって、大人になって思えばほんまにそうやんな。あの子は正しかった。ほんま笑えるって思う。
あの子の言ってたことはじつはぜんぜん間違ってなくて、うち、ずっと家でも、しゃべらへん道具のボールみたいな存在やったから。

今やったら毒親って言うらしいね、ああいうの。
母親の名前はタマミで、自分のことをいつも自分で〈タマ〉って呼ぶ女だった。齢はめっちゃ若くて、うちが五歳の頃に十八歳。
継母やねん。
うち父親がけっこう金持ちで、むかしからあのあたりの地主とかそういうので。不動産管理とか、何店舗か自営業でやってる商売の片手間っていうか、前妻、つまりうちの実の母親に任せてたスナックが八戸ノ里のほうにあったんやけど、その実の母がうちが四歳の時に心筋梗塞でポロッと死んじゃってさ、そしたらすぐに、そのスナックでキャストやってたタマミが、うちの新しい母親になってたってわけ。
父親もエグいよね。
妹がすぐできたよ。そうそう、ちょうど幼稚園でルナPボール現役でやってた頃。
妹の本名はあんま言いたくないな。すごいシンプルで良い名前なんやけど、それも由来が、俊香ちゃんは、って、あ、シュンカってうちの名前ね。タマミが「俊香ちゃんはパパの漢字、名前にもらってていいよねえ」って、五歳のうちを見下ろして言ってたんだ。
「赤ちゃんにもパパの名前あげたかったけど、でもそれだと俊香ちゃんとおそろいになっちゃうからやめとくね」って。
ばーり怖い。二番目の女っていうんはほんまに怖い。あの時の顔、今でも夢にみるよ。なんかもともと、ねちねちした女やねんよなあのひと。
幼稚園のセーラームーンごっこでいつもうさぎ役やってた、ほんまは気ィ強いの隠してブリっ子しとったあの子に、けっこうよう似とったんかもしれへんわ。
初めて顔合わせさせられた時からうちと離れるまでの十何年間か、タマミはずっと若かった。
十八から三十歳の女やねんからまあ若くて当たり前なんやけど、幼い感じのワンピースとかりぼんの付いたスカートとかよく着てて、髪もこうふんわりさせた三つ編みとか、シュシュ巻きつけたハーフアップとか、いわゆるあざとい系の感じで、それはそれとしてなんやけど、それよりとにかく言動っていうか、いつも声が甘ったれてて、うちはそれがすごい怖かった。
財産目当てでうちの父親と再婚したんちゃうかって親戚からは言われとったみたい。
でもうち的には、たぶんそれはちゃうんやろなと思ってる。
タマミは父親のことを心から好きで好きでたまらんかったんやろなって気がする。
ほら、今やったらTwitterとかでさ、インスタとか、好きなひとの投稿ぜんぶにいいねしたりするやん、好きなひとのさ。うそやんあんたそれぜんぶいいねするんマジで、みたいな。
そういう感じで、父親の言動ぜんぶにウン、ウン、って嬉しそうに頷いて、そばに居られるだけでこれ以上の幸せないって感じの表情で、いつも。家でもスナックでもずっと。誰が近くで見ていようとぜんぜんかまわずに父親の顔とか肩とかにずーっと身体ひっつけて嬉しそうにはしゃいで距離感ゼロなん、距離感ゼロ。父親にだけは。
小さい時の親のすがた憶い出そうとしたら、なんていうかね、毎回同じ光景なんよね。
淡い色のふわふわした小柄な生き物が、隙のなくスーツを着こなした背の高い男のひとのまわりにつねにまとわりついているような、それか、花びらみたいにまわりで舞い踊ってるような。
父親はぜったいにうちには振り向かんの。逆光で、ぜったいに振り向かない父親の隣で、ふわふわした生き物だけがたまにこっちを見て、得意げに微笑んでうちのこと見下ろしてくるの。

そうは言っても、あの女にはけっこう可愛がってもらっとったよ。むしろすごい守られてた。守られてたっていうのは、たぶん世界じゅうから。
世界じゅうから守ってあげるっていうのはあの女の言葉。
自分はファンタジーみたいな可愛い服ばっか着とんのに、うちにはスーパーで買ってきた型遅れのトレーナーにだぼだぼのジーンズばっか着せてたのも、自分は髪を栗色に染めてやわらかいリボンで結んでたのに、うちにはぜったいに散髪屋のショートカット以外の髪型をさせてくれんかったのも、うちは肌が弱いからあんまし顔触ったらあかん言うて、三日に一度しか洗顔させてくれんから毎日ギトギトの脂顔で登校させられとったんも、男に媚びるようになったらあかん言うて、小六になっても中一になってもぜったいにブラジャー付けさせてくれへんかったんも、眼鏡をコンタクトに変えたいってお願いしたら「おしゃれとかやめなよ。似合わない。きもいよ」って笑われたんも、ぜんぶぜんぶ、ぜんぶ、うちを世界じゅうから守りたいから。
継母やねんけど、そういえばなんでか顔がうちとすごく似てた。妹よりうちのほうがタマミと顔いっしょやったんちゃうかな? 挙動も似てるんちゃう、今思えば。
そっくりの顔いうても、向こうは完璧フルメイクで、こっちは寝起きすっぴんくらいの差はあるねんけど。
でもどんなに手ェ入れたって、化粧した顔もすっぴんの顔も、同じ人間やったらなんていうか根っこにはどっちも〈自分〉やっていう愛着があるやんか。
で、たぶんタマミは〈自分〉が大好きな女やねん。ほんで〈自分〉が好きすぎて、大事すぎて、寝起きすっぴんの〈自分〉みたいな顔した、みすぼらしいうちのことも愛さずにはいられんくて、でもほんまのトコはぜんぜん愛したくなくて、やけど娘になったし愛さなあかんから、まあ、しゃーなしでああいうネジれた感じになっとったんやと思う。
〈自分〉にどこか似てる生き物が〈自分〉のそばにつねに居たとしたら、そいつには〈ほんとうの自分〉を脅かさない位置にいつだって居てほしいし、脅かさない存在やから弱いし、弱いから守ってあげんとやし、守ってあげられるんなら、いつだってかんたんに、自分の好きなように虐めることだってできる。
うちやってたまに、自分のことめちゃくちゃに虐めてみたくなる。
めちゃくちゃに虐めてみたらどういう世界線たどるんかな、こいつ。みたいな。
女性性の否定? 娘が女になるのを認めたくなかった?
あー、そういうのもあったかもね。
けどうち的にはやっぱ、〈自分〉説を推しときたいかな。

初めて精神科行ったのは十四歳の時。近鉄乗って、鶴橋の病院。
医者に症状説明すんのってむずかしいよね。緊張するし。今やったらけっこう冷静に解説できるよ、あの時の自分の感覚のこと。
一言でいうとね、心の目が完全に見えなくなっちゃったって感じ。
あ、今の表現すごくしっくりきたな。そう、心の目が見えなくなっちゃったんですよね。
家がしんどいからほな学校行ったら楽になるんかいうたらぜんぜんそうちゃうくて、なんかいつもタマミが背中にのっそり、呪いみたいにもたれかかってるような気がして落ち着かんの。やから授業中も休み時間もずっとうつむいとって、ずっと制服のプリーツばっか見つめとって。指のささくれ剥いて。
でもそんなんしとったらクラス全員からキモいって思われるやん。毎日全身臭かったからタダでさえキモいし、ほんでそのうち机の下で本ひらいて読むようになったねん。図書室のやつ。適当に。あー、何やったやろ、森絵都やったかな、柳美里かな? 文豪とかそんなむずかしいやつちゃうかったけど。
で、いつもどおり授業中に読んでたある日なんやけど、突然教室の前のほうで「バーン!」てめっちゃでかい音がした。
顔上げたら、先生が黒板に教科書ぶち当てとって。
ほんで睨んでんの、うちのこと。
「高安さん、あんたいっつも何しとんねん。何持ってんねん。立ち。見してみ」
そん時、生まれてから一番鳥肌立ったよ。
教室にいる人間が全員座ったままグワッと振り返ってて、全員がうちを見てたんよ。全員が。なんかもうすごい凄まじく冷たい目で。ひとりふたつずつの目玉で。全員が。うちのことを、ただただ〈見て〉た。
目玉がどんどんどんどんうちのこと追い詰めてきてものすごい圧で身体を押しつぶしてくるから、それで怖くて怖くてもう無理で、たぶん、叫んで教室飛び出してたみたい。
そっからちょっと記憶がトンでて、うちの教室は三階なんやけど気ィ付いたら一階のトイレが突き当たりにある暗い廊下にしゃがみこんでめっちゃ泣いてた。
泣いて泣いて泣いて、最終的にはなんで泣いとるんかぜんぜん思い出されへんくなって、それでも涙とまらんし、で、涙出しきったら目が乾いてきて、あーなんか痒いな、って目こすって開けてみたら、なんかそっから、ぜんぶの景色の見え方がまるっきり変わってもうてん。
まず文字が読めない。
それまで家でも学校でもずっと本とか漫画読んでゲンジツトーヒしとったのに、ふしぎなことにそこに書かれとる日本語がぜんぜん読まれへんくなっとって、どうかすると吸い忘れたタバコの先端の長い長い灰みたいにボトリ、ボトリと文字がこぼれてカーペットを汚していって、それで自分がいつのまにか小説とか漫画を読む言葉をすっかり失くしてもうてるのに気がついて、むなしくてそれでもう何もやらんくなって、とりあえず部屋にこもってケータイで自殺サイト見たりひたすら寝たりしてたらなんだかぜんぶの調子が悪くなって、この世のぜんぶが怖くなった。
部屋にとじこもってたらタマミがキレるんよ。妹も一緒にキレてた。
近所に響くのもおかまいなしに廊下でキレて叫んでうちの部屋のドア叩くから、しゃーなしに開く。ドアを。
そしたらふたりが並んで立ってて、こっち見下ろしてるからうちも見あげようと思うんやけど、それがさ、どんなに見上げても見上げてもどっちの顔も確かめられない。ふたりの影だけが足もとにやたら巨(おお)きく伸びて、廊下も天井も覆い尽くして、その下のふたりの顔を見なあかんのに、なぜだかどうしても見ることができひんの。目が見えない。
水のない水の底で永遠にもがいてるみたいな、あの時のうそ寒い感触を思い出したら、未だに全身にたちまち鳥肌が立つ。

話しはじめたら思ったより長くなりそうやし、うちんチの事情とかよそのひとには意味わからんよね。ごめんね。と、女はそこで一旦話を区切り、わたしにバニラミルクセーキを追加注文していいかどうか訊ねてきた。
運ばれてきたミルクセーキにはカチカチのバニラアイスが沈んでおり、メニューの反対側に記載されている通常のミルクセーキがまったく同じ値段であるのにわたしたちはふたりで驚いて、え、これならバニラで頼まなダルいですよね、と女はげらげら笑った。わたしにひと口くれようとする。その動きがあまりにしぜんだったので、ついくちびるをしぜんに差し出し、ストローの先を舐めてしまった。
「これ飲んだの初めてですか?」
インタビューの場所指定のやりとりした時に、ここ、よく来るって言ってたので。いつもは別の飲んでるのかなって思って。
わたしの質問に女は、ああ、と宙を見やり、これは初めて。ていうかいつも適当に目ェついたの注文すんねんけど、飲みもんは大体六百円より下のもんばっか。
あ、でも初めてここ来た時に注文したのは山菜ピラフなんですよ。ここ、メニューのこのいちばん右下のとこ。
「初めての時が、あなたが捨てられた時なんですよね」
そうそう、そうなの。女は軽快に頷き、インタビュー記念に、久しぶりに頼んじゃおっかなあ、山菜ピラフ。と、メニューをじっと見下ろした。

タマミにここへ置いてきぼりにされて捨て子になったのが、十八の誕生日の翌々日。
その頃には病気がずいぶんひどくなってて、もう視界ぜんぶがもんやり曇って、何も見えんくなってて。そんなうちを、突然タマミが家から連れ出した。
あの時期は幻聴もきこえてたし、ひたすら死にたくて、第一タマミとおるから病んどるのに、なのに、いつのまにかその病む原因のタマミがそばにおらんと落ち着かんし、もしタマミがうちのそばからいなくなったらどうしようっていつも考えてて、自分で自分が怖かった。
お風呂入らんで(入れてくれなくて?)ありえんほど臭いうちが廊下でしゃがんでわあわあ泣きつづけてるところに、ある日タマミがびっくりするほど優しい手つきで肩ぽんぽん、てしてきてさ、それで言ったの。
「ね、みんなで甘いもん食べにいこか」って。
妹が外に出る服貸してくれて、妹も一緒についてきてくれて、三人で。
出かけた先がどうして新世界やったんか未だにわからへんねんけど、なんでやろな。駅出たらそこらへんにホームレスも野良猫もようけおるし、街ぜんぶが動物園みたいやからかな(笑) 捨てても困ることないやろ思ったんかな。知らんけど。
ここ〈喫茶ドレミ〉に入って、メニュー開いて、そしたらさあメニューがすっごい細かいんよね。ほら、細かいじゃないですか。 字も数も。やからうち、すぐに選ばれへんかったの。目ェ見えへんくなって、文字読めなくなっちゃってたから。
タマミと妹は一瞬で店員呼んで「アイスコーヒー」って、それズルズルッと飲み干して。
でも三十分以上もうちが注文迷ってウジウジしとるの見て、イライラしたんかな。それなのにあの日はふたりともすごい優しかった。いや、そうじゃなくて、あの日は最初からここにうちを捨てに来る予定で、やからずっと優しかったんやと思う。
いつもやったら「悩んでるところが気持ち悪いからお茶でいいよね」って勝手に注文されてしまうのに、「ゆっくり考えて好きなの頼みなね」って、タマミ、こうやって、そう、こうして、テーブルの上に五千円札をそうっと置いて、うちにやわらかく微笑んだんだ。
それからタマミは妹だけ手を引いて立ち上がって、「シュンカちゃんが好きなの選べるまで、タマたちはそこの銭湯に行ってくるから」って出て行っちゃった。
タマミたちを見たのはそれが最後。
どれくらい経ったかわからへんけど、そのうちあの人たちがもう二度と帰ってこやんのやって気がついて、それでうちはタマミのくれた五千円でとりあえず山菜ピラフを注文したねん。
ここ米系と麺系、カレーか山菜しかないの。笑っちゃうよね。おいしいんやけど。ほらみて、山菜ピラフ、山菜スパゲティ。
待ってるあいだに、お腹空いちゃったからさ。

継母によって捨てられたその後の生活について、女はとても饒舌に語ってくれた。
当座をしのぐつもりで漫画喫茶に連泊するもすぐに身体に疲労が溜まって耐えられず、継母から餞別として受け取った五千円は五日も経たないうちに底を尽いた。女はケータイのプロフィールサイトに開設されている掲示板(当時はまだガラケーだった)で相手を募りとにかく寝ることで日銭を稼ぎ、そのうち数回の常連になってくれた三十半ばの男と意気投合して、その男にいくつかのバイトを紹介してもらう。
天下茶屋の町にある電柱から電柱を渡り歩き、ドライブスルー形式で商品を手渡す覚醒剤の売り手。翌朝から漁船に送り込まれる予定の借金まみれの若い男と深夜のファミレスで向かいに座り、相手が逃亡しないようにひたすら話し相手をする仕事。うさぎを繁殖させる仕事。そのうさぎを謎の会合へ売りにいく仕事。その他いろいろ。
男には別の女がいたので家には上げてもらえず、女も女でそこまで男に頼る気はなかったから、週に二度ほど天王寺や生國魂神社周辺のラブホテルに連れていってもらう以外は安居酒屋で夜を潰し、昼はあいかわらず掲示板で男を募集して寝た。
あの頃、家ないくせに毎日でかいお風呂にばっかり入ってたわ(笑)
気持ちよかったなあ。女はにひひ、と口角を上げる。
風呂には大体毎日入れていたので清潔ではあったものの、しかしコジキはコジキなので自分の全身がどうしても臭かった、と女は言い、何の予定もない日は天気がよければ夕陽ヶ丘の長い坂をだらだら登り、愛染さんや大江神社、一心寺あたりを茫漠とした精神のままよろよろさまよって、口縄坂で天王寺の街並みを足もとに感じつつ一休みし、それから四天王寺の広い境内へたどり着く。
入り口の鳥居を入ればすぐそばに瓦葺きで朱塗りの四天王寺中学・高校の校門があり、女はそこを通る時だけ身を縮めた。
灰色のスカートを穿いた、自分とそう齢の変わらない中高生たちの気配がする。悔しさや気後れはなかったけれど、そうして身を縮めなければあの空間にたちまち蛇みたいに飲み込まれてしまうような気がして怖かった、と語る。
四天王寺中学・高校の女子生徒たちから女は「よろぼろさん」と呼ばれていたそうだ。
よろよろ歩いてぼろぼろやったから。女はそう言う。

四天王寺の境内では女はたいてい、赤青二体の仁王像が祀られている中門前のベンチか、その中門をさらに左手にまわっていった先の、東側にある亀井不動尊、あるいは亀井堂の藤棚の下でぼんやり過ごした。
亀井不動尊の草むらや石畳には人懐こい猫が何匹も転がっているし、さらに左手に進んで六時堂前の石舞台をはさむ二つの池に行けば大量の亀もいる。
石舞台のほうにも猫はたくさんいた。いたというよりそこらじゅうの地面に落ちていて、どれも陽を浴びてもちもちとふくらみ、石橋を通り過ぎる坊さんの集団が「きょうは上(石舞台)に乗っとらんなあ」と軽く声をかけていく。
亀は薄っすらと目を閉じてフジツボみたいに板にくっついている。
生き物の、俗っぽい命の気配がやたらとするお寺なので、なんだか居着きやすかったのだと女は言う。
じつは春にある大きなお祀りで、かつて童舞をやらせてもらったことがあるのだと女は嬉しそうに教えてくれた。当時存命だった祖父の伝手であったという。
聖徳太子の命日に執り行われるその法会では、普段猫だの亀だのが寝そべっているその石舞台が華やかに彩られる。
石舞台の四方に曼珠沙華(マンジュシャゲ/彼岸花)を模したくす玉のような巨大な飾りがそびえ立ち、その真紅の花の周りには黄泉の国の使いであるつばめが吊るされ飛び交っている。鮮やかなエメラルドグリーンの敷物。金銀五色のしなやかな幡。六時堂の軒よりも大きな、仁王像の目玉のような大陸の太鼓。
女はそこで、極楽鳥・迦陵頻伽の舞〈迦陵頻〉を数人の、同じ年頃の子どもたちとともに舞った。
宝冠と桜の簪(かんざし)を頭に挿し、曼荼羅の羽を背負い、一度見たら忘れないほど美しい、尾の長いオレンジ色の衣装だった。
舞うといっても単純なもので、両手をひろげ、鉦を鳴らし、雅楽にあわせて四股を踏むように足をワワッと前に差しだすのだ。

四天王寺の境内では毎月二十一日に盛大ながらくた市がひらかれる。
数年前のちょうど今の季節、彼岸の頃、女はそこで掲示板で引っ掛けた男と待ち合わせをしていた。
そこに来たのが自分の父親やった時の気持ち、どう。わかる?
女は瞳をきらきらさせてテーブルに胸を押しつけ、わたしの目を射るように見つめた。
出会い系やで。親がやってる思わんやん。でもまあうちの親やったらやるかな。金あったし、女好きやし。一般的にいうたらそこそこ男前やし。ほんでもさ、そんな、ものすごい確率で当たるわけないと思うやん。
がらくた市の人混みのなか、待ち合わせ場所を何度も何度も変更し女をさんざん惑わせた先に立っていた父親は、かつて一緒に暮らしていた時よりもずいぶんと若々しい面立ちになっていた。
ラルフローレンのシャツから覗いた胸は筋肉質で、肌は茶しぶのように黒く、定期的に日焼けサロンに通っているのかもしれなかった。白髪のない短髪。イヴサンローランのサングラスを掛けていたが、クラッチバッグのブランドは憶えていない。
四天王寺中学・高校の校門前に女が向かったら「おい」と横柄な呼び声がし、振り返ったら、顔の横でクラッチバッグを下品に振り回しながらこちらへのしのしと近づいてくる中年男性がいて、それがどう見ても自分の父親であったので女は仰天した。
父親も驚いており、数年ぶりに目にする互いの顔をしばし呆然と眺めた。
女が何も言えずに父親を見つめつづけてどれくらい時間が経過したか。
それまで膜が張っていたかのように何もきこえていなかった耳がプツンとはじけ、がらくた市の喧騒が女の五感にどっと盛大に流れ込んできた。
あ、とひと声こぼした女の手を父親は握り、「おい、シュンカ」と上から目線で口角を上げると、女が何も答えないうちに「じゃ行こう」と引っ張ってきたので、女はとてもびっくりしたそうだ。

寝たか寝てないかでいえば寝ていない。と女は強調した。
とりあえずお前の話を聞きたいからと父親は喫茶店か食堂に行こうと提案したが、女は掲示板で男を釣るのは金と風呂と睡眠がその目的であるために「ホテル行かんのやったら帰る」としぜんに口に出してしまい、それに対して女の半歩前を歩く父親はギョッとせずにはいられなかっただろうが、しかしあまりにも女が頑なだったので仕方なく夕陽ヶ丘をくだり、新世界沿いに建つ黄色い壁がメルヘンな連れ込み宿〈タワーサイドホテル〉に入ったという。
入室して即、願い通り大きな浴槽に湯を溜めはじめ、女はホットパンツとタイツを脱ぎ、あとはブラジャーとパンツだけの格好になってクイーンサイズのベッドに仰向けに寝転がった。
父親はもちろん服を脱ぐことはなかったが、女は自分の父親がほかの男たちと同様に全裸になっていく工程を想像し、てかてかに光る黒みを帯びた背中の隆起や、下着からはみ出た尻のタテ線の、驚くほどナルシスティックな様子を脳裏に思い浮かべ、そのすがたを薄目で見上げた。
ベッドに腰掛けて女に背を向けた父親は、おい、今も病気の薬ちゃんと飲んでんのか、と女に訊ねてきたという。
飲んでるわけないやん、金も保険証もないって答えたら、せやな、って笑ったんよね、父親。せやなって、ただひと言、それだけ。
なんかそれでさ、ふつうやったらムカつくとかなったんかもやけど、うちはそれ聞いて「ああ、それでこそうちの親やなあ」となったわけ。
逆にほっとしたっていうか。
たぶん可哀想がられちゃったら、ほななんでうちのこと捨てたんか、その理由がなくなってしまうから。
捨てられた理由がなくなってもうたら、なんでうちがここにいるのか、この街にいるのか、その理由さえもなくなっちゃうから。
その週は世話になっとる男にぜんぜんかまってもらわれへんかって、ほとんど風呂に入れへんかったしふとんでゆっくり寝られずにおったから、久しぶりのホテルのベッドがほんまに気持ちよかったあ。
だいぶ古いホテルやって、床も天井も得体のしれない汚れでベタついていて、おそろしく悪趣味なバラ模様の壁紙にはヤニと精液の臭いがこってりこびりついとったわ。
天井と壁をぎっしり埋め尽くす色褪せたバラ模様が巨大な魚の赤い鱗みたいやった。その魚を二枚おろしにさばいて、内と外をぐるりと裏返してまるでそのなかに寝ているみたいやと思ってん。
そしたらふいに、その魚のなかに寝とるうちを、四天王寺の舞で踊った迦陵頻伽が、そっとついばみに舞い降りてくるような感触がしたんよ。
迦陵頻伽ね、ほんまに綺麗な生き物やの。
ああ、生き物って言ってもええんかなあ。極楽浄土で歌い舞い踊る、上半身がひとで下半身は鳥の形をしとるねん。羽は腰のあたりから生えていて、天使みたいなもんやとうちは思う。
小さい頃にそれを踊った極彩色の自分がふわふわ、ひらひら、ホテルのベッドで力尽きて寝とるうちの上に降りてきて、にっこり笑って、幸せそうに歌っとった。ああ、綺麗やなあって泣きそうになってしまった。ぼろぼろのコジキになったうちを迎えにきたんかなあと思ったよ。男からもらった性病で股がかゆかったし、客しばらく取られへんし、そやったらこのまんま迦陵頻伽の自分に連れてってもらうのもええなあって。

後妻が娘を追い出した件についてひじょうに後悔していたと父親は女に言ったそうだ。
父親は後妻から「娘が自分で家出をしたのだ」と聞いており、女はもう十八歳であったので、自分は後妻と娘の諍いのほとぼりが冷めるまで辛抱強く娘の帰宅を待っていようと思っていた、病気でふらふらになっているところを連れ出され、置いてきぼりにされたという事実を知っていれば、あの時自分は間違いなくお前を迎えに行っていただろうと女に謝罪をしたとのことだった。
俺の家に生まれたばっかりにこんな人生にさせたな、ぜんぶ仕方がなかったのだと、父親はまるで事後のように、実の娘に背を向けてタバコを吸った。
女をホテルのベッドでゆっくり休ませた後に父親はジャンジャン横丁で美味しい寿司を食べさせてくれ、それから街に流されるように散歩をしていたらまたいつのまにか夕陽ヶ丘に戻っており、それはちょうど落日の時刻だった。
大交差点の坂のてっぺんから見下ろす天王寺の夕陽は、女がホテルで幻視した迦陵頻伽のあでやかな羽の色をしていたそうだ。あたりは咲きたての甘い梅の匂いに満ち満ちていた。
熟睡し、満腹になり、父親と並んで夕陽が落ち溶けるのを眺めていると、やがて女の感覚の内に、久しぶりに何かを〈見ている〉という明瞭な意識が蘇ってきた。
はっとして眺望から顔を上げ、四方を見回すと、心の目が見えなくなって以来はっきりと認識できていなかった景色が、車が、草木が、空の色が、ひとが、ひとびとの表情が、すべてまた色鮮やかに女の目に映っていた。
女はその瞬間、自分がふたたび心の目を取り戻したのだと知り、よろこんだ。

その後、女は父親に自宅に一緒に戻るかと訊かれるも、今の自分はコジキなので恥ずかしい、どうせ後妻に馬鹿にされてまた鬱になるだろうから自立できるまで帰らないと頑なに首を振り、連絡先だけ父親に手渡し解散したらしい。
あの日から数年が経ち、今はそれなりの仕事をしていると女は言った。
それなりって言うても箱ヘル。相生橋筋の裏らへんにあるセーラー服着用箱ヘル店。坂町のあたりに住んどるよ。そう、家もあるねん。
源氏名はこれ(名刺をくれた)でやっとるから検索して。パネル出てくるよ。
と、その時カラン、と〈喫茶ドレミ〉の入り口のベルが鳴り、二十代後半とみえる女がひとり入店した。髪が長く、凛とした美人である。
その女は奥の座席を陣取るわたしたちに気がつくと「あ」とまばたきし、こちらへ近づいてくる。
「……すみません、もうお邪魔しても大丈夫ですか?」
髪の長い女がインタビュー対象の女の隣に腰を下ろすと、女は露骨に嫌な顔を見せた。途端に居心地の悪そうにくちびるを尖らせ、先ほどまでの饒舌さをすっかり飲み込んでしまい、わたしからさえも視線を逸らしてレースカーテンの向こうを見やり、バニラミルクセーキをずずずと啜った。
「……長時間お待たせして、こちらこそすみません」
わたしは髪の長い女に頭を下げた。春が近づき気温が高くなってきたとはいえ、インタビュー終了の予定時刻までずいぶんな時間を外で待たせていたのが申し訳なかった。この二時間ほどどこにいたかを訊ねると、商店街のほうのべつの喫茶店で本を読んで待ってくれていたという。
「シュンカちゃん、疲れた?」
髪の長い女がやわらかく微笑んで女を覗き込む。
インタビューの女は一瞬だけわたしたちに視線を戻し、けれどまたふっと、窓の外を向いてしまった。
さっきまで臨場感たっぷりに話していた母や妹との別れなど、はじめから一切なかったのだというけろりとした表情で。
*
ピンクブラウン色の長い髪の女はインタビュー対象の女の妹であり、わたしの友人の友人の友人である。
そもそもインタビューを提案したのはこの妹であった。
わたしが昨年からウェブメディアで読み切りの短篇小説を連載していることは、SNS等を通じて周囲の日常的な友人も認知している。
わたしは明確な線引きをすればプロの書き手ではなく、昼は別の職に就き、週に一、二度ほどミナミのバーで働き、それらのあいまにあるふとひとりになる時間をなんとか使って、日々こつこつとこんな文章をこしらえる。
大学時代から創作系の学科に属していて、書きものを続けているうちにやがて文章関係の知り合いは増えた。けれどそれは、日々自分が属している日常的な世界のひとびととは、ほとんど交わることがない。
文章を書くという行為はあまりにも地味だ。作りあげる工程において誰かと創作におけるよろこびや苦しみを共有したり、知ってもらえたりはできない。
そしてまた発表時においても、音楽や絵のようにスピード感をもって皆に伝達することができない。
自分の作ったものを誰かに体感してもらうのに、あらゆる面でおそろしくコストがかかるのだ。
だから敬遠されがちになるのも、娯楽が多様化した今の時代では仕方がない。
文章関係でない日常的な友人たちに小説を書いていると自己紹介をしたり、書いたものを読んでもらった際、これは一体どこまでが現実にあったことなのかと訊ねられる瞬間が頻繁にある。
これにはけっこう参ってしまう。
参ってしまうのはわたし自身の勝手であるし、物語は書かれた時点でわたしから手放されるべきであるのだから誰にどう読まれてもいいのだけれど、どう読まれてもいいのだというそんな意識が根強くある一方で、これがわたしの現実であると、わたしが体験し、見たものであるのだと、そう他人に認識されたくはない気持ちがこれまた根強く存在しているのだ。
わたしの書いたものがすべて現実をもとにしているというのは、半分事実で、半分事実ではない。
わたしのなかですべての物語は、言葉に変換し〈ここ〉に書いた時点でそのすべてが事実になる。体験したことになる。体験したことから生まれる言葉もある。けれどそれは事実に生まれ変わりながら、言葉に生まれ変わったせいでほんとうの事実からは、どんどん遠く離れていく。
だからここには、〈ほんとうのこと〉なんてひとつもない。

小説を一般にむけて公開しているとそういうジレンマが、もともと覚悟していたとはいえ、あまりにも現実的にこの身に迫ってきて参ってしまう。
これはあの出来事ですよね、と読んだひとから邪推して言われることが実際にある。それがしんどくてしかたがない。
事実なんだけど事実じゃないんだよね。そうぽつりと愚痴をこぼしたわたしに、ある日、味園ビル の〈ホテル・アドリアーノ〉で飲んでいる時に、友人が「おもしろい知り合いがいる」と言った。
「うちの友だちの友だちのお姉さんやねんけど、ばり虚言癖やねん」
虚言癖、と言われて思わず身を固くしてしまったわたしに、しかし友人は「でもね、虚言癖言うても、すごいおもろい子やねん」と笑う。
「この辺とかアメ村でもよく飲んでる子で、妹と住んでて飲む時もいつも一緒やねんけど、いつも言うてることがちゃうねん。とくに自分の過去の話が」
自分の過去の話を他人に披露するのが大好きな女。しかし毎回その内容が大きく異なっており、一体何が彼女のほんとうであるのか、未だに誰もわからない。
彼女の過去のパターンは数え切れないほどある。ハッピーなパターンもあれば、ダウナーなパターンもある。どれが実際の過去なのか想像するのも馬鹿らしいほどにバリエーションが豊富だそうだ。
虚言癖とは言うものの、たぶん彼女にとっては毎回のすべてが真実で、そして毎回披露する内容が異なっているという、その〈毎回異なっていること〉そのものが、そもそも彼女にとっては真実なんじゃないかと、友人は言った。
*
友人に女の妹を紹介してもらったのは年が明けてすぐだった。
妹はわたしがウェブで大阪を舞台にしている連載小説を書いていることを友人からあらかじめ聞いており、そのせいもあるのか、「姉のことを小説に書いてみたらおもしろいと思いますよ」とわたしにおもむろに提案し、微笑んだ。
事実を小説にすればおもしろい。事実こそが小説の種なのだとまたしても無邪気に言われた気がしてしんどくなりかけたが、わたしの向かいに座って微笑む妹の目は、どうやらそういう意味は含んでいないようだった。
「姉は、ものすごく自由なひとですから」

それシュンカちゃんが好きなやつやね、と妹は、女が啜っているバニラミルクセーキを見つめて微笑んだ。よく微笑むひとだと思った。女を保護しているというよりも彼女のそばにいることで逆に安寧を得ているような、素直な微笑みであるのが印象的だった。
父と継母と女と妹の四人家族。父親は八尾市の大地主の一族で、継母は父親の学生時代の知り合い。女も妹もともに前妻の娘である。妹が高校を卒業しメイクの専門学校に進学したと同時に父親が大阪市内に部屋を借りてくれて、姉妹で同居をはじめた。
妹から事前に聞かされていた情報はこのようなものだったので、女の話がスタートしてすぐに、今回の過去は凄絶なパターンのほうだったかと動揺した。
しかし女は終始ニコニコとご機嫌で披露してくれる。
凄絶ささえも、手の先の先、足の先の先まで、愉しんでいるかのように。
何か注文するかと妹に訊ねると、妹は首を振った。
「いえ、もうじきに帰りますから。ありがとうございます」
垢抜けた華やかなコンサバメイクを施した妹と、それとは対照的に、縁取れるだけ縁取り塗れるだけ塗ったというふうなギャルメイクの姉。
メイクだけではなく、交互に眺めていると、ふたりの顔立ちは確かにちがうのではないかと思った。
妹は後妻の娘だから血は半分しか繋がっていない。そう語っていた、さっきまでの女の過去話が脳裏をよぎる。
同居し、バーへ飲みに行く時も銭湯へ行く時も、買い物も遊びも何もかも、すべてふたり一緒のふしぎな姉妹であるとわたしの友人は評していたが、しかしこの違和感は一体なんだろうと思う。
常時行動をともにしているのであれば、毎回異なる自分たちの物語を他人へ披露する姉に妹は毎回つじつまを合わせて加担しているのだろうか。いや、それとも最初から合わせる気など微塵もなく、ただ黙って微笑みながら姉を見守っているのか。
見守っている? その不自然さにふと顔を上げる。
窓の外を鳥が一羽はばたいていった気配がしたが、気のせいのようだった。
インタビューの冒頭で女が、幼稚園でのセーラームーンごっこでルナPボールを志願した際、皆初めは彼女を仲間としてつつがなく受け入れていたのに、ある瞬間「ルナPボールは道具やからしゃべられへんし、手、ないで」と冷たく突き放され、それ以来ほんとうにしゃべれない道具となってしまった、と語っていたのを憶い出した。
その時の光景をわたしは見てもいないのにとても鮮やかに憶い出せてしまう。
彼女を突き放し、嘲笑し、けれどそれで安堵を得ていた偽のセーラー戦士たちのなかに、きっと妹はひそかに紛れて立っていた。
たとえばちびうさのような、脇役のふりをした主役として。
あるいはもしかしたら。
あんたはルナPボールになればいいと、彼女の耳もとで微笑みながらうそぶいたのは。

ルナPボール。と、わたしはつい口からこぼしてしまいそうになる。
「シュンカちゃん、Iさんにお礼しときなね。たのしくてよかったね」
ちょっとお手洗いに、と妹は無駄のない所作でフレアスカートの裾を持ち上げ、店奥の暗がりにあるトイレへと立っていった。
途端、テーブルの上へ溶けかけのバニラの汁をこぼしたようにねとついた沈黙が広がっていく。突然込み上げてきた気まずさにわたしはピクリとも動けない。
一秒、二秒、三秒。四秒。五秒。
なまぬるく白い沈黙のバニラ汁はじわじわとテーブルを侵し、それからポトリと一滴、ふいにわたしの膝の上に垂れ落ちる。
あの、と女は口をひらいた。
……あの、妹、なんかこわいですよね。すいません。
「いえ……」
いいですよ、正直に言ってもらっても(笑) ふたりそろって変なんです(笑)
だから仕方ないんです、うちら。ふたりでいないと。
ふたりでいないとっていうか、いつもわたしが一方的に妹に守ってもらってるんですけど。そう、すごい守られてるんです。妹に。
守ってくれてるっていうのは、たぶん世界中から。
世界じゅうから守ってあげるっていうのは妹の言葉。
こうしてIさんみたいな良いひとに会わしてもらえるのも、おいしくバニラミルクセーキ飲めとるんも、むかしあった嫌なことを今こうして楽しく話せるのも、薬なしで外出られるんも、あんたはほんまに駄目な人間だねっていつも笑って言ってくれるのも、ぜんぶぜんぶ、ぜんぶ、うちを世界じゅうから守ろうとしてくれとるから。
指を始点にスライドさせて巻き戻したように、女はまた饒舌に、はじめから物語をかたりだす。
さっき聞いたものととてもよく似た、けれど異なる、自分にまつわる家族の物語。
「あの、」話を止めようとしたわたしに、女は空虚な瞳で笑いかけた。
「仕方ないんですよね、ぜんぶ。……うち、生まれちゃったから、この星に」
背後から水洗の音が響き、妹の戻ってくる気配がする。
ほんならうちのこと書いた小説、読むの楽しみにしてます。ほんまうちIさんのやつめっちゃ好きやから。ほんまやから。
女はバニラミルクセーキの最後のひと口を勢いよく啜り込み、お待たせです、と戻ってきた妹に手を引かれてゆっくりと立ち上がる。
妹の前で女の口はふたたび固く閉じられて、ごちそうさまでした、とわたしにハキハキ頭を下げたのは妹のほうだった。
〈喫茶ドレミ〉の狭い店内を出口に向かいながら、テーブルや植木鉢や壁に、まるでバランス感覚を失ってしまった人間のように女は幾度も幾度もぶつかってはよろけ、転びかける。
ベルを鳴らして出たその先でも道ゆくひとびとに次から次にぶつかって、妹に手を引かれた女のすがたはなかなか遠くなりはしない。
心の目が見えなくなっちゃったんですよね、と言っていたあの瞬間の表情だけ、今もまだつづく彼女のたったひとつの真実であるような気がした。
女の目には、きっとまだ何も映ってはいない。
そういえば女が話そうとしていた二度目の物語は、あの時止めなければどんなものになっていただろう。
仕方ないんですよね、ぜんぶ。……うち、生まれちゃったから、この星に。
わたしは女のつぶやいた印象的な言葉を反芻しつつ止めるのを忘れていたカメラをようやく止めて、家に戻ったら、彼女が話そうとしていた幻の二度目の過去の物語を書いてみたらどんな気持ちになるだろうかとそう思いついて、けれどそんな自分自身の欲望やエゴに心の底から吐き気がした。











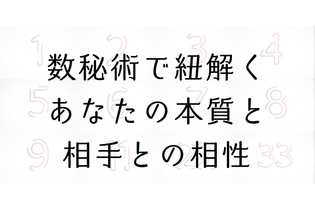










本を読むのが好きです。小説を書いたり、書評を書きます。関西出身在住。