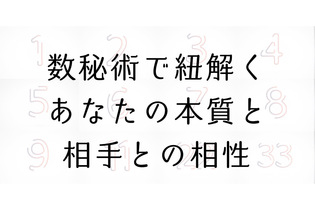泳ぐように、溺れるように、書いている
「わたしは、”途中”を愛せないんだよなあ」。文章を書く最中は、いつも苦しくて仕方がない。なのにどうして、この仕事を続けているんだろう――。エッセイスト 中前結花さんがJ-POPになぞらえて書く連載エッセイ、第7回。(サカナクション/新宝島)

友人と電車で揺られていたら、前に立っていた、まだ10代に見える女の子が
「わたし、付き合う前がいちばんたのしいんだよね」
「付き合うと、もう興味がなくなっちゃうんだよ」
と隣の男の子に話していた。
わたしはその彼を、てっきり女の子の彼氏だとばかり思っていたから、
「あら、どういう関係なのかしら」
と、つい聞き耳を立ててしまう。すると彼の方も
「そうなんだ。みんなそうじゃない? 俺もそうだし」
とにこやかに答えた。
そして電車がゆっくりと銀座駅で停車すると、ふたりは手を繋いで降りていってしまう。
「ねえ、今のってどういうこと?」
慌てて、隣の友人に小声で尋ねると、
「わたしも、どちらかと言えば片思いの段階がたのしい」
とすました顔で特に求めていない返事が返ってきた。
なんだか「そうじゃなくて」と混ぜっ返すのはもう面倒になってしまって、「人それぞれやね」と言っておく。
「人それぞれ」、この言葉を持ち出すのは「このお話はこれでお終い」の印である。
ひとりになった帰り道、なんとなく、自分はどうだろうと考えてみたけれど、片思いなんてちっとも好きじゃないなと思った。
遠くから「なんとかお近づきになれないだろうか」なんて悶々としたり、送ろうと思ったけれど断念してしまった下書きのようなメッセージが山のように溜まったり。そんなのは苦しいばっかりで、とうてい愉快な気持ちにはなれなかった。
やきもきしている「途中」の段階よりも、想いが通じた相手のためにプレゼントを選んだり、着ていく洋服を考えあぐねたり。
決まったものを大事にする方がずっとずっとたのしいように思うけれど、まあ、いずれにしてもやっぱり「人それぞれなんだろうな」ということで、考えるのはもうお終いにする。
だけど帰宅して、原稿に手をつけようと机に向かったところで、さっきの話をもう一度思い返している自分に気づいた。そして、なんだかじわりと喉の奥のあたりに苦味のようなものを感じる。
「わたしは、”途中”を愛せないんだよなあ」
パソコンの中の原稿に目をやりながら、たっぷりとため息をついてしまう。
なにも恋愛ばかりではなかった。
なにを隠そう、書くことを生業にしているくせに、わたしは「書いている最中」がこれっぽっちも楽しくないのだ。
途中を楽しめない、工程を愛せない。
思えば、うんと小さいころからそうだった。
母によると、「崩すならやりたくない」と頑なに積み木遊びをしない子どもであったと言うし、自転車に乗るのも、お人形遊びをするのもちっともおもしろくなかった。
そんなわたしが気に入っていたのは「砂絵」や「リリヤン」で、しかめっ面で大作に挑んでは、完成したそれらを飾って、いつまでもいつまでも惚れ惚れと眺めていたと言う。
わたしが好きなのは、「完成したときの快感」と「完成したもの」であって、その途中にはまったく興味が持てないらしい。
ただの面倒くさがり屋と言えばそうかもしれないけれど、本当はずっとずっとそれがコンプレックスだった。
すこし前、会社の隣の席の同じような仕事をしている同僚に、
「書くの、たのしいですか?」
と聞いてみた。その人は、
「ものにもよるけど……基本的にはたのしいです」
とやさしい顔で微笑む。
「基本的にっていうのは、全体の……8割ぐらいですか?」
と尋ねると、
「どうしたんですか、たのしくないんですか? 誰よりたのしそうなのに」
と笑われる。どうにも悲しくなって、
「書いてる最中はたのしくないですね……すこししか」
と、なんだかよくわからない見栄を張ってしまった。
人それぞれ、人それぞれ。おまじないで不安を封じ込める。

この仕事は好きだ。それは間違いがないのだ。
企画をまとめるのも、取材に出かけるのだってたのしい。
なにより読んだ感想をもらったときのうれしさったら。
文章を通して、誰かの代弁ができたり、役に立てたりすれば尚のこと、わたしは言葉で丁寧になにかを届けることを愛しているのだと、心から思ったりする。
だけど嫌いだ。好きじゃない。
書いてる最中が、もう苦しくて苦しくてしょうがないのだ。
水泳で息をせずに泳ぎ続けているような気分で机に向かっている。
筆にスピードが欲しいとき、要は、うまく進まないとき、わたしはよく手を止めて、息継ぎのように音楽を聞いたりする。
サカナクションの音楽は気分を高揚させてくれる曲が多くてどれもお気に入りだけれど、『新宝島』という曲は、いちばん好き、というのとはまた違って、わたしの中で、ちょっと特別な曲である気がする。
この曲を聞くと、とある「教え」を思い出すからだ。
丁寧に描くと
揺れたり震えたりした線で
丁寧に描く
と決めていたよ
――サカナクション『新宝島』
わたしが尊敬する、とある書き手は「移動距離」というような言葉を使いながら、こんなふうに教えてくれた。
書くうえで考えるべきは「読者をどこに連れて行きたいか、だよね」と。
それについてわたしは「ああ、きっとそうなんだろう」と本当に思う。
ただ「聞いてほしい話」を連ねているわけにはいかなくて、乱暴とは知りつつも「はあ」だとか「ほう」だとか、要は「読んだあとの心持ち」をつくっているつもりで書いている。
読んでくれる人を、日常や、読む前の場所とは違った場所に運ぶつもりで、文章を書いているのだ。
とはいえそれは、わたしだけの満足で終わっていることも多かろうけど。
書くときはいつだって、わたしには明確に読んでくれた人を連れていきたい場所がある。
見せたい景色だって、感じて欲しい心地だって、しっかりとある。
そしてそれは、本当は、自分がいちばん味わいたいものであったりもするのだと思う。
それだというのに、そこへ連れていくための列車の運転が、あるいは線路を敷く工事が、どうしてこうも辛いのか。
向いていない仕事を選んでしまった。ああ、明日にも辞めたい。
そんな考えを頭の隅に置きながら、うんうんと苦しんで原稿をおし進めている毎日で、こんなにたくさん抱えて、なにがたのしいんだかと自分を奇妙に思うことさえある。
どうしてこうなってしまったんだろう。
原稿の手を止めて(もうずっと止まっていたけれど)、ずっとずっと過去に潜ってみる。
そして思う。「母の仕業ではないだろうか」。
5年前に亡くなった母は、大層よく褒めてくれるひとだった。
絵を描けば「見たことのない発想」と、額に入れて飾ってくれ、習字を持ち帰れば「お手本よりもいい」と、やっぱり壁に飾ってくれた。
飛び出す絵本のようなものを自作した日には、「世界中のひとが欲しがる」と言ったし、わたしもそうに違いないと思った。
自分がつくったもの、自分が選んだもの、とにかくすべてが大好きで、そんなふうに自惚れるわたしのことさえ、母は「ゆかちゃんは、気に入るのが上手ね」と言った。
いま思えば、決して裕福ではない家庭で育ち、母の手作りか親戚のお姉さんのおさがりの服やおもちゃばかりに囲まれていたのに、わたしにはそのすべてが自慢だった。
家にあるもので何かをつくっては母に見せれば、母は「すごい!」と抱きしめて、「どこに飾ろうかしら」と言った。
すべての目的が、「母に見せること」になっていた。
打ち明け話になってしまうけれど、中学2年生のときのことだ。
美術の授業で制作する課題を、有名なコンクールに出すことになって、わたしは水彩画で「世界平和」を願うポスターを描いていた。
下絵と簡単な彩色が終わったところで、「なんだか凡庸だな」と思ったわたしは、わざわざ赤色の絵の具を購買部で買い足して、背景をすべて赤色で塗りつぶしてしまった。
なんだか、特別な「わたしらしさ」が欲しかったのだ。ところが、
「……あれ」
想像してた格好良さはそこにはなかった。
急いで水を乗せてスポンジに吸わせたり、雑巾で拭ったけれど、もちろん赤色は取り消せない。
「世界はひとつ。平和を祈ろう。」という文字の後ろで、空とビルが轟々と燃え盛っている。意図せず、とんだ「風刺ポスター」ができあがった。
無理にこすったせいで、水でふやけて紙はボロボロになってしまったけれど、提出日は明日に迫っている。
「どうしよう……」
自宅に持ち帰り、そっと広げて母に見せると、
「これは……」
とはじめて、時が止まったように黙って眺めていた。
「せめて、サインペンで下絵をもう一度上からなぞったら?」
そう言われ、わたしはサインペンで下絵を丁寧になぞっていく。
美術は、国語の次に好きな授業だったけれど、線をなぞるような細かい作業は大嫌いだった。
夕飯を済ませても作業は続いた。ようやくなぞり終わり、ところどころ白色を乗せていくけれど、真っ赤な印象は到底薄まらない。
潜水のような苦しい作業を続けるうち、休憩がてら横になったところで眠りに落ちてしまっていた。

そして翌朝目を覚ましたわたしは驚く。
絵が生まれ変わっているのだ。
手前の空やビルや街並みはふんわりとのどかな色合いなのに、ずっと続く空の彼方の向こうはうっすらと赤く染まっていて、遠くで迫り来る危険を知らせているようだった。
「世界はひとつ。平和を祈ろう。」
わたしが寝ている間に、このコピーにも命が吹き込まれていたのだ。
「お母さん!」
台所まで走ると、
「ごめん!そんなつもりなかったんやけど」
とお弁当を詰めながら慌てて母が謝る。
「なんで仕上げてくれたん?」
と尋ねると、
「だってお父さんに見せたら、『あいつ、なんか悩み事でもあんのか?』って言うから……」
ポスターが赤いこと以外、わたしには悩み事などなかった。
「ちょっとだけ白くしてあげようと思ったら、たのしくなっちゃって。ごめんね、叱られたらお母さんが謝りに行く」
なぜか母はたくさん謝って、わたしを送り出してくれた。
「謝ったりしなくていいのに」
わたしはとても晴れやかな気持ちで学校へ向かった。
そして。
数カ月後、その絵はコンクールで賞を獲ってしまう。
「お母さん!!」
半べそをかきながら慌てて事情を話すと、母は台所で呆然と立ち尽くしていた。
大阪の大きな施設で展示されると言うので、母とふたりで見に行った。
額に飾られた絵の下には、どこか偉い大人の人のコメントで
「強いメッセージ性を感じます。紙の質感に手を加えてるのもいい。遠くの赤い空に、ハッとさせられました」
と書いてあった。
最初はなんのことだかわからなかったが、何度も雑巾で拭ってボロボロになった様子を、その人は「紙の質感に手を加えている!」と感じてくれたらしかった。
なんて心の美しい人だろうかと思った。
「ごめんなさい」
飾った絵に向かい手を合わせて、母とふたりで頭を下げた。
悪いことをした。ズルをして表彰された。
「もう二度としません」
本当によくない。よくないことをしたのだけど、
「最高にいい絵やなあ」
とわたしは内心惚れ惚れとしていた。
そして、母の横顔を見て、やっぱり母もそう思っているのだろうとわかった。
お互い口には出さなかったけれど、帰りの電車で母はとても満足そうだったのだ。
思えば、母は、小学生のころからたっぷりと書き溜めたマンガや詩集を、誰にも見せず大人になり、娘のわたしにようやく「実はね」と打ち明け見せてくれたような人だった。
ひとり、つくる工程だけをたのしんできた。
特にマンガはプロのような出来栄えだったけれど、「誰かに見せた?」と聞くと、ううんと首を横に振っていた。「おばあちゃんは、お仕事で忙しかったからね」と言う。
わたしは、遠い日のお母さんなんだ。
母は、幼いころの自分にかけてほしかった言葉を、いつもいつもわたしにかけてくれていたのだろうなと思う。
わたしは、子どものころの母のぶんも、たっぷりたっぷり褒めてもらった。
そしてわたしが他所で褒められると、母は本当にうれしそうだった。
わたしはもっともっと褒められて、母を今日のようにいろんなところへ連れて行ってあげたいと思った。
丁寧に描くよ
揺れたり震えたりしたって
丁寧に歌うよ
――サカナクション『新宝島』
すごい! と褒めてもらえなくなって5年が経つけれど、相変わらずわたしは、書いたり作ったりを繰り返している。
母を失ったことで、悲しいけれどわたしの世界は広がった。
たくさんのひとに読んでもらいたい、だとか。
こういうひとに届いてほしい、だとか。
読んだあとに、こんな心持ちでいてほしい、だとか。
母の代わりに、もっとたくさんのものを求めるようになった。
だけど、なにかを完成させて「お母さん!」と大きな声で呼びながら立ち上がる瞬間の幸せがわたしには忘れられない。
一刻も早く作業を終わらせて立ち上がりたい、見てもらいたい、という一心で息を詰めて作業を続けてしまうのだ。
もっと息継ぎをしながら、ゆったりとしたクロールのように進めばいいのに。
プールサイドに手をかける瞬間だけに恋い焦がれてしまう。
早く終わらせたい。早く遂げたい。
だからこそ、その瞬間にたどり着いたときの喜びが、すべての苦しさを「なかったこと」にしてくれるのだけど。
この原稿もプールサイドが見えはじめ、わたしはようやくたのしくなってきた。
よく考えれば、そんなに辛くなかったようにも思うし、いい運動をしたあとのような爽快感さえある。苦しいばかりではなかったような気がしてきた。
書き進めていることには変わりないし、読み返せば、結構上手に書けているんじゃないだろうかとも思えてくる。それならそれで、一向に構わないのだ。
さて、わたしは何で悩んでたんだっけ。
この仕事が好きだし、たくさんの人に読んでもらえればいいなあと思う。
まあ泳ぎ方なんて、ひとそれぞれでいいじゃない。
実はわたしは泳げないんだけれど。
photo/ぽんず(@yuriponzuu)
『いつもJ-POPを聴いていた』のバックナンバー
#1「排水口とラブレター」(スピッツ/チェリー)
#2「22時の「なんでもないよ」」(宇多田ヒカル/Flavor Of Life)
#3「9年前から心に住む、不動産屋のあのひと」(槇原敬之/遠く遠く)
#4「決戦は4月30日。一番好きなあの子に会いに行く(DREAMS COME TRUE/決戦は金曜日)
#5「大人はスーパーマンじゃないけれど」(SMAP/たいせつ)
#6「ロマンチックとレコーダー」(aiko/アンドロメダ)
#7「泳ぐように、溺れるように、書いている」(サカナクション/新宝島)