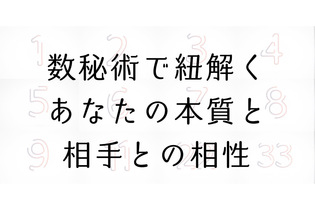ありがとう、と君に言われると
なんだかせつない
さようならの後も解けぬ魔法
淡くほろ苦い
The flavor of life
――宇多田ヒカル「Flavor Of Life」
22時の「なんでもないよ」
誰もが同じ音楽を聴いて、音楽がわたしたちを繋いだり、離したりした。そんな時代を過ごしてきた――。中前結花さんが、平成のヒット曲になぞらえていつかの思い出を語る連載エッセイ。第2回は、宇多田ヒカルの「Flavor Of Life」。「ううん、なんでもない」で思い出す、2組の夫婦のお話です。

2018年も暮れるころ、仕事を半ば無理矢理に片付けてしまって、そわそわとした気持ちと一緒に、わたしは横浜アリーナへ向かった。
しんと静かな中で、1曲目「あなた」が始まったときの、あの胸から湧き上がってくる、苦しいような緊張感と気分の高まりは、時間が経って思い返しても、ちっとも褪せない。
張り詰めた空気で、ホールがはち切れてしまいやしないかと不安なほどだった。
宇多田ヒカルのコンサートツアー。
本人にとっても、実に12年ぶりとなる久々のステージだった。
歌声を聞きながら、宇多田ヒカルの曲と一緒に過ごしてきた年月を思った。
小学生のころに出会った「Automatic」から20年。
いろんなことがあったし、きっと宇多田ヒカルにもいろんなことがあった20年だ。
そんなことを思っていると、目のちょうど半分あたりまで涙が押し上がってきて、下半分がうまく見えない瞬間が何度も何度も訪れ、「うまく見えない」のはあまりにももったいないから、わたしはその度、ワンピースの袖を引っぱっては一生懸命に涙を吸わせるのだった。
宇多田ヒカルの曲で描かれている主人公が、わたしは好きだ。
きっと「誰にも迷惑をかけられない人なのだ」と想像し、勝手に想いを寄せる。
どの曲に出てくるのも、相手のことをただ深く思っていて、それでも、無理に追いかけたり、胸の内をすべて告げたり、そういったことができずにじっと黙って堪えている人だ。
強くて弱くて、素敵だと思った。
久々のステージで披露されることはなかったけれど、わたしには、歌ってくれることを密かに期待していた曲があった。2007年に発売された「Flavor Of Life」だ。
この曲を聞くと、 ある2組の夫婦のことを思い出す。
***
大学生のころ、「ピンクのロングスカートのナース服がかわいいから」という理由で、わたしは毎日のように早朝から「整骨院」で働いていた。
整骨院を掃除して、学校に行って、夜はまた整骨院で働く。そんな日も珍しくなかった。
卒業したら、東京のテレビ局で働きたいと考えていたけれど、家具や家電を一式揃えたり、大都会のマンションに敷金を払ったりできるような裕福さが、わたしの家にはなかったのだ。
学校の勉強をしながら、3つのアルバイトを掛け持ちした。おかげでいつも眠かった。
その整骨院の先生は、とても変わった中年の男性だった。恰幅(かっぷく)と姿勢がとてもいい。
大きすぎる声で話すのは、ハキハキと早口で、どこか女性的な関西弁だ。
センターで分けられ撫で付けられた髪は、耳の下まで垂れ下がっているのに、後ろ姿を見ると耳の上まできれいに刈り上げられていて、他では見たことのないヘアースタイルだった。
金曜の夜は患者さんが少ない。
あまりにも眠くて、わたしは受付の椅子に座ったまま、つい居眠りをして前後にこっくりこっくりと揺れてしまう。カーテン越しにそのシルエットを見て、先生は
「中前さん、船漕いでるみたいやわ」
とよく注意をしてくれた。
「すみません」
最初は恥ずかしくて顔が熱くなったものだけれど、1年も経てば、「船よ、中前さん」と言われることに慣れてしまった。
やがて、見かねた先生は「出航よ!」と大きな声で言うようになったので、「すみません!」と大きな声で返して、その度にナース服の水兵は急いで港に戻る。
きっと、端から見るととてもおかしなふたりだった。
どうしたの?と急に聞かれると
ううん、なんでもない
――宇多田ヒカル「Flavor Of Life」
それにしても、来るかどうかわからない患者さんをただ座って待つ、というのはとても忍耐が試される仕事だったように思う。
お互いの眠気を紛らわせるために、先生とはよくカーテン越しに雑談もした。
「中前さんは、どんな音楽が好きなの?」
「歌詞を読むのが好きなので、日本語の歌がいいです」
「ふうん。最近いいと思ったのは?」
「宇多田ヒカルの、新しい曲が好きです」
「どんな歌詞か言うてよ。いちばん好きなとこ」
「2番のサビがいいんです。“どうしたの?と急に聞かれると、ううん、なんでもない”って歌詞があって。いいなあって……」
しまった、と心の中ですぐに後悔した。そうだ、先生は美容院帰りの常連の患者さんに
「うわあ、前の方がよかったですわ!」
と平気で言うようなひとだった。
先生は、何かを言い淀むことなどない。
「言いたいことが言えない、みたいな。切ない感じなんですけど……」
伝える自信をなくしたわたしが消え入るように言うと、
「言いたいことぐらい言うた方がいいのに。女の人って言わへんひと多いけど」
と言った。“女の人”と聞いて、わたしは先生の奥さんの顔を思い浮かべていた。
物腰がとてもやわらかなのに、キリッとした印象のあるエキゾチックな顔立ちの美人で、わたしはこの奥さんのことがとても好きだった。
いつも、失礼ながら「なぜ先生と……」と不思議に思ったものだ。
「でも、“言わさへん”というのが、時には大事やからね」
と先生は続ける。
「奥さんと出会ったときね、もう、都合なんて聞かずに、どんどんどんどん予定を入れて、奥さんのスケジュールをぼくが埋めちゃったの」
「どういうことですか?」
「勝手に決めちゃうんよ。映画やら舞台やら食事やら水上バスやら、全部先に予約しちゃうの」
「そんなことして、奥さん困りはったんちゃいますか?」
「困ったかもしれへんけど、律儀な人やから、予約してるものをすっぽかしたりはしない。そしたら自然といっぱい会えるでしょう。律儀な人が好きやからね。その作戦でええの」
そんなまさか。
奥さんが何度も何度も「ううん、なんでもない」と飲み込む様子を想像した。

帰って、炊事をしている母にまとわりついて、すぐにこの話をした。
「先生やっぱり変わってはるわ。わたしやったら、嫌やもん」
その頃、わたしには別のアルバイト先に好きな人がいて、その彼が海の底のように静かで落ち着いた人であったことを、なぜかうれしく思った。
母は、仕事をこなしながら「へえ」とか「まあ」とか相槌を打って最後まで聞いたあと、
「せやけど、嫌やったら行かへんでしょう。奥さんも、ちゃんとうれしかったと思うなあ。好きでもないのに、そんな勝手なことばっかりしてたら、水上バスから落とされてしまうわ」
と笑った。びしょ濡れで「出航よ!」と叫ぶ先生を想像してしまう。
「誘ってくれる、ってうれしいもんよ」
母は洗い物が終わるといつも、丸くてかわいい急須にお茶を淹れる。
聞きながらわたしも、そんなものか、と思えてくる。
たしかに海の底のようなひとが好きだけれど、このまま何の波も起こらないのはつまらない。
そして母は、恥ずかしそうにずいぶんと昔の話をした。
まだ会社勤めだったころ、職場にそっと憧れている先輩がいたのだと言う。
「食事に誘ってくれたりして、素敵な店を予約しておいてくれはるの。ますますかっこいいなあ、と思ったわ」
しかし、その男性はあるとき「家族のことが嫌い」と話したのだと言う。
「いろんな事情があるやろうから、それで嫌いになったわけではないけど、家族のこと『あんなもん』って言うたんが、なんか悲しかってん」
とお茶をすすった。
「お父さんは、絶対言わへんなあ」
「ほんまやね」
今では考えられないけれど、出会ったころの父は、あまり口数の多い青年ではなかったという。もちろん先々の予定を勝手に決めるわけもなく、
「映画を観に行くことになったけど、なんしょう? なんしょう? 言うて、いっこも決まらへんしなあ」
母は、20年以上過去の父にぼやく。
だけれど「優柔不断やね」とわたしが言うと、
「でもお母さんは、それが楽しかったなあ。一緒に決めるのも、うれしいもんよ」
と言った。
父がいないところで、「内緒よ」というように母はよく父を褒めた。
***
それから10年近くが経つ。
そういえば…… と急に思い出して、父に連絡しようと思った。
22時をすこし過ぎてしまったけど、起きているかしら。近ごろの父は早寝だ。
「お母さんと、初めて行った映画ってなんやったの?」
とメッセージを送る。母は数年前に亡くなってしまったので、父に確かめるしかないのだ。
珍しくすぐに返信が来たけれど、
「寅さんのことか? いや、違うかったかな?」
真相は闇の中だ。
母と出かけた映画や施設の半券をすべて保管している父が忘れているはずがないと思ったけれど、ふたりだけの秘密なのかもしれない。
「そう。参考に聞きたかっただけ」
と送ると、
「なんでや? デートか?」
と返ってくる。返事に困って、
「お母さんが褒めてたからさ」
と打ちかけてやっぱりやめる。なんだかもったいない気がして、
「ううん、おやすみ」
とだけ送った。
なんでもない、なんでもない、と出し惜しみしてみる。
だけどいつか、たとえばちょっとしたことで父が落ち込んでいるとき、この話をしてあげるのもいいなと内心思っていた。
たちまち元気になるのは間違いないだろう。
さようならの後も解けぬ魔法は、きっとあるとわたしは思う。
Photo/ぽんず(@yuriponzuu)
『いつもJ-POPを聴いていた』のバックナンバー
#1「排水口とラブレター」(スピッツ/チェリー)
#2「22時の「なんでもないよ」」(宇多田ヒカル/Flavor Of Life)
#3「9年前から心に住む、不動産屋のあのひと」(槇原敬之/遠く遠く)
#4「決戦は4月30日。一番好きなあの子に会いに行く(DREAMS COME TRUE/決戦は金曜日)
#5「大人はスーパーマンじゃないけれど」(SMAP/たいせつ)
#6「ロマンチックとレコーダー」(aiko/アンドロメダ)
#7「泳ぐように、溺れるように、書いている」(サカナクション/新宝島)