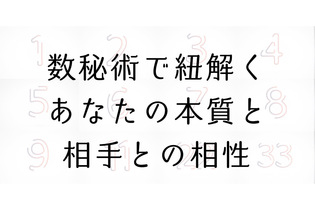9年前から心に住む、不動産屋のあのひと
反抗期だってなかったのに、珍しく不機嫌に揺れたあの春のこと。そんなときに、東京で一度だけ出会った不動産屋さんのこと。中前結花さんが、過去のヒット曲になぞらえていつかの思い出を語る連載エッセイ。平成最後となる今回は、槇原敬之の「遠く遠く」と、東京に越してきた9年前のお話です。

見上げると、空をピンク色が覆い隠してしまうほど桜が満開だった。
歩道橋を駆け下りながら、もう東京に出てきて9年になるのかとぼんやり思う。
今年は何かにつけ「平成最後」と騒がれる1年だったけれど、なんだか遠いことのようで、どれもちっとも実感がわかなかった。今になってようやく、「そうか、終わるのか」と、じんわり悲しいような気分にもなる。
時代が去っていく、という今まで知らなかった種類のさみしさだ。
だけど、毛筆で丁寧に書かれた「新しい元号」も、上品さと清々しさを感じて、すごくすごくいいと思った。
情が薄いのがゲンキンなのか、わたしは、なんでもすぐに気に入ってしまう。
ついこの前も、
「関西に帰りたい、とは思わへんの?」
と友人に聞かれた。
「東京、好きやからなあ」
と答える。
「駅の人全員が振り返るほど泣いてたくせに」
と、まるでつい最近のことのように9年前の春の話を持ち出されるから弱ってしまう。
わたしの上京は、涙涙の思い出だった。
新幹線のホームに舞った 見えない花吹雪思い出す”
――槇原敬之「遠く遠く」
反抗期なんて一度だってなかったくせに、その頃のわたしはちょっとばかり不機嫌だった。
東京で就職する、というのは自分で決めたことなのに、いざその日が近づいてみると、たまらなく不安でどうしようもなかったのだ。
友だちとの別れを考えると、辛さのあまり頭痛がしてしまうし、ちっとも勇気を出せないくせに随分長々とアルバイト先のひとに想いを寄せていた。「もう二度と会えないかもしれない」と思うと、焦りと諦めの気持ちが交互にモクモクと体の中で立ちこめてくる感覚に襲われる。
卒業シーズンらしく、テレビから槇原敬之の「遠く遠く」が流れると、チャンネルを変えた。
なにをするのも憂鬱であったし、なにより母と離れる自分を想像することができなかった。
わたしが、口を尖らせていつまでたっても準備を始めないせいで、
「東京に、部屋探しの旅行に行こっか。ふたりで行ったら楽しいよ」と母が誘ってくれた。
この頃のわたしは、母にはなにか特殊な能力が備わっているのではないだろうか、と疑っていた。
例を挙げればきりがないけれど、たとえば「友だちとごはん食べてくる」と言うと、「これを持っていけば」と大きな袋を持たされたりした。
「なんで?」と聞くと、「帰ってきたら教えてあげる」と笑う。
帰り道、その袋は見事に餞別のプレゼントでいっぱいになっていた。鈍感なわたしは、さぞ驚かせやすかったろう。
いくつかの送別会を開かれるたび、わたしは大きな袋を抱えて、泣きながら家に帰った。そんなわたしを母は、チャイムも鳴らしていないのに玄関先で「おかえり」と出迎えて肩を抱いてくれた。同じ人間とは思えなかった。
「ここの不動産屋さんを予約しようか」
「水族館もプラネタリウムもあるんやって。ここに泊まろうよ」
女学生のようにはしゃぎながら母が予約したのは、池袋の「サンシャインシティプリンスホテル」だった。娘の旅立ちがさみしくないのだろうか、と不思議に思う。
右も左もわからないふたりの東京旅行。池袋には不思議な格好の人たちがたくさんいて、どちらともなく「大阪の日本橋に似てるね」と言い合った。
予約していた不動産屋さんに向かうと、テキパキとした男性が「お待ちしておりました」と同時に椅子をふたつ上手に引いてくれた。
物件情報の束を見せてくれるけれど、紙をめくる速さが速くて追っつかない。これが東京のスピードなのだろう。
「ここが、いいと思います」
言われるがまま、車でそのマンションに向かうことになった。これもまた東京の速さだ。
駐車場で車を停めるとき、バック駐車のハンドル捌きが見事で、「わあ、すごい」と母が言うと、「そうでしょう」とミラーに得意そうな顔が映った。
考えていたよりも、家賃が1万5000円ほど高いけれど、新築の部屋はどこもかしこも真っ白でピカピカだった。オートロックで、ゴミ捨て場も住人しか入れない。ツヤツヤの洗面台は、覗き込むと自分の顔が写りそうだった。
「ここにしましょう」
急すぎやしないかと思ったけれど、断る理由も見つからなくて困ってしまう。
「あの……ここは、どこですか?」ようやく尋ねると、
「タバタです」
「タバタですか……」
余計に困ってしまった。タバタとは何なのだ。
すると、母は手帳の後ろに付いている東京の路線図を見ながら、
「なるほど、山手線に乗れば1本で会社に行けるんですね」
と知ったようなことを言って、
「お母様、その通りです!」
と、得意そうなひとは、もっと得意そうな顔をしていた。タバタとはいったい何なのだろう。
帰り際、「駅まで歩いてみてもいいですか?」と母が提案して、ふたりで駅までの10分ほどの道を歩くことになった。こじんまりとしたスーパーがあって、小さい商店が並ぶ通りを、並んでふらふらと歩く。
アーケードをくぐり抜けて駅に着くと「田端」の文字が見えてきた。
「ああ書くのか」
「ああ書くのよ」
田端か。悪くないなと思った。
「明日の夜までに決めます」と得意なお兄さんには伝えて、すこし考えることにする。

翌日、ふらりと別の不動産屋にも入ってみた。小柄なおじさんと若いお兄さんが「兵庫県からいらしたんですか」「どんなお仕事をされるんですか?」と、部屋を見せる前にいろいろと話を聞いてくれた。
若いお兄さんの名前は「新家さん」といった。
「にいや」ではなく、「しんけ」と読むのだそうだ。
「このお仕事にぴったりですね」と言うと、「ちょっと恥ずかしいんですけどね」と照れるようにくしゃっとなった笑顔を見て、なんだかいいひとだなと思った。
話をするうち、
「シャクジイコウエンっていう駅があるんです、ここなんてどうでしょう。見てみませんか?」
と聞く。きょとんとするわたしの様子を見て、
「石の神様の井戸、と書きます」
と言ってくれた。わたしは「どう書くのか」にこだわるところがある。
「西武池袋線にも乗ってほしいので」と新家さんに連れられて、電車で向かうことになった。
移動中、新家さんとはいろんな話をした。実家が石神井公園の近くであること、社会人4年目であること、本当は他に就きたい仕事があったけれど、今はこの仕事が気に入っていること。
「石神井公園」で降りて、駅まで歩く途中、道の向こう側におせんべい屋さんがあった。
「あそこ、おいしいんです」と新家さんはそんなこともおしえてくれる。
しばらく歩くと、部屋についた。築8年の木造だけど、しっとりとやさしい佇まいだった。
鍵を開けてもらうと、ひんやりとした空気と広々とした床が広がっていた。2階建ての2階で、予定より1万円も安い。小さい押入れがあって「ふすまを外してもいいかもしれません」と新家さんは言った。
そして「工作台にするのはどうですか?」と提案してくれる。身につけるアクセサリーはほとんど自作していることを伝えたからだ。
「いいかもしれない」
東京に来てはじめて、うれしい気持ちで「ぽっ」となった。出窓とは言えないけれど、窓枠の手前にちょっとした余裕があって、ここには花瓶を置くのがいいだろうと思った。
「ここに花瓶を置くのはどうですか?」
と新家さんが言うから、「ふふふ」といっしょに盛り上がった。
帰り道、「おせんべい、買って帰る?」と母が言って、立ち寄ると、お店はお休みだった。「ごめんなさい、本当にすみません」と、新家さんはとてもすまなそうに謝った。なんにも悪くない、とふたりでぶるぶると首を振った。
遠方だと何かと面倒なので、今晩には部屋を決めて、明日の朝に契約をしてから兵庫に帰ることになっていた。
すこし悩んでいるふりをしたけれど、心の中で本当はもう決まっている。
あの押入れの下段には好きな本をたくさん蓄えて、上段ではコレクションしているボタンをたくさん並べて工作しよう。帰省のときには、おせんべいを買って帰ろう。
あの街に住むのか、電車に揺られながらそんなことを考えていた。
ところが、池袋についたとき、駅の出口で若い男性と中年の男性が「ついてくるなよ!」「お前だろうか!」「ずっとつけて来てるだろ!」と大きな声で口論をしていた。片方が掴みかかり、たちまち殴り合いになる。
わたしは人が人を殴るのを初めて見た。標準語に慣れていなかったこともあり、怖さで思わず足が固まってしまう。
「物騒ですね、行きましょう」
慣れっこなのか、新家さんがとても頼もしかった。
その夜、池袋のロッテリアで母と向かい合って座っていた。
わたしが口を尖らせて黙っていると、
「石神井公園がいいんやろ?」母は言った。
「でも怖くなっちゃった?」母はやはりエスパーだ。
さっきの殴り合いが、わたしには恐ろしくて堪らなかった。ここは、ぼんやりとのどかな兵庫の山奥とは違って、東京なのだと改めて思い知る。
違うのは、速さばかりではない。窓の下を覗くと、夜だというのにちっとも暗くなくて、大勢の人が途切れずに無関心そうに行き交っている。
「オートロックがいいかもね。2階じゃ不安かもね」
母がぽつりと言って、すこし黙って考えたあと、
「そんな気がしてきた」と答えた。
一度しか降りたことのない石神井公園の駅を思い出すと、なんだかとても切なかった。
得意顔のお兄さんに電話すると、
「いやあ、絶対にいい部屋ですからね! いい選択ですよ! 明日いらしてください!」
と快活に答えてくれた。このひともまた、いいひとだと思った。
そして新家さんには、断わりの電話をしなければいけなかった。
もう一方と迷っているという話はしていたけれど、あんなに気に入った顔をして断るだなんて、とんでもない大人になってしまった気分だ。
「お母さんが電話してあげようか」と母が言ってくれる。
「ううん。自分で言う……」
これまではなんでも「うん、お願い」と言ってきたけれど、これからはそういうわけにはいかないんだから。
営業所に電話をすると、すぐに新家さんだと声でわかった。
「今日はありがとうございました、すごく悩んだんですけど」
「はい。お部屋、決まっちゃいましたか?」
と向こうから言ってくれた。それも極めて明るくやさしい声で。この人もまたエスパーなのかもしれない。
「そうなんです……」
「あの、僕が言うのはおかしいんですが、やっぱりオートロックがいいと思います」
「え?」
「初めてのおひとり暮らしですし、今日お母さまともお話しさせていただいて、ひとり娘を東京に、ってどんなに心配な気持ちだろうって思ってしまって……。不安にさせるのは良くないと思いました。田端、すごくいいところだと思います、僕賛成です。駅の近くに小さいお寿司屋さんがあるんです。おいしいですよ。安心して、お仕事頑張ってくださいね」
涙が出てきてしまった。
突然泣き出す娘を、母はコーヒーの入った紙コップを持ったまま飲まずに、眉をひそめて見ている。
「ごめんなさい」
泣きながら言うと、
「いえいえいえ、こういう仕事なんです。大丈夫ですから。また思い出したら、おせんべい買いに行ってみてくださいね。東京、きっとたのしいですよ。では」
電話を切って、涙をいっぱいこぼしながら
「オートロックがいいと思うって。田端いいところだって。お寿司もあるって。仕事頑張って、って言ってくれた」
と伝えた。
すると、言い終えたその途端、今度はわっと母が泣き出したものだから、わたしは驚いてしまう。
「東京にもいい人いるんやね。すごくいい人やったね。お母さん安心したわ。ゆかちゃんも、新家さんみたいなお仕事ができるといいね」
母はわたし以上に不安だったのだ。
母は昨日、長い人生ではじめて「東京」という街にきた。洗濯機を回したこともないひとり娘が、「東京で仕事をする」と言い出した。
平気なはずがなかったけれど、鈍感なわたしにはそれがわからなかった。
物件探しをしていて、下見したひとつの物件を断った。
ただそれだけなのに、不安でひたひたになっていた母と娘の心を「東京でも、なんとかやっていけるかもしれない」とポッと暖かい火が乾かしてくれるような出来事だった。
新家さんは、向き合う正面には立たず、隣にそっと立ってくれるようなひとだった。わたしもこんなふうに仕事がしたい、と心から思った。
今でも仕事をしているとき、わたしの心の中にはいつも、一度しか会ったことのない「新家さん」に住んでもらっている。
9年経っても、わたしはこの夜のロッテリアでの出来事をずっとずっと忘れない。
大事なのは “変わってくこと” “変わらずにいること”
――槇原敬之「遠く遠く」
その2カ月後、3月の終わり、わたしは東京に越してきた。
たくさんの友だちが見送ってくれ、我慢していたのに、駅のホームで友だちのひとりが泣きそうな顔になり、それを見ると堪えられなかった。今生まれた赤ん坊のように大きな声をあげて泣き始めるわたしを、母は無理やり新幹線に押し込めた。
友だちからもらったたくさんの餞別の中には、「泣いちゃうCD」なる意地悪なものが入っていて、上京ソングがたくさん入っていた。その中にもやっぱり、「遠く遠く」が入っていて、「ちょっと古いなあ」と思ったけれど、聞けばいちばん涙がこぼれた。

田端にひとりで越してきた。
白くてぴかぴかの部屋。まだ家具も家電もなにもない。床にはダンボールが4つと大の字になったわたしが転がるだけだ。
毎日、朝ここで目を覚まして、毎日、ここへ帰ってくるんだ。そう考えると不思議な気分だった。
横になっていると、ベランダの塀の上には水色の空がめいっぱい広がっていて、塀の下とコンクリートの隙間からは、明治通りを挟んだ向こう側に並ぶ桜のピンクがチラチラと見えた。
「へえ」
と、裸足のままベランダに出て、塀の手すりにグッと胸を寄せて、景色を見渡してみた。
「え」
遠く向こうだけど、つまようじの頭ぐらいの大きさで光る、作りかけのスカイツリーを見つける。
「この部屋にしてよかったかもしれない」
故郷に恋しいものをたくさん置いてきてしまったけれど、この先、ここでもまた同じぐらい恋しいものができるかもしれない。そう思うことにしようと思った。
まずはベランダ用にスリッパを買おうと考えていると、携帯電話が鳴ってメールが入った。自分の目を疑う。想いを寄せていた、バイト先の彼だった。めずらしい出来事にハラハラと胸を打つ音が早くなる。
バイトを卒業する日、同じく就職していくメンバー4人で集まって、小雨の中、近くの山をすこし登って夜景を見に行った。車に戻る途中、彼と目があって、何か言いかけたけれど、何を言えばいいのかわからなくなって、わたしはそのまま目を伏せて「雨冷たいな」と言った。
最後のチャンスをふいにして、わたしの永い恋は、その日終わった。
どうしたんだろう、とメールを開く。
「研修先が決まって、東京で受けることになりました。来週にはそっちに越します。
もし会えたら。なんかこの前、話し足りなかったような気がしました。
迷惑じゃなければ。それでは。
仕事頑張れ。」
携帯電話を胸に抱きしめて、ベランダの塀を肩で擦りながら、ヘタヘタとしゃがみこんだ。
引き寄せた膝に顔をうずめて、思わず「ひゃあ」と叫ぶ。
なあんだ、ちゃんと春じゃないか。
そのまま屈伸をして、もう一度手すりの外を見ながら背伸びをすると、桜のピンクはさっきよりも、うんと濃く見えた。
スリッパを買いに行こう。ピンクのカーテンも買おう。空はどこまでも広くて、これからのすべて、どんなことも上手くいくような気がした。
今度こそ、なにか言えたらいいなあ。
何もかも遠く遠く離れたわけではなかった。
お祝いだと母に買ってもらったコートとお財布だけをひょいと持って、わたしは部屋を出た。「カチャンッ」と鍵が閉まる音が響く。そんなことにも「おおお」と感激した。
新家さんの言うとおり、「東京はたのしい」のかもしれない。
「あ」と、ふと思い出して、カーテンとスリッパを買うのは明日にすることにした。
「そうだ、おせんべいを買いに行ってみよう」
早く母に送ってあげたい。
風が吹いて花びらが舞う明治通りを早足で歩いた。
風は向かい風なのに、まるで空を飛んでいるような気分だった。

Photo/ぽんず(@yuriponzuu)
『いつもJ-POPを聴いていた』のバックナンバー
#1「排水口とラブレター」(スピッツ/チェリー)
#2「22時の「なんでもないよ」」(宇多田ヒカル/Flavor Of Life)
#3「9年前から心に住む、不動産屋のあのひと」(槇原敬之/遠く遠く)
#4「決戦は4月30日。一番好きなあの子に会いに行く(DREAMS COME TRUE/決戦は金曜日)
#5「大人はスーパーマンじゃないけれど」(SMAP/たいせつ)
#6「ロマンチックとレコーダー」(aiko/アンドロメダ)
#7「泳ぐように、溺れるように、書いている」(サカナクション/新宝島)