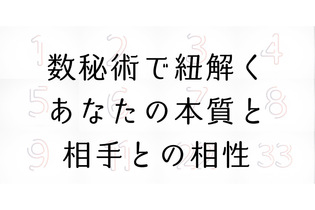12月、“結果”が出るそのときに思うこと
駆け抜けた1年を振り返る季節。そして、闘いの“結果”を突きつけられる季節。勝てなかった悔しさも、その悔しさを「温泉でも行こう」と癒しあう尊さも、大人になった私はちゃんと知っている。エッセイスト 中前結花さんがJ-POPになぞらえて書く連載エッセイ。(WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜)
引き出しの奥へと手を伸ばす。
たまにはこうして肩を並べて飲んでWOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜/H Jungle with t
ああ、あれだって紅白に出たんだっけ、と振り返る。200万枚以上を売り上げたヒット作だもの。それは当然の結果だろう。
あのころ、「紅白歌合戦」はきっと、今以上に特別で大きな「12月の結果発表」だったろうと思う。出る人にとっても見る人にとっても、それはそれは大きなご褒美だった。
「WOW WAR TONIGHT ー」は小室哲哉が手がけた作品の中でも3番目によく売れた曲で、他曲と比べると、やけに「リアル」なのがおもしろい。描かれているのは、美しい男女の恋愛ではなく、大人の男の哀愁と葛藤、そしてすこしの「悦」だ。
当時は幼くてこの歌詞の良さはわかっていなかったけれど、いま読み返すと、なんと胸の奥をぎゅっと握り掴んで、ギシギシと揺らす歌詞なのかと唸ってしまう。
温泉でも行こうなんて いつも話しているWOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜/H Jungle with t
「落ち着いたら温泉でも行こう」と仲間と話しているこの主人公は、この先もきっと、温泉には行かない。
熱海や箱根くらい、すこし無理をすればいくらでも行けるはずであっても、彼らはの温泉旅行は決して実現しないのだろうな、とぼんやり思う。
大人にはどうやら、毎日の暮らしを乗り越える中で、お酒を片手に体を寄せ合って「温泉でも行けたらな」と言葉を掛け合う癒しがあるらしい。そしてお決まりの文句は、なんだか年々愛おしいものになる。
お決まりの話題、というのもまたいいものだ。
長いか短いかわからない人生、なにかをはじめるのに「遅すぎる」ということなどないのだとよく教わる。
流れる景色を必ず毎晩みているWOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜/H Jungle with t
今年も12月になった。
そんな闘いの数年間を終えて、あの先輩たちは、今年のこの月をどんなふうに過ごすのだろうか、とふと思い、そしてすぐに、自分を反省する。
この1年もあの人たちは懸命に活躍していたから、きっと毎日は忙しいに違いないのだ。
年末に訪れる結果は、なにもあの煌びやかな決勝のステージだけではないんだから。
どうか、それぞれに良い結果の出る、実りのある12月でありますように。
そんなことを考えながら、黒いタイツの足で、わたしは駅の階段を駆け下りていた。今年の終わりも、わたしは愛しい人たちにたくさん会いたい。
Photo/ぽんず(yuriponzuu )
『いつもJ-POPを聴いていた』のバックナンバー
#1 「
排水口とラブレター 」(スピッツ/チェリー)
#2 「
22時の「なんでもないよ」 」(宇多田ヒカル/Flavor Of Life)
#3 「
9年前から心に住む、不動産屋のあのひと 」(槇原敬之/遠く遠く)
#4 「
決戦は4月30日。一番好きなあの子に会いに行く (DREAMS COME TRUE/決戦は金曜日)
#5 「
大人はスーパーマンじゃないけれど 」(SMAP/たいせつ)
#6 「
ロマンチックとレコーダー 」(aiko/アンドロメダ)
#7 「
泳ぐように、溺れるように、書いている 」(サカナクション/新宝島)
#8 「
恋は、たとえば引いた下線を見せ合うような 」(星野源/恋)
#9 「
12月、“結果”が出るそのときに思うこと 」(WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜/H Jungle with t)
ライター、エッセイスト。ものづくりに関わる、人や現場を取材するインタビュー記事と、これまでの人生や暮らしの「ちょっとしたこと」を振り返るエッセイを中心に執筆。兵庫県うまれ。https://twitter.com/@merum...