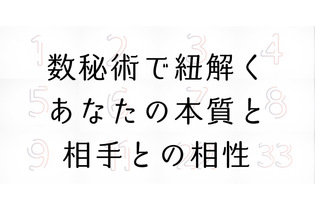大人はスーパーマンじゃないけれど
「30代への突入。我ながら、難しい年齢に差し掛かったなと思う。いったい『大人』ってなんなのだろう」――。エッセイスト・編集者の中前結花さんがSMAPの『たいせつ』にのせて綴る、通勤電車で起こったある事件と当時の上司のこと、それから、大人になるということ。

職場で、
「◯◯さんに相談して、こうすることにしました」
と報告を受けることが多くなった。
「そう。それはいいね」
と口では「わかったよ」というふうに言うけれど、実のところはそう言いながらも、心のうちに、ふぅっと微かに小さな竜巻のようなものが舞う。
その竜巻の正体。
それはきっと、
「自分が、いちばん最初に相談する身近な相手ではなくなった」
ということに未だに慣れずにいる違和感なのだろうと、察しがついたのはつい最近のことだ。
踏ん張りながら毎日を生きていれば、年齢は重ねるし、立場も変わる。今では編集長としてメディアをまとめたり、メンバーを率いたりする身だ。
だけども、なんだか慣れない。うまく大人になれていない。
どうにもそんな気がして仕方ないのだ。
肩を落として落ち込むほどではないけれど、そんな戸惑いと小さな小さな憂鬱が、このところ、そっと両肩にもたれかかって離れてくれない、と感じることが多くなった。
振り返れば、「相談する側」から「相談される側」に回るのはずいぶんと楽だった。
一通り経験したことや、自分なりに考えてきたことを、「こうじゃないかしら」なんて、したり顔で話す。「そうですね!」と言われれば得意になったし、「本当にそうですか?」と言われれば、ちゃんと不安になった。
それでも負けじと一生懸命考えて、わたしだって前に進んでいるぞ! と、みなぎる何かでいっぱいに満たされるのだ。
だけど今はちがう。
ちゃんと「相談される人」が「相談する人」に応えられているか、を路傍の石のようになって我慢して眺めている。
そして、その応えのひとつひとつに「なるほど」だとか「たしかにそうかもしれないな」とたくさんの新鮮なことを知る。
いつからかわたしは教えてもらうことばかりになっていた。それはもちろん大きな喜びでもあるけれど、わたしが見てきた大人たちも、本当にこんな感じだったんだろうか。
30代への突入。我ながら、難しい年齢に差し掛かったなと思う。
同じ歳のAKBのメンバーはとうに卒業してしまったし、けれども仲間との飲み会に顔を出せば「若い人が片付けて」とお腹いっぱいお肉を食べさせてもらえることもある。
恋愛も結婚も出産も夜遊びも、そして離婚までも、「今がぴったりだ」「そういう年頃でしょう」と言われたりする、奇妙なお年頃なのだ。
もうすこし経てば、いっそ楽になる気がして、「早くもっと大人になりたいなあ」と子どもじみたことも思う。でも、電車で席を譲られて「結構です」とご立腹の祖父母世代の姿を見ると、いくつであっても、置かれる立場と心のちぐはぐに戸惑ってしまうこともあるのだろう、と考えたりもする。
だって、人は何歳になるのもはじめてだからだ。

会社帰り、飛び乗った終電の京王線に揺られながら、堺正章に「いつまでもアイドルと言われるのは、つらくない?」と尋ねられたときの、香取慎吾の顔を思い出していた。
ずいぶんと真っ直ぐとした目で、「そういうことではないのだ」「求めてもらえる限り、求めてくれる人を支えるのだ」というようなことを丁寧に伝えていたように思う。
思えばSMAP以前、「アイドル」とは、10代から20代にほんのすこし差し掛かった頃合いまでの、みずみずしくて未成熟な、だからこそ美しく魅惑的な少年少女を指していた。
「グループ」とは多感な年齢のいっときを共にし、互いの足りない部分を補完するものであったし、「ファン」の多くはその儚さを愛おしく思ったりしたのだろう。
だけど、彼らによって塗り替え続けられる常識と功績が、すべて変えてしまった。
年齢なんて、先人たちがつくってしまった目安でしかないのかもしれない。
SMAPは、よくそのことを教えてくれる人たちだった。
ドラマならこんなとき、疲れた顔が景色と一緒になって電車の窓に映ったりするんだろう。
「わたしはこれでいいのかしら」
と、窓に映る自分の姿に問いかけたりしてみたい。
だけど現実の満員電車の中で、窓にしっかり顔が映っているという状況というのは、極めて運がいいと言えると思う。誰かと誰かの背中の狭間で、かろうじて携帯を操作しながら帰るのが常だ。
自分のことは棚に上げて、「みんなこんなに遅くまで何をしているんだろう」と毎晩わたしは不思議に思うのだった。
そういえば、SMAPの「たいせつ」という曲はおもしろいことを言っていて、渋滞で進まない車の中で、なぜか彼女が楽しそうだ、という描写がある。
聞けば、その彼女はこう言うのだ。
ささやかでもそれぞれに暮しなのね
――SMAP「たいせつ」
わたしはよくこのフレーズを、満員電車の中で思い出す。
ここにいる全員に、そしてここにいない全員にも、間違いなくそれぞれの「人生」や「暮らし」がある。
たとえドラマチックとは程遠いとしても、それぞれの物語の主人公として、それぞれに時間と出来事を重ねて、いま同じ時間に同じ電車に揺られているのだと思うと、それはとてもおもしろいことのように感じる。
目の前のおじさんだって、かつてはお兄さんだったし、坊やだった。
頑張ったり、ズルをしたり、聞けば涙してしまうほど気の毒なこともきっとあっただろう。
そんないろいろを経て、おじさんは大人になって、今から自宅に帰るのだ。
「それぞれに暮らし」。
他人に憤りそうになるときや、妙に人を羨ましく思ってしまうときにも、心を落ち着けるのにとても便利な言葉だった。
そんなことを考えていると、悪い癖で、ついつい立ったまま眠りそうになる。
東京の電車に揺られること9年。
そういえば上京して1年目のあの日も、わたしは電車の中で立ったまま眠っていた。
***
2011年の1月。
その頃のわたしは、活気あるIT企業でようやく希望した部署に配属されたばかりとあって、とてもとても張り切っていた。
新しい上司のことを、母には電話で「東京丸出し! みたいなハンサム」と説明した。仕事に厳しく、近寄りがたい。ひんやりとクールなタイプのハンサムだった。
時間の使い方、手際、机の上の小物のセンスまで、なにもかも洗練されているように見える。
打ち合わせの準備が悪い人は、その上司に「時間を大事にしてください」と指摘された。
先回りして提案したとき、準備がいいときは、「素晴らしい」と低い小声でその人はつぶやく。
わたしはなるべく「素晴らしい」ように、とにかく毎日張り切っていた。
その上司は、新卒1年目のわたしにも必ず敬語で話し、決して私語はしない。それがさみしくもあり、なんだかキリリと見えて格好よかった。
それでいて、他部署の人から「新卒のプランナーだと不安だ」と言われてしまったわたしのことを、「立派なプランナーで、うちのエースです。失礼な言い方はやめていただきたい」と庇ってくれたりもするから、卑怯だ。
わたしは「完璧」を地で行く上司に惚れ惚れとして、毎晩、母に「今日も、東京っぽかったわ〜!」と電話で報告しながら、最寄りの駅から自宅マンションへと跳ねるように帰った。
そんなある日。
その日も一日ずいぶんと張り切っていて、わたしはクタクタだった。
山手線の車内、イヤホンで音楽を聞きながら、立ったまま浅い眠りに落ちていて、
「田端〜 田端〜」
という声で目が覚め、「あっ!」と急いで閉まりかけのドアからスルリと降りた。
「よかった」そう思いながら、動き出そうとする電車のドアを振り返ると、窓ガラス越しに、たっぷりと艶のある「馬のしっぽ」のようなものを持っている男性の手が見えたのだ。
「馬……?」
不思議な思いで、電車がスピードを上げて走り去っていくのを見送ると、突然首もとにひやりと風の冷たさを感じる。
「えっ」
急いで首の後ろに手をやった。わたしの腰まで伸びていたロングヘアは、肩の上でパツリと切られてしまっていた。あの馬のしっぽは、わたしが数年間大事に伸ばしてきた髪だったのだと気づく。
知らない人に、結った髪を突然バッサリと切られた。
帰ることもできず、わたしは何度も手の感触で切られてしまった毛先を確かめながら、混乱と恐ろしさで、しばらく呆然と駅のホームに立ち尽くしていた。
母にはとても電話できなかった。
「東京は最高なのだ」という話しかしてはいけないと思っていたし、母はわたしの長い髪を愛おしそうに撫でることが多かった。
ようやく、そろりと駅のベンチに腰をかけて、買ったばかりのiPhoneで「電車 髪 切られる」と検索してみる。
「電車で髪を切られました!」と書いている知恵袋の投稿にたどりついたことで、いくらか気分が落ち着いた。
「そうか、たまにあることなのかもしれない」
何しろここは東京だ。毎日、わたしの知らないことばかり起こる街であるし、よくよく考えてみれば、そろそろ髪を短くしたいと考えていたような気もする。
切られてしまったものはしょうがないのだ。
いいきっかけになったから、週末に美容院でちゃんと切ってもらえばいい。あまり深く考えないようにと、早足で踏みしめるようにいつもの道を帰った。
自宅でそうっと鏡をのぞいた時は、やっぱりショックだったけれど、両親にざんばら頭を見せずに済んだことを考えると、かえってひとり暮らしでよかった、とさえ思った。
「大丈夫、大丈夫」
わたしは翌朝も変わらず、張り切って会社に向かうことにした。

定時よりも早く出社してせっせと資料をつくっていると、ふわりといい香りがして、ハンサム上司が後ろを通った。
「おはようございます」
わたしは例によって張り切って挨拶をしたけれど、上司から返事はなかった。
「あれ……」
と手を止めると、上司はそっと横に立っていて、じーっとわたしを見つめたあと、
「……髪。どうしたんですか?」
と静かにたずねた。はじめての私語だった。
「あ、昨日電車で知らない人に切られてしまって。週末にちゃんと切りに行きます。変な髪型ですみません……」
そのとき、その人は怒りと困惑を混ぜたような顔をしていて、
「そういう日はね、休みなさい」
と言った。
「でも、今日までの仕事があったので」
と続けると、
「そんなことは、いいんだよ」
とため息をつくように言う。敬語ではなくなっていた。
「警察は? 友だちには言った? 家族には? ひとりでそのまま帰ったんじゃないよね?」
「いえ、ひとりで知恵袋で調べて。それで……帰りました」
「どうして」
「心配かけるし」
「だけど平気なわけがないでしょう」
「大丈夫です」
「本当に?」
「でも……もう、大人なので……」
「まだ大人ではないんじゃないかな」
「……」
「会社やぼくは、関西のご両親から預かっているつもりでいるんだから、これからは、そういうとき、誰かに連絡をしなさい。ぼくでもいいので。まだ大人になんてならなくていい。あまりにもかなしいとき、ひとりで帰ってはいけないよ」
そんなことを言われると、なんだか急にかなしくなって、わたしは涙を堪えようと天井を向きながら話したけれど、ぽろぽろと目の両端から粒になって、たくさんの涙が頬の上を過ぎて行った。
いったいぜんたい、なぜだろう。
昨日のわたしはずいぶん落ち着いて大人びていたのに。
上京してからというもの、東京に慣れるため、希望の部署に異動するため、とずいぶん気を張り続けて背伸びしていたけれど、「まだ大人ではない」と言われたことで、「なんだ、そうだったのか」と安心したのかもしれない。
結局その日は上司の計らいで帰らせてもらい、美容院で思い切ってショートのボブにした。
美容師さんには「自分で切って、失敗してしまったのだ」と話した。
詳しく説明すると、また泣き出してしまいそうで心配だったのだ。
翌朝も張り切って会社に行くと、上司はもう席でカタカタと仕事に取り組んでいた。
「おはようございます」と着席すると、上司はコロコロとキャスター付きの椅子で席の近くまで寄ってきて、「短い方がいいじゃない」とだけ言って、またコロコロと自席に帰ると仕事に戻った。心憎いほどの完璧さ。
わたしはこのとき、ああ、この人に褒めてもらうために毎日を頑張ろうと思った。
以来わたしを仕事ばかりの人間にしてしまったのは、この上司であったのだ。

時は流れ、転職も繰り返し、もちろんわたしの今の上司は彼ではない。
それでもずいぶんと長い間目をかけてもらって、仕事を変えるときは必ず相談したし、片思いの相手へのメールの文章を代筆してもらうほどの仲にもなった。
不満を並べると、「きみが悪い」とよく叱られもした。
会社を辞めて数年が経ったとき、お酒を飲みながら
「1〜2年目の頃は、ちっとも話しかけてくれなくて、ずいぶん怖かったですよ」
と話すと、
「すごく焦ってていっぱいいっぱいだったんだよ。歳上の部下に囲まれて、どうしていいのかわからないことも多かった。感じの悪い奴だと思われてるのもわかっていたから、帰りには落ち込むしさ」
と語ってくれたのが意外だった。
「まだ子どもだったから」
と上司は言った。
思えば、たしかに、わたしを除く全員が、その上司よりも歳上のチームだった。
相手に厳しくすることは、自分を厳しく追い込むことだ。
「時間を大事にしてください」
と注意するとき、本当はどれほど怖かったろう。今ならそれがよくわかる。
澄ました顔をして、みんなと同じ壁にしっかりとその人もぶつかりながら暮らしていたのだった。
そんなことを思い出していた。
ひとは Supreman じゃない
Superman じゃない
Superman じゃないけれど
――SMAP「たいせつ」
ゆるやかに速度を落として、電車が最寄駅のホームに滑り込んで行く。たくさんの人だかりと一緒になって、扉から吐き出され、みんな「今日もやり終えた」というようにそれぞれの背中でそれぞれの家に帰って行く。
こうやって、毎日の「暮らし」を積み重ねて時間は過ぎていくんだけれど、いったい「大人」ってなんなのだろう。
当時の上司と同じ歳になった。
あのとき、その人は23歳のわたしを「預かっているつもり」と堂々と言ってくれた。わたしはそんなことを言って安心させてあげることはできるだろうか。
当時のことを、その人は振り返って「まだ子どもだったから」と言ったけれど、そんなふうには到底見えなかった。
いまのわたしはどうだろう。人の目には、どんなふうに映っているんだろうか。
そんな想いを背負って、とぼとぼと帰るわたしの暮らしもまた、わたし以外は誰も知らないものだ。
だけどひとつだけ。その上司を真似ているうち、自分の癖になった習慣がある。
「今いいですか?」と聞かれたときは、パソコンから手を離し、必ず体ごと相手に向き直す。どんなに忙しくても、それはそうしなければいけないと自分で決めていることだった。
してもらってうれしかったことを、返していくターンに差し掛かっている。
そして、今のわたしを支えてくれるもっと大人の人たちもいて、その人たちの苦労を、わたしはまだ知らない。
人は何歳になるのもはじめてなのに、みんな「平気」のような顔をして、その人だけの暮らしを一生懸命積み重ねながら生きているんだ。
苦しくもあるけれど、前を歩いてくれていた人たちがいることは、どれだけ心強いことか。
「人間って偉いよなあ」
そんなことを思いながら、今日も月の下を歩く。
誰もスーパーマンじゃないけれど、いつも主人公を頑張って、本当に偉いのだ。
イヤホンを耳にさして再生すると、SMAPのカラフルな歌声が耳に心にと流れ込んできた。
Photo/ぽんず(@yuriponzuu)
『いつもJ-POPを聴いていた』のバックナンバー
#1「排水口とラブレター」(スピッツ/チェリー)
#2「22時の「なんでもないよ」」(宇多田ヒカル/Flavor Of Life)
#3「9年前から心に住む、不動産屋のあのひと」(槇原敬之/遠く遠く)
#4「決戦は4月30日。一番好きなあの子に会いに行く(DREAMS COME TRUE/決戦は金曜日)
#5「大人はスーパーマンじゃないけれど」(SMAP/たいせつ)
#6「ロマンチックとレコーダー」(aiko/アンドロメダ)
#7「泳ぐように、溺れるように、書いている」(サカナクション/新宝島)