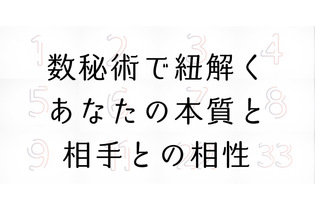こぼれそうな思い
汚れた手で書き上げた
あの手紙はすぐにでも
捨てて欲しいと言ったのに
――スピッツ「チェリー」
排水口とラブレター
誰もが同じ音楽を聴いて、音楽がわたしたちを繋いだり、離したりした。そんな時代を過ごしてきた――。中前結花さんが、平成のヒット曲になぞらえていつかの思い出を語る連載エッセイ。第1回は、スピッツの「チェリー」と人生で初めて渡したラブレターのこと。

人生で一度だけ、ラブレターをしたためたことがある。
と言っても、後々、受け取ったその人に
「あれってさ、どういう意味?」
と、大真面目な顔で聞かれたものだから、
書いたことはある、しかし届いたことはない、というなんとも不恰好な思い出だ。
そんな苦い記憶を、わざわざわたしの胸の片隅から引っ張り出してしまう曲がある。
スピッツの「チェリー」だ。
昭和の終わりに生まれて、わたしは平成しか知らない。
ようやく物心がついたころ、テレビではPUFFYがゆらゆらと揺れ、安室奈美恵は人気絶頂で結婚し、5人組となったSMAPの勢いは加速していった。
小学校のころ、CDのヒットランキングを紹介する番組を見そびれた夜は、
「明日学校に行けない。行きたくない」
と泣いたほどだ。
誰もが同じ音楽を聴いて、音楽がわたしたちを繋いだり、離したりした。
そんな時代を過ごしてきた。
その時々で、自分自身と重ね合わせるような音楽は目まぐるしく変わったけれど、今でもいつもそばにある音楽がいくつかある。
スピッツの曲も、そのひとつだ。
「ロビンソン」「チェリー」「空も飛べるはず」が流行ったのは、いずれも小学生のころの話だけど、彼らの曲を耳にするときは今でもいつも、夕暮れ時のアスファルト道の情景がふっと浮かんでは消え、まったりと甘美な気持ちにさらわれる。
ところが「チェリー」の2番、
「あの手紙はすぐにでも捨てて欲しいと言ったのに」
というあたりで、あの書き損ないのラブレターを思い出しては現実に引き戻され、胸がシクリと痛むのだ。
どうか捨ててくれているといいけれど。
「チェリー」の構成はちょっと変わっていて、手紙の話をしてわたしをすこし傷つけたあと、曲の終わりには「君を忘れないー」と何食わぬように冒頭のAメロに巻き戻る。
「最初の場所に戻った」という印象で、「3番」と呼ぶには違和感があるのだ。
そしてそのあとすぐに訪れる、
「ズルしても真面目にも生きてゆける気がしたよ」
という唐突なフレーズ。わたしは、この一節に大いに自分を重ねていた。
ズルしても真面目にも
生きてゆける気がしたよ
いつかまた この場所で
君とめぐり会いたい
――スピッツ「チェリー」
不器用ながら、どちらかと言えばよく褒められる。
人からはよく「ズルい」なんて言われたけれど、何事も「もういいや」と諦めることができずに、わたしは人知れずいつも一生懸命だった。
「手を抜くこともできる」というのがどこか心のお守りで、こんなにがんばらなくていい、ということも本当はちゃんと知っている。
それを損だと思うこともあった。
そして「いいなあ」と想いを寄せるのもまた、「ズルをしない、損ばかりしている人」だった。
*
大学に入って、わたしはアルバイト先の飲食店で恋をした。
同じ歳の男の子だったけれど、1年以上先にそこで勤めていたせいで、わたしは彼に敬語まじりで話していた。
学生のアルバイトがたくさん勤める店は、色恋の話題も絶えない。
親切で話し上手な、美容師学校に通う男性の先輩がよくモテた。
だけど、わたしが好きだったのは、一番よく排水口掃除を担当してくれる口下手な彼だった。
掃除中に話しかけると不機嫌そうに振り向く。
「ごめんなさい」と言うと「別にいいよ」とうつむく人だった。
レシート情報とレジに入った金額を付き合わせて勘定する「レジ締め」という面倒な仕事があったけど、美容師の先輩は、雑談なんて交わしながら素早く手際よく見事に計算をした。
排水口の彼は、何にも言わずに黙って数えた。
誰と約束しているわけでもないのに、必ず丁寧に3回も勘定するのがおかしかった。
重い炭酸ボンベも、いつも彼が交換していた。
見ていないふりをして、わたしはずっとそれを見ていた。
あるとき、店裏の更衣室で盗難が続いた。
誰かが人の財布からお金を抜いていると言うのだ。
「誰だ」「誰だ」なんて、みんなが品なく色めき立っているなか、彼は特にその話を口にしなかった。
しびれを切らした店長が、冗談なのか、はたまた本気なのか、「このままやと更衣室にカメラをつけなあかんようになる」と言い出すと、彼は初めて口を開いて
「そんなことをしなくても、盗難が起きている日とシフトを付き合わせて見ていけば、わかってしまう」
と言った。
彼には犯人がわかっていたのだ。
ほどなくして、その正体であった女の子は店を辞めさせられた。
「いつからわかってた?」と尋ねると、「割と最初から」と彼は伏し目がちに言った。
そして一瞬迷ったように黙ったあと、
「4人で働いてるときに起こったから。ぼくと中前さんは絶対に違うから」
と付け加えた。
胸がトトトッと鳴るように脈が早くなるのを隠しながら尋ねた。
「なんで、わたしは疑わへんの?」
「だって、よく排水口の掃除してくれるから」
意味がわからなかった。
「◯◯さんこそ、しょっちゅうしてくれるでしょう。わたし、月に2〜3回しかやってない」
「知ってる。だけど、中前さんは気づいてない。掃除のルールになってるけど、この店で排水口に手を突っ込んで本当に掃除してるのは、ぼくと中前さんだけやから」
彼は言った。そうだったのか……。
「まさか」と驚いていると、
「ぼく、そんな人は、人のものを盗まんと思うねん」
と、ぼそりと言った。
ズルは下手だけれど、損ばかりでもないな、と思った。
その一件が、「そっと眺めていた」だけのわたしの想いを、前よりずっと深くて濃いものにした。
「ぼくと中前さんだけ」というのは、なんと甘美で贅沢な響きだろう。
それがたとえ、よく詰まる排水口の話であってもだ。
そしてなにより「信用されている」というのがうれしかった。
2月が訪れて、わたしは意を決した。
ひとに想いを伝えたことなどなかったけれど、これはきっと伝えなければならないものだ、と感じたのだ。
甘いものが苦手なひとだったから、2月14日には何を渡せばいいのかと悩んだ。
デパートの地下を、足が棒になるぐらい歩き回って、結局、ハートの形をした小さなおかきを買った。
「風邪をひきかけている」と聞いたから、そのおかきにオロナミンCをつけて袋に詰め込み、手紙を添えた。
それを、バイト中の彼のかばんの中に何も言わずに入れて帰ることにしようと決めた。
一世一代のラブレターだった。
「風邪の具合はどうですか。
いつも炭酸ボンベの交換をありがとう。
割れたガラスの廃棄もありがとう。
◯◯さんが丁寧に排水口を磨いてくれるから、
◯◯さんが晩に働いた次の日は、洗い場がちっとも臭くありません。
◯◯さんは、ちゃんと勘定してエビを解凍するから、
翌日は、エビを余らせずにすみます。
客席のテーブルを拭いておいてくれてるのも知ってます。
ありがとう。ちゃんと見ています。
だからわたしは、◯◯さんが晩に働いた翌日に働くのが好きです。
最近はそういうシフトが多いから気持ちがいいです。
だけど本当は、同じ日に働く人のことがうらやましいです。」
我ながら、なんと遠回りなのか、と嘆きたくなるけれど、これがそのときの精一杯だった。
男性更衣室に片足を突っ込んだが、彼のカバンが見つけられなかったから、下駄箱に入っている、いつものスニーカーの上に急いで袋をねじ込んだ。
振り返ると、「なにしてんの」と、にやにやした女性の先輩が後ろに立っていた。
「お願い、誰にも言わないで。お先失礼します!」
それだけ早口で伝えると、一目散に走った。
細い店裏の通路を走り抜けて、階段を駆け上がった。
息が上がって、恥ずかしくて情けなくて泣きそうな気持ちになった。
歩道橋の上でようやく呼吸を整えながら、彼が働く店を見下ろした。
きっと今日も這いつくばって掃除をしてから帰るのだろう。
あの手紙はいつごろ読まれるのだろうか。どう思うのだろう。
そして、なんと返事をくれるだろう。そう考えるだけで、階段を駆け上がったときよりも、胸がどくりどくりと揺れて、熱い気持ちでいっぱいになった。
ようやく彼がその手紙について触れてくれたのは、バレンタインデーの4日後だった。
わたしが接客に励んでいると、シフトに入っていないはずの彼が店までやって来たのだ。
恥ずかしさのあまり、気づかないふりをしていると、トントンと肩を叩かれた。振り返るとすぐそばに立っている。
そして、照れることも申し訳なさそうな顔をするでもなく、きょとんとした顔で言う。
「オロナミンCありがとう。あれってさー」
この話もまた冒頭に巻き戻る。
きっとわたしも、君を忘れないのだと思う。
photo/ぽんず(@yuriponzuu)
『いつもJ-POPを聴いていた』のバックナンバー
#1「排水口とラブレター」(スピッツ/チェリー)
#2「22時の「なんでもないよ」」(宇多田ヒカル/Flavor Of Life)
#3「9年前から心に住む、不動産屋のあのひと」(槇原敬之/遠く遠く)
#4「決戦は4月30日。一番好きなあの子に会いに行く(DREAMS COME TRUE/決戦は金曜日)
#5「大人はスーパーマンじゃないけれど」(SMAP/たいせつ)
#6「ロマンチックとレコーダー」(aiko/アンドロメダ)
#7「泳ぐように、溺れるように、書いている」(サカナクション/新宝島)