夫と愛人との、奇妙な共同生活。たくさんの男を溺れさせた岡本かの子の魅力と孤独 2/2
■誰になんと言われようとも
歌人として活動を始めた岡本かの子は、小説家としてはそれほど早く大成したわけではない。一時期は、どこの出版社に小説を持ち込んでも、丁重に断られていたくらいだった。また、谷崎潤一郎に自身の小説を送って教えを乞うたものの、そのことを「小説と一緒に反物を一反送って来てね、すぐ送りかえしてやった」と言われてしまっている。
かの子の気の遣い方はしばしば野暮で、「やりすぎ」であり、粋な心遣いや気配りができた女性というわけでもなかったらしい。しかしそれでも、川端康成の紹介で『鶴は病みき』が「文学界」に載るまで、無下にされながらも小説への情熱を捨てることはなかった。
かの子の作品はよく、「ナルシシズム」や「装飾的な文章」といった言葉で評される。編集者に塩対応されようとも小説を書き続け、また周囲に容姿を「不器量」だと囁かれながらも、自身に宿る「美」を疑わなかった。自分に対する絶対的な自信、信頼。それはかの子の人生を突き動かすだけでなく、小説にも表れていたのである。
『新装版 かの子撩乱』瀬戸内寂聴著,講談社文庫,2019年,423頁
かの子の愛人だった仁田は、当時の共同生活のことをこう振り返っている。
誰になんと言われようと、自分は美しい。著名な作家に無下にされようと、自分の小説には価値がある。世間になんて噂されようと、夫と、また愛人を愛していることに変わりはない──この自信、ナルシシズム、真剣さこそが、おそらく岡本かの子の揺るぎない魅力だったのではないだろうか。
もっと美人になれたら、性格を改善できたら、家事や仕事をちゃんとこなせたら、自分に自信が持てるかもしれない。強烈に自分を信じることができた岡本かの子は、現代に生きる私たちの、そんな思い込みを吹き飛ばしてしまう。自信とは、何かを達成して手に入れるものではない。何はなくとも、最初から持っていていいものなのだ。
しかしわかってはいても、自分に自信を持つことは難しい。そして、私たちは疑問に思うだろう。かの子のその強烈な自信の源は、いったいなんだったのだろうと。
■孤独と悲しみが深くなるほど華やぐいのち
短編『老妓抄』の終わりを、かの子はこんな詩で結んでいる。これはかの子自身の詩ではなく、あくまで小説の主人公である老妓が詠んだ詩という体ではあるのだが、これを晩年のかの子の心情を表したものと考えてもそれほど的外れではないはずだ。
「年々にわが悲しみは深くして いよよ華やぐいのちなりけり」
夫から愛人から、そして息子である太郎から、どれだけの愛情をもらっても、かの子はなお孤独で、その悲しみは年々深くなるばかりだった。
そもそも、夫がいようと子どもがいようと愛人が何人いようと、人が「満たされる」なんて状態になることは、稀なのだろう。仏教研究家でもあったかの子は、そのことをどこかで冷静に悟っていた。愛されても傅かれても、念願だった小説の才能をようやく認められても、かの子はなお孤独で、おそらくはずっと寂しかったのである。
だけどそのことを、「いよよ華やぐいのち」と表しているところに、かの子の感性がよく反映されている気がする。どれだけ愛情を注がれても、孤独からは逃れられないという悟り。だけどその諦念と悲しみが深くなるほど、いのちが華やぐことをかの子は知っていた。彼女の自信の源は、そんなところにあったのではないだろうか。
美人で、いつもにこにこ笑って愛想がよく、気遣いができて、美味しいごはんを作れる。そんな条件はたとえひとつも満たせなくとも、男性を虜にすることは可能だ。令和に生きる私が考える「いい女」の基準のほうが、大正・昭和期を生きた岡本かの子よりもよっぽど保守的で、なんだか恥ずかしくなってくる。そして、自分が虜にした男性たちからどれだけ愛を注がれようとも、人が満たされることはない。
『新装版 かの子撩乱』瀬戸内寂聴著,講談社文庫,2019年,419頁
夫である一平は、かの子とその愛人との共同生活について、こう語っていたらしい。
道徳も批難も跳ね返す、真剣な、真実の生活。そっくりそのまま真似はできなくても、岡本かの子の自信、常識やぶりの思想、孤独、諦念、それ故の美しさ。
これらは必ず、今日の私たちにも、勇気を与えてくれるはずだ。
Illust/野出木彩












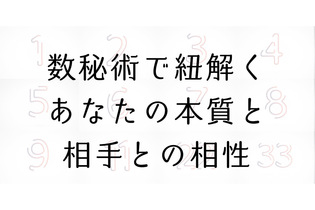










旅と文学について書くコラムニスト・ブロガー。1987年生まれ、神奈川県出身。