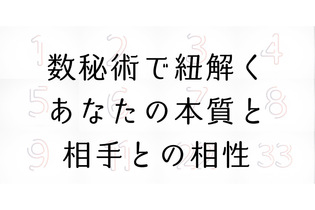母を手放す #2「母みたいになりたくない」と悩むあなたへ
母娘関係に苦しむ女性を楽にするシリーズ、第2回目は文筆家の小野美由紀さんが寄稿。「母みたいになりたくない」感情を乗り越えるまでの道のりを綴っていただきました。


母みたいになりたくない。
それが私の長年の悩みだった。
似たくない、と思えばますます似てくる気がする。ふと鏡のなかに、大嫌いな母とそっくりな顔をしている自分を発見したり、人と話したりしているときに、いつのまにか母と同じ嫌味な言い回しをしていることに気づいたとき、心臓がどきりと高鳴り、不吉な妄想が始まるのだ。
「私、あの人とそっくりになってる」って。
私の母はまあ毒母に該当する人間で、その呪縛から逃れるまでには思い出すだけで両肩が脱臼しそうになるくらいの大変なエピソードが幼少期から山ほどあり、25歳で『グラップラー刃牙』なみの死闘を繰り広げて(詳細は『傷口から人生 メンヘラが就活して失敗したら人生が面白くなった』の「母を殴る」の章をどうぞ)やっとこさ私は母からの精神的な自立を果たした。
しかしその後も「母みたいになりたくない」という思いは日常のありとあらゆる瞬間に顔をのぞかせ、随分と長い間、うっすらと残る呪いの残りカスのようなものに苦しんでいた。
その苦しみから私を救ってくれたのは、セラピーでも、カウンセリングでもなく、ある生物学者の書いた一冊の本だった。
福岡伸一。
『生物と無生物のあいだ』『できそこないの男たち』など、多くの名著を残している生物学者である。
生物の進化について解説した彼の著書『動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』には、こんなことが書かれていた。
「人間の構造はちくわ」である。
人体は口から肛門までの1本のちくわの穴のような構造をしていて、
私たちが普段、“体の中”だと思っている鼻、耳、目(涙腺)や尿道、女性の膣、子宮などは、ただの体の表面に出来た「窪み」である。
くぼみの表面は体の外側と言えるし、さらに、口から肛門までの管の中も、その表面は外側である。
「体の内部」など、ありはしないのだ。
それを読んだ瞬間、目の前がピカッと光り、人生観がガラリと変わるような気がした。
■子宮は神聖なものでなく、子どもの「仮宿」
なあんだ。
私が血のつながりという絶対的な強い呪縛に苦しみ、自由を効かなくされていると思っていた「母親」という存在は、
たかが10ヶ月かそこら、体表にできた「窪み」をちょっと借りていただけの仮宿だったのか。
子どもを産むための大事な器官として崇め奉られている膣や子宮も、生物の構造というやや突き放した視点から見れば、体の内部ではなく“外側”でしかない。子どもは発生した時点からすでに親の体の外部で育ち、つかの間のエアポケットとして母の体を利用したのち、より広い世界へと排出される。
生物的に見れば、親子関係というのは、ただそれだけのものなのだ。
このいささかクールな視点は、私を随分と楽な気持ちにしてくれた。
これまで母との関係について心労で倒れるくらいに悩んだりしたのは、それこそ「血の濃くつながった、お腹を痛めて産んでくれた唯一無二のお母さん」みたいな気持ちがあったからで、この人との関係をどうにかしないと私の人生終わってしまう、と思っていたからに違いない。
また「母と娘は結びつきが強いもの」「お腹を痛めて産む行為は神聖なもので、女性特有の素晴らしいミッション」みたいな固定観念もあった。
しかしまあ、ところがなんてことはない、母の子宮から出たからといって、私は決して母のコピーではない。もちろん染色体の一部をもらっていることには変わりはないし、家庭の環境を共にはしているけれども、母の子宮は仮宿であり、モトを辿れば父の種でもあり、もっと言えば父と母の背後にあるでっかい社会である。私は社会の子どもであって、母の泥人形ではない。
獣は腹から生まれたら、すぐに歩き出す。子どもは自分一匹分の餌しか採らない。母の体内から出てしまえば、「自分の命は自分のもの」である。
人間だけだ。「家族」とか「親子」の結びつきを、こんなにもありがたがるなんて。
不思議なもので、そう考え始めた途端、これまで母と私の似ている点ばかりを気にして嫌な気持ちになっていたのが、反転して「似ていない部分」ばかり目につくようになってくる。
最近、祖母を看取るために、1ヶ月ほど実家と自分の家を往復して、家族と長い時間を過ごす機会があった。
祖母が亡くなった後、遺体を清める作業を私は看護師さんと一緒に行ったが、母は「死んだ人の尊厳に関わるから、体は見たくない」と言って一人、ベッドから離れていたし、
葬式にどこまでもオプションをつけて、華美にやりたがる母に対し、私は「おばあちゃんは前に出たがるタイプじゃなかったから、シンプルにやろうよ」と反対した。
一事が万事、こんな調子で、母と私は全くもって嗜好が合わなかったのだ。
考えてみれば、母はバブルの絶頂期にバリバリ仕事をしていて、とにかく1番を取るのが好き、勝つのが好き、お金が大好き、人を見れば疑うし、人より勝っていないと許せないタイプだ。
私はと言うと、物心ついたときにはバブルはとうに終わっており、競争よりも個人的な充実の方が大事、お金より精神的な充足が欲しい、勝ち負けよりも多くの人と一緒に仲良くやりたいタイプである。
そんなのが一つ屋根の下にいたら、揉めるのもあたりまえだ。
■親子だから仲良くする必要なんてない
母と私は、たとえ遺伝子を受け継いでいたからといって、全く別の人間だ。
生きている時代も趣味嗜好も違う。
類似点は、探そうと思えばいくらでも探せるが、それと同じくらい、相違点も探そうと思えば探せるのである。
そうしてこなかったのは多分、私の「いつまでも親に囚われていたい、人生の責任を誰かに押し付けていたい」という甘えの心ゆえだ。そう、30歳にしてやっと気づいた。
私は今なら、正々堂々と「母のこういうところが嫌い」だと言えるし、母の良いところも、かなり客観的に見ることができる。
親子だから仲良くしなきゃ、と思うこともなくなり、
「実家には半年に1度しか帰りません。それ以上になると、あなたは私の気持ちを考えて発言しなくなるので、適切な距離を保ちましょう」と平然と言えるようになった。
「そのうち死ぬ、年上の、昔関係が近かった人」くらいの感じで、自分が傷つかないほどの遠さから、余裕を持って慈しむようになった。
そう、人間はそのうち死ぬのだ。そう思えば、多少のことはどうでもいい。
私は私の人生を充実させることで忙しい。
同時に、自分の欠点についても、
「親のせいで、こうなった」とか「親子のトラウマが」とか、「お母さんみたいになりたくないからこうしよう」とか、考えなくなった。
だって、全く別の人間なのだ。母と私は。
そう思えた途端に、子どもを産むことに対する恐れもだいぶなくなった。
私ではない人間を一人、仮宿に宿らせて、出すだけなのだ。 命の重さには変わりないが、別に、自分の分身を作るわけじゃないのだ。他人を生むだけだ。だったら気分は楽じゃないか。
先日実家に帰ったときに、ふと自分が使っているのと同じブランドの化粧品が洗面所に転がっているのを見て
「あーあ、やっぱり親子だな」と、自然に思う自分を見つけてハッとした。
いつのまにか、母と似ている点を見つけても、嫌でなくなっていた。
「やっぱり親子、でも、私とあなたは他人」。
子宮と羊水の膜に覆われていない身体の表面はすぅすぅする。むき出しの皮膚は社会と摩擦を起こし、時にはひりひりすることもある。
しかしそれは同時に、この上ない自由の涼やかさなのである。
おかあさん、ここまで育ててくれてありがとう、さようなら。

小野美由紀さん
文筆家。1985年生まれ。慶応義塾大学フランス文学専攻卒。恋愛や対人関係、家族についてのコラムが人気。著書に『傷口から人生。〜メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった』(幻冬舎)、『人生に疲れたらスペイン巡礼~飲み、食べ、歩く800キロの旅~』(光文社)、『ひかりのりゅう』(絵本塾出版)などがある。