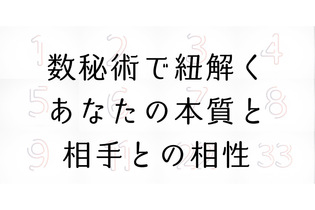泣き顔と真冬のスプリングコート
私は天気予報を見たことがない、見る必要もない――。思い入れのある服を“ドレス”と名付け、その服にまつわるエピソードを綴るリレーエッセイ「私のドレス」。第8回は、エッセイスト 中前結花さんのドレス。

わたしは、天気予報を見たことがない。
もちろん、テレビで映るのをぼんやりと遠くから眺めていたことはあるし、読み上げてくれる女性に「かわいいオネエサンだなあ」と見惚れたことは何度もあった。
だけど、自分から進んで天気を確かめたり調べたことはない。
それはきっと、まぶしく晴れていようと、うっすらと雲ががっていようと。もしも、ボタボタと雨粒が空から落ちていたとしても、特にわたしには関わりがないからなんだろう。
車には乗らないし、布団やクッションの類は、自宅にいるときにしか干さない。別に、どんな天気であっても、わたしは一向に構わないのだ。
なにより、わたしは、天気で気分を左右されたりしない。
そしてそれは、ファッションにしても同じことだった。
暑かろうが寒かろうが、いつだってわたしは着たいものを着る。もしも扉を開いて雨粒が顔にかかったら、傘をさして出かける。それだけの話なのだ。
■どうしても着たい服
そんな調子なので、いつも人から
「どうして、そんなに薄着なの!」
「雨の日に、なんて靴を履いてるの!」
などとばかり言われている。
だって、今日がこんなに冷えるだなんて。まさか夜からは雨が降るだなんて。天気予報を見る習慣のないわたしには、そんな先のことはわからないんだもの。
玄関横にしまわれたビニール傘は、優に15本を超えてしまっている。スエードのヒールは、雨で何度もだめにしてしまったけれど、やっぱり「これ以外は嫌だ」と毎朝身につけるものを選んでしまうのだった。
小さい頃こそ、母も「今日はだめ」「それは夏のスカート!」と必死に止めてくれていたし、わたしが季節感のないトンチンカンなものを着たがらないよう、似たようなサマーニットと冬物のニットを揃いで編んでくれたりもした。
だけどいつからか、防寒のカーディガンなんかをカバンに押し込みながら、「寒くなったら着るのよ」と自由にさせるようになる。
もはや、娘の洋服への強いこだわりにほとほと愛想を尽かし、疲れていたのだろう。なんだか、ずいぶん可哀想なことをしてしまったように思う。
■そのコートとの出会い
「洋服へのこだわり」なんて言うけれど、人から見たとき、わたしが決しておしゃれではないだろうことは、自分でもよくわかっている。特にブランドへのこだわりもなく、ただ「いいなあ」と思ったものをバラバラと買い揃えている。
1900円のワンピースを着て、頭には6万円の帽子を乗せていることだってよくある話で、そのどちらも同じくらい、わたしにとってはお気に入りなのだ。
わたしが魅了されるのは、ほとんどがその「色」だった。
ひと口に「赤」と言っても、濃いのから薄いの、ちょっと黄味がかったものまでいろいろあるし、毛糸の赤と、綿の赤と、ベロアの赤も全然違う。
「今日は、つるっと光った赤が着たい」
「今日は、シトッとしたグリーンがいい」
布団の中で目覚めるとき、わたしはいつもそんなことを思う。
前の晩から用意するようなことはしない。その日、どんな色が着たいかは朝になってみないとわからないからだ。
そんなわたしにとって、一番の苦痛は「これを着なさい」と格好を決められることだ。
「制服」とはその最たるもので、中学から高校の6年間は毎日違った髪飾りを結ぶことで、なんとか気持ちを保っていた。
そんなこともあって大学生になると、なにかが爆発でも起こしてしまったように、派手な色合いの洋服ばかりを好むようになる。
そして就職を控えた、大学4年生の冬のことだ。
母と出かけたデパートで、わたしはショッキングピンクの春物のコートを惚れぼれと眺めていた。わたしが見ても「これは明らかに、とんでもなく派手だ」ということがよくわかるそのコートは、500円玉よりも大きなボタンのついた膝までのロング丈で、撥水加工をしたようにパリッと美しかった。
母はその様子にすぐに気づき、はっとして「これは、会社には着ていけないよ」と言った。理由は「あまりにも派手」であるし「こういうのは、ドラマで観月ありさが着るようなデザインよ」ということだった。たしかに、どの作品かはわからないけれど、ドラマの観月ありさはいつも派手である。
「東京は、このくらいが普通かも」
「きっと違うけど、試着してごらん。鏡で見たらええんよ」
店員さんに断りを入れて、わたしはそのパリッとハリのあるコートの袖に腕を通し、近くにある姿見を母と一緒に覗き込む。
「……よう似合うてるわ」
ひどい自惚れとひどい親バカだったのかもしれないけれど。
ともかく、わたしの派手な顔立ちとショッキングな色合いのロングコートは、なんだかずいぶんと相性がよかった。
忘れもしない、値段は2万9000円だ。その頃、わたしたちはとても貧しかった。上京するための引越し資金を、アルバイトを掛け持ちしながら必死で貯めていた。それなのに、
「1万円だけ出してあげる」
と母は言う。
「ううん……やっぱりやめとく」
ハンガーにコートを戻して、そのまま店を離れかけたが、やっぱり吸い込まれるようにそこへ戻り、そのコートを連れ帰ってしまった。帰りの電車で「お給料もらったら、1万円返すからね」とわたしが言うと、母は「だけど会社には着ていっちゃだめよ。あれは、観月ありさみたいやからね」と何度も言った。
以来、そのコートは「観月ありさ」と呼ばれるようになる。
卒業間近の大学にも、わたしは観月ありさを何度か着ていった。友人たちは「それを着てると、他の人が風景に見える」と言う。
わたしは、とてもとても気分がよかった。だって「そういう気分の日」だったからだ。
■スーツのボタン
春には上京し、社会人になった。
そしていくつも東京で春を迎えたけれど、観月ありさを平日に羽織ることだけは遠慮しておいた。これは休日に楽しむ洋服。母との約束だったからだ。
やがて何度かの転職を繰り返し、わたしは社会人6年目にして、ようやく子どもの頃から憧れ続けたテレビ局に入社することとなる。
夢とは、いつか叶うようにできているのだと思った。
だけど、きらきらとした思いも束の間、「営業職の側面もあるから」と毎日スーツを着るよう命ぜられてしまう。
「スーツですか……」
すこしでもカジュアルだと、朝から何度もお小言を言われるので、わたしは濃紺のジャケットばかり着ていた。天気とは関係なく、気分は毎日、今にも雨が漏れしたたりそうなほど、どんよりと曇り、とても重たい。
打ち合わせで発言をすると「まだ早い」と帰り道にたしなめられる。公募の研修を受けたいと申し出ると「入社6年目までは無理だ」と笑われる。「メールをしました」と席まで伝えに行かなければ、非常識だと30分以上叱られたりもした。
毎晩のように取引先との飲み会が続き、苦手な紹興酒もたくさん飲まなければならなかった。お酒の席で年齢を聞かれ「27です」と答えると、「なあんだ、つまらない」と言われ、毎回「ひどーい」とカラカラと笑わなければいけない。
限界だった。
「外国だと思うしかないよ」と恋人は慰めてくれるけれど、わたしは海外こそ蛍光イエローのバナナようなワンピースや、ハッと目の覚めるようなグリーンのノースリーブが着たい。
だけどもう、そんなに遠くへ出かける元気もなかった。
「なにが一番嫌だ?」彼に尋ねられ、「もう……スーツなんて着たくない」とわたしはおいおい泣いた。スーツの胸ボタンのように、もうなにかもが苦しい。彼は眉をハの字にして「辞めてもいいよ」と真面目に言った。
「わたし、文章が書きたい」とつぶやくと、うんうんと頷きながら、「それに……洋服はピンク色が似合うと思う」と彼は言った。涙を拭いながら「そうなのよ」とわたしが答えると、彼は安心したようにハハハッと笑っていた。
■憧れと離れて、「わたし」になった
秋が終わる頃、わたしは退職を願い出て、なんとか受理してもらうことができた。年末までは、この会社でしかできないことを頑張ろうと努めたけれど、本当は退職の日をずっと指折り数えていた。とにかく早くその国から逃げ出したかった。
そして、ようやくその朝が来る。
取引先との挨拶は済ませていたし、あとは局内を回るだけだ。出社し、分厚く重たいコートを脱ぐ。だけどいつものスーツは着ていない。
わたしはコートの下に、観月ありさを着てきた。タイトなスプリングコートだからワンピースに見えないこともないだろう。ショッキングなピンクの洋服で「お世話になりました」とお菓子を配ると、みんなが驚いた顔で見ていた。構うもんか。立つ鳥だしこのぐらい派手でも迷惑はかけなかろう。「もう戻れない」と思うと、とても心地よかった。
建物を出るとき、振り返ってまじまじとビルを見上げた。幼い頃から夢を見させてくれた場所。学生時代は夜行バスに乗り何度も何度も説明会や面接に訪れ、その度にここで働きたい、と胸を膨らませた。わたしにできることはなかったけれど、この場所が、わたしの憧れのすべてだった。
声には出さず「ありがとうございました」と一礼して、泣きながら電車に乗った。派手なピンクのスプリングコートと、真冬と、泣き顔。どれも最高にチグハグで、やっぱりわたしはおしゃれではないなとつくづく思った。
あれから4年とちょっと。クローゼットを開けると、観月ありさは未だにパリッと美しい。
今日もわたしは、着たい洋服を着て、書きたいものを書いている。
やっぱり天気はちっともわたしに関係がない。雨が降ろうと、風が吹こうと、自分の空を晴らす術は知っているからだ。
暑い日だって、凍える日だって、その日着たい洋服を着る。わたしの天気を決める神様は、いつの日も、わたしなのだ。
『私のドレス』のバックナンバー
#1 ファッションジプシーを卒業した日(チャイ子ちゃん)#2 “ママじゃない私”を守るためのMame Kurogouchi(小沢あや)
#3 今日もおめかしをして、我が推しに会いに行く(岡田育)
#4 すべての服がすこしずつ大きいこの世界を、1日でも多く好きでいたい(生湯葉シホ)
#5 あなたがどこに行こうと、私はここで光っているから(雨あがりの少女)
#6 「自分に似合うものを知っているんですね」(土門蘭)
#7 ワンピースの女王(くどうれいん)