すべての服がすこしずつ大きいこの世界を、1日でも多く好きでいたい【私のドレス #4】
古着屋で見つけた40サイズのワンピース。体の小さい私には明らかに大きすぎたけれど――。思い入れのある服を“ドレス”と名付け、その服にまつわるエピソードを綴るリレーエッセイ「私のドレス」。第4回は、エッセイスト・生湯葉シホさんのドレス。

体が小さく、身長も低くて、私にはむかしからすべての服がすこしずつ大きい。あとからちょうどよくなるはずだから、と母に3年間言い聞かされていた制服のブレザーは最後まで全然ちょうどよくならなかったし、いまでもフリーサイズの洋服の試着をするときは決まって、ちょっとぶかぶかめに着るのがかわいいデザインなので、とフォローされる。
これまで私にそう声をかけてくれた無数の店員さんたちの言葉が本当ならば、この世のほとんどの服はちょっとぶかぶかめに着るのがかわいいデザインということになる。
あ、なんか、どうやらそうじゃないっぽいな? と気づいたのと、人からの視線が怖くなりはじめたのは同じ頃だった。
■「こんな似合わない服を着ているのを見られたら笑われる」
きっかけがなんだったかははっきりと覚えていない。6年生のとき、サエちゃんとユキちゃんとマリちゃんという3人といつも一緒にいて、サエちゃんとユキちゃんは背が高くほっそりとしていたから、比べるとシホとマリは脚が短いよね、という冗談を同級生に言われたことがあったような気がするし、いま思い返すとそれを言ったのはサエちゃん自身だったような気もする。
いや、サエちゃんに言われたのは「シホって音読のときすぐ顔赤くなってウケる」だったかな、でも、ほとんど同じことを中1のときに、文芸部の顧問だった金子先生にも言われたことがある。
合唱コンクールで、朝の会で、人権作文の発表会で、「人前にがて?」とサエちゃんや金子先生やそうじゃない誰かに聞かれ続けて、聞かれるたびに体がこわばって、指先と肩を中心に、意図しないふるえ方をした。目が悪くなってぶ厚い眼鏡をかけ始めたのはもっと前のことだったっけ、やっぱりもういろんなことが思い出せない。
ただ、気がついたときには他人からの視線が怖くて、電車通学もプリクラを撮るのも人前で食べるお弁当も、ぜんぶがだめになってしまっていた。そんな状態は調子のいい日と悪い日の波を腹痛みたいに繰り返しながら、20代前半まで続いた。
おしゃれをするのが嫌いだったというわけではない。10代の頃は友だちとラフォーレ原宿や109(や、母と地元の板橋イオン)に行ったりもしたし、そこで当時エビちゃんの影響で流行っていた小花柄のスカートを買ったり、ときどきは冒険してセシルマクビーでギャル服を買ったりもした。
ただ、友だちと服を見ながら華やかなファッションビルを歩いているときの純粋なうれしさと、試着室の鏡で自分の姿を見たときの「こんな似合わない服を着ているのを見られたら笑われる」という恐怖はいつでも同時に存在して、その恐怖に食い殺されそうになるとき、私は試着室から出られなくなった。着ている服のサイズが自分には大きすぎること、脚が短い上にそんなに細くないこと、友だちの視線で緊張して体がふるえてしまうことの恥ずかしさ、なにもかもが強迫的に襲ってきて、カーテンを開けようとする手を止めた。
どうしてこうなっちゃったんだろう、なにをすれば治るんだろう、と考えるのは、決まってお風呂に入っているときだった。湯船の中で、折りたたむと短すぎてドラえもんのあぐらみたいになる自分の脚を見るたびに、そうやって小6で止まってしまった体の成長のことを意識するたびに、自分ひとりだけが永遠に子どもなのだと泣きたくなった。
身内のことをこんなふうに言うのは変だけれど母はとても美しい人で、特に格好いいのはどんなにごつい腕時計でも似合ってしまう大きな手と真っ赤な口紅が似合う大きな唇だったから、そのどちらも譲ってもらうどころか借りることもできない自分はなんなのだろう、とよく思った。
■服って似合わなくても着ていいんじゃないのか?
背が低いことはかわいいことだよ、と言ったのは最初に付き合った恋人だったような気もするし、大学時代の部活の先輩だったような気もする。……とかいって本当は私にそう言ってきた人のことはみんな覚えているのだけど、そんなくだらない呪いの話は今さらしたくない。
体が小さくて気弱そうに見えることがどうやら特定のジャンルの異性の興味を引くらしいというのは、(好むと好まざるとにかかわらず)女性の体を持って生まれてきた人なら早い年齢で気づくことだと思うし、なんとなく楽だからその層にアプローチしてみた時期も正直に言えばあった。その頃の自分のファッションの指針はただ一点、「モテそう」だった。ばかじゃないの。だから本当にこの話はもうやめる。
20歳を超えたある日、実家の近くを自転車で走っていたら新しくできた古着屋を見つけて、そこで極彩色の変な色のスカートを衝動買いしたことがあった。絶対にモテない、無難じゃない、なんなら友だちにだって笑われるかもしれないスカートをなんの考えもなく買ったその日から、なんとなく、もしかして服って似合わなくても着ていいんじゃないのか? と思いはじめた。
同じ店に2度目に行ったとき、私は生まれてはじめてヴィンテージの服を買った。
店内をぼんやりと見てまわっていたら目についたそれは黒いノースリーブのロングワンピースで、タグに印刷された「40」という数字と素材の表記がかすれていた。これは古いものなんですか、と聞くと、ドイツの1950年代のワンピースです、と店主がレジから返事をしてくる。狭い店なのに、こちらから言わない限りは立ち上がって服を薦めたりしてこない店主のスタンスを好きだと思った。
40、ということは日本のサイズで言うと11号とか13号にあたる。ふだん5号か7号を着ている私には、服を体にあててみるまでもなく大きすぎた。けれどなぜかその日は、「これ私が着たら大きいですよね?」と聞く勇気があった。たぶん、その前に変な色のスカートを買っていった客として認知されているから大丈夫だ、という妙な自信がついていたのだと思う。
店主は洋服や骨董品でいっぱいになったレジのスペースから顔を覗かせるみたいにして、私をじっと見た。見られている、と思って体がこわばる。店主はすこし考えて、「めちゃでかいですね、たぶん」と言った。
そうかめちゃでかいよな、と笑ってしまって、笑った勢いで試着させてもらった。13号サイズの人が着たらおそらく膝下丈になるであろうワンピースの裾はほとんど床につきそうで、鏡に向き合いながら、でか、と思わず口に出した。
けれど大きすぎることはわかりきっていたから、試着室から出ていくのはそんなに恥ずかしくなかった。「実はヴィンテージの服を初めて着たんですけど」と言うと店主はちょっとうれしそうにして、「ヴィンテージはいい」と言った。それは目の前の客に対しての助言というよりも、頭に浮かんだ言葉をそのまま言ってみたという感じだった。それでも私は臆病だから「似合ってなくはないですかね?」とおかしな質問をして、「いいと思いますよ」と言われてホッとし、流れるようにその服を買った。
■どちらが似合うとか似合わないとか、考えるのはやめた
たぶん、なにかをきっかけに物事が劇的に変わるなんていうことはほとんどなくって、私が平気でオーバーサイズの服やメンズの服を着たり、絶対に必要のない箇所に変なびらびらがついていたりする服をおもしろがって買ったりできるようになったのも、別にそのワンピースが直接的なきっかけだったわけではないと思う。
けれど、今年28歳になる私にはいまでも人の視線が怖くて外に出られない日がある一方で、20代前半の頃よりも服を着るのが楽しい日がはるかに多い、というのは本当のことだ。オセロを1枚1枚ひっくり返すみたいにそういう日をすこしずつ増やしていくことができたのは、いろんな人やファッションとの出会いと、あのワンピースを買ったときの記憶があるからだ、と素直に思ったりもする。
1年くらい前、いろんなブランドの香水が一堂に会する百貨店の催事に行ったとき、あるブランドの調香師がそこに来ていた。彼は、自分のブースを訪れた客のファッションや雰囲気を見て、その人のイメージにいちばんぴったりの香水をその場で調香する、と言った。
どきどきしながら私も調香をしてもらった。スパイシーなレザー、白檀、ジャスミンの混ざりあった香りにうっとりとしていたら、彼が注意喚起をするみたいに指を振って、こんな言葉を何度か口にした。「でもこれは僕から見た今日のあなたであって、あなたのすべてではありません」。
その日は、ちょうど例のワンピースを着ていた。私はその服を大きいままで着こなすことにもう慣れていたし、ときどきは人に「似合いますね」と言ってもらえることすらあった。家に帰って服を脱いで、ユニクロで買ったXSサイズの部屋着に着替えるとそれは自分にぴったりで、けれど私はそのどちらの服がより似合うとか似合わないとか、そういうことを考えるのはもうやめていた。少なくともその日は、そういうことは考えなかった。
すべての服がすこしずつ自分には大きいこの世界を、そして大きな服を着たときに私の肌と布のあいだに生まれるいびつな隙間を見て、ふざけやがって、と思うこともいまだにある。けれどそれは自分を受容できない日の私の視線であって、ほかの誰の視線でもない。私の体は、視線は、その日の私の持ちものではあるけれど、私のすべてではない。
だから、「やっぱりなに着てもいいんじゃん」と思える日をすこしでも増やすために、黒いワンピースを部屋の見える位置にかけてから今日も寝る。朝起きたときに最初に視界に入るのがそのワンピースだとうれしいから、このごろはずっとそうしている。私から見える世界を1日でも多く好きでいたい。
Title design/めいめい(@meimay_yoshioka)
『私のドレス』のバックナンバー
#1 ファッションジプシーを卒業した日(チャイ子ちゃん)#2 “ママじゃない私”を守るためのMame Kurogouchi(小沢あや)
#3 今日もおめかしをして、我が推しに会いに行く(岡田育)










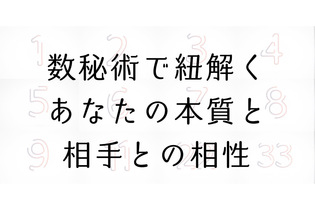










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。