ファッションジプシーを卒業した日【私のドレス #1】
忘れられない服。ここぞという日に着る服。自分を変えてくれた服。「私のドレス」は、そんな思い入れのある服を“ドレス”と名付け、その服にまつわるエピソードを綴るリレーエッセイです。第1回は、チャイ子さんの“ドレス”。

「また黒のノースリーブ着てるの?」
お出かけ前の玄関で、靴を履こうとしている母に私は呆れたように言った。
ふふん。得意げな顔で母は答える。そうよ。素敵でしょ。
そしてふわふわと巻き髪を肩の上で揺らしながら、赤い唇から歯をのぞかせて言う。
「さ、行くわよ」
私が小さい頃から、母の外出着はノースリーブだった。
家の中ではさまざまなバリエーションの部屋着を着ていたが、ちょっといいレストランに出かけるとき、ちょっとしたお祝い事をするときなど、ハレの日の服装は決まってノースリーブなのだ。
さすがに真冬になると着ないが、春先にはタートルネックニットのノースリーブから始まり、夏は襟の詰まったノースリーブシャツやノースリーブサマーニット、シルクやリネンの涼しげなもの、そして秋口のトレンチコートの下まで、彼女のノースリーブコレクションは続いた。
そしてその多くが黒色だった。
幼い頃からシックでシンプルな服を着させられていた私は、高校を卒業するまでその系統を好んで着ていた。だが、大学で上京すると、それはガラリと変わった。
赤文字系から青文字系まで、いろいろな系統を渡り歩く、まさにファッションジプシーと化したのだった。
あるときはギャル系に目覚め、またあるときは古着を買い漁り、またあるときは全身ギャルソンで身を固め、あるときはストリートにハマるなど。それはそれはめまぐるしく好きな服や系統を変えていた。
家族の仲が良いこともあり、私は上京しても年に3〜4回地元に帰っていた。また母もちょくちょく東京に買い物に来ることがあったため、離れて暮らしている割には母と顔を合わせることが多かった。
そして会うたび母は、私の服の系統が変わっていることに驚き、また幾分か楽しんでいる節もあった。
「ふうん、今はそういうのが好きなんだ」
それを褒めるでも否定するでもなく、「このブランドがさー」と私が話すのを、好奇心を持って聞いていた。
そしてある日。
夏休みで帰省していた私に、珍しく母が一緒に買い物へ行こうと提案してきた。
「ちょっと、あなたに似合いそうな服、見つけちゃったのよ」
えー系統違うからなーと渋る私に、いいのいいの見るだけでも、と母は誘った。
そして玄関に、お気に入りの黒のノースリーブを着て登場したのだった。
ノースリーブ以外も、着ればいいじゃん。ほらもっと明るい色のワンピースとか、Tシャツとか、いろいろあるでしょ。
百貨店へと向かう道、そんな私の問いかけに、「そうねえ」と微笑みながら彼女は言った。
だって、私の腕がいちばん映えるでしょう。
どんなに食べても太らない、あまりにも羨ましい体質を持つ母はすらりと華奢で、その腕はとても綺麗で細かった。
とはいえガリガリと貧相でもなく、すっとした肩から伸びる白い両腕は、確かに当時40代後半とは思えない出で立ちで、また、ぴったりとした黒のノースリーブはその肌のきめ細やかさ、そしてすっきりと贅肉のない背中や腰回りを強調していた。
「いろんなお洋服にトライするのは大事。好きな系統のお洋服を着るのも大事。でもね、自分をいちばん引き立ててくれる、自分の良さを一番映えさせるお洋服を1枚持つことも、必要だと思うのよ」
そしていたずらっ子のように笑いながら、こう言ったのだった。
「流行最先端の服を着ている人より、自分に合う服を着ている人のほうが、ずっとイケてんのよ」
百貨店で母が見つけた、私に似合いそうだという服は、肩から鎖骨にかけゆったりと開いた、ベロアのトップスだった。
「あなた首回りが綺麗だから。鎖骨を見せた服が絶対似合うわよ」
言われるがままに試着室に押し込まれ、大きな鏡を見ながら懐疑的な気持ちで1枚ずつ服を脱いでいく。
試着室は、不思議な空間だ。
小さな箱の中に、この服は似合うだろうかと小さな希望を抱えいそいそと入って行く。
かぶったフェイスカバーをそっと取るとき。あるいは、少し前かがみになり後ろのファスナーを上げ終わったとき。鏡の自分と対面する前のその瞬間には、わずかながらの緊張が走る。
似合うか、似合わないか。それは自分が一瞬で判断できるものだ。さあイエスか。ノーか。
母の見立ては、大正解だ。
そのベロアのトップスは、驚くほどに私にぴったりだった。
それから私は、徐々にファッションジプシーを卒業し、シックでシンプルな服を好んで着るようになった。
そして気づけば、「自分を映えさせる服」を選べるようになっていたのだった。
鎖骨が綺麗に見えるよう、首元が開いているもの。黒髪に合う、ぱきっとした色のもの。ゆったりさせず、ぎゅっと絞ったウエストのもの。
友人の結婚式でのドレス。仕事のパーティーで着るドレス。デートの服。
そんなシチュエーションで、私はいつも、自分の良い部分を引き立てる服を身に纏うようになった。
思えば、あのベロアのトップスは、「自分の強みを見つけ、それを前面に出して磨いていけ」という母からのメッセージだったのかもしれない。
くるくると目まぐるしく服の系統や髪型を変える私は、自分の良さも悪さもひっくるめ自分自身を見つめられていない、放浪の身のような状態に見えていたのだろう。
あの日の買い物は、本当に自分自身に似合うもの、自分の強みと向き合うきっかけを与えるためのものだったのかもしれない。
何度も何度も着倒したことにより、ベロアのトップスはすっかりくたくたになってしまった。
けれど私の良さを引き出してくれる、“ぴったりな服1号”なそれを手放すことはなかなかできなくて、もう着られることはないにも関わらずクローゼットに変わらず君臨し続けている。
そして、母はというと。
もう60歳も間近だというのに、変わらずノースリーブを着続けている。
そして腕の細さも、綺麗さも変わらず保ち続けているのだった。
「女優さんとかCAさんとか、人に見られる職業に就くと、それまで垢抜けなかった子もどんどん綺麗になっていくっていうじゃない? 腕もね、出してると人に見られる緊張感で細くなっていくのよ」
などと、よくわからないことを言いながら。
次に母に会うのは、この寒さが抜け、暖かくなった時期だ。
きっと彼女はまた、お気に入りの黒のタートルネックをスプリングコートの下に着て出かけるのだろう。
そのときは私も、あの日母に買ってもらったベロアのトップスによく似た、鎖骨が映える服を着て行こう。
そんなことをふと、考えたのだった。
Title/めいめい(@meimay_yoshioka)










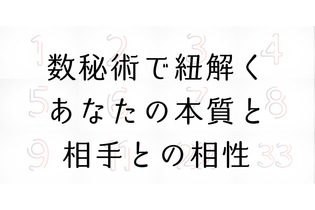










外資系広告代理店でコピーライターをしつつ文章をしたためる。趣味は飲酒。ブログ「おんなのはきだめ」を運営中。