やがて幻になるこの街で「鬼さん味園、手の鳴るほうへ」
めまぐるしいスピードで開発が進み、日々変化していく大阪の街。 いま目の前にあるわたしたちの街が徐々に幻になっていく光景を、リアルなのに少し不思議な物語で描く。 小説家・磯貝依里による大阪を舞台にした読み切り短編小説連載です。

こんなふうに右の足先から股で呑み込むみたいにゆっくり、トロッとした感じでポールに巻きついて。それから左脚はそこに絡めるように後ろでクロス、そこからポールにくっついたままくるりと回転して降りたらやわらかく崩れ落ちて、顔を上げて挑発――。
夕暮れのアメリカ村、ダンススタジオ。おもての喧騒がなだれ込むようにきこえてくるダンスフロアの真ん中で、双子の妹のルリはわたしにそう説明しながら、まるで照明を落とすようにふっとまぶたを伏せ、一連の動きをいとも簡単に披露してみせた。
それは血の気が一気に引いていくような冷たく透き通った踊りだった。そうして音もなくポールを滑り降りるとルリは、脱皮したばかりの白蛇が腐葉土のなかで濡れたとぐろを巻くようにその場でうずくまり、正面に置いた姿見の奥の自分に向かって切れ長の誘い目を流す。
たとえばほかのポールダンサーの踊りが観客の血流を沸騰させるものであるならば、ルリのそれはまったく真逆のものだとわたしはいつも思う。
じゃあシュリもやってみて、と言われ、彼女の真似をしてわたしがポールに巻きつくと、ルリは無邪気な声でけらけら笑った。
「なんや、シュリの身体はぜったいに緊張してしまうんやなあ」
そういえばわたしたちがこの世に誕生したその時も先に分娩台の上へ転がり落ちたわたしは全身を固く固く縮こめていて、いつまで経っても泣き声を上げずに口を真一文字に結んでいたという。一方ルリは母親の産道を全身で楽しむようにくるりくるりとなめらかに滑り降りてきて、まばゆい光を浴びたその瞬間、やわらかな伸びをしながら元気な産声を発したのだと、いつだかに母が言っていた。
「……みんなに観られるかと思うと緊張するに決まってる」
ぬるぬるの手汗で上手に力を入れられずなかなかポールを掴めずにいるわたしは早々に根を上げて、スタジオの隅に座り込む。
仕方ないなあ、とルリは困り顔で眉を寄せた。
「じゃあわたしが本番と同じ流れで踊るから、ちゃんと見て覚えてね」
はい、と差し出されたルリのスマホをわたしは受け取り、音楽アプリのなかから〈鬼の寄り合い用〉と名付けたフォルダを探し出し、そのあいだにルリはスタジオの隅に置いていた真っ青な薄衣の衣装を取ってきて、本番と同じようにふわりと羽織り、ひとつ大きな息を吐くと、両手を広げ、床に沿わせた片脚にピンと強い力を込めた。
「じゃあ、いくよ」
流れ出した数十年前のヒット曲のイントロにルリは嬉しそうに身体をしならせ、ひと筋の澄んだ水のように憑依する。わたしたちがまだ細胞の一欠片ですらなかった頃の、何十年以上も前に流行したそのヒット曲が、ルリの手にかかればみるみる新鮮に生まれ変わっていく。
サビのメロディがダンスフロアに溢れ出すとその脚はふわあと一八〇度にひらかれて、瞬きをして見上げたら、おそろしく美しい生き物が天を突くポールの先端で見事な羽をひろげていた。
自分とまったく同じ顔をしたその生き物の、丸く妖艶な軌跡を必死に目で追いかける。
ルリはほんとうに美しい。
もうあと数週間後にはわたしたちが一緒に浴びるはずの歓声とライトの極彩色と観客の放つ熱い吐息がまるで今ここに見えるかのようで、わたしは込み上げてくる心臓の鼓動を飲み込みながら、ぎゅっとこぶしを握りしめた。

スタジオでの練習を無事に済ませた途端、どうしてもキンキンに冷えたおいしい生ビールを飲み干したくなり、わたしたちは千日前へと向かった。
アメリカ村を南下しながら少しずつ東に寄っていき、御堂筋の大きな道路を渡る。一方通行で南へ向かっていく御堂筋の車の濁流を横断する時はいつも、増水した太い泥の河川を突き進む幻の自分のすがたをつい想像してしまう。
道頓堀の喧騒をなんとか進み、夜であればホストやスカウトたちがたむろする千日前商店街の入り口へと滑り込む。
千日前商店街、相生橋筋商店街、心斎橋筋商店街。ミナミの中心地にはいくつものにぎやかしい通りが縦横に広がり、互いの身を食い合う大蛇みたいに繋がっていて、千日前商店街に入って大量の人波に揉まれているうちにいつのまにかべつの筋の商店街に入り込んでいたりする。
おもてに腰掛を並べた屋台風の飲み屋通りに差し掛かるとやがて商店街のアーケードが終わって、ようやくあの建物が見えてくる。
なんば南海通りを抜けた先に建つ味園ビルは、千日前に横たわった赤黒い巨人のような外観だ。
かつて昭和後期の一大レジャー施設として建てられたもののバブルがはじけてからは一気にテナントが削げ落ちて、そこへ生まれた頃から不況しか知らないひとびとが平成時代の中頃からバーフロアで店を始めた。
もとはスナック街があった二階に今は大小さまざまなバーやライブハウスや食事処や美容院が四十軒以上も並んでいる。いわゆるウラなんばの最深層の場所のひとつで、毎夜にぎやかな声が響く。

わたしが最初にここを訪れたのは去年の夏。その少し前、わたしは二年間勤めていた東心斎橋の〈ラウンジ・梅〉という店のホステスを辞めた。
ほかにやりたい仕事があったというわけじゃない。ただ、自己愛を垂れ流しにした芸能人きどりのホステスたちと毎日待機室でくだらない会話を交わすことや、その会話のせいでじわじわと自分の表情筋が死んでいくような気がすることや、その情けない顔をつねに貼り付けていることなんかがくだらなく思えて衝動的に辞めてしまったのだ。
けれど仕事を辞めたからといって自由の身になれた気もしない。とりあえずふとんに包まって朝から夜へ陽の光が天井をのっそりと移動していくのを毎日ひたすら眺めつづけていたら、いつのまにか心も身体も調子をくずした。
そんな中、わたしのアパートから十五分のところに住んでいるルリが、ある晩遅くに「シュリちゃん、あーそぼ」と、やって来た。
すっかり引きこもっていたわたしにルリはにこにことサンダルを履かせ、髪を梳かし、勝手に買ってきた化粧水をすりこんでファンデーションを塗りつけると、
「たのしいトコに連れてってあげる」
そう言って、着替えさせたわたしを自転車の荷台にのせ、わたしのアパートのある桃谷から千日前通りをまっすぐに、上本町、日本橋と、夜空に放たれた鋭い矢のように走り抜けた。
二十分もすると、難波の中心にうずくまる赤黒い巨大な建物にたどり着く。
「とりあえずお酒を飲もう、元気になるから」
幼い頃から、いつだってルリは驚くほどに軽快なのだった。
「ここはミソノ。わたしが世界でいちばん好きな場所」
その時に目に飛び込んできた赤と青の巨大な円形を、わたしは一生忘れない。
小学生の時に算数でよく見た図形問題みたいな、わずかに重なり合って横に並んだ赤と青のふたつの円。
ネオン管で作られたその輪の中には、赤のほうに〈味〉、青のほうに〈園〉の文字が収まっていた。周囲もネオンの海である。けれどふたつの円形は、ほかの人工的な光よりも一層強烈な視線で難波の街を見下ろしていたのだった。
まるで、敵の襲来を警戒する幻の生き物のように。
レトロな蔓細工の施されたレンガ色の螺旋スロープを妹に手を引かれてのぼっていくと、エレベーターホールの向こうに夥しい数の店があった。ロの字型の廊下。そこを進んでいけば、何かイベントをやっているところもあるのか、すさまじいボリュームでテクノやアニソンやスカが鳴り響く店がある。
ドアの色やその周りの装飾は各々が趣向を凝らして手作りしているから統一感など一切なくて、まるで身体の内奥に細かくけばけばしい孔が無数に開いているかのようだった。
広い店もあれば身を寄せ合う小鳥のように常連客がうずくまっている四畳半の狭い店もある。けれどいずれの店でも共通していたのは、ヤニまみれのポスターも空き瓶もビールサーバーも蛇口も、招き猫もランプも水タバコもクッションも椅子もカウンターも標本も、そのぜんぶが埃を被って息をひそめながら、それでいて爛々と輝いていたことだ。
廊下をぐるりと一周まわったところで、二階正面にほど近い〈なんば紅鶴〉と看板の出ている店にルリは勇ましく入っていった。
入り口脇の大理石のベンチに使い古されたホワイトボードが立てかけられている。
〈第百三十六回 鬼の寄り合い〉
かすれたマジックペンで走り書きされた汚い字。入場無料ドリンク注文要。
「はやく、おいでおいで」
狭い入り口の向こうからルリの声に引っ張られた。
ひと一人通るのがようやくの入り口に比べて店内は予想以上に広々とし、あたりに漂うのは黴(かび)の臭いか、古びた木の臭いか。黒い石畳のフロアは縦長で百人以上は収容できるだろうか。突き当たりには一段高いステージ、店内の隅には中華風の赤いやぐらで組まれた半個室の休憩スペースもあり、そのそばでは金色のシャンデリアが輝く。
ビルの外とは何かが違う気配を感じる。空気がどこかやわらかい。それに少し、生あたたかい。けれどそれが一体何なのか、わからない。
六角形の可愛らしい紅のぼんぼりの灯りの下、のらりくらりと仕事をしている店員らしき男の子にルリは慣れた調子で威勢よく挨拶し、麦焼酎のウーロン割をふたつ作らせた。
「どぞ」と、長髪で丸眼鏡をかけた、こぐまみたいな男店員はとてもていねいにグラスを手渡してくれて、その冷たい液体にくちびるを浸しながら店の奥を覗いてみると、さっきまではまったく何も見えていなかったのに、闇に慣れはじめたわたしの瞳に突然何十人もの色とりどりの影が浮かび上がってきたので思わず息をのんだ。
「ここにいるのはみんな鬼だよ 」
ルリの言葉を耳にして、わたしはようやくその状況を理解した。
この街には鬼がいる。
そういう噂を、聞いたことがある。
鬼と呼ばれるそのひとたちは鬼と呼ばれるずっと前から棲息していて、きょうもどこかで遊んでいる。そのどこかのうちのひとつがこの味園ビルであるのだと、にんまり笑ったルリの瞳が語っていた。
鬼という名はそもそもいわゆる蔑称だった のに、時が経つにつれてそっちがほんとうの名前になってしまい、もとは〈彼ら〉が一体何と呼ばれていたのかみんなもうすっかり忘れてしまった。
名前は忘れられたけれど鬼の特徴は誰だって知っている。鬼はサブカルチャーが好き。アンダーグラウンドが好き。誰かが軽んじるものを拾いあつめて自分なりに愛するのが好き。音を流して歌って踊る。溺れるほどに酒を飲む。
だけどそれは名前じゃなかった。
そういう類を好むひとはいつだって誰かから無遠慮に観察されて容赦なく解釈されつづけて、観察する側に悪意がなければないほどに〈彼ら〉の存在は陳腐に形容されつづけ、「サブカルっぽい」「はいはいアングラ」と誰かが悪意なくつぶやくその度に、〈彼ら〉はひとりまたひとりと虚しさに溶けて消えていった。
そうして消えていく〈彼ら〉のことを誰が最初に鬼と呼んだのかはわからない。けれど鬼は鬼と呼ばれて、やがて鬼たちも自分たちを鬼と呼びはじめた。
鬼が鬼であることを自覚した途端、鬼たちのあたまの両側にほんもののツノがにゅるんにゅるんと生えはじめた。ちょうどこの街で、この国で、鬼を忌避する法律ができた頃のことらしい。
鬼が鬼になってからも、誰かから観察されるのは変わりない。ひとは鬼のことを馬鹿にしながらも、どうやら見ずにはいられない。
それどころか青汁を飲み干して「まずい、もう一杯」と笑うひとみたいに、くさしつつも喜んで、鬼たちの性質を理解しようとする。自分たちの叶えられなかった夢を無責任に託すかのように 。
そういう人間の勘違いに抵抗する鬼もいるけれど、ほとんどの鬼たちは日々自分自身の鬼の所業に忙しいから背を向ける。
だから鬼たちは誰かにその背を見られることには慣れている。ひとびとの古びた身勝手な夢想のために、鬼たちはいつのまにかただのオブジェになってしまった。見られる存在。見られる身体。
それはこの、味園ビルの見た目そのものみたいだった。
鬼たちは半年に一度ほど盛大な宴をひらく。その晩開催されていた〈第百三十六回 鬼の寄り合い〉は、わたしたちが入った頃にはもう宴のピークを過ぎつつあった。
暗いフロアの右奥にはDJブースが据えられて、背の高い典型的なしましま柄の男の鬼が左右に尻を振りながらポップスを流していた。明るいメロディラインのアイドル曲なのに、酸で鼓膜を溶かされているような強烈なディレイが重ねられているせいで何が何だかわからない。
フロアの中央には青い巨大なビニルシートが敷かれ、そこにはなぜなのかローションがぶちまけられてぬるぬる光っている。そのローションの海から上がってきたらしい全身をぬめらせた男や女やそのどちらでもないたくさんの鬼たちがシートのそばで車座になって、一心不乱にスナック菓子を頬張り、酒を飲み、音に身体をゆらしていた。曲の拍子に合わせて時おりオー、ジャッジャー、と雄叫びと拳をあげる。
その横の輪ではクイズの機械をピンポン鳴らして大喜利が繰り広げられていた。
バーカウンター脇の半個室では、ラバーランジェリーをまとった鬼の女王がべったりと口紅を塗った顔をゆがませて、豚そっくりの女の鬼をろうそくだの鞭だの針だので虐めている。それを観ている鬼たちがいる。すると突然背後の入り口から、どうしてなのかキリストの処刑衣装を身に着けたふわふわ髪の中年の鬼が嬉しそうに身をくねらせながら店内に駆けてきて、ローションの海に飛び込んだ。音楽のゆがみはどんどん激しくなる。
一杯目の麦ウーロンが空になる頃にはなんだか意味もわからないのにわたしまで愉快な気持ちになっていて、そうして気づけば意味もわからないのに車座に加わって鬼たちと一緒に音に合わせて拳を振り上げ、ジャッジャー、と笑っていた。
ほんものの鬼の顔を間近で見たのは生まれて初めてだったから興奮した。
その時突然、音がやむ。暗転したフロアにゆっくりと青いライトが点いて、それまで一心不乱に踊っていた汗まみれの鬼たちが何かに気がついてつぎつぎにその場に腰を下ろした。
後方でふわりと広がる気配に瞬間、振り返ったわたしは息を飲む。
そこには半裸に色鮮やかな青の衣装をまとったルリがいて、彼女は薄っすらと微笑みながらステージに立てられたポールに向かってひとすじの風みたいに走っていった。
さっきまでひとだったはずのルリの頭の両側には、ライトに照らされた群青色の鬼のツノが生えていた。

ビール飲みに来た、と練習後のわたしたちが勢いよく味園のバー〈デジタルカフェ・スクリプト〉に飛び込むと、たまにバーカウンターに入っているわたしたちと同い齢のランちゃんが、いらっしゃい、と大きな瞳をくりくりさせて乗り出した。
ランちゃんの注いだビールをひと息で飲み干し、わたしたちは声を揃えておかわりを頼む。
「朝イチでスタジオに缶詰しとったから、ゆうべからずっとお酒ガマンしとってん」
「ええ、そんな長い時間も練習しとったんや、お疲れさまあ」
ランちゃんにはもうとっくに立派なツノが生えている。ランちゃんはルリが最初に紹介してくれた野良の歌手だ。わたしがここへやって来る前から、ルリとはいつも一緒に鬼の寄り合いに出演している。
ランちゃんは平成時代のアニメが大好きで、そのカバーを歌いながらくるくる踊るチャーミングな鬼だった。ぬるんと生えた小ぶりな黄色のツノにいつも黄色いレースのリボンを巻いている。
「シュリちゃんはまだツノ生えへんねんなあ。鬼になってずいぶん経つのになあ」
わたしの頭をひょこひょこ心配そうに見遣るランちゃんに、ツノは永久歯みたいなもんやから。と、ルリが言う。
「ものすごい勢いで生えてきて乳歯を押し出すようなやつもあれば、乳歯が抜けてもぜんぜん生えてこやんやつもあるやろ」
「さすがルリちゃんやなあ、例えがさすがやわ」
ランちゃんはルリの信奉者だった。
確かにルリは特別な女だと思う。
しなやかな身振りや頭の回転の速さ、誰をも惹きつける言動、どんなに地味な服を着ていようとも隠しきれないその色香は、暗闇で強く匂い立つ蘭の花がそのまま人間に形を変えたかのような霊気を帯びていて、だから去年、彼女が味園で踊り子をしていることを知った時もわたしはぜんぜん驚かなかった。
「来月はいよいよシュリちゃんのデビュー日やなあ」
ランちゃんはわたしたちをあらためて眺め、嬉しそうに笑う。
「もう準備万端?」
「たぶん」
わたしは〈デジタルカフェ・スクリプト〉の向かいにある〈紅鶴〉の、そのステージを思い浮かべる。
来月の鬼の寄り合いでわたしは初めて踊り子の鬼になる。ルリの隣で、たくさんの鬼の仲間たちの前で、目映い光を全身に浴びてポールダンスを踊るのだ。

初めて味園を訪れたあの日、見事なポールダンスを踊り終えたルリに感動し、わたしも鬼になってみたいのだと言った時、ルリは全身を喜びで膨らませ、青いツノをさらに青々と光らせて抱きしめてきた。ルリはいつだって誰かの身体にかんたんに触れて、すぐに惜しみない愛を表現する。
とにかく何の鬼でもいいからわたしも鬼になってみたかった。鬼はなりたいと願うものではなくて気づいたらなっているものなのだと怒る真面目な鬼もいるかもしれないけれど、そんなことは気にしなくていいよとルリはわたしに微笑む。
わたしはとくに取り柄のない人間だったから、ひとまずルリに踊りを習うことにした。
「踊る鬼はいいよ、うわあ綺麗やなあって、みんなに大事に見てもらえるからね」
その日からルリはわたしの先生となり、ルリがよく借りているというアメリカ村のダンススタジオにわたしは通い、三日に一度の手ほどきを受けることになった。
わたしが知らなかっただけで、ルリはとても評判の踊り手なのだとほかのポールダンサーたちが教えてくれた。味園ビルを中心の島として、時にはよそへも出張し、激しい音楽に合わせたポールダンスやストリップ、エアリアルをフロアで披露して客を熱狂させるという。
元からダンスの訓練を受けていたわけではない。わたしの知っているルリは、東成区の小さな歯医者で、歯科衛生士として毎日真面目に働いている。聞けば大人になって夜遊びをおぼえはじめた頃に急に興味を持ちはじめて、知り合いのダンサーからレッスンしてもらえることになったのがステージに立つきっかけだったらしい。
一晩じゅう汗だくで踊り果て、桃色の視線を雨のようにびしょびしょに浴びるのがうっとりするほど心地いい、その汗で身体じゅうに張り付いたチップの紙幣を剥がすのはそれ以上に気持ちがいい。ルリはわたしにそう言っては、自分に生えた青いツノを愛おしげに撫でる。
そんなルリと一卵性の双子であるにもかかわらず、どうやらわたしのほうにはまったくと言っていいほどに踊りの才能はなかったらしい。どれほど頑張ってもルリの見事な動きには辿りつきそうもなかったし、撮影した練習動画を見てみれば、まるで屋台のケバブが情けない湯気を出しながらモタモタ回転させられているような無様さだった。
それでもルリはわたしを見放しはしなかった。それどころかまだ高速回転の動きもままならないというのに、先月の平日真っ昼間、いきなりわたしを呼び出したかと思ったら、九月の半ばの〈鬼の寄り合い〉にふたり揃って出演する約束を取り付けてきた、と満面の笑みで飛びついてきたのだ。
「ステージが決まったら誰だってぜったいに踊れるようになるから、大丈夫」
ルリがあまりにも嬉しそうに言うものだからわたしは「ありがとう」と頷くほかにどうしようもなく、いつもひと晩で二百人近くの客が来るよとルリが笑うのでぞっとして、けれど突然訪れた緊張と逃げたい気持ちのそのあいだに、いよいよ自分もほんとうに鬼の仲間になれるのだという、灯火みたいに小さな興奮が揺れているのを感じたのだった。

近々ここへも鬼退治の噂があるらしい。というのを、ランちゃんとルリと三人で、〈紅鶴〉から向かって左側廊下にある〈ホテル・アドリアーノ〉というバーで飲んでいる時にカニヤマさんから聞いた。
カニヤマさんはいつもツノをふさぐみたいにヘッドホンを装着していて、確か齢は六十歳手前、顔は陰気なのに性格はすこぶる陽気だ。本業は漫画家らしい。ルリのことをとても可愛がっている。
そのカニヤマさんが眉間にしわ寄せてウィスキーを舐めながら、店内に飾られた木魚をチーンと鳴らして「先月キタもやられた、こっちもじきや」と言う。
「鬼退治なんて風習、平成のむかしでとっくに終わったんちゃうんですか」
「リバイバルや」
「リバイバル」
警察の行いに使うタイプの言葉ではないような気がしたけれど、カニヤマさんがビールをご馳走してくれたので素直に頷いた。
音楽を流して踊ったり歌ったり酒を飲んだりする鬼たちを警察が駆逐する行為に対して、鬼退治だなどとふざけた名前を付けたのは、誰なんだろう。
もうずいぶん遠い時代に大規模な鬼退治が流行ったことがあったのだと、わたしも鬼になりたての頃に鬼づてに聞いた。
捕まったり消された鬼もいたけれど、ほとんどの鬼は散り散りになりつつもなんとか生き延びた。しかしながらその時生き残った鬼のなかには警察に島を奪われた者たちもいて、カニヤマさんもそれまで過ごしていた島を失い、ようよう味園に流れ着いたという。
「鬼退治、あんたらも気ィつけや。つぎの寄り合いの時に来よるかもしれん」
「まさか」
ランちゃんがふふ、と笑う。
「その油断が大敵や」
ランちゃんの無邪気なまるまるとした微笑みがちょっとだけ気に障ったのか、カニヤマさんはわたしとルリにだけビールの追加をご馳走してくれて、アルコールで紅潮したランちゃんの頬をデコピンでピコンとはじいた。
「むやみに鬼を取り締まったらあきません、鬼も鬼で生きてます、悪いこと何もしとりません、って新しい法律がいくらできてもな、言葉の約束事なんていつでも解釈こねなおせるんやで。言葉に守られとるかぎり、俺らは言葉に裏切られる。ひとも鬼も順応してきた証拠を積み重ねて、それで歴史はくりかえす」
せやから、とカニヤマさんが続けて何かを言おうとしたその時、ぬいぐるみやこけしに埋もれた入口のドアが開いた。
「おつかれす」と、〈紅鶴〉の店員のこぐまみたいな男の子がのそのそ入ってきて腰を下ろし、そこでカニヤマさんの話は線香花火の火の玉が落ちるように消えてしまい、ふたたびバーのなかは暗くなる。
わたしもランちゃんもこぐまみたいな男の子もみんな、カニヤマさんがかつて暮らしていた島がどんな場所だったのかを知らない。
わたしたちが今、一体どんな言葉に守られているのかも知らない。
こぐまみたいな男の子に続いて、さらに三人の知り合いがどやどやと賑やかに入ってきて、おう、おまえら飲んどったんか、とわたしたちに手を振った。
ひとりは鬼の寄り合いでいつも古いプロレス音楽のDJをしているオリグチさんという白いツノの鬼。残りのふたりはとくに一芸をやっているわけではないけれど毎晩味園に飲みに来てはくだを巻く三十半ばの鬼で、サチカとアンコ。
みんなそうたくさんお金を持っているわけではない。住所不定の者もいるし、ふらりと入ったバーのカウンターを見回してみれば無職だって珍しくない。明日をなんとか生きのびるため、溺れるように酒を飲みにくる鬼も多い。
わたしだってそうだ。ラウンジを辞めて単発の派遣をくりかえしてようやく食い繋いでいる。とりあえずふらふらしているわたしには正直しんどい遊び代や飲み代だけれど、それでもここへ足繁く通うのはとにかく何か、この世界と自分とを結びつけるものが欲しかったからなのかもしれない。
ルリに連れられて味園へ入り浸るようになってから、同じように訪れる鬼たちと夜を過ごすようになってから、わたしはずいぶんとこの世界で息をするのが楽になった。自分が本を読むのが好きだったことを、本が好きな鬼と話していて憶い出した。それから絵を描くのが好きだったことも、音楽を聴くのが大好きだったことも憶い出した。誰かと他愛のない話についてだらだら喋るのが、大好きだったということも。
鬼たちはやさしく、温かい。鬼たちと過ごしていると、自分が自分の正しい機能をみるみる取り戻していく。
白い鬼と何かを話していたルリが大声で笑った。
見たことなどないはずなのに、ここへ来て踊りをはじめた頃のかつてのルリの幻が突然わたしの隣席にふっとあらわれて、今目の前にいるルリと二重写しになる。
青く美しいツノを生やしたこのルリも、今のわたしと同じようにこの世界と自分とを結びつけるものが欲しかったんだろうか。ここに集うたくさんの鬼たちと言葉を交わし、温かい時間を過ごして朝を迎え、そうして誰かに、無表情な人間たちの世界の底でうずくまっているみっともない自分を、見つけ出してもらいたかったんだろうか。

真っ青な薄衣の衣装をまとったルリは散らかった楽屋のなかで天女のごとくひるがえり、わたしの胸もとに手を伸ばした。そんなゆるい着方しとったらポールに擦れて脱げちゃうよ、とルリはわたしの羽織ったお揃いの、けれど真っ赤な薄衣の衣装のずれを直し、微笑む。
「うん、上出来」
本番はこれからだというのにルリはもうすっかり満足げだった。
とうとうやって来た〈第百三十八回 鬼の寄り合い〉はすでに開場しており、ランちゃんの話によると入場規制を出すほどの大入りだという。ルリとわたしは昼過ぎに起き、夕方まで最後の練習に打ち込んでそのまま味園に来た。タイムテーブルではちょうど日付の変わる午前0時がわたしたちの出番だった。
味園ビル三階の楽屋の床を通して、宴の響きがあしのうらに伝わってくる。
スロープを降りて〈紅鶴〉に向かう途中「見て」とルリが遠くを指差すので振り向けば、祭り行列のように飛び跳ねたりふざけあったり戯れながらネオンの海の底をこちらへぞろぞろやって来る鬼たちがいたので、思わずあっと目を瞠(みは)った。
ルリの瞳もこの街じゅうのネオンを吸い込み輝いていた。
この街の裏の底を生きのびる鬼たちが両手を振ってやって来る。金棒の代わりに一夜の期待をかつぎ、笑いを夜空に放り投げ、人間たちの波間を縫ってぞろぞろぞろぞろやって来る。
並んで見下ろすわたしたちの二色の薄衣の裾を涼しい秋風がすうっとくぐり抜けていく。
いい? とルリはわたしの右手を握りしめる。
いい。と、わたしは緊張に掠れた低い声を絞り出す。ルリの手のひらの温かさは、去年わたしをこのビルへ導いたあの夜とぜんぜん変わっていなかった。
〈紅鶴〉のフロアは興奮しきった鬼たちであっというまに満杯になり、バックステージの裏で大きく息を吸ったわたしは手のひらに鬼の字を書いて十文字を切りかぶりつくと、メインステージに設置された二本のポールの足もとへ、先に駆けていったルリの後を追って飛び出した。
込み上げてくる動悸で咽喉が引きちぎれそうだった。
フロアの中央にもポールが一本突き立てられており、そこではすでに男の娘の鬼がブーメランパンツやブラジャー、レザーのハーネスに何十枚ものチップを挟んでポールの先端でくるくると舞い踊っていた。彼の鎖骨付近に大きく彫られた蛇と菊の刺青が汗と脂を吸って水から揚げられたばかりのように生き生きと蠢き、なめらかな褐色の肌は照明を受けて光り輝いていた。燻すような熱気。びっしりと鋲が装飾された殺人道具みたいな彼の厚底のヒールが遠心力でさらに重みを増し、観客の顔の間近でヒュッと風を切る。男の娘の鬼の踊る光景を、ルリはステージ上からじっと見つめている。
やがてわたしたちが照明を浴びて現れたことに気づいた観客が徐々にこちらを振り向き集まってくると、ルリはわたしにニッと歯をみせてねっとりと右のポールに脚を巻きつけた。
緊張のせいで遠のいていた耳がその瞬間プツンとはじけ、全身に音楽が流れ込んでくる。
真っ白なライトで満たされたステージからは前列の観客のすがたしか見えないけれど、そこ此処に見知った鬼たちの気配がした。
フロアのどこかで膝を抱えながら、ムッとした愛らしい顔でわたしたちを見上げているカニヤマさんを感じる。先に歌の出演を終えたランちゃんが両手を胸に当ててわたしたちを見守っている。サチカやアンコもいる。ここへ最初に訪れた時に出逢ったしましまの鬼や水色の鬼も、〈紅鶴〉のこぐまみたいな男の子の鬼も、廊下にひしめくいろんな店で毎夜くだらない話を交わす、いろんなツノを持った鬼たちも。
みんなが観ている、と目を開けたら、自分でも信じられないような速さで回転し、いつのまにかポールの先端へたどり着いていた。
回転が右に寄る度に視界をかすめる青い色。
真っ青な影が残像を残して空中をよぎっていく。回り、演技し、全身をしならせるその度にそれはいともたやすく現れて、鏡面状に踊るわたしの影に重なっていく。
曲のピークが訪れる。何度も何度も教えてもらった技の完成風景を眼に浮かべながら左脚を差し出し、空へ駆けのぼるみたいにステージを蹴って、思い切り逆さに飛び上がる。
そうしてそのまま左から下りるように両脚をひろげ、わたしたちはふたり同時に宙に大きな円を描いた。
ふわりとひらいた脚の余韻を水面のようにゆらめかせ、場内は静まり返っていた。そこへ、ひゅう、と口笛がひと筋突き抜ける。するとフロアは徐々に熱を取り戻し、ようやく息をふきかえした観客たちのすべての瞳がわたしとルリに吸い寄せられているのがわかった。
わたしの赤い紗とルリの青い紗の裾がわずかに重なって回転する。
二色の円形。わたしたちが毎夜ひそむ赤黒い巨人のようなこのビルの、あの巨大なネオンを見上げているのと同じ瞳の色。
みんなが口を半開きにしてわたしたちを仰いでいる。
それはどこか、わたしたちに勝手な夢想を抱く人間たちがこのビルを見上げる時の表情と、なぜだか似ているように見えて不思議だった。
ゆるゆると回転が止まりはじめると、隣で回っているルリの顔が見える。
幸せだ、と思った。

と、その時、〈紅鶴〉の入り口の向こうで大音量の曲をも突き抜ける叫び声が響き渡り、瞬間、ステージが明転して一気にすべてが掻き消えた。
おい、鬼退治がきた! と、男の鬼が凄まじい勢いで観客を掻き分けてフロアに飛び込み、声を張り上げる。
大勢の鬼たちの緊迫した眼の光がその一点に注ぎ込まれた。
鬼退治。
鬼退治。鬼退治?
鬼退治……?
フロアで身を寄せ合っていた観客たちが男の声に反応して至るところで互いを見やり、つぶやき合う。首を傾げ合う。同時に、鈴の音のような得体の知れない音が周囲からさざめきたった。きっとそれはこの場にいる鬼たちの、突如いっせいにふくれあがった鼓動の反響にちがいなかった。
やがて「あっ」とみるみる血相を変えて立ち上がり、客たちは男と同じように叫びスイッチを入れられたように〈紅鶴〉を飛び出し逃げはじめた。
ポールの頂で脚をひろげて逆さまになっているわたしにはその混乱の渦が、頭上でみるみる様子を変化させていく空模様のように見えた。早回しで晴天から豪雨へ、そうして嵐へ渦巻いていく、さっきまでやわらかに集っていた雲たちが散り散りに分かたれていく。
もう何秒ものあいだ脚をひろげつづけているだろう。全身が引き攣り、下方を支えている右手がぐらりと軋み、滑る。痛い。もうこれ以上は保たないと思う。それより鬼退治。鬼退治が来たんだ。わたしたちも逃げなければだめだ。島を追われたカニヤマさんの顔が脳裏に浮かんだ。
痺れかけている両脚の先を閉じてポールから身体を剥がし一気にステージの床へ滑り降りようとしたその時、しかしわたしの視界の端で、青い薄衣がひらりと舞った。
「シュリ、最後まで踊って」
身体を正位置に引き上げたルリが、バレリーナの形をとって勇ましく胸を反らしていた。
「降りたらだめ。まだ、みんな観てくれとるんやから」
津波の引いたフロアには確かに十数人の鬼たちが取り残されていた。
みんな呆然と立ってわたしたちを見上げていた。波にさらわれてしまったのかランちゃんのすがたはどこにもなかったけれどわたしたちのすぐ足もとにはカニヤマさんがいた。ぽっかりと力の抜けた、それなのにすがりつくような眼でわたしたちを見上げていた。知らない鬼も残ってくれていた。入り口に酒樽を積んでハリケードを作ろうとしている〈紅鶴〉の店員もいれば、こぐまみたいな男の子はいつもどおりのぽやんとした表情のまま、まるで何事もなかったかのように音響とレーザーを操作してわたしたちのつぎの動きを待っている。
ルリは隣で踊りつづけていた。
入り口の向こうでは何かが割れる音と、たくさんの鬼やひとの声が混ざり合いうねっている。逃げたものの行き場がわからずに揉まれ揉まれてフロアに戻ってきた数人の鬼と眼が合う。なにもかもぜんぶがめちゃくちゃだった。
わたしは躊躇いを飲み込みながらもう一度ポールを握りしめた。
ルリの後を追って同じバレリーナのポーズに片脚を上げる。
その途端、引き潮のフロアからパチ、パチ、と手のひらが小さくはじける音がきこえ、それはやがて豪雨と錯覚するほどの拍手に変わり、頂のわたしたちを大きくやわらかく包み込んだ。
最後の技をきめると音楽は手繰り寄せられた糸のようにフェイドアウトしてゆき、ポールから降りたわたしたちはそのまま冷たいステージに膝をつき深々と頭を下げた。
外はまだ混乱の最中で、わたしたちが踊りを終えるや大量のひとの群れがこちらへなだれこんでくる気配がした。ふたたび大きな津波が押し寄せて残っていた鬼たちがみるみるうちにひとびとに飲み込まれて流されていき、けれどその流れにしぶとく抗うように波間から鬼たちが顔を出し、アンコール、と叫んでは沈みまた浮かび上がり、アンコール、と叫んではまた沈んで浮かんで、拍手の残響が混乱の波を乗り越え、ひとの侵入を最後まで粘り強く拒むかのようにいつまで経っても鳴り止まない。
浮かんでは沈むその鬼たちのなかには見憶えのあるわたし自身の、あるいは初めてここを訪れたルリの顔もあるような気がした。初めて眼にした鬼の踊りに釘付けになっているそのすがた。出逢ったその瞬間、自分も鬼になりたいと願ったそのすがた。
アンコール、アンコール、と遠いどこからかカニヤマさんの声がきこえてきて、ルリがわたしの手を取った。拍手はまだ鳴っている。鬼も鬼で生きてます、悪いこと何もしとりません。カニヤマさんがこのあいだ言っていた言葉がふいに胸に蘇る。
一度踊りきって緊張のすっかりほどけたわたしたちはそれから顔を見合わせて、込み上げてくる笑みを交わし、ふたたびポールに脚をかけた。
悪いけど今はいちばんたのしいところだから 、綺麗なルリと綺麗にくるくる回るから、もうちょっとだけ踊らせてほしい。もうちょっとだけ待ってほしい。
だってこのビルの宴の夜はついさっき、はじまったばかりなのだから。










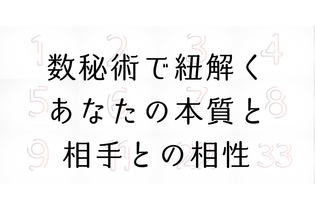










本を読むのが好きです。小説を書いたり、書評を書きます。関西出身在住。