やがて幻になるこの街で「愛のていねいな暮らし」
めまぐるしいスピードで開発が進み、日々変化していく大阪の街。 いま目の前にあるわたしたちの街が徐々に幻になっていく光景を、リアルなのに少し不思議な物語で描く。 小説家・磯貝依里による大阪を舞台にした読み切り短編小説連載です。

「お忙しいところ大変おそれいります、〈千里中央ローファイ・メモリーズ〉でございます」
まるでつるつるの蚕の糸を吐くように、わたしは澱みなく呼びかけた。
声を出すのと同時にお辞儀をしたためにヘッドセットがギシ、と軋む。
目の前のパソコンモニターにはくすんだ色のシステム画面が映しだされていて、通話が開始されたその瞬間に、お客さま情報の枠が桃色にぴかぴか点灯した。
画面左上に記載されている顧客名をカーソルでぐるぐるなぞりながら訊ねる。
「こちらはサタケ・ユキエさまのお電話でお間違いございませんでしょうか」
《はい》
「いつもご利用ありがとうございます。本日ご連絡いたしましたのは、今月のお支払いが期日を過ぎてもお済みでないようでしたので、……」
わたしが舌を丸めて絶妙な温度に言葉尻を濁すと、サタケ・ユキエもすでに何百回とくりかえしてきた慣れた口調で《……ああ》と、ため息を吐いた。
何万と存在している督促対象の、そのなかの一体誰に通話が当たるのか。
それはコンピュータのランダムな思し召しではあるけれど、サタケ・ユキエはむかしからのリボ払い未納の常連客なので、わたしにとってはこれが彼女との五十四回目の通話だった。
「あさって十八日の午後三時までにご入金いただくことは可能でしょうか?」
《あさってはむり》
「それでは、いつ頃でしたらご都合よろしいでしょうか?」
《二十日が給料日だから二十日にしといて。あたしはいつも二十日だから》
サタケ・ユキエはひどく不機嫌だったが、これもいつもと変わりない。
《毎回ちゃんと二十日にゆうちょから入れてるでしょ? ちゃんと書いて残してる? 土日が入ったらずれるけど、基本あたしは二十日だから》
「かしこまりました、それでは二十日にご入金お待ち申し上げております」
《ほんっと、〈あれ〉はお金ばっかり食うんだよねえ》
あー、ほんじゃーね。ばいばーい。まったねー。と、サタケ・ユキエは受話器から遠ざかり、通話はぶじに終了する。
電話が切られるとその途端、それまで桃色にぴかぴか光っていたお客さま情報の枠は点灯をやめ、文字が縮んで画面上でうずくまり、まるで小さな生き物の心臓がとまってしまったみたいだった。
顧客名、年齢、職業、住所。分割払い、あるいはリボ払いの残金表示。前月までの支払い状況。
その下に付されている備考欄に「二十日に支払い予定」とすばやく打ち込み、再架電不要のボタンにチェックを入れた。支払い予定日付をカレンダーから抽出する。そうすると支払い予定日の三日後まではもうサタケ・ユキエに電話が飛ばされることはない。
彼女がきちんと支払わなければ、また数日後、誰かが彼女に督促の電話をかけるのだ。
ふーっ、とため息を吐く。更新ボタンをクリックする。
すると画面は一瞬で変わり、つぎの〈団地〉未払いのお客さまへと繋がれる。

かつてはなだらかな山の表面にもはるか遠くまでつづく平地にも、真っ白なウロコが一面びっしりと貼りついていて、目を細めて近づいてみればそれは一つひとつの小さな家で、中にはあらゆる家族が棲んでいて、ここはそんな団地で埋め尽くされたひとかたまりのニュータウンだった。
大阪府の北の果てにある緑の深き千里山。それがきりひらかれて団地のウロコが植え付けられたのは、今から一八〇年ぐらい前のことだ。
当時の千里ニュータウン建設の映像は、テレビの懐古特集やネットサーフィンでわざわざ観るまでもなく、わたしのなかに深く深く根づいている。
まぶたをとじてみれば今すぐにでも思い描くことができる。
生まれたてほやほやの団地棟が果てしなく並んでいるあの懐かしい景色。
バギーに赤ん坊をのせた若い母親たちが団地棟の前を群れになって通り過ぎ、駐輪所をそなえた一階の入り口からはサラリーマンが連射で排出されて、街から都心へと列になって働きにいく。
やんちゃな子どもたち。整頓されたニュータウンの、一切の乱れが排除された完璧な空間。それでも子どもたちはなんとかその隙を見つけ出し、公園の隅に生えた雑草を抜き取り、投げ合い、駆けまわって遊ぶ。
ここには小学校も中学校もございます。病院も公園も、もちろん墓地もございます。近くには芸術的な建造物もございます。こんにちは、こんにちは。世界のひとが。こんにちは、こんにちは。さくらの国へ。世界の国からこんにちは。こんにちは、こんにちは、握手をしよう。
とにかくかつてこの地は呆れるほどに広大で、それでいてミニマルな幸福の集積地だった。

団地趣味、という奇怪な言葉が流行しはじめたのは、バブルがはじけ、廃墟時代を経て、千里ニュータウンの巨大な死体が行政や民間の手によって、無理やり現代的なリノベーションを施されはじめたのとほぼ同時期だったらしい。
団地はいい。団地は落ち着く。けして裕福ではない、団地に漂うノスタルジー。
そんな無意識が誰から誰へというわけでもなく、いつのまにかこの国のいろんなところに満ち満ちていた。
団地、という言葉を示されれば、誰もがほとんど同じ光景の記憶を思い浮かべずにはいられない。
かさかさに乾いたねずみ色のコンクリート階段の、四角いらせんを駆け上がれば見えてくる鉄扉の玄関。軽いのか重いのかよくわからないそのドアを小さな手で引っ張り開けると、鼻にひろがる生あたたかな〈じぶんちのにおい〉。
狭すぎる靴脱ぎ場ではべろべろに傷んだいくつもの靴やサンダルが重なり合い、傘は将棋倒し。新聞だの古雑誌だのチラシだのの紙束が玄関でタワーをつくっているせいで、上がればたちまちこけそうになる。
短い廊下を一歩、また一歩と進み、リビングを目指す。
〈じぶんちのにおい〉が濃くなっていく。
廊下の途中には脱衣所、風呂場、それからトイレ。脱衣所の洗濯機の上には湯船で遊ぶプラスチックのおもちゃの山。歯磨き粉で汚れた鏡。けして取れない黴(かび)の色。トイレのドアには両親の仕事のシフトが貼られている。その横には幼稚園で作ってきたチューリップの折り紙と、月刊雑誌の付録のシールの白い剥がれ跡。
テレビのあるリビングがこの小さな空間のすべての中心だった。
もちろんテレビの周りも恐るべき散らかり様だった。ぬいぐるみだの季節はずれの七夕飾りだの、支払督促状のぶ厚い封筒だの。母親が放り投げてそのままにしている介護雑誌だの、とりあえず出っ張りにひっかけた洗濯物付きのハンガーだの。それが落下して雪崩れた服の山だの、くしゃくしゃに潰れた薬局の袋だの。教科書の飛び出たランドセルだの。
リビングから地続きのダイニングには食卓があって、クロスのかけられたそこには始終出しっ放しの醤油瓶やソースなんかが転がっていたりする。目玉焼きの黄身のこびりついた朝食の皿まで出しっ放しだ。
ぱんぱんのゴミ袋もいくつ溜まっているかわからない。
その食卓の席からまっすぐ目を上げてみれば、奥の和室が正面に来て、障子のむこうに学習机の影がのっそりと見える。
とにかくいずれの団地の家も、尋常でなく物が多い。
そうしてその散らかり様には、まったくもって規律がない。

田舎にすむ祖父母などいないにもかかわらず、そっとまぶたを閉じてみれば、そこには穏やかな里山と風を受けてつやめく田んぼの畦道、川原の砂利道、それから沼の水芭蕉を懐かしく思い浮かべることができるのと同じように、現在のこの国の子どもたちは、あの散らかりきった団地で暮らした経験が一切ないにもかかわらず、あの光景をとても色鮮やかに憶い出し、心のもっとも温かい場所でいつくしむことができる。
それは遺伝子レベルの刷り込みであるのだといつかどこかで聞いた。
ノスタルジーという感情は何よりも強烈な宗教であり、本能であるのだとも。
そうして、遠いむかしのこの国の人間たちがかつて架空の田舎の記憶を心の拠りどころにしていたのと同じに、長い年月をかけていつのまにかひとは、架空の団地の記憶を心のよりどころにするようになっていた。
そんな人間の頼りない感情を相手にふしぎな商売をはじめたのが、わたしの勤める〈千里中央ローファイ・メモリーズ〉だった。
会社は二本柱で構成されている。
まずは何よりも団地の記憶の生産。
工場の場所は重要機密事項であるから、わたしのようなボトムの社員には一切の情報が与えられていない。うわさではその原料が千里山地域でしか採取できないために、旧千里ニュータウン団地街のいずれかにあるらしい。けれどそこを歩き回っても、それらしき施設を一度も目にしたことはない。大きな工場であるのはまちがいないと思う。
工場で大量生産された団地の記憶は、発注者が送付してきた希望アイテムに注入されてダンボールに梱包される。
赤ん坊から小学生までずっと手放せなかったブランケットの切れ端に注入してほしいと注文書に記入する者がいたり、子ども時代ずっとランドセルにぶら下げていたキャラクターキーホルダーに注入してほしい者、肌身離さず抱きしめていたファミリアの白いクマのぬいぐるみに注入してほしいという者もいる。
同僚から聞いてとくに面白いと思ったのは、小学生の時に履いていた上履きを二十年ぶりにわざわざネット購入して、サインペンで過去とまったく同じ落書きを施し、子どもの時の癖字を苦労して再現しながら名前を書いて、それに注入してくれと送ってきた男の客の話だった。
それは、無機質なよりしろであれば何でもいい。
架空の団地の記憶を注入されたアイテムは〈団地〉という商品となる。
使い方はとってもかんたんだ。
日々の生活において何かストレスに晒された時〈団地〉に強く触れれば、即座に脳のスクリーンに〈平均的な団地の部屋〉の光景が映し出され、身も心もあの団地の散らかりきった暗い空間へと転送される。そうして懐かしい団地の世界に没入する。鼻腔が、あの〈じぶんちのにおい〉に生あたたかくやわらかく満たされていく。
胎内めぐりだとそれを表現するひともいる。
ストレス値は瞬時に下がり、つぎに目を開けた時、ノスタルジーの快楽物質を分泌したひとびとは、生まれ変わったように穏やかな精神状態で生きていくことが可能となる。
注入当初はあくまで素体である〈団地〉は、もちろんその後、それぞれの好みの団地の部屋にカスタマイズができる。
二本目の柱は、その〈団地〉利用料の回収だ。
会社の方針として〈団地〉はひじょうな高価格に設定されている。分割とはいえ、まさに生涯の家がひとつ買える。
しかも〈団地〉は買い切りではなく、本体注入代金とは別で毎月の利用料がかかる仕組みとなっていて、もしもクレームが入れば、客には携帯電話の購入と利用に例えて説明するようにと会社からは指示されている。
〈団地〉に触れてその世界へ没入する機会が増えれば増えるほど、利用料は跳ね上がる。一分間あたりの利用料金自体は法外な値段設定ではないものの、一カ月で三万円を超える客も少なくない。
低収入者ほど生活のなかで〈団地〉に深く触れ、癒しをもとめる回数が多いため、膨れ上がった利用料金の支払い能力をうしなう者もあらわれる。
そこで会社は低収入者用〈団地〉プランとしてリボ払いシステムを用意した。
リボ払い利用料は毎月五日に引き落とされるけれど、その五千円や一万円ですら支払えないという客も大勢いる。
そんなひとびとに督促の電話をかけ続けるのが、わたしの毎日の仕事だった。

きょう、またサタケさんに当たったよ。と、わたしが浸水させていたひよこ豆をざるにあげて布巾で水気をとりながら言うと、夫のフーちゃんは「たのしかった?」と訊いてきた。
「たのしかったというか、サタケさんはいつもどおりサタケさんだった」
「なにそれ」
フーちゃんの笑いには一切の屈託がない。生ハムと熟柿のサラダにさらさらのフェタチーズをふりかける彼の手際はおそろしく軽やかで、それに比べて必死にハリラスープをこしらえるわたしの挙動は、自分でもぜんぜん見ていられない。
ハリラスープはモロッコの伝統料理で、フーちゃんのやり方では塩味を馴染ませた牛肉とひよこ豆、玉ねぎ、にんにく、生姜を炒め、自家製のトマトソースと水を注ぐ。そこへとろみを足すために片手のひら分の米を入れ、いくつかの香辛料、香草で時間をかけて煮て、最後にレモン汁で仕上げする。モロッコの味噌汁みたいなものだとフーちゃんは言う。
千里中央のモノレール駅からすぐのところにあるフーちゃんの知り合いの店から買ってきた丹波地方の赤ワイン、それからきのう焼いておいたおからパンをオーブンで温めて青磁の器に盛り、ふたり腰を下ろして「いただきます」と手を合わせた。
「あ、おいしい」
やっぱりスープを飲むと指先の冷たさが一気にとれてほっとする、とフーちゃんは笑う。
フーちゃんは〈千里中央ローファイ・メモリーズ〉ではわたしの上司だ。といっても部署がちがう。料金回収部門コールセンター課のわたしと、〈団地〉生産部門機能開発課のフーちゃん。
会社では一度も会ったことがない。わたしはハセガワさん、あるいは愛ちゃんと呼ばれるけれど、フーちゃんはハセガワ部長とみんなから呼ばれているはずだった。
豊中市にある国立大学の基礎工学研究科で情報知能学を学び、りっぱな研究をして論文を書きあげて博士となり、就職し、三十四歳で部長補佐に就任したフーちゃんはまごうことなきエリートだ。おこづかい程度のわたしの貧相な給与とは桁違いのお金を、毎月持って帰ってくる。
会社では一度も会ったことのないわたしたちが一体どうやって出逢って、そして付き合い、結婚したのだったか。
どうしてだかふたりともぜんぜん憶い出せなくて、でもそれも随分むかしの話なんだから憶い出せなくても仕方ないよとその話になる度にフーちゃんは言う。
最初に出逢った時よりも今の愛のほうがずっとずっと可愛いから、もう憶い出せないのかも。と、やわらかな笑顔でわたしの髪を撫でてくれる。
フーちゃんは優しい。
そしてあらゆるものごとにていねいだ。
季節ごとに必ずふたりでいく旅行ではその土地の名産品を欠かさずに買い、とりわけ陶器には目がなくて、じっくり吟味し大切に連れ帰り、まるで養子をもらってきたかのように愛おしげに食器棚に仕舞うのがおきまりだ。
服は子どもの頃からシルクとリネンとコットンが好み。ゆったりふんわりしたユニセックスなコーディネイトが彼にはとてもよく似合う。色白で首のながい華奢なフーちゃんは、シンプルなスタンド襟のロングシャツに黒の太いコットンパンツ、それからスポックシューズを愛用していて、会社へもその格好で働きにいく。今みたいな冬の時期はくるぶしまで丈のあるノーカラーコートを軽やかに羽織る。
刈り上げられた小ぶりなマッシュルームカット。茶色く透ける髪。きめ細やかなうなじ。しなやかに光る肌。細い顎。涼しげな一重まぶた。
清潔なフーちゃんのうしろすがたがわたしは大好きだった。
熱帯雨林のように家じゅうに大量に置いてある観葉植物を選んだのもフーちゃんで、その世話に夢中になっているのもフーちゃんで、かんたんな大工仕事やつくろいものをしてくれるのもフーちゃんで、無添加のほうがおいしいんだよと言って北摂のあらゆる食料品店を熟知しているのもフーちゃんで、入念な掃除も、毎晩の料理のつくり方を教えてくれるのもフーちゃんだった。
学生時代にしょっちゅう海外へ旅に出ていたフーちゃんは世界じゅうの料理に詳しい。
子ども舌で、ハンバーガーやらスパゲティやら店屋物を大好物としてきたわたしにとっては、結婚当初、フーちゃんが時間をかけて用意してくれるタイ料理やギリシア料理や中東料理、台湾料理なんかの異国料理も、野菜だらけのお味噌汁も、どれもぜんぜんおいしそうには見えなくて、色合いもにおいもどうにも食事だとは思えなくて、箸をつけるのがとても躊躇われた。
でもそれもすぐに、フーちゃんを好きすぎるパワーで完全克服した。

食事を終え一緒に風呂に浸かりドライヤーで髪を乾かし合って、電気を落とした寝室のベッドで、フーちゃんは日課にしているSNSの更新をしていた。
わたしはサイドのクッションに座り、顔と肌にココナッツオイルを塗りたくる。
フーちゃんのSNSアカウントは知っている。互いに繋がってもいる。
フーちゃん の写真日記SNSは大人気で、四万人ものファンが日々フーちゃんの写真の更新を待っている。一昨年の年末ボーナスで買っていたわたしには想像もできないような値段のカメラを家でもいつも携えていて、それで撮影される解像度の高い、けれどおそろしくやわらかなタッチの写真のほとんどが、わたしたちの家の生活の光景だった。
湯気たつ夕食のひと皿。数時間かけて煮詰めるジャムの色。買いたてのガジェット。干した洗濯物から透ける緑のこもれび。新調したドライフラワーの花束。愛娘同然の陶器や服、靴。それらを置く天然素材の棚。植物たちの成長もよう。
それらの写真には時おり、わたしの横顔やうしろすがたが写り込んでいる。
わたしのいる写真はすべてわたし以外のところにピントが合っているのでわたしの顔がはっきりと誰かに知られてしまうことはないけれど、それでも、綺麗なパートナーさんですね、だとか、好きがいっぱい伝わってきます、だとかのファンコメントが連なる時もけっこうある。
フーちゃんは基本的に返信はしない。それでもそのコメントをとても嬉しそうに眺めているのをわたしはちゃんと知っている。
フーちゃんがようやくスマートフォンとカメラを手放しふとんに潜り込んだのでわたしも隣に潜り込む。
フーちゃんの肩と腰があたたかい。
「ねえ、フーちゃん」
わたしは首もとに鼻をすり寄せて石鹸の匂いをすんすん嗅いだ。
「そろそろ赤ちゃん、できるかな」
「そうだねえ」
授かりものだから、などという陳腐な台詞をフーちゃんはぜったいに口にしない。そこが好きだ。
「できた時の名前、もう考えてある?」
「考えてある」
「教えてくれないの?」
「まだ教えない」
わたしはくふふ、と微笑い、フーちゃんの落としてくるくちびるを受けとめる。
広いおでこをひと撫でして胸もとへそっと手を下ろしてくるフーちゃんにわたしのぜんぶを委ねつつ、きょう帰りの更衣室で仲良しのマジマさんが教えてくれた吹田市にある不妊治療専門病院の話をした。
かなでクリニックっていうんだって。マジマさんはひとり目はすぐにできてそれでふたり目もほしくて、でもどうしてもできなくて行ったんだって。マジマさんも友達からの紹介なの。とても良いところだって言ってた。病院のなか、壁もインテリアもテレビもぬいぐるみもぜんぶ珊瑚色で可愛いんだって。
妊娠を希望し一定期間避妊せず性交渉をおこなっているにもかかわらず妊娠の成立をみない場合を不妊という。と、ずっと前にインターネットで調べていた。
フーちゃんもわたしも子どもがほしいと思う。だいたい毎晩パジャマを脱がし合い抱き合いキスをして汗をかいて絡まり合い眠る。
でもこれっぽっちも何かが実る気配はない。
前は気にしてなかったけど最近だんだん悲しくなってきた、とこぼしたわたしにマジマさんが話してくれたのがかなでクリニックの治療だった。
「健康診断以外で一度もお医者にかかったことないから、病院に行くなんてこわいけど」
でもフーちゃんとの赤ちゃんができるならがんばれるよ。わたしは目を閉じて、乳首をころころ転がされて、ああ、とだらしなく半びらきにした口から虚空にそうつぶやいて、自分がちゃんとがんばるところを想像した。
フーちゃんが好き。きっと、フーちゃんとの子どもも、大好き。
「愛、むりはしないで」
フーちゃんが顔をあげた。それでわたしの、眉の毛流れにキスをする。
「むりしないで、そのままでいいから。今のままで、愛とていねいに生きられたら僕はそれでもうたのしいから」
愛の身体気持ちいい。ほんとうに好き。フーちゃんがわたしにとろけ込む。その目はわたしの肌につつまれて、もうわたしの目を見ていない。
フーちゃんの声は絶対的な温度で完璧に優しい。
なのになんだかわたしの気持ちはまるで線香花火みたいにみるみる縮み、ジュン、と音をたてて地面に心細く落ちていってしまった。

サタケ・ユキエはどうやら約束の二十日に〈団地〉の支払いを行わなかったようだった。
今朝、出勤して熱々のルイボスティーを注いだマグカップを持って座席に着くと、隣でマジマさんとシンドウさんが話していた。
あたし当たったのよお、きのう。不在着信で出なかったんだけど。マジマさんが手を振り振り、顔をしかめた。やだあ。とシンドウさんも同じ顔をする。
みんなサタケ・ユキエが苦手であるらしい。と、この部署に配属されてじきに気がついたが、わたしはどっちかといえば彼女が出るとアイスの当たり棒を引いたような気持ちになるので好きだった。
サタケ・ユキエの無遠慮な物言いもひるがえって心地がいい。多少ぶっきらぼうではあるものの、彼女の声にはやさしさ成分がきちんと含まれている。
コールセンター課での料金督促業務に就いてから、電話口でひとを容易く傷つけてくる人間に数え切れないぐらい出遭い、傷つけられてきたから、そういう違いはすぐにわかる。
わたしたちは督促者というより、誰かの罵詈雑言を交代で受け止めるいけにえなのだと表現するほうがきっと正しい。
だいたい従量課金制のリボ払いだなんて地獄以外のなにものでもないのだからその地獄に手をのばすひとなんてもともと地獄に生きている人間であるにきまっている。
一昨日だって一発目の架電から《んな金払えるわけないやろが。何をえらそうに言うとんじゃアマ。何様じゃ。お前が股開いて代わりに払えや。死ね。今ここで死ね。殺すぞ》と、ヘッドセットが割れるほどの大声で恫喝され、気持ちがずたずたになりトイレでさんざん泣いて吐いて、こわくてこわくて、それからまったく仕事にならなかった。
そういう時はわたしも〈団地〉がほしくなる。
だけど手を出したら駄目だとみんなわかっている。わたしたちの薄給ではぜったいに〈団地〉を維持できない。
わたしは〈団地〉を体験したことはないけれど、いつだったか、もう名前も忘れた同僚のひとりが社外の知人の〈団地〉を触らせてもらった、ほんとうに良いものだったとうっとり報告し、それから彼女の様子は徐々におかしくなり、やがて目の焦点が合わなくなっていってここを辞めた。
寿退社だと上司は言っていたが、数カ月後、シンドウさんのパソコンのリボ督促画面に彼女の名前が浮かび上がって大騒ぎになった。
団地。あの汚くて貧しくて狭苦しい空間が、ノスタルジーの名のもとに、どうして代え難いほどの癒しとなりうるのか。
もう一八〇年も前の、今生きている人間は誰ひとり暮らした経験のない建造物と生活にどうして想いを馳せるのか。
わたしにはエゴと差別だとしか思われないそれについてフーちゃんはとても肯定的だ。
静かな清潔を好み、正しい要素でつくられた食べ物を手をかけて調理し、愛するひとと向かい合って食事を摂ること。家のなかを心地よく整え、光の差すほうへと向かう、手触りのよい巣づくりをすること。
発達しつづけるテクノロジーにすべて身をゆだねるのではなく、むしろそれと上手に距離をとって付き合い、かすかに抵抗しながら、自分たちの暮らしを自分たちのやり方でささやかに発展させて、小さな物語を紡いでゆくこと。
現代のわたしたちが夢中になっているていねいな暮らしのそれは、かつて団地のニュータウンがつぎつぎと建設され、生活の一つひとつに手をかける時間がようやくできた、あの時代の人間たちの、かけがえのない愛の祈りなのだと、フーちゃんはそう語るのだ。

平穏な日々に、不穏がふたつ、あらわれる。
ひとつはサタケ・ユキエの訃報だった。
発見者はわたしだった。二十日の支払いがなされなかった彼女へはその後毎日誰かが架電していて、フロア中央のホワイトボードの、最終警告の締め日が近づくごとに減っていく顧客数字のなかにいつまで経っても残留しつづけていた。
月が代わり、翌月分の支払い督促が開始される頃、わたしの画面にサタケ・ユキエが現れて、そして、何日も通じなかった電話が突然通じた。
《ユキエは死にました》
クルマに飛び込んで自殺でした。と、わたしにのっそり告げたのはしゃがれ声の老婆だった。
《ユキエは死にましたが、お支払いはつづけます》
孫が〈あれ〉を使いたいと言うので……、と老婆は咳き込む。サタケ・ユキエの〈団地〉は彼女が赤ん坊の頃に与えられたパンダのぬいぐるみで、愛おしさのあまり口で撫でこすりつづけたせいでおでこが汚く変色し、首も折れてぼろぼろになったものだというのを、老婆との会話でわたしは初めて知った。
《いま、おいくらになっとりますか》
わたしが画面上のリボ残高を答えると、老婆は一分ほど沈黙し、それでも《支払います》と言った。支払日は年金支給日にしたいと申し出があった。
ママー。と、小さな子どもの声がヘッドセットの向こうから聞こえた。わたしは目を閉じてその子どもが今電話の向こうでぼろぼろのパンダのぬいぐるみを抱きしめて大泣きしているのを見た。ぼろぼろの唾臭い〈団地〉のにおいに包まれてやがて安心を取りもどした孫がふかぶかと眠るのを、老婆はほっと見下ろすんだろう。
サタケ・ユキエは自殺する前に、〈団地〉の部屋に自分が立っている光景をカスタマイズしたりしたのかもしれない。
御愁傷様でした、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。わたしは老婆に向かって宙に頭を下げ、通話を切断した。
お客様情報欄に、彼女の経緯を書き残さなくてはいけなかった。

もうひとつの不穏はコールセンター課の指導主任であるイタオさんだ。
「愛ちゃん、僕と不倫してみない」
休憩中の自販機コーナーでふたりきりになった折、イタオさんは唐突にそう切り出した。
「え」
「不倫。しない?」
不倫、という言葉よりも親しくもない上司が初めてわたしを〈愛ちゃん〉呼びしたことに仰天した。仰天、というか不快だったが、顔はあくまで平然を意識して、わたしはホット抹茶オレをずるずる啜りながら目を逸らした。
「……わたしは〈団地〉生産部門機能開発課の、ハセガワ部長の……」
「もちろん知ってるけどさ、愛ちゃん、僕が愛ちゃんを気に入ってるの知ってるでしょ」
知っていた。随分前から知っていて、それは同僚から聞いて知ってもいたし、パソコンの向こうから届くねっちょりした異様な視線からも知っていた。だけど図々しいなんてレベルじゃない。あほですか、と思わず吐き棄てそうになるのをこらえ、けっこうです。と首を振った。それに、
「イタオさん、いろんな子に手を出してるってよくうわさに聞きます」
「まあ、僕、ほかの男のモノを自分のモノにするってフェチがあるんだと思うよ。相手が強力であればあるほど燃える」
燃える。じゃないし、そもそもフェチの使い方がおかしい。
精悍な身体つきで声のよくとおる、目鼻立ちのはっきりしたイタオさんはコールセンター課の女性には確かに人気で、その不埒な誘いにめろめろと乗ってしまうひとも多い。イタオさんも隠したりしないから余計に妙な人気が出、それで本人も調子にのっている。のが気持ち悪い、とわたしは思うけれど、イタオさんはそんなわたしまで誘おうとするのか。
自販機コーナーの入り口を大きな身体で塞がれていたから言葉だけではどうにも切り抜けられそうになくて、わたしは思わず「フーちゃん」と小さく叫んだ。
「なに、部長のこと家でフーちゃんって呼んでるの? 愛ちゃんやっぱ可愛いね」
イタオさんは何を思ったのかいきなりこちらへ手を下ろしてきてわたしの髪を、頭を、それからうなじをぐいっと強引につかみ、撫で、それから自分の胸もとに引き寄せようとして、わたしはありったけの声で叫んだはずなのにぜんぜん声なんて出てなくて、床に抹茶オレのしみがみるみる広がりわたしはイタオさんの腕に一瞬完全に抱かれてしまった。
「あっ……」
イタオさんはわたしを抱きしめたその瞬間反射したようにうめき、その大きな身体からわずかに力が抜けた。
わたしは今度こそ全身の力を込めて彼の身体を突き飛ばした。
驚くべきことにさっきはあんなに敵わないと思ったその身体が、まるで布切れのようにいともかんたんに吹き飛んでいった。呆気にとられて、すぐに逃げ去ればいいのに振り向いてしまった。
わたしは心臓がとまりそうになった。
暗い床にへなへなとうずくまるイタオさんの表情が、入社したての頃に研修映像で見た〈団地〉利用者の幸福そうなそれと、まったく一緒だったのだ。

フーちゃんが丹念に整えてくれていた美しいわが家を散らかすのは、びっくりするほどにかんたんだった。
わたしは寝室の隣にあるフーちゃんが〈書斎〉と呼ぶ部屋に座り込んでいた。
体調不良で会社を早退して全力で走って帰宅してブーツを脱ぐのももどかしくて右足だけつまさきに引っ掛けたまま家に上がってしまって、廊下の途中で戸棚につまずいて転んで泣きそうになったけど、こらえた。擦りむいた足はしぜんと〈書斎〉に向かった。
〈書斎〉は平日の夕食後や休日の朝にフーちゃんがひとり穏やかに過ごす部屋だ。愛を好きでいるためにはひとりの時間もほしいと言って、ここで暮らすのが決まった時、フーちゃんがつくった。愛もいる? と訊かれたけれど、わたしはフーちゃんと過ごしつづけてもフーちゃんを好きでいつづけられる自信しかなかったから、いらない、と即座に断った。
ほとんど球体のようなお気に入りのロックグラスにレモン水を注ぎ、積ん読を少しずつ消化しては、時おり窓のおもてにカメラを向けてシャッターを切る、〈書斎〉でのフーちゃん。穏やかな顔の色。
こんなに興奮して入室したのは初めてだった。とまらない動悸を飲み込み、大きく息を吸い、冷静に努めて部屋じゅうを見渡す。両サイドの本棚は右が趣味の文学、左が学生時代にあつめていた理系の研究書だ。左の本の並びのなかに一箇所だけ埃のうすい場所を見つけた。
そこだとすぐにわかった。
本を押し退けると灰色の金庫があった。頭をフル回転せずとも暗証番号を解けると思って、フーちゃんの好きな数字。だめ。わたしの誕生日。だめ。初めてこの家にやって来た日。だめ。いつかに話したわたしたちの子どもの理想の誕生日。それでもだめで、解けると思ったのにフーちゃんに裏切られた気持ちで胸がいっぱいになって、それまで精一杯我慢していたのにもうこれ以上こらえきれなくて目からはとうとう涙がこぼれて、わたしはいちばんぶ厚い鈍器のような本で金庫の錠をめちゃくちゃに叩いた。
金庫が壊れてくれるはずがなかった。
どぽどぽと溢れてくる涙が顔じゅうの化粧を溶かしていって、背後の本棚からはフーちゃんの気配を感じた。
たくさん付箋の貼られた研究書。
フーちゃんが、彼の人生のなかで何度も何度も読んできたもの。ずっとずっと研究していたもの。いまもずっと、研究しているもの。
塩からい膜のむこうにタイトルが並ぶ。
『アンドロイドの生産可能性』
『情報知能工学の到達点』
『ディープラーニングと機械学習前史』
『どうすれば「人」を創れるか』
『アンドロイドは人間になれるか』
『AIのノスタルジー』
フーちゃんの蔵書の一冊一冊が、彼が長年愛しいつくしんできたそのなかみのすべてが、本の背の文字から伸ばされた透明な手になってわたしの首を絞めてきて、わたしはみるみる呼吸のやり方がわからなくなっていく。息の吸い方と一緒にフーちゃんのこともみるみるわからなくなって、けれど同時に、フーちゃんをいつもやわらかく包んでいる光のようなあの膜の、そのうすらいが一枚一枚ゆっくりと剥がれていって、それから、しだいにいろんなことがわかっていく。
何年も何年も、どれだけ毎晩フーちゃんとつよく抱きしめあっていても、これっぽっちも何かが実る気配が生まれてこなかったこと。
フーちゃんとどうやって出逢ったのか、その記憶がどこにもないこと。
毎日毎日会社で誰かからの罵詈雑言のいけにえになりつづけて、泣いたり吐いたりして、それでも、あそこを辞めたいなどと、自分が一度も思わなかったこと。
わたしを抱きしめる時のフーちゃんがいつも、わたしじゃないどこかを見つめてとろけ落ちていたこと。
一度も会社でフーちゃんと会えずにいたこと。
一度も医者に行った経験がないこと。
そして、一度たりともほんものの団地を見た経験がないのに、まるで映写機に照らされたスクリーンになったかのように、自分が団地の光景をいともかんたんにまぶたの裏へ浮かべられたこと。
身体の奥の細胞ぜんぶが見知った団地の光景でいっぱいになっていたこと。
むしろ自分がその瞬間、〈団地〉そのものであったのだということ。
もう二度と後戻りできないほどに散らかしてしまったフーちゃんの〈書斎〉に、少しずつ、シャーベットの欠片みたいに凍えた夕陽が差し込んできていた。

愛、と背中を撫でられてむっくり起き上がったら隣にフーちゃんが腰を下ろしていた。
湯気のたつホットミルクがわたしのマグカップになみなみと注がれている。
飲む? とフーちゃんがわたしの顔の前に、そっとそれを差し出してくれる。
「はい」
東北の土でつくられてあるそのマグカップは熱々で、思わず取り落としそうになったのをフーちゃんがナイスアシストで支えてくれる。
ゆっくり飲みな、やけどするよ。フーちゃんは帰ってきたての冬の寒さを身体のどこにもまとっておらず、おととい干していた白いボアの部屋着すがたで、髪からは牛乳石鹸の匂いがしていた。
いつのまに帰ってたの、と訊くと、いつだっけ、と微笑う。
フーちゃんの机の上の時計は夜の十時を指していた。
本をいっぱい引きずり下ろしてさんざん散らかしたはずの〈書斎〉の中はチリひとつなく綺麗で、整頓されて、いつもどおりの静かな空気に満たされていた。本はすべて本棚に並んで眠っていた。
窓ガラスにわたしが映る。涙に濡れて溶け落ちていたわたしの化粧は、会社にいた時のままに顔を縁取っていた。
「いつも先に帰ってる愛がどこにもいなくて、家じゅう探したらここですやすや寝てたからびっくりしちゃった」
温かな部屋着のフーちゃんは、ごはんができているよとわたしに言う。
フーちゃんにうながされて立ち上がる。ずいぶん深く眠っていたみたいで両足に力を入れたら日ごろ滅多に感じない強烈なめまいがした。
きょうのごはんはキーマカレー。ヨーグルトもおいしいのを買ってきてあるよ。ひらかれたドアから、リビングのまろやかな灯りと複雑でむずかしいスパイスのにおいが溢れ出す。寝起きのわたしは目やにをぬぐい、甘えたあくびを吐き出して、幼児の足どりでその光のほうへと向かう。
「お腹すいたって顔に大っきく書いてある」
フーちゃんが最初のひとさじをわたしの口に運んでくれる。
「……ん」
おいしい。と、ミンチをくちびるに垂らしてぼんやり噛みしめるわたしをフーちゃんは愛おしげに眺めて微笑った。
きょうの食事もフーちゃんの手のひらから生まれたていねいな優しい味がした。ここにあるわたしたちのすべてが何ら異常なくいつもどおりで、残りの今夜もこのままなだらかに明日へとつづくいつもどおりなのだと思って、安堵する。

寒い部屋にひとりうずくまり長い夢をみていた自分の身体が、自分の身体じゃないみたいに重たかった。スプーンを持つのも億劫で、一体どれだけの長く深い夢をみていたんだろうと思う。
フーちゃんも今夜はちょっとだけ、疲れた顔をしていた。
「きょう、仕事たいへんだった?」
「すこしね」
愛は? と訊ねられてわたしは、すこしね。と、口角を上げ、首をかしげた。
「でもあしたもふたりとも仕事だから」
「そうだね」
早く寝ないとね。フーちゃんは汁一滴残さずに食べ終えたカレー皿とヨーグルトのグラスを持って流し台へ立った。フーちゃんの大好きな台所。この家でいちばんの、こだわりの台所。手狭ではあるけれど彼の使い勝手に忠実に整えられてある、とっておきの研究室。
水の音にあわせて細い腰がふわふわ動くのが可愛かった。フーちゃんが大好きだと思った。
愛のも貸して、と伸ばされたその手を、わたしは強く引っ張った。
「……フーちゃん、ずっとずっと、死ぬまで愛して一緒にいて」
フーちゃんは驚いた顔をしていた気がした。カレー皿はテーブルの上を滑っていって、わたしが引っ張ったはずの手はいつのまにかフーちゃんのほうが最初に引っ張ったみたいになっていて、両手はぎゅっと、手首から肘へ、二の腕へとのぼっていくと、やがて肩が強く抱き寄せられる。
フーちゃんが目を閉じるその前に今夜こそはわたしが先に閉じるのだとまぶたを落とそうとしたその瞬間、自分の右手にできたばかりの血のかさぶたが見えた。
本のページで切れた傷。
硬いものをどこかへぶつけた際に間違えて殴打したにちがいない、青黒い痣も手の甲にあった。
愛、とフーちゃんがつぶやく。
今夜もフーちゃんのほうがわたしよりも先にわたしのなかへと蜜のようにとろけ落ちてしまった。
温かでやわらかで清潔で美しいフーちゃんに抱きしめられながらわたしは半分だけまぶたを閉じる。
ぜんぶ閉じてしまえばきっと、さっきまで見ていた夢のつづきに襲われてしまう。
フーちゃんの身体から伝わる眠気を必死で拒み、とろけ落ちたフーちゃんをけして揺り起こしたりしないよう、抱かれていた自分の身体をぐるりと裏返し、わたしが彼を抱きしめる。
抱かれるフーちゃんは安らかという言葉そのものだ。
心の底から大好きだと思って、くちびるを強く噛みしめる。
あしたもあさってもこれからもずっと、永遠の時間のその果ての先までずっと、わたしはこの家でぜったいにフーちゃんとふたりきり、愛の祈りで暮らすのだ。
わたしは舌に残ったキーマカレーの味をなぞりなおす。










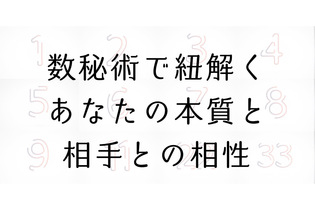










本を読むのが好きです。小説を書いたり、書評を書きます。関西出身在住。