やがて幻になるこの街で 「くだもの大戦争」
めまぐるしいスピードで開発が進み、日々変化していく大阪の街。 いま目の前にあるわたしたちの街が徐々に幻になっていく光景を、リアルなのに少し不思議な物語で描く。 小説家・磯貝依里による大阪を舞台にした読み切り短編小説連載です。

青々としたバナナの木の大群が、高すぎる空に向かってざわざわと揺れていた。バナナの葉の緑も空の青もどちらも言葉の上では「あお」と言う時があるのに実際はぜんぜんべつの色であるのがふしぎだと、生ぬるい風のなか、それを見上げながら思った。
バナナの巨大な森は、なんばパークスの最上階にあるパークスガーデン最南端に設置されている。パークスガーデンは〈都市のオアシス〉の認定をはじめ国内外からさまざまな賞を受け、アメリカCNN局による〈世界でもっとも美しい空中庭園トップ10〉にも選出されており、初めて足を踏み入れるや「ラピュタみたいだ」と形容する来場者も少なくなく、平々凡々な人間であるところのわたしも御多分に洩れずそうだった。
子どもの頃母に手を引かれて最初にここを訪れた日、「ラピュタみたい」とつぶやいたジブリオタクのわたしに母は、あんたってきっと平凡な大人になるわね。と、ため息を吐いたのだったが、それ以降わたしは道を違うことなくきちんと平凡な大人に育った。
《バナナはもがないでください。いずれ皆さんのお手もとに届けられますので、バナナはもがないでください》
時おり、植物棚や花壇の脇のスピーカーからそんなアナウンスが流される。
グランドキャニオンのように幾層もの植物エリアが襞(ひだ)状に重なるパークスガーデンの、その中央の広場にはパラボラアンテナに似た巨大な施設があって、そこではフアンフアンと響く妙なメロディーがつねに発信されている。バナナをもがないでくださいというアナウンスがその妙なメロディーと晴れた空でねっとり混ざり合う。それがある種の洗脳であると気がついているひとは、わたしのほかにいるのだろうか。

街では戦争が起こっている。
ことのはじまりが一体どういうものだったのか、それを記録しているひとは誰もいない。母から聞いた昔話だと、かつて大阪で都構想の議論が煮詰まりに煮詰まった際、年老いた反対派議員のひとりが議会の休憩時間に食べていたメロンの皮を賛成派議員の顔にうっかり半分、にくしみ半分でベチャッと飛ばしてしまったのが発端であったというし、通っていた大学の教授の話だとその火種はすでに七十年代の西成暴動の時代にあって、真夏のある日、釜ヶ崎のくだもの屋で「買ったすいかが腐っていたから取り替えてほしい」と訴えた日雇い労働者が現れたことで、千人以上の労働者仲間と店が警察沙汰の大投石騒ぎとなった事件がそのはじまりであるらしく、またインターネットで情報を掘り起こしてみれば、通天閣にバナナを抱えたキングコングの巨大アドバルーンが設置されたのが由来だとも、岸和田のだんじり祭りに源流があるのだとも書いてあった。
いずれにせよそれはほとんど自然発生的に勃発したのだという意識が大体の市民のなかに共通していて、原因を研究しようという学者も政治家もいない。そもそも戦争とは自然発生的にうまれるものだ。なんて意識をこの街に棲むからには持たなくてはいけない。ひとは殺さないけれど、しかしひとを苦しめるタイプの戦争は、果たしていつから戦争になってしまうのか。その線引きは誰にだってできやしない。ひとは苦しめないけれど、しかしひとを殺すタイプの戦争も、また。
西成のくだもの屋の暴動がいまこの街の戦争のきっかけだったのだと言っていた教授のゼミに当時わたしはセフレがいて、四限終わりに彼の下宿へ転がり込んで汗まみれのセックスを一発かましたあと「ところできちんとした恋人の状態って一体どういう状態だと思う?」と、なんとはなしに訊いたことがあった。
彼はすぐに答えた。
「そのふたりのあいだに約束事があるいうことちゃう?」
その時、ああ、まるで平和条約のようだ、と思ったのをわたしはいまでも鮮明に憶えている。
一見幸福な平和条約を結んだとしても、それが平和条約であるかぎりほんとうは単なる停戦条約なのであって、結局はいつか必ず戦争が起きる未来があることを言ってしまっているようなものなのだ、だから真の意味での平和な約束なんてないのだと、そしてふたりのあいだに正式な約束事が結ばれた状態を「きちんとした恋人」と呼ぶのであれば、それはきっとその平和条約みたいに、よりいっそうふたりが他人同士であるという輪郭を虚しく際立たせ、いずれ何らかの決着が来ることをあらわしているだけなのだと、そう思った。
それならば約束事なんてたったひとつもないわたしたちの関係はどうなるんだろうね、とわたしは彼の裸の胸に頬を押しあてながらつぶやいて、けれど彼はわたしのつぶやきを受け取る前に意識の糸を引っ張られるように深く深く眠り落ちてしまっていたし、その一年後にわたしたちは澱んだ靄が明けるみたいにしてあっさりと別れてしまった。
平和条約が街同士で取り交わされる予定はぜんぜん耳にしないものの戦争のルールはきちんと確立されていて、とにかく何事にも、くだものを使用すること。
府民全員が所持すべき基本的な装備として数多のくだもののなかからバナナが選出され、その象徴および兵器増強政策としてパークスガーデンにバナナの巨大な森が植栽されたのはいまから二十年も前のことだった。〈安く、甘く、やわらかい〉という有識者による意見のほか、黄色は何より景気がええわ、という府内全域にわたって実施された商店街アンケートの結果も選出理由のひとつだった。
〈くだものは食べるにも投げるにも第一にバナナ派〉だった母に連れられて、七歳だったわたしはファミリアの新品のワンピースを着せられてパークスガーデンのバナナの森開園記念テープカットセレモニーに参加した。セレモニーの一般来場者にはバナナ色のピンバッジが配布され、テープの張り巡らされた壇上にも紅白幕の代わりに黄白幕、ピンクのサングラスがトレードマークだった当時の大阪府知事の手にはバナナ型の実寸マイクが握られていた。
「皆さんにとってはこれまで何の変哲もないくだものでしかなかったくだものが、きょうから新しい存在意義を生み出します。皆さん、わたしたち全員で盛り上げていきましょう、生まれ変わらせましょう、大阪。戦い抜きましょう、大阪。バナナ、大阪!」
バナナ、大阪! と叫んでいたピンクのサングラスの大阪府知事はそのセレモニーのすぐ後にパチンコ店との不正取引で逮捕されてしまったけれど、そのこともあってセレモニーで使用されたバナナ型マイクは同様の商品が府内で爆発的に流行した。〈大阪人にバナナを手渡すとおもむろに耳もとへ持っていき、「もしもし?」と電話機のふりをする。かと思ったらその瞬間「電話やない、バナナやないかい!」とセルフでツッコミを入れる〉というほぼ都市伝説だった古いギャグが、バナナ型マイクの流行と普及によりそこらじゅうで見られる日常の光景となり、それどころか「電話やない、マイクやないかい!」というギャグに変化し、さらにはほんもののバナナが戦争の基本的装備に指定されたことから、「マイクやない、バナナやないかい!」という、まるで騙し絵みたいにトンチンカンなギャグへと変わり果ててしまった。
武器としてのバナナの存在が府内のあらゆる街に浸透すると、バナナを携帯するためのバナナホルダーが税金をもとに制作され配布された。それはちょうど任天堂のゲーム『マリオカート』の、ゲットしたアイテムのバナナを自分のカートの後ろにずらずらずらと装備したあの時みたいに尻のあたりに下げられる、強力なワイヤーホルダーだ。三歳以上の子どもから外出可能な高齢者までは携帯が義務付けられているから、街では観光客以外のすべての人間が黄色く青臭いしっぽをゆらゆら垂らして歩いている。
いざという時がくれば、ホルダーからすばやく実をもいで投げつける。
武器となるくだものそれ自体は各自治体からの支給はなく、それぞれが自分の財布からお金を出して調達しなければならない。
戦争がはじまってスーパーや百貨店のくだもの売り場が拡大されたかといえば、母によるとぜんぜんそうではないらしく、相変わらず店内入り口の脇にそこそこのスペースで商品展開されているだけだし、陳列されているくだもののバリエーションも戦前と同じで、商店街や飲み屋街にあるむかしながらのくだもの屋は贈答用の高級くだものはりぼんを付けて奥の冷蔵ケースに、特売のくだものは軒先の台に雑に盛って、戦時中にも関わらずのんびりと営業している。
基本装備に指定されているのがバナナなだけで、くだものであればこの戦争では何を使用してもかまわない。

パークスガーデンで青くみずみずしい空気をめいっぱい吸い込んでから、夕方六時過ぎ、わたしは仕事に向かった。
職場は東心斎橋の八幡筋にあるラウンジだ。東心斎橋ではあらゆる飲み屋筋に色とりどりのネオンが蠢き、数え切れないほどの雑居ビルが建つ。日が沈めば路地のそこ此処にアルコールの臭いが満ち満ち、道路の端には韓国の乾物を売るゴザが敷かれたり、揚げ物や粉モンを売る焦げた鉄板の屋台が明かりを灯したり、細いくちばしでタバコを吸いながらキャッチを繰り広げるカラスのようなホストやキャバ嬢たちが群れをつくって気怠げに立つ。老舗のタバコ屋の正面にあるわたしの職場のビルは一等地だった。
道にせり出した壁がゆるやかなカーブを描く大きなビルの三階に、わたしの勤める〈ラウンジ・梅〉は入っている。エレベーターで上がると赤いビロードの絨毯敷きになっていて、ぶ厚い大理石の扉を開ければ蜂蜜みたいなとろみの照明のなかに三十席のフロアが広がっている。わたしはホステスではなくただの給仕係の黒服で、一晩中ひたすら席の氷を取り替えたりキープボトルやシャンパンを運んだりグラスや皿を下げたりする。この仕事に就いてまだ半年も経っていないから予約の整理や金銭の管理、客の誘導なんかの重要な役目はまだ与えられていない。そういう間違いがあってはならない仕事は五年選手の先輩であるカドミチさんやマツベさん、サワさんの三人がやることになっていて、わたしは彼女たちの下で数時間黙々と働く。
オーナーに聞いた話によると戦前はテーブルにカットフルーツ盛りを五千円で出していたけれど、戦争がはじまってからはくだものを出したらその場ですぐに戦闘がはじまってしまうためにメニューから消してしまったという。その名残として、フロア奥にあるキッチンでは、壁に〈カットフルーツ盛り:りんご、メロン、オレンジ、いちご、ぶどう、その他各季節のくだものをすべて飾り切り〉とマジックで書いてあるのがそのままになっている。
フロアのホステスたちはみんな薄い薄い羊膜のような間仕切りを身体から放出していて、その膜がそれぞれの存在を護っている。誰からも傷つけられることなく、わざわざ自分から傷つけにいくこともない。カラスの羽翅のような付け睫毛や紅い口紅など濃すぎる化粧のせいで彼女たちの顔はどれもまったく同じに見えたけれど、完璧な個人主義で作りあげられた空間のなかでは逆に個性など一切必要ないのだということを、そのケバケバしい化粧の羅列と甘い香水の香りに教えられているような気がした。
〈ラウンジ・梅〉の閉店は深夜二時で、ぴったり時刻どおりに終えられる日はそうそうなく、しかし今夜は週中でなおかつ給料日前であることから日付の変わる前に一気に客がはけ、看板を消し、洗い物と翌日の準備を済ませてホステスたちを送り出してもまだ午前一時になっていなかった。
三階の別室にある黒服専用のロッカールームにカドミチさん、マツベさん、サワさんと一緒に着替えに向かった。ホステスたちのようにきらびやかなドレスは身に纏わず、黒服には黒服のための簡易ワンピースが制服としてオーナーから充てがわれていて、ぽっちゃり気味のマツベさんは勤務が終わればいつもビロードの廊下をぼふぼふ歩きながら、もう一秒だって早く脱ぎたいのだと勢いよくチャックを下ろす。ほんのり渋い赤みを帯びた黒いワンピースを腰まで脱ぎ落とし、白くてぷりぷりの豊かな上半身を揺らすマツベさんの後ろ姿を、カドミチさんとサワさんは「よく熟したライチを剥いたトコみたい」だと笑う。
「あの八十歳のジジイ、席に着いた女の子全員に売春はやっとらんのかって訊いてきよって、ほんま最悪やったわ」
ロッカールームの明かりを点け、三人の先輩がタバコを渡し合ってお疲れ様の一服を交わす。カドミチさんが今夜来ていたタチの悪い客の文句を言い、文句とともに濃い煙を吐き出した。
「ていうか八十歳でハタチぐらいの女の子とえっちしたいとかって」
「まじウケる」
やばすぎ。股ぐらのあれバナナどころかカリカリの干し芋のくせに、とげらげら笑うマツベさんのまるくて白い背中の肉をぼんやり眺めながらわたしは自分のロッカーの扉を開け、しかし驚いてすぐにまた閉じた。
「カンナちゃんどうかしたん?」
「……いえ、なんでもないです」
マツベさんとは正反対の、棒のように痩せたサワさんがふんわり微笑み、わたしを見る。大丈夫です、とわたしはぎこちなく口角を上げ、もう一度ゆっくりとロッカーを開いた。
ハンガーに掛けてあったわたしのTシャツの両肩には濡れたバナナの皮が、裾にはべしゃべしゃに潰されたいちごの汁がまるで大きな血痕みたいに染み付いていた。
半年前にセールで買った白いシャツが見るも無残なすがたに汚されている。
わたしは脱ぎかけた制服のワンピースのチャックをふたたびうなじまで引っ張りあげ、三人の先輩たちから隠すようにしてくだものの汁まみれになったTシャツを手早くリュックに突っ込んだ。べたついたハンガーを制汗シートで急いで拭う。かがみこんで作業しているわたしの横で、さっきまでくだらない話に盛り上がっていた先輩たちが、唾を飲み込みながらこちらの様子を観察しているのが背中にじわじわ伝わってくる。
訊かずともこれはきっとリーダー格のカドミチさんの仕業だし、第一誰の仕業なのかを訊ねることは何より野暮だ。
ロッカーの奥のカゴに入れていたパーカーは無事だったのでワンピースの上にさっと羽織り、リュックを抱きしめ、じゃあお先に失礼します、とわたしは三人に笑顔を向けた。
おつかれー、とサワさんがにんまり笑う。会釈を返す。
「あ、カンナちゃん。忘れてんで、これ」
マツベさんがわたしのロッカーに手を突っ込み、バナナホルダーをぶんぶん振り回して声をあげた。家を出る時には五つ装填していたバナナの房が三つに減っていた。自分のくだものじゃなくてわたしのを使ったのか。ケチだな。
「ありがとうございます」
みるみる染み出してくる嫌な臭いの汗を身体中に感じながらわたしは溺死者みたいなどす黒い表情で笑い返し、朝よりもずいぶん軽くなってしまったバナナホルダーを受け取るとエレベーターホールに向かって猛ダッシュで逃げ出した。
付き合って五年になるわたしの恋人は、もともとが大人しい性格だったせいもあってか、難波や梅田、天王寺などの繁華街で突然戦闘が開始されると、誰より先に逃走するのが癖だった。いつもは上手に逃げるのだけれど、一年前の梅雨の真っ只中、地下鉄御堂筋線の心斎橋駅で、棘皮をていねいに除去したドリアンの剥き実を多数の民間戦闘員が千個以上も投果しあう〈第二十六次ドリアン暴動〉の現場に運悪く居合わせてしまい、熟した白い果肉の発する、排泄物のように強烈な激臭を全身に浴びてトラウマを負った。
その頃の心斎橋駅は御堂筋線の改修工事のためにホームの通行部がひと一人がようやくカニ歩きで進めるほどの極小サイズになっており、パニックに陥った大量の乗客の津波の底で、どうあがいてもすばやく逃げることができなかったそうだ。その時わたしは〈ラウンジ・梅〉での仕事中で、恋人からのSOSの連絡に瞬時に気づくことができなかった。
以降恋人は繁華街でのデートを疎み、唯一連れ出せるのは、地上の観光スポットの開発でかつてより歩行者が減ったショッピングコンコースなんばウォークの、イートインの豚まん屋だけになってしまった。
向かいにわたしがきちんと座っているのを確認し、それから運ばれてきた熱々の豚まんに酢をかけてかぶりつくと、デート時の恋人はようやく安堵の表情を見せてくれる。
くだものなんかより肉のほうがおいしい、とつぶやくその優しい表情を目にする度、こんな戦争なんて早く終わってしまえばいいと思う。でもそれを言うことはできない。府内のあらゆる人間に思うさまバナナを投げられるこの戦争に、わたしの母はむかしから楽しそうに参加していたし、何より誰も死んだりしないから。誰かが戦争を終わらせたいと言えばいいのにと誰もが思っているのに、けっして誰も言い出しはしないし、誰もが笑顔で生きているから。
ドリアンの臭いにやられてしまったあの日以来、恋人はわたしとセックスをしてくれなくなってしまった。

LINEで教えられていた飲み会会場に到着すると、すでにわたし以外のメンバーは揃っていて、あわてて「ごめんなさい」と頭を下げた。
合コンの会場はなんばグランド花月付近、千日前の南海通り商店街にある〈はつせ〉というお好み焼き屋。企画したのはカドミチさんで、メンバーはマツベさん、サワさん、そして、彼女たちのプライベートの飲み友だちのさらにその友だちだという三十三歳の男のひとが四人で、「積極的な合コン」というものを趣味にしているカドミチさんが、一昨日の勤務後になぜなのか初めてわたしを誘ってきた。
「カンナちゃんさあ、彼氏おるって言うとったけど、これはこれでまた別腹やしおいでや」
着替えながらそう誘ってくるカドミチさんに、別腹ってデザートみたいなものでしょうか? と訊いたら「そうそう」と頷くので承諾してみたら、会場がどっさりお好み焼きを食べる〈はつせ〉だと言うので、それでは恋人の存在のほうがデザートみたいになってしまうなという気持ちになった。
入店すると十人サイズの座敷に通された。白黒の市松模様みたいに男女で交互にざぶとんに座り、じゅうじゅう音をたてる鉄板に向き合った。手前右角に着席したわたしの左隣は、トモヒコさんという名前の元バンドマンだった。
「じゃあとりあえず合コンの鉄板ゲーム、くだもの大戦争しまーす」
大きなコテを器用に使ってお好み焼きを何枚も焼いているカドミチさんが、はりきってそう提案する。オーソドックスでいーねー、とマツベさんの左隣に座っているロン毛の男が笑い、「ここ、ほんまもんの鉄板あるしねえ」とサワさんがじゅうじゅう焼ける目の前の鉄板を指差して親父ギャグを言い、けらけら喜ぶ。
「ほんなら、まず言い出しっぺのうちから! うちはー、桃!」
「えー、意外ー」
よっ、男好き! とマツベさんがカドミチさんにヤジを飛ばす。そんなマツベさんにカドミチさんは「よく言われるけどさあ、桃好きの女は男好きって偏見やよォ。くだもののなかでは桃がエロいとか、女の子はピンクが好きとか、いまはもう、そういう古い時代じゃありませーん」とくちびるを尖らせ、しかし確かに透けて見えるあざとさで、ロン毛の男にぺろりと舌を出す。
くだもの大戦争というゲームはカドミチさんが言うように若い世代の合コンでは鉄板だし、幼稚園児や小学生の学級会レクリエーションでだって行われる。ルールは至極単純で、それぞれ挙手して「戦争でいちばん使いたい好きなくだもの」の種類とその理由を発表する、それでそのひとの性格や好みがわかる、ただそれだけだ。
「うちが桃使うのが好きなんは、相手に当たると良い匂いがするし、絨毛が生えとるから、投げる時に握ると、まるで誰かを抱きしめたみたいな気持ちになれるから」
「ほらー! やっぱ男好きなんやんかー!」
つっこまれたカドミチさんはまた舌を出してはにかむ。
握ると気持ちのいい桃。連射可能なぶどう。爽やかなオレンジ。とにかくデカいからドッジボール気分になれるパイナップル、青い時と熟した時とで触り心地の異なる洋梨、日本人のソウルフルーツみかん、飾り切りしたらいろんな形で戦えるりんご。
で、カンナちゃんは? と焼きそばを頬張っている正面の眼鏡の男がわたしに訊く。
「……バナナ、です」
子どもの頃にバナナの森開園テープカットセレモニーで目にした母の笑顔を思い浮かべつつのっそりと手を挙げたわたしに、トモヒコさん以外の全員が声をそろえて「うわあ、平凡」と爆笑した。
わたしが理由を口にする前にくだもの大戦争のゲームはフェイドアウトしていって、わたしはもう何もしゃべることがなくなってしまい、残りの二時間ほどずっとジョッキの烏龍茶をすすり熱々の鉄板にうつむいていた。
ワリカンで会計を済ませて〈はつせ〉を出ると、その日〈ラウンジ・梅〉の出勤にあたっているマツベさんとサワさんはそのまま東心斎橋へ向かい、男ふたりが彼女たちを店まで送ると言い、カドミチさんは合コンで意気投合したロン毛の男と腕を組んで、彼の行きつけだという裏なんばの飲み屋へ行ってしまった。
わたしが財布を仕舞いながら電車の時間を調べていたら、隣でわたしと同じように突っ立っていたトモヒコさんがふいに顔を覗いてきて、もう帰るん? と目を細めた。
「俺らもどっか行く?」
とりあえずふたりで歩き出して、南海通りから地下鉄なんば駅へ続くアーケードは恐ろしいほどの人混みだったから、東へ舵を切って日本橋方面へゆるゆると進んだ。
並んで歩いているとてのひらの肌が幾度となく無意識に触れた。ぽつぽつと交わす話題はトモヒコさんがさっきくだもの大戦争で答えていた洋梨の思い出話になり、それから「バナナは平凡やけど結局いちばん便利やと思うよ」とトモヒコさんはふわりとほほ笑んだ。
よくよく見上げてみたトモヒコさんの顔は、まるでやわらかなナイフですっと切り込みを入れたみたいな一重まぶたの、とても涼しげできれいなものだった。こざっぱりとしたツーブロックの黒髪が夜風にそっと撫でられていた。わたしの恋人も彼とよく似た静かなタイプの顔立ちだけれど、トモヒコさんのそれは恋人よりも軽薄で美しい色気があった。
口下手で吃りがちなわたしの話にトモヒコさんは穏やかに耳を傾け、ていねいに相槌を打ち、白檀に似た香水の匂いをわたしのほうへ漂わせ、すると会話はどちらともなく性的なものとなり、トモヒコさんは、かつてバンドをやっていた頃に付き合っていた女と繰り返していた暴力的なセックスの味がいまだに忘れられず、どんなひとが相手でも毎回そういう行為になってしまうと言い、わたしはわたしで五年付き合っている恋人ともう長いあいだセックスしてないとつい口に出してしまって、そうこうしていたらいつのまにかふたりともの足がラブホテル街のほうへ向かっており、一体何がどうしてそうなったのか、一軒の真新しいホテルの前に到着するとトモヒコさんが「ここ、入ってみる?」と、口の端に軽薄だけれど美しい笑みをたたえて振り向いていた。
トモヒコさんが指差したそこは、確か老舗のラブホテルだったのがつい先月くらいまで工事中で、いつ頃に完成したのか、入り口に巨大な鳥居のあるやたらと派手なぜんぜんべつのラブホテルに生まれ変わっていた。
「……『千と千尋の神隠し』の湯屋みたい」
「ほんまやな」
足を踏み入れた瞬間に何百年何千年と時が経ちたちまち異世界に飛ばされてしまいそうだと思って、しかしトモヒコさんはするすると鳥居をくぐり、「イラッシャイマセ」とアナウンスの鳴り響く自動ドアに自ら吸い込まれていって、ランプの点灯している空室の宿泊ボタンを何のためらいもなく押した。
トモヒコさんのセックスは宣言どおり未体験の暴力セックスで、セックスというよりほぼ無重力の絶叫アトラクションだった。
めちゃくちゃになったキングサイズのベッドの上で、背中じゅうに刻まれた鋭い爪痕と両胸に付けられた真紫の噛み痕と血まみれの腕をわたしがぼんやり撫でていると、お風呂、一緒に入る? とトモヒコさんは缶のオレンジジュースを手渡した。明かりが点いたままの薄ピンク色の部屋は馬鹿みたいにまぶしくて、浴槽に湯を溜めに向かうトモヒコさんの白いしなやかな背中までもがピカピカ光って見えた。
カンナちゃん恋人がおるんなら、俺これからセフレかな、とお風呂場に行く前のトモヒコさんはぽつりとわたしに言って、そうなのか、と思った。セフレと言われて大学時代のセフレのことを憶い出した。平和条約。わたしと恋人が五年前に結んだ恋人という平和条約。恋人と最後にデートした二カ月前、豚まんの最後のひと口をゆっくり咀嚼しながら恋人は、もうデートするの、しんどい。もう、やめよう。と、空虚な顔でわたしに言った。恋人の真っ青な顔を眺めていたわたしの鼻腔は、熟したドリアンの腐臭でいっぱいになっていた。
その日以来、恋人からの連絡はない。
ちょうどいい温度に蛇口をひねってきたトモヒコさんがベッドに戻ってきて、わたしの握りしめていたオレンジジュースの缶を取り、とてもおいしそうに飲み、枕もとに置かれていたリモコンに手を伸ばした。
ブイン、と鈍い音がしてテレビが点き、大きすぎる音声とともにニュースの画面が広がった。
《……です。……くさんの被害者が出ている模様です。現場は新世界で、戦闘により多数の被害者が出ている模様です》
普段は二十二時台のニュースで目にする可愛らしい女リポーターが顔じゅう引き攣らせて叫んでいる。頭にはバナナ色の防災ヘルメットを装着し、バナナ型の実寸マイクをふるえる手で握っている。リポーターの背後は暗闇のなかでもはっきり伝わるほどに騒然とし、見慣れた新世界のネオンの空を時おり細かな物体が弾丸のように横切っていく。弾丸はみるみるうちに豪雨のように激しくなる。リポーターが悲鳴をあげ、しゃがみ込んで画面から消えた。
中継からスタジオに切り替わる。
《えー、ただいま臨時ニュースをお伝えしております。番組の途中ですが、ただいま臨時ニュースをお伝えしております。先ほど新世界にて、くだものではなく、大量のどて焼きが投げつけられる戦闘が勃発いたしました。どて焼きで攻撃を開始したのは西成の住民を中心とする民間戦闘員で、およそ五百人規模の戦闘員が参加しているとみられております。くだものでの応戦がはじまっていますが、どて焼きの圧倒的戦力の前にはなす術もないようです。付近の皆さまは十分に警戒してください。繰り返します、ただいま臨時ニュースをお伝えしております。戦争が先ほど新たなフェーズへと突入いたしました。戦争が、先ほど新たなフェーズへと突入いたしました》
トモヒコさんの瞳にニュース画面の強烈な色彩が映り込み、躍っている。トモヒコさんはオレンジジュースの缶を持ったまま固まって、わたしも同じように隣で素っ裸のまま固まっている。くだものでなくどて焼き、戦争、新たなフェーズ、という言葉を念仏みたいに繰り返すニューススタジオのコメンテーターの顔が真っ青なのにどこか他人事で、どうしてだか喜んでいるように見える。
……まじか。と、トモヒコさんが立ち上がった。
「……俺、西成に住んどるんよ」
こんな計画ぜんぜん知らんかった、と呆然とするトモヒコさんの向こうで、浴槽から溢れた湯のごうごうという音が聞こえた。すぐそばでどて焼きの豪雨が鳴っているみたいだった。早く湯を止めに行かなくてはいけないのにトモヒコさんもわたしも一歩も動けなかった。
どて焼きの暴動は収束の気配を見せることなく画面はただひたすら現場中継とスタジオの行き来を繰り返し、時間感覚がブラックホールに吸い込まれていく。画面のなかの激しい戦闘はどれだけ時間が進んでも何も変わらない。黒い雨が夜の新世界に降りつづける。時おり思い出したようにスマホを見れば、あっというまに数時間が経っている。
シーツに根が生えたようになったわたしたちはそれから朝まで無言でテレビの臨時ニュースを眺めつづけ、チェックアウトの一時間前にようやく我に返った。ゆうべ入室した時には、ヤって寝て起きたら出る前にもう一発ヤろうか。などと笑っていたのにもうどちらの身体にも一滴の性欲すら残ってはいなくて、すっかり冷めた風呂の湯を抜き新しく入れて、わたしとトモヒコさんはぜんぜん違う方向に顔を向けて黙って浸かり、黙って拭いて黙って着替えた。
「あ」
シャツとスラックスを身につけたトモヒコさんが数時間ぶりに声をこぼす。
どうしたんですか、と訊ねると、これ、と言ってゆうべ床に投げ捨てたバナナホルダーをわたしに見せた。
「きのう合コンの前に使ってもうて、バナナあと一本しか残っとらんかった。こんな丸腰で、俺、西成まで帰れるかな……。この騒ぎやったら、どこのくだもの売り場もすっからかんやろうな」
トモヒコさんのバナナホルダーはずいぶん乱暴に使い古されていて、腰に巻く革部分が毛羽立ち、ところどころひび割れていた。トモヒコさんが生き生きと誰かにバナナを投げたり、濡れた皮を服や靴やポストやベランダに仕込んだりする光景を思い浮かべた。
わたしのバナナホルダーの残弾も同じく一本で、きのうの合コン終わり、カドミチさんとマツベさんとサワさんが手を洗いに席を立った隙を狙って、彼女たちの高級そうなブランドバッグの底に、皮ごと拳でぐちゃぐちゃに潰したバナナをこっそり入れたのだった。
臨時ニュースはとうとう午前のニュースと合体し、いまだ新世界の暴動の様子を映している。カメラのレンズが遠くから飛んできたくだものの皮とどて焼きの汁で、ベシャッ、と汚れた。
「大丈夫です」
わたしは飛び出すように立ち上がり、バナナホルダーを装着した。トモヒコさんのとても綺麗な瞳を見た。そしてホテルのアメニティやバイブレーター、コップなどを引っ掴み、つぎつぎリュックに放り込むと、もう一度「大丈夫です」と大きく頷き、トモヒコさんに備え付けのシャンプーボトルを手渡した。
「戦争は、新たなフェーズに突入したから、わたしたちもう何をやっても大丈夫です」
その言葉を口にした時のわたしはきっと、パークスガーデンのバナナの森の、青々と風にうねる葉っぱみたいにみずみずしく力強かった。
ホテルの備品を詰め込めるだけ詰め込んだリュックを勇ましく背負い、部屋を出た。新世界からそう遠くはないラブホテル街の至る所で、落下した焼夷弾から立ちのぼるガソリンの煙みたいにどて焼きの臭いがしゅうしゅう噴き出していた。臭いは抜けるような青い空と高く高く交わっていた。たくさんのひとびとが路地を慌ただしく駆けずりまわっている。
「じゃあ、また」
トモヒコさんが不安げな顔で手を振った。
「じゃあまた」
さっきまで溶け合っていたひとかたまりのわたしたちが、糸を引きながら離れ離れに、反対方向へと分かれていく。わたしは重くなったリュックの肩紐をギュッとつよく握りしめる。夏直前のこの街は暑くも寒くもなく、とても気持ちよく、きょうもパークスガーデンのバナナの巨大な森に散歩をしに行こうとふいに思う。いつかまた恋人ともあそこへ散歩に行きたいなと思う。たぶんいま、恋人は家に引きこもり息を飲んでテレビの画面に釘付けになっているはずだ。
バナナの森へたどり着いたら、この戦争で生き残れるよう、いちばん立派な木に祈る。
それからわたしはもうひとつ願う。あの優しい恋人がどうかこの新しい戦闘に、加わりも傷つけられたりも、しませんようにと。










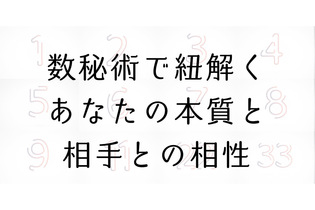










本を読むのが好きです。小説を書いたり、書評を書きます。関西出身在住。