やがて幻になるこの街で「異界の言葉で書かれた手紙」
めまぐるしいスピードで開発が進み、日々変化していく大阪の街。 いま目の前にあるわたしたちの街が徐々に幻になっていく光景を、リアルなのに少し不思議な物語で描く。 小説家・磯貝依里による大阪を舞台にした読み切り短編小説連載です。

死ぬ前にはかならず遺書を書かないと。
そんな叔母の声が夕立のあとの裏庭を泳ぎ、わたしの耳をとろりと舐めた。
足もとには枯れ落ちて羽虫の死骸みたいになった沈丁花の花びらが散らばり、雨上がりの夕日がわたしたちの頬を照らしていた。
「遺書を書くと、身体から魂がするりと落ちてくれるねんて」
裏庭に突っ立っていた叔母は、花ばさみをぶらつかせて気だるげに微笑った。わたしは四畳半に敷いてもらったふとんのなかから、そんな叔母の様子を眺めていた。
叔母の声は遠くにあるようで、しかしながら夢とうつつをふらつくわたしのところまで真っ直ぐに届く。
「むかし知り合いが言うとった。もしそれがほんまなんやったら、そしたらこの世の全員が、すごーく気持ちよく死ねると思うねん」
花ばさみが茎をちょん切る音があたりに響く。裏庭に咲く春の花が一輪一輪ていねいに切られてバケツに浸けられていく。
「ね、チューちゃんはどう思う?」

幼い頃に叔母の家へ滞在するのは決まって春休みの初めことだったから記憶はいずれも沈丁花の濃い香りで満たされていて、だから数年ぶりの訪問で裏木戸のそばに植えられた金木犀 の匂いをくぐり抜けると、なんだか鏡合わせの世界へ足を踏み入れてしまったような奇妙な心地がした。
叔母の長屋の表の引き戸はわたしが赤ん坊の時に壊れてしまい、それっきり直されていない。直すつもりもなかったようだ。
長年の雨風で腐食したぼろぼろの木戸は巨大な粘菌みたいな色をしている。
錆びた取っ手をまわして押せば、猫の額の裏庭がある。
なーん。と、か細い鳴き声を響かせて真っ白な猫が目の前を横切った。
コスモスの草むらをゆうゆうと掻き分けて入り込み、そのまま満開の白い花弁のなかに溶けてどこかへ行ってしまう。叔母は猫など飼っていなかったし近所の野良を手なづけたりもしていなかったはずだけれど、もしかしたら晩年にはわが子のように愛おしんで、餌を撒いたりしていたのかもしれない。
叔母の家は生野区の、桃谷と今里のあいだにある。
いつも車で母に連れられていったので、どういう道をたどってあの長屋まで行くのがいちばん近いのか、未だによくわからない。
叔母は生涯独身だった。母のたったひとりの妹だ。わたしからみて祖父にあたる男は彼女たちが幼稚園を出るか出ないかの頃によそに女を作って二度と帰ってこなくなり、母が先に結婚して家を出るまで、叔母の母、つまりわたしの祖母との女三人でずっとこの生野の家に棲んでいたという。
祖母はわたしが一歳を迎える前に死に、それからの十数年は叔母がひとりで暮らした。仕事は何をしていたのか、一体何で生計を立てていたのか、実の姉である母ですら詳細を知らないような謎のひとだったが、彼女が植物をとても丹精していることはこのあたりの古い路地では有名だった。
叔母が裏庭でざくざく花を取っていると路地の陰のそこ此処から近所のおばあさんたちがぬるりぬるりと現れて、
「オモー、イェッポヨォ。チョンヒャン」
と、呪文を口にしながら顔じゅうを干しナツメみたいに皺だらけにしてささくれ立った手を伸ばし、叔母はそこへどっさり切り取った季節の花を分けてやるのがお決まりだった。
路地のおばあさんたちの頰はいつも驚くほどに日焼けて紅潮していて、小さかったわたしにはそれがひどくおそろしかった。
チョンヒャン、という言葉は呪文ではなく叔母の名であるシズカの別の読み方なのだと教えてくれたのは叔母自身で、わたしのカナミという名は「チュシルと読むんよ」とも言っていた。
叔母はわたしのことをチューちゃんと呼び、叔母はわたしの前では自分のことをチョーちゃんと呼ぶので、ときどき、鏡越しに手を伸ばして互いの身体をまさぐるようにチューとチョーが混じり合い溶け合ってわたしたちはどちらがどちらなのかわからなくなり顔を見合わせてけらけら笑った。
叔母はわたしと二十も齢が離れていたのに、いつだって子どもだったわたしと対等に接する奇妙な女のひとだった。

十五年前に叔母が亡くなってからもう誰も棲んでいないこの長屋は毎年の夏の強い陽射しを浴びるごとにどんどん朽ちて、ひと月に一度ほど空気を入れ替えに行く母が「そろそろ引き払い時やね」とため息を吐いたところを、わたしが、じゃあ棲んでみてもいい? と手を挙げた。
「ええけど、あんたがむかし遊びに行っとった時よりえらいボロやで」
いい、とわたしは即座に頷き、その場で母から鍵をもらった。
先月、九月の終わりのことだ。
一人暮らしをしてみたかった、というよりも、下品に言ってしまえば要するに「ヤリ部屋」がひとつ欲しかったのだ。
今わたしが暮らしている実家は大阪と京都のほとんど境目にあるので、大阪市内にある職場までは徒歩も入れると二時間近くもかかっている。
電車に乗るのは好きなので通うだけなら不満はなかったものの、今年の春、一緒に過ごす関係の男ができてみると途端に家の遠さを不便に思うようになった。
男は既婚者なので、行為をするとなれば難波か梅田か京橋のラブホテルにしけこむしかない。安い・きれい・時間が長い、の三拍子揃ったお気に入りのホテルは何軒かあったものの、なにごとも割り勘のさっぱりした関係で、というのが当初からの約束だったから、オーガニック専門スキンケアコスメ用品店の安月給アルバイトという身分にあるわたしには、泊まりに行こうとそうそう頻繁に口にできるわけではなかった。
母からもらった鍵にさっそく猫のキーホルダーを付けてかばんに入れ、男に《来週から叔母さんチで暮らすことになった。市内だよ、生野だよ》と報告のLINEをしたらすぐに既読が付き、《カナミと叔母さんのふたり? 》と返ってきたので、わたしは通話に切り替えて、「ひとりだよ、叔母さんは十五年前に自殺したから」と言い、すると男は急に気分を悪くしたように咽喉をつまらせて、どうしたん、とわたしが訊くと、
《……やって、自殺したって、なんか嬉しそうにカナミ、言うから》
と、うなった。
「ごめんごめん、ぜんぜん悪気はない。自殺した場所もその家ちゃうから安心して」
わたしはあわてて謝った。男は不審そうにまたうなる。
怒らせた、と一瞬冷や汗が吹き出たけれど、そこに引っ越したらどういう家具を置いて、ふとんのサイズはどれで、といった話をするうちに男の機嫌が次第によくなったのでほっと安心して通話を切った。
通話している最中はずっと眼裏に叔母の顔が浮かんでいた。
わたしは叔母のことが大好きだったから、たとえ「自殺した」という言葉でさえも、叔母にまつわる何かしらについて口にすればいつだってしぜんと笑みがこぼれてしまうのだ。

ひと月に一度とはいえ几帳面な母がきちんと手入れしていたお陰で、長屋はすぐにでも棲める状態になっていた。
ぞうきんで磨きあげられた玄関の床板は、肌寒い季節でもいつだって裸足だった叔母の、温かいあしのうらの跡が指の先まできれいに浮かび上がっていそうなほどにつやつやと光っている。
金木犀の匂いに背中を押されて玄関を上がり三歩もすすめばもう居間で、その六畳のほかには障子続きで隣に四畳半がひとつ、短く狭い廊下の先にある風呂場と手洗いの奥にこちらも四畳半で、それが叔母の部屋だった。
幼い頃、遊びに来る度にわたしが寝かされていたのは居間の隣、裏庭に面した四畳半だった。
一体どうしてだか わたしはこの長屋に滞在すると毎回かならずひどく体調をくずした。もともとそう身体が丈夫だったほうでもない。熱だの腹痛だので、小学校もしょっちゅう休んでいた。
「チューちゃんの弱さはチョーちゃんゆずりよ」
生まれた時からね、何から何まであんたはぜーんぶ、チョーちゃんにそっくりやったんやから。自分から泊まりに来たくせいにいつも裏庭の四畳半で寝込んでしまうわたしに、叔母はそう言って笑うのだった。
叔母はわたしのことを生まれた時から知っているけれど、わたしは自分の記憶にいつから叔母がいるのかぜんぜんわからない。たとえば夏、固められた土を割って突然生えあらわれる背高泡立草のように叔母はいつのまにかそばにいて――まるで前世からわたしの面倒を見てくれていたかのように――、臥せるわたしのひたいに、冷たく絞った手拭いをあててくれていたように思う。
あの頃の朝、叔母はまだ虫も鳴かないような早い時間から起きてきて、たっぷりと繁る裏庭や裏木戸、長屋の正面なんかに絡みつく大量の植物の世話を日課にしていた。
叔母が丹精する花はどれも立派なものに育った。四畳半のふとんのなかからその様子を眺めるわたしに叔母はたくさんの花の名を教えてくれて、具合が良い時には水をあげる役を仰せつかることができた。
畳に脚を投げ出し、縁側のつめたい床に汗ばんだ頰をつけて眼をつむっていると、叔母は特売のバニラアイスを湯呑みに入れて持って来てくれる。
水底のような座敷から見上げる春の裏庭は何かを超えたように光に充ち満ちて、黙ってアイスを掬うわたしたちの眼を焼いた。
病弱で爛れた毎日を送っていた幼いわたしに叔母はひとつも辟易することなく、むしろあんなわたしと遊ぶことで悦んでいるようにも思えた。
眠ったり起きたりを繰り返して蜉蝣のようになったわたしの足指をいじったり、わたしの少ない髪の毛をてのひらで波立たせてみたり、この座敷にすっかり馴染みきって融け込んでしまいそうになるわたしをやわらかく触る。
そんなふうに叔母はわたしの身体のどこかで遊んで、この世界からわたしがこぼれ落ちてしまわぬよう、ずっと見張っていてくれていたのかもしれない。

初日の今夜はひとまず、かつて寝かせてもらっていた四畳半にふとんを敷くことにした。鶴橋の市場に寄って買ってきた懐かしい味のするこってりしたキムチをビールで流し込み、押し入れに手をかけて振り向いたらもうすっかり日が落ちていた。
男には明日の晩に初めてここへ来てもらうことになっている。
このあばら屋ぶりに男はどんな表情を見せるだろう。薄い板と板とを無理やりハメて組み立てたような、今にも崩れ落ちてしまいそうな長屋。
それが小さな町じゅうにずらりと並び、支えあいもたれあう。
この町うまれの有名な詩人はここらの風景を〈鶏舎長屋(タクトナリ)〉と記したそうだ。と、むかし叔母が言っていた。そうだ、叔母は詩や小説なんかをとてもよく読むひとで、日記や何か、とにかく言葉を書くのも好きだった。
土の臭いのするふとんに寝転がり、真っ暗な天井を見上げて胸に手を組んでいると、突然激しい雨が降り出した。
叔母の葬儀がこの長屋で行われた日のことを憶いだす。
狭い居間には絵本でみた極楽浄土のような祭壇が整えられていた。わたしは白の、当時〈りぼんワンピース〉と勝手に呼んでいたふわふわの礼服に、同じく白のりぼんを長い三つ編みにぶら下げて叔母の棺の前に座っていた。
日の落ちきった頃から雨が降り出して、弔問客がぽつぽつとしか来ない静かな秋のお通夜だった。
ろうそくの火が屏風やくだものに映り込んでちらちらと滲むのに、なぜだか惹かれてずっと見ていた。
すうっと撫でてもひとつの棘も立たないつややかな棺 。
あのなかで叔母が眠っていた。納棺の際、色を失くしたくちびるに平生滅多につけていなかった紅が引かれ、蝋色の顔には白い死装束がとてもよく馴染んでいた。
「チューちゃん、具合悪なるからもう寝なさい」
お通夜の光景に夢中になっているわたしを諌めた母の声が、居間のふすまの向こうからきこえた気がした。
叔母の部屋は今もまだあの頃のままだ。
そういえば叔母が死んだその年の春、ここで寝転がっている時に今と同じような凄まじい雨を眺めていたことがあった。と、そう思い出した瞬間、まるで背後から誰かに髪を引っ張られてゆっくり足もとの穴に落ちていくかのように、あの日の光景がわたしの脳裏に蘇った。

その日の午後、身体の具合がとてもよかったので叔母に手を引かれて出かけた。
難波で服を買ってもらい、鶴橋駅で降りて散歩をしながら帰ろうと叔母が言ったのを憶えている。
東南側の改札を出て、強烈な焼肉の臭いの立ちのぼる近鉄の高架沿いに進むわたしたちを待っていたのは、まるで牛や豚の臓腑のようにぐねぐね入り組んだガード下の真っ暗な商店街の迷路だった。
クモの巣にまみれた切れかけの蛍光灯がチカチカ点灯しているだけの、言葉どおりの闇の路地だ。商店の煤けたビニルのひさしはいずれも無残に破れ垂れ下がり、錆びた鉄の軒先ではあらゆるものが剥き出しで、昭和三十年、四十年 代のポスターや看板が当たり前にそこらへ飾られたまま。
ぐねぐねの臓腑の路地で数珠つなぎに並ぶスナックや雑貨屋や飲み屋、食料品店の多くがシャッターを下ろし、その奥にひそんでいる生野の老人たちの生ぬるい体温がこちらにまで染み出してきていた。
歩いていると時おり黄色い灯が見えて、するとそこには中年女が立ったり座ったり、乾きかけのチヂミをゴザの上で売りながら近所同士で談笑し、キムチをビニル袋にぎゅうぎゅうに詰めていたりする。
「ここは市場やから朝がにぎやかで、夕方 を過ぎたら死んだみたいに静かやの」
叔母 ゴムサンダルをぺたぺた鳴らしてそう微笑んだ。
ガード下からはずれ、今度は町のほうへ進んだ。ようやく馴染みのある風景が見えてきてほっとした。
古い路地長屋が立ち並び、どの家も頭を低くして建てられているのに玄関先だけは盛大に植物まみれで、おもてに干された洗濯物は隣の家との区別がつかない。
子どもは路地裏からすぐに飛び出してきてそれを母親や祖母が後ろから叱り追う。鉄工場。ゴム工場。サンダル工場。銭湯。酒屋。民族食料品店。電機屋。もう営業していない大量のスナックや喫茶店や大衆食堂。神社。
チワワを近くで遊ばせたアッパッパすがたの老婆がひとり小ぶりな玄関石に腰を下ろし、初夏の陽射しに背を灼いて何をそんなに真剣に眺めているのかと思ったら行政から届いた緑色の封筒にじっと視線を落としていた。
叔母はそれをちらっとだけ一瞥して、なんでもないふうに通り過ぎていく。
あじさいのたくさん植わっている町だった。春なのでいずれもまだ休眠から醒めたばかりの茶色い生垣だったけれど、ところどころに新芽が出ていた。
わたしはそれを見て、小学校でリトマス試験紙について習ったことを叔母に話した。酸性とアルカリ性で分けられる。あじさいが青と赤に分かれているのもその仕組みのせいであるらしい。
その授業の一貫として、学級会で〈仲間分け遊び〉というのを行なった。それは校内にある様々なものをそれぞれの特徴に基づいて青、赤、黒の三つに分別するという遊びだった。たとえば花についての仲間分けであれば、木に咲く花は青い画用紙の上へ、地面に咲く花は赤い画用紙へ、どちらか判断しかねるものは黒い画用紙へといったふうに淡々と仕分けていく。
「……そう。おもしろい遊びしたんやねえ」
叔母は道端のあじさいの新芽にぶらぶらと触れた。
「そうやって、この世のものごとはみーんなきっちり分けられとるんやわ」
くちびるを尖らせてどこか不機嫌そうに感想を言う叔母にわたしは焦り、でもどちらでもないものもあってそれは黒い画用紙のところへ行くのだと強調すると、しかし叔母は、
「そやいうても、そういう三つに分けられとるんやろ。世の中にはたしかに曖昧なものもあるいうのに、なんでもきっちり分けられて、なんでもきっちり決められるんやわ」
と、冷たい苦笑いをこぼした。
ちょうど、雨の最初の滴が鼻にぽつりと落ちてきた。
「なんや、かなんな 」
姉はそう微笑い、さ、もう帰ろ、とわたしの肩を押してはや足で家に向かった。
帰宅後、ひとりの客が訪ねてきた。
おもちゃを散らかしたまま四畳半のふとんに寝転がり、途切れることのないおもての雨脚を眺めていたわたしの視界に、ひょいと大きな黒傘が飛び込んできた。黒傘は裏木戸周辺の花々をじっくり観察した後、開け放した部屋で寝ているわたしに気がつくと、濡れた土をざらざら踏んでこちらへ近づいてきた。
こんにちは、と黒傘はゆっくり頭を下げた。
「病気?」
わたしは寝たまま頷いた。三十半ばの端正な顔立ちだった。
「どこのお嬢ちゃん?」
黒傘は軽いため息とともにわたしを見つめた。雨がさらに勢いを増した。裏庭の植物の根もとから太い水のすじがどくどくと氾濫した川のように流れていく。
黒傘はわたしから眼を離さない。
「チョーちゃん、いたはる?」
その時、ふすまが開いて「池村さん!」という叔母の頓狂な声が響いた。
黒傘は、やあ、と顔をゆるませ、叔母に手を振った。叔母はわたしにはきこえない声で黒傘に向かって何かをつぶやき、驚くべき素早さで縁側を滑り降りた。
「ちょっと近くまで来たから」
黒傘が微笑む。叔母の頰が普段より桜色に染まっているような気がした。黒傘は懐から白い封筒を取り出した。
それを叔母に静かに手渡すと、傘を差したまま叔母を抱き寄せてなにかを耳打ちした。
黒傘の腕のなかで叔母は今にも泣きだしそうな顔になりくちびるを真一文字に結んでいた。叔母はしっかりと黒傘に抱きついた。
初めて目にする突然の男女の抱擁に、吃驚したわたしは口を押さえた。
黒傘のてのひらに肩を撫でられ、叔母は嗚咽をこらえて二、三度頷いていた。
しばらくすると黒傘は叔母を縁側に戻し、傘を持ち上げて、ほんならまた、と裏木戸に手をかけた。
「お嬢ちゃんも、またな」
奇妙な客が帰った後、叔母はうつろな瞳で裏木戸をずっと眺めていた。
それ以来黒傘がこの長屋を訪ねてくることはなかった。けれど、叔母が黒傘に対してひっそりと涙をこぼしていたすがたを、わたしはその後一度だけ見たことがある。
あの雨の日から一週間ほどが経ったとある夕方、寝飽きたわたしは話し相手をもとめて叔母の四畳半に足を向けた。ちょうど叔母に読んでもらいたい本があったのだ。それを脇に抱えてわずかにふすまを開けた。
指一本分ほどの隙間から、叔母が座卓に向かってこっくりとうつむいているのが見えた。
首が折れてしまったのだろうかと思うほどに叔母は深く深くうつむいていて、さてはうたた寝してしまっているのだと、にやにや笑いをこらえながら声を掛けようとした。
ところがその叔母の様子がおかしい。着ているワンピースがもろ肌脱ぎになっていたのだ。
水蜜桃のような叔母 うつくしい乳房がすっかり丸見えになっていた。その両乳房を、互い違いにした腕で抱いていた。
座卓の上には一通の手紙が開かれていて、その横には一葉の写真があった。
写真の像は黒傘の男だった。叔母はその写真に視線を落としながら自分の剥き出しの乳房をかき抱き、ひそひそと嗚咽していた。時おり写真のなかの黒傘にくちびるをなすりつけながら、乳房に爪を立てたり、ゆっくりと乳首を揉むような仕草をみせる。
手紙に敷かれていた封筒はあの日黒傘が叔母に渡したものだった。
便箋に書かれていた内容は、どうしてだかわたしには意味のわからないものだった。
叔母がなぜあのようなことをしていたのかはわからない。
いつもわたしの髪をやわらかく撫でてくれるその手が彼女の乱れたワンピースの股の奥に差し込まれたところまで覗き、なんだか気分がぞっとしたのでわたしはすぐに自分の寝ている部屋へと引き返した。
黒傘のことは母にも、誰にも言っていない。
叔母がわたしたちの知らない男のマンションの一室の、その湯船のなかに赤々と沈んでいたのは、それから数カ月 が経ってのことである。

カナミえらい盛っとんなあ。と、男は素っ裸で畳に寝転がるわたしの乳をうしろから抱いて笑った。盛っとるいうか、さっきからずっと触られとるから仕方ない。
男は、もうずいぶん長い時間わたしの乳房をいろっていた。揉まれすぎたせいでいつのまにか全体がわらび餅のようにたゆたゆとゆるみ、乳首はぷっくりと膨れ染まって、そう大きくないわたしの胸が、やわらかく心地いい秋の日溜まりそのもののように縁側の上へ真っ白にとろけ落ちていた。
今朝、夜通しの商売を終えた男はそのままこの長屋へやって来て朝日を背にしながら一心不乱にわたしを抱いた。
このあいだ寝たのは一カ月 ほど前のことだったから飢えているのも仕方がないと思いつつ、このひとには本命がいるし、それにわたし以外にも長く可愛がっている飼い猫が二、三匹いるのだから飢えているわけでもなし、それでも、こんなにもこの身体をむさぼってくれるのか、嬉しい。という奇妙な感動があった。
まじわっている最中、狭い四畳半じゅうにふたりの甘ったるい口臭が満ちていて、この長屋自体が三十七度の体温を持った巨大な生き物みたいだった。
男はわたしの身体の形を盗りながら あらゆる場所をつねり、なぶり、殴り、締め、気絶させ、撫でる。
長屋が生き物になったかとそう思いながら四つん這いで壁にすがりつき腰を動かしていると、やがて自分たちまでもがなんだかまるで生まれた時からそばにいるのでどちらともなく繋がってしまった幻想的な動物のようだと思って、振り返ってキスしていたくちびるをわずかに離し、わたしはつい男に「好きです、ほんとうに好きです、ねえ、わたしのこと好き?」という、この世で一番くだらない問いをよだれまみれの口からこぼしてしまう。
男はそれを聞くと笑って頷き、まるでわたしに人権など存在していないかのように下腹をこぶしでにじり潰しながら、とても気持ちよさそうに射精したのだった。
咽喉が乾いたな、と寝返りを打った勢いで立ち上がると、もう夕方が足もとまで来ていた。
畳に敷いた煎餅ぶとんのシーツがまぐわった勢いで大きく裂けていて笑ってしまいそうになった。男の腿がその裂け目にきれいにはまっていて、わたしに腕枕をしてくれていた形のまま深い眠りに落ちている。
でもそれは今日二度目の腕枕だ。一度目はわたしの股から垂れる精液をぬぐってくれた後、最初の眠りに吸い込まれるまで優しく敷いてくれていた。それからしばらく経ち、先に眼の醒めたわたしが体勢を変えたら、男は腕枕していた腕をふにゃふにゃと伸ばし、今度はわたしの腰に甘えるようにぎゅうっと抱きついて、寝言をつぶやき夢のなかへ戻っていった。
二度目の腕枕は、さっきわたしが起き上がる瞬間に、その手をほどいたわたしの身体を宙に探しつつ、まるで虚勢を張るようにふたたび形づくってきたのだった。
さんざん虐めた女の身体を探す腕。わたしのほかにもこの手に虐められ、また、抱き寄せられているはずの飼い猫たち。虐めることを、幾人かの女たちから優しくゆるされているその手。
男は出逢った時からサディストだけれど、こんな光景を見下ろせば、サディストなどというのは究極の甘えん坊なのではないかとふと思う。
台所の流しでコップにぬるい水を注ぎ、一気に飲み干した。
ゆうべの大雨にも負けず、裏庭の金木犀はまだぎっしりと花を付けたまま、強烈な芳香を放っていた。わずかに肌寒いと感じるほどで、金色の風が全裸のすきまをさわやかに抜けていく。
甘い香りはいくら拒んでもわたしのなかへ侵入してくる。酸素はあるはずなのに呼吸が苦しい。
この季節が好きなひとと嫌いなひとは一体どちらが多いだろう。
子どもの頃に習った〈仲間分け遊び〉のことが蘇ってくる。
世の中にはたしかに曖昧なものもあるいうのに、なんでもきっちり分けられて、なんでもきっちり決められるんやわ。
いつだかの叔母の声が温かい吐息とともに、ふっと耳にかかる。ああいう寂しいことをつぶやく時の叔母の表情が大好きだった。
あれでは虐めたくなっても仕方がない。そんなよくない気持ちがふつふつと湧いてくるような、儚い色の瞳だった。
突っ立ったまま甘い香りになぶられつづけていると、さっき自分がこぼしてしまった「好き」という言葉への後悔がじわじわと這い上がってきて苦しくなった。
ほかの女たちも、この陳腐な台詞をこの男に伝えずにはいられなかっただろうか。
男がむっくりと起き上がるのが見えた。
裏庭の夕日で硬い身体が逆光に縁取られている。
「ねえ、あなたさ、四六時中、まいにち誰かしらの女の子と一緒にいて、嫌になったりせんの?」
「なに?」
「だから、飽きたりせんのかなって」

まあ、ほんまに猫みたいなもんやな、と男は言った。猫? そう、猫。男は笑う。
猫、何匹か飼っとってもとくに気にはならんやろ。家のなかをうろうろしとる、それを放っとくか、たまに撫でてみるか。こっちはこっちで暮らしとるし、あっちはあっちで足舐めたり。気が向いた時にだけ、こっちは気にしたらええし。やからべつに、飽きはせんよ。そういう問題じゃないから。
そんなふうに言う男のことをまぶしく眼を細めて眺めていたら、彼のうしろすがたがいつのまにか、黒傘を差していない黒傘の男になっていた。
「そんなのは男の勝手や言われたら、そうかもしれんけど。でもなあ、女には女の勝手もあるし」
女の勝手。
ささくれ立った畳をざりざり踏んで黒傘の近くへ行くと彼はわたしの肩にふわりと布をかけてくれて、それは叔母が着ていた懐かしいワンピースだった。
「そういえば、猫は嫌やって言われたこともあったな。うちは魚のほうがええわとか、むかしそんなこと言うとったな」
かまってもらいたがりな気持ちをなめらかな身のこなしの奥に隠し、あくまで気ままに見せかけて男の近くで歩きまわり、横たわる。横たわったこの身体に向こうの都合で手が伸びてくるのを歯噛みして待つ。
そんなむなしい光景よりも、濁った水の底でひとり静かに暮らしながら自分が浮き上がりたい時に浮かび上がり、水面から背びれや鱗をわずかに出してはまたすぐに沈む。そんな日々のなか、水面にきらめいたその一瞬を偶然どこかの男が見かけたりして、そうして愛でてくれたほうが僥倖だ。
男の視線のような月あかりの降り注ぐ水面に、ぴちゃんと跳ねる魚すがたの叔母が見えた。
同じに気ままなすがたでも、猫と魚じゃ大違い。
低く落ち着いた叔母の声音を帯びはじめたわたしの言葉に黒傘はなぜなのか笑って、「ほんまにあの子とよう似とるな」とわたしの頭を優しく撫でた。
それから黒傘の幻は、おいで、と手を伸ばし、わたしを叔母の四畳半へと連れ出した。

黒光りする床板。叔母の部屋には薄暮の気配が充満していた。さっきまでのまじわりの疼きはすっかり引いて、身体がすっかり軽かった。
干乾びた窓には青い魚模様の風鈴が吊るされていた。
「前に会うた時は、名前、きいとらんかったね」
「チュシルです」
叔母にはチューちゃんって呼ばれていました。と、するする口から流れ出た。
なぜカナミという読み方で伝えなかったのか。
胸騒ぎをおぼえさせる金木犀の香り につつまれて、黒傘の端正な瞳を見つめていたら、しぜんとくちびるがそこへ吸い込まれてしまうかのように「チュ」の音を形づくっていた。
わたしは自分の名の漢字を床板に書いて教えてやった。
黒傘は、そうか、と頷き、叔母のふとんにごろりと寝転がった。
「チョーちゃんと初めて会うた時、今のチュシルちゃんくらいの齢やったな。えらい綺麗な子やなあって思ったよ。ほんでも、むかしのことなんてもうほとんど忘れてしもたけどな」
そう言うと黒傘は寝転がったまま、唐突に、叔母の小さな箪笥から長形の封筒をひとつ取り出した。見憶えのある形は、幼い頃、あの雨の日に黒傘が叔母に渡していたものとそっくりだった。
「これ、チョーちゃんからの最期の手紙」
わたしは思わず黒傘の隣に腰を下ろした。
右横で仰向けになっている黒傘は、脚を高く高く組むと、いつから火を点けていたのかタバコを深く深く吸い込みながら、天井に封筒を透かして見上げていた。
前に会った時の印象ではとにかく端正で上品で、こんなにも行儀が悪くはなかったので驚いたが、今目の前にいる彼の醸し出す、隠された粗野な臭いがとても甘やかで心地よく思えた。
夕方の黄色い空気の底、黒傘の股のあいだに萎えた大きなものが見えた。黒傘はすっかり裸だった。
これは叔母が自殺する前に最期に見たこのひとのすがたなんだろうか、と思った。
「いつからそんなこと始めたんやろか。あんまり会われんから、ときどき手紙を交換しとったんやわ。最初はたのしかったけど、そのうち喧嘩はぜんぶ、手紙の上でするようになってしもた」
言葉であらわそうとしたら、自分の中にある良いものも悪いものもそのすべてが一緒くたになって漏れ出してしまう。
一字、一文、一行。こうしてあなたに宛てて書きはじめたらどうにも手が止まらなくなってしまう。
好きだという気持ちも、憎いという気持ちも、睦みあった後の虚しさも、どんなに身体がもとめていても、どんなに一対一で結ばれたくとも、永遠にあなたとわたしは同等の立場にはなれないのだということも。
曖昧に澱んだ気持ちは身体の奥に閉じ込めているままでは報われない。
だから、自分のなかに澱んでいる言葉を手紙に書きつけて封をしたら、まるで身体から魂がするりと落ちてくれたように清々する。
耳もとで、そんな叔母の透明な声がにわかに響く。
「たまに行くと長屋の裏木戸んとこでいつも出迎えてくれて。俺がこうして裸で寝とるあいだにこっそり手紙を書いとって、帰りに俺にそれ渡すと、チョーちゃん決まって言うたもんやった。
手紙書くんはお酒飲むみたいにええもんや、気持ちええもんやて。なんぼこの世にしんどいことがあっても、いっぺん言葉で書いたらぜーんぶ気持ちええに変わる。愛人や本妻やなんやいうても、そんなもんお酒と手紙の前では何のこともない。そう言うて」
死んだ日もたくさん酒を飲んでいた、と黒傘は言った。
叔母が酒好きだったという記憶はどこにもなかった。この男の言っていることが真実だとは思われない。
それともわたしの知らないところで、叔母は、この男と酒を飲んで爛れるように過ごしていたというのだろうか。
「そういう強気なことばっかり言うもんやから、つい、たくさん泣かせた」
黒傘はわたしの顔を見た。彼の言葉の意味はよくわからなかったけれど、あの雨の訪問の日こと、叔母がこの男の写真に顔をこすりつけて乳房を抱きそっと泣いていたことを憶い出し、きっとそのことを言っているのだろうと思った。
黒傘はわたしに最期の手紙を手渡し、読んでみて、と微笑った。
遺書だ。と、爪で封をはじこうとするも、しかし硬く糊付けされていた。
叔母の最期の手紙は、誰からも開けられることなく十五年を経ていた。少しでも力を入れたら、劣化した封筒が、焼きすぎたパイ皮みたいに手のひらからパラパラとこぼれてしまいそうだった。
わたしは指先に力を込め、黒傘の前で思い切り封を開けた。

かさついた便箋がおのずからふわりとひらく。息を飲んだ。
叔母の遺書は、この町の文字でびっしりと記されていた。
セピア色のインクが色褪せて、枯れ落ち、土に散らばった金木犀の花の粒のような丸い文字で埋め尽くされている。
セサンエソ チェイル……。と、最初の文をつぶやきかけて、わたしは便箋から顔を上げた。黒傘が、ぼんやりした瞳でわたしの口もとと、それから視線の先を見つめていた。
わたしが読み拾うことのできるのはわずかな言葉だけだった。祖母や母や叔母は知っているこの町の言葉を、わたしはほとんど身につけずに大人になった。わたしのなかに残っているのは自分の名前と、それから、長屋を囲む路地の至るところから楽しげに顔を出す、近所の老婆たちが交わしていた言葉の響きぐらいだ。
ひとつの文字も読めないらしい黒傘が、はは、と何かあきらめたように笑って、新しいタバコに火を点けた。
便箋に散らばった金木犀の文字は黒傘が煙を吐くとすぐにでも吹かれて飛んでいってしまいそうだった。
黒傘はすかした表情で格好つけてタバコをくゆらせていたが、わたしは、彼には叔母の最期の手紙を読むことができないのだと思ったら、自分がこの手紙を書いたわけでもないのになぜだか腹の底から清々した。
読めるか読めないかではなく、便箋の上では、叔母が「それ」を言葉として吐き出したその気持ちよさだけが、こうこうと金色の強い香りを放っている。
黒傘には異界の言葉に見えているだろうか。いや、黒傘にだけではない。
たとえわたしにこの言葉の血が流れていようとも、叔母の言葉はそこに記されているというただそれだけで、もう遠い世界のものだった。
サディストは究極の甘えん坊。
同じ飼われるのなら猫よりも魚のようになりたい。
これを黙々と書きつけていた、自殺する直前の叔母の静かな横顔。
叔母の気持ちも、わたしの気持ちも、どんな言葉にのせようと、誰かに正しく届けられることなんて、けっしてこの世界ではありえない。

ほんならまた来るわ、と朽ち果てた裏木戸に手を掛ける男に手を振りかけて、「やっぱりそこまで送る」とわたしは彼の背中に駆け寄った。
寝起きにもう一度めちゃくちゃにまじわって、それからふたたび終電間際までたっぷり寝た男はとても機嫌がよかった。夜の風がいくつも身体を吹き抜けて、目には見えないのに確かにそこにあった。
日の落ちた路地を手を繋ぎながら駅に向かっていると、長屋の切れ目にところどころ建っている新しいマンションのあたりから、拍子木の音に絡まって韓国か、中国か、それともほかのアジアの国か、わからないけれど透き通るような民謡の合唱がきこえてきた。
同い齢くらいの若い声だった。男も女もいた。
この町では朝も夕もいろんな言葉がきこえてくる。わたしのしゃべる曖昧な言葉も、この町ではただのひとつの小さな音でしかない。
どこから来たのかと誰かから訊かれることもない。ここでは、国がありすぎるあまりに国が遠い。この町にはあの鶴橋のガード下の商店路地の、牛豚の臓物みたいにぐねぐねうねる長い複雑な歴史があって、さまざまなひとがいて、みんな、ただひとつの音でしかない。
気持ちいい音やなあ、と男が拍子木の響きに目を細めた。
空には薄っすらと雨雲がかかっていて、秋の匂いに水の気配が混じるのを感じながら、わたしはつぎに男が長屋を訪れる日について想像した。
男のうしろすがたは、あの夕方の一瞬以来、もう二度と黒傘の男に変わることはなかった。
赤と白の近鉄電車が左右の景色を切りひらいてわたしたちを追い越していく。もうじき駅が見えるところで猫の鳴き声がどこからかきこえてきて、けれどそれに気がついたのはわたしだけで、男はひとり早々と、べつの光の灯る向こうの世界へと歩いていってしまった。











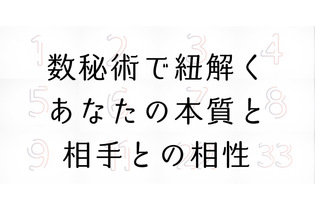










本を読むのが好きです。小説を書いたり、書評を書きます。関西出身在住。