
ずっと「ボロボロの筆は努力の証」なんて思ってた
「あなたの絵が好きです。たとえ、あなたが恐い顔をしたおじさんだったとしても、必ずあなたの絵を好きになっていました」

小さい頃、絵本を読んでもらうことが大好きだった。
母が大げさな演技をつけて、毎晩何冊もの絵本を読み聞かせてくれたことを、今でもよく覚えている。気に入った絵本は、全ページのセリフを丸暗記するほど読み込んだ。
小学生になり、周りの友人達が徐々に活字だけの難しい本を読みはじめても、絵本から卒業できずにいた。おかげでいまだに挿絵のない本を読むとすぐに疲れて頭が痛くなってしまう。
そうして日々絵本と過ごしているうちに、自ら絵を描く仕事がしたいと思うようになった。なんとなく、絵を描く以外のことにあまり興味を持てなかったから。
高校を卒業後デザイン系の学校に進学し、そこでたくさんの絵を描いた。その間、たくさんの美しい絵本にも出会った。特に衝撃だったのが、ロシアの画家ユーリー・バスネツォフが描く世界。
人間味溢れる動物たちの表情や色とりどりの植物、鮮やかな色彩に一瞬で心を奪われた。彼が描いた生き物たちは、みんな本当に生きているように見えた。
オオカミが二足歩行をしていたり、ウサギがドレスを着ていたり……現実ではあり得ないヘンテコな世界が違和感なく完成していることに、とにかく驚いた。熱い恋のように胸がドキドキ高鳴るのを感じたりもした。
自分もこんな風に“生きている絵“を世の中に残したいと影響を受け、なんとなく似た絵を描いていたように思う。
卒業間際になってとうとう、私は就職せずフリーランスのイラストレーターになることを決めた。両親はそんな私の進路を否定することなくすんなりと受け入れてくれたが、内心ハラハラしていたに違いない。まさか母は、自分が読み聞かせていた絵本がここまで子供の人生に影響を与えることになるとは、思ってもみなかったことだろう。
■一枚の絵を描くたびに、筆を買い替えてきた
フリーランスのイラストレーターになって、もうすぐ5年が経つ。
知り合いから仕事を紹介してもらったり、展示販売をしたり、一昨年には念願だった絵本を出版する夢も叶い、特別裕福ではないが、今は不自由なく生活できている。
個展では毎回200点近くの作品を描くのだが、最近ではありがたいことにほぼ完売するようになってきた。

個展の様子(写真提供:五島夕夏)

個展の様子(写真提供:五島夕夏)
全てアナログでデータにも残さず販売しているため、手元には自分の絵があまり残っていない。
とにかく描いて、展示して、販売して、の繰り返し。その都度、キャンバスや絵の具などの画材を買い足す。中でも絵を描くための“筆“は、毎週のように買い替えている。
■筆がこちらを見つめてくるたびに、胸が苦しくなる
「筆は、自分の髪の毛のように大事にしなさい」
学生の頃、美術の先生にそう言われたことがある。
絵を描く者にとって筆は重要な相棒であり、丁寧に手入れしなければならない。モノを大切に扱うこと――それは、子供の頃から誰もが自然と植え付けられる常識。他の人たちと同じように、例外なく理解してきたつもりだった。
それでも、それなのに、なぜだか、筆を大事に使うことができない。いつも、一枚の絵を描き終える頃には柄(え)の部分が絵の具でひどく汚れ、筆先がボサボサの寝起き頭みたいになってしまう。筆圧が強いとか、絵の具を乗せすぎるとか、使ったあとすぐに洗わないとか、理由はいくつも浮かんでくる。
頭ではわかっているのに、時にはたったの数時間で、筆の命をまるごと吸い取ってしまうのだ。というわけで、そんな力尽きた筆が、我が家には何十本も束になって残っている。ふとしたとき、もう決して使われることのないその筆たちと目が合うと、胸がキューっと締め付けられる。
はじめて絵本を描いたとき、緊張しながら持った筆。いつかの恋人に絵を贈るとき、胸を焦がして持った筆。何を描いても納得がいかなくて、持つのも嫌だった筆。その時々の思いを乗せて、筆がこちらを見つめてくることがある。なんともむずがゆく、どこか心地の悪い感覚。
それなのにどうしてか私は、ボロボロの筆を手放せなかった。乱暴に扱った筆に対する罪悪感か、思い出が詰まっているからか、単純に面倒くさいから……なんとなく、どれも違うような気がした。
■「たとえ、あなたが恐い顔をしたおじさんだったとしても」
話は少し戻るけれど、学校を卒業してすぐフリーランスになった私には、厳しく指導してくれる師匠も同業の友人もいなかった。
そんな中で参考にしたのは、雑誌やテレビの中で見る熟練のアーティストや画家たち。彼らのアトリエには、決まって長い年月をかけて使い込まれた道具が散らばっていた。その一見なんてことのない薄汚れた絵の具や筆が、ものすごくかっこよく見えた。
そんな憧れの人たちの姿を真似して自己陶酔することが、筆を荒く扱うはじまりだったのかもしれない。絵を描く自分にとって、使い込まれた筆たちは自信の証だった。努力していると実感し安心できる勲章だった。自身の苦労を可視化することで、自立したイラストレーターとして生きている実感を得ていたのだと思う。
当然、最初の個展ではあまり絵が売れなかった。
どんなきっかけでも絵を知ってもらえる機会になればと、絵と関係のないモデル業などの仕事依頼を引き受けたこともあった。そのおかげで私自身を応援してくれる人が増えたことはとてもうれしかったが、自分の絵そのものに価値を見出してもらえているのか、漠然とした不安がぴったりと張り付いてきた。
それでも絵が誰かのもとへ旅立つことがしあわせで、少しずつ、ほんの少しずつ、前に進んだ。SNSでのメッセージや個展で直接いただく言葉が、絵を描く人生を支えてくれた。
「お金を貯めて、部屋中あなたの絵で埋め尽くすのが夢なんです!」と笑いかけてくれる人。
「なぜだかわからないけど、この絵が欲しいと思ったんです」と真剣に伝えてくれる人。
先日開催した個展で、あるお客さんから手紙をいただいた。そこには、
と書かれていた。
恐い顔をしたおじさんには申し訳ないが、何よりもうれしい言葉だった。ようやく、自分という存在から絵が独り立ちし、自由に歩き出してくれたのだと実感した。
■数えきれないほど筆を汚して、たどり着いた答え

イラストレーターとして少しずつ実績を重ねた今、気づけば周りには自分の絵を求め、愛してくれる人がたくさんいる。
強く握り絵の具をたっぷり重ね、どんどん筆を汚した数年間。
自分の頑張りを認めることができるのは自分自身だけだと思っていたが、それは間違いだったのかもしれない。いつの間にか、心から信頼し安らげる居場所がちゃんとできたのだと、個展に来て作品を眺めてくれる人たちの顔を思い浮かべ感じた。
もうひとりじゃない、自信を持っていいのだ。これからも、絵を描き作品を作り続けていく。“生きている絵“を世の中に残すために、自分のことを知らない人にも絵が届くような、新しいことにも挑戦していきたい。
数えきれないほど筆を汚して、ようやくたどり着いた答え。
このさき私が思いを託すのは、汚れた筆じゃない。そう思えるのは、信じられる居場所と信じてくれる人たちができたから。
「私は死ぬまで、ずっとずっと絵を描いて生きていく」
ボロボロの筆をゴミ袋に押し込んだとき、なんとなく、そう思った。
絵を通じて出会った全ての人へ、感謝を込めて。
Photo/池田博美










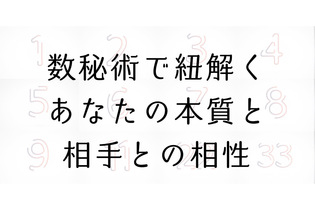










学生時代に出会ったロシアの絵本に大きく影響を受け、絵本画家を志す。
現在はフリーのイラストレーター・絵本作家として活動中。