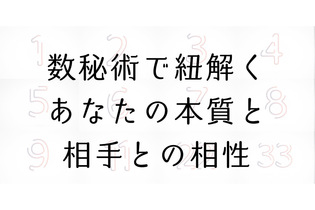「パンパンの荷物はダサい」らしいが、こちとらゲイでして
「もう少しイケメンだったら」「ゲイじゃなかったら」いつも自分の中にある足りないものから逃げたかった。そんな思いを背負わせていたポーチは、不足感を埋めるかのようにいつもパンパンだった。けれど、平成が終わるこの瞬間に手放してみようと思う――。ライター・編集者の太田尚樹さんによる特集エッセイです。

本屋でたまに女性誌を見る。
好きな方の連載が載っていたりするし、今の女性の気分が知りたいと思うからだ。「女性を知る」という行為は、僕にとって「自分を知る」という行為に近い。それはなにも石田純一さんみたいなキザなことが言いたいのではなく、僕はゲイだから、「女性」という圧倒的な生物的差異がありながら親近感を抱く存在について、いつも知りたいと思うのだ。
女性誌の中には共感も違和感もころがっていて、それらを一つひとつ見つめることは、「やっぱり僕は僕なんだな」と僕に思わせる。女性誌を読むという行為は、性において曖昧にうまれた自分の輪郭をなぞるようなものだ――。
大げさな書き出しになってしまったが、実際はただ所在なげに立ち読みしている。女性誌エリアはどこの書店も混み合っていて、女性たちが肩をすぼめて並ぶ列に図体のデカい自分が割って入るのは、毎度申し訳なくなる。いつも列の後ろの方から棚に腕を伸ばして、『GINZA』を手に取る。そして松尾スズキさんの連載を読んで、『VERY』を読む。『anan』も読む。その後は、目についたものを気ままに手に取る。
昔から僕には女友達が多いからか、女性に紛れてこういうことをするのが恥ずかしいとは感じない。なんなら「こだわりがある男」に見えていそうで、格好いいと思われているんじゃないかと想像したりさえする。本棚から自分の内面に視線の先を移せば、人の目ばかり気にしている時点でそもそも格好よくないとわかるのだけど、小心者なので仕方ないと自分を許している。小心者のまま、平成を終えようと思う。
ところで、先日見ていた雑誌には「パンパンの鞄からは卒業しよう!」と書いてあった。鞄やポーチがものでいっぱいの人は、過剰な不安にかられていてダサいらしい。誌面の中では、あたかも自然であるかのように不自然なポーズをとった女性が何も入らなそうな小さなバッグを持って笑っていた。入るのは財布とスマホ、リップくらいだろう。メイク道具は要らないのか。こういう美人は、メイクが少し崩れたとしても、男たちに「隙」とカウントされて終わるのだ。世の中はつくづく不公平だと思った。
さて、そんな戯言はいいとして、僕はこの記事を読みながら「これは絶対、鞄が小さい編集者の企画だなあ」と思った。
パンパンの荷物がダサいことなんて、当の本人が一番知っている。なにも、女性誌で大発見のように取り上げてもらう必要はないのだ。というかむしろそっとしておいて欲しい。それは僕が20代、荷物の精査ができない人間として過ごしていたからよくわかる。
■7年間、「不安」をポーチに詰め込んで

今回「平成」の終わりと一緒に捨てることにしたこのポーチは、7年間もパンパンだった。
これまで詰め込んできた物は、セロハンテープにスッとする目薬、油取り紙にスティック糊。思い返せばいろんなものがあるが、そのほとんどは使われることもないまま、狭い空間でこすれ合って色褪せていった。
一度「吐き気止め」という変わり種が友人の要請で活躍したけれど、タイムカプセルから取り出したのかと疑うほど劣化したパッケージを見られてしまい、吐き気に追い打ちをかけていたらどうしようと不安になった。友人は何も言わず飲んでくれた。
荷物のひとつやふたつ、出先で足りないとわかれば誰かに借りればいいし、大抵は何かで代用できる。何なら買ったって構わない。だけど、あれもこれも連れて歩くことをやめられなかったのは、もうこれ以上「ああ、足りない」と感じたくなかったからだ。
小さな頃から、いつも自分の「足りないもの」ばかりが目についていた。「もう少しイケメンだったらなあ」、なんてよくある悩みは良い方だったが、思春期に出くわした「ゲイじゃなかったら、もっと人と繋がれた」という不足感には面食らった。
具体的には書けないが、いろいろと家庭内がドラマチックなのも面倒だった。何度も「こんな家に生まれていなかったら」と想像して、何度か家出にチャレンジしようとしたが勇気が出なかった。昔から小心者だったのだ。
僕は早くから「不足」にとんでもなく飽き飽きとしていて、そこから逃げようと必死だった。その逃げ足は思春期を終えた頃にはまるでアスリートのようになっていて、みんな僕のことを「ストイック」だとか「完璧主義」と言うようになった。だけど当の本人にはその評価はうれしいものではない。「完璧」という目標は、以前の僕にとってずっと「それしかないもの」だったからだ。
ポーチに詰め込んだたくさんのかわいいガラクタたちは、そんな切実さの表れだった。
■「完璧」の輪郭を掴んだ気になって
ちなみにこのポーチは「マザーハウス」のもので、それにも大きな意味があった。
「マザーハウス」は、代表の山口絵里子さんが大学院在学中、「途上国から先進国に通用するブランドを作る」という思いを持ち、たったひとりで当時のアジア最貧国バングラデシュにて立ち上げたブランドだ。
山口さんは創業期、何度も現地で人に裏切られた。時には一緒に働いていた工員にパスポートを盗まれ、またある時には工場ごともぬけの殻になった。それでも彼女は「悪いのは社会システムだ」と、人を信じることを諦めなかった。そして「マザーハウス」をアジアに17店舗を抱える、グローバル企業にまで育てあげた。
学生時代に彼女の自伝『裸でも生きる』を読んだ僕は、あまりの感動にダラダラと泣いた。これだ……! この燃えるような熱意と濁ることなき慈愛、何度も立ち上がる強さこそが、人として「完璧」なそれだと思った。
「完璧」の輪郭をようやく掴んだと思った僕は、決して見逃すまいと、進行方向をマザーハウスに向け、一直線に走り出した。文字通り大阪店に駆け込んで買ったのがこのポーチで、そしてマザーハウス大阪店にアルバイトとして入社した。それからの僕にとってポーチはさながら「お守り」で、流れで買った神社のお守りはただの「お土産」になった。
■不安よりも、日々と生きる
だけどつい先日、鞄からこのポーチを取り出した時に「そろそろ買い替えなきゃな」と自然と思った。
そう最初に思った時の感情はいたって平坦なものだったが、時を同じくしてこの企画の相談を受け、「そう言えば僕、これを捨てようとしてるんだな」と改めて驚いた。
というのもお守りに対して「買い替える」という概念は、物騒だからだ。このポーチはその重苦しい役目を終え、ただの古ぼけた愛らしい日用品に戻ったのだということを、僕はその時に知った。
たしかに今の自分は、あの当時のように「変わりたい、強くなりたい」とは思っていない。幾分軟弱になってしまったのか、と内省してみたがきっとそうでもない。僕の「逃走」の人生は、いつの間にか終わっていたのだ。
自分に何があったかと思い返してみると、いろいろありすぎたような気もするし、何もなかったような気もする。
僕は「平成」という派手さのない低温な社会を全速力で逃げて、逃げて、逃げ続けて、その道中でさまざまなことを学んだ。逃げていただけのはずが、気付いていたら山を登っていて、「なんで登ってるんだっけ?」と自問自答した。
そしてふと立ち止まって景色を見渡すと意外と綺麗で感動して、「あぁ、こんなとこまで来れたんだ」と安心もした。そこからまたゆっくり走り出して、時には深い谷にも落ちて、そこで「孤独」を履修した。しなやかになって、強くなって、優しくなって、また走りだしたらなんか違った。
前よりずっと上機嫌になって、呼吸はずいぶんと落ち着いていて、良き友に出会って、色んな知恵を授かって、世界の見方が変わって、そしたら景色がどんどん鮮明に見えて、今立っている場所の楽しみ方がわかってきた。
僕はもう「『完璧』という桃源郷にたどり着けば、『逃走』も『闘争』も終わる」と信じていた僕ではなくなった。だから、満身創痍の道中で肌身離さずもっていたこのお守りも、必要なくなったのだろう。
今は昨日より今日、そして今日より明日、何かひとつでも新しいチャレンジをやってみたいと思って、生きている。そうしてこれまでできなかったことができるようになった日は本当にうれしいし、新たな生き甲斐を見つけた日には飛び跳ねて喜んでいる(最近はフラダンスを始めた)。遠い先に視線を奪われて転ぶより、足下を入念に踏みしめ、今見えている日常の妙を見逃したくない。
聞くところによると、コカコーラも、デニムジーンズも、「ビッグになる」という目標を掲げた人が成し遂げた発明ではないらしい。コーラは、元々薬品だったものを、おもしろがって炭酸で割ったことで生まれ、デニムジーンズは船の帆布をズボンにしてみたことから始まった。発明というのは、「何やってんだよ!」と笑っちゃうような毎日を続けた人が、見逃さなかった日常の妙だ。
僕のような一般人は、そんな世紀の大発明とはきっと無縁なまま一生を終えるだろうが、人生をよくする発明も、きっとそんな感じで「あれやってみよう!」というチャレンジから生まれるのだと思う。その積み重ねと共に歩み、踊り、時には引き返したりする内に、僕らは過去に描いていた「完璧」さえもゆうにこえる脚力を持つ。
■「あのビルすごいね」
実は昔、山口さんと乗り合わせたタクシーの中で、そんなことを言われた。
たしか僕は絵空事に近い、自分のキャリアビジョンについて必死に語ったのだけど、彼女は優しい笑みをうかべてそう答えるだけだった。「あのビルすごいね」山口さんは当時できたばかりの高層ビルを指さして笑った。僕はただ「はあ……」と答えて、あいた口が塞がらなかった。「こんなに走り続けている人が、なんでそんなことを言うんだろう」。当時の僕には、山口さんの言葉の真意がわからなかった。
だけど今はわかる気がする。僕が勝手に「完璧」と憧れた山口さんもきっと、ただ眼下の煌めきを見逃すことなく、春の湿り気をもった暖かな土を、鉄琴のように高音を奏でる冬の地面を、しっかり踏みしめて生きてきたのではないだろうか。「毎日を丁寧に」、それは決して「毎日を生温く」というわけではない。日々を見逃さず生きるということなのだ。
「ふぁ〜なんか、僕もいろいろ大変だったなー!」
今日の僕は、こうしてあくびをかきながら過去を振り返り、また春が来たことを喜んでいる。窓を全開にする。風が吹いていて気持ちがいい。遠くで汽笛の音がボンヤリと空中をさまよっている。
僕は目を閉じて、これまで「逃走」に付き合ってくれたポーチに、そしてこうして時を超えても、僕にたくさんの学びをくれた「マザーハウス」に、心からの愛と感謝を贈った。本当にありがとうございました。
平成が終わり、令和とやらがやってくる。果たしてどんな時代になるのか、僕には全く見当もつかないが、どうなろうと逃げも隠れもせず、今度はスリムなポーチを小脇に抱え、イカしたポーズでもキメてやるつもりだ。

フラを練習する僕(Photo by @miyamo1073)
Photo/池田博美