
地獄で撮られた写真を燃やしに行く
元恋人との写真を捨てられなかった。それは、綺麗な思い出があるからとか、見返すたびに懐かしさを感じていたから――とかではなく、あの「地獄」の日々を生き抜いた自分自身の努力が消えてしまうような気がしていたから。

霊園までの道は桜が満開だった。
前方の席には、仏花を入れた紙袋を足元に置いた人たちが座っている。親族の供養だろうか。少なくとも、同じ目的で霊園に向かっている人はいなそうだなと思った。
桜並木の下で、バスはよく揺れた。急な坂道を進むとき、腕に抱えていたアルバムがシートベルトの金具にあたってゴトゴトと音を立てた。
それを聞いて、一刻も早くこのアルバムを焼いてくれ、という気持ちが強くなる。
■遺影みたいな写真
「平成のうちに捨てたいものってありますか」と編集さんに聞かれたとき、最初に思い浮かんだのが1枚の写真のことだった。
B5ノートを見開きにしたくらいの大きい写真だ。モノクロで、3年前まで付き合っていた恋人と私が写っている。撮影者は、ポートレイトで有名な写真家だった。
写真を撮られた瞬間の記憶は、酒でベロベロだったのであまり正確ではない。ただ、その写真家がわざとらしく我々を笑わせようとし、「もっとガ~ッとくっつこうか!」とでかめの声で指示してくれたのは覚えている。恋人に抱き寄せられて引きつった顔で笑った瞬間、バシャッ、とシャッターを切る音がした。
動物の予防接種みたいだな、と考えているうちに、私たちの番はもう終わっていた。
1組2分くらいだったんですよその撮影、と言いながら、Googleフォトに同期されたまま残っていた2年前の写真データを編集さんに見せる。
編集さんは「なんか……」と言いかけて少しためらったあと、「遺影みたいですね」と言った。
■「別れるなら俺は死ぬけれどいいのか」
恋人と過ごしたその2年間にタイトルをつけろと言われたら、わりと即決で「地獄」を選ぶ。
アルバイト先の同僚として出会い、彼の謎めいているところに惹かれて付き合った。双極性障害だというのは始めから聞いていたが、デートを繰り返すうち、私も引きずられるようにして体調を崩すようになってしまった。
彼は、1軒目に訪れた喫茶店で「もう動けない」としゃがみ込んでしまう日もあれば、子どものように何件もの予定をハシゴして走り回る日もある人だった。それが彼の障害に由来していることは当然わかっていたが、私に対しても暴言を吐いてくる日と優しくする日がランダムにやってくるのが厄介だった。
もちろん、双極性障害を持つ人が皆そういった態度を他人にとるわけではない。カウンセリングには私もたびたび付き添ったが、彼の問題は障害そのものではなく、「躁鬱の自分は誰からも第一に尊重されるべき」と思い込んでいる身勝手さにあった。恋人は気に入らないことがあると実家の家具を壊し、怒鳴り、メールで暴言を吐いた。
「なんでその人と別れないの?」という質問は交際中、友人たちからおそらく70回くらいはされたと思う。しかしその期間の私たちは端的に言って共依存の関係にあったので、彼は「別れるなら俺は死ぬけれどいいのか」というスタンスだったし、私は私で「この人の不安を取り除けるのは私しかいない」と本気で思い込んでいた。
■霊園で写真をお焚き上げしてもらう
霊園に着いたバスは、まばらな客を案内所の前に降ろすと速やかに去っていった。
管理事務所を探しながら、広大な霊園の坂を上り下りする。墓石はどれも新しく、つるりとコーティングされた表面には「ありがとう」「夢 希望 感謝」といった言葉が彫られていた。
管理事務所の受付で「お焚き上げをお願いしたいんですが」と告げると、制服姿の女性がすっと立ち上がって私の抱えるアルバムを一瞥した。
お写真ですかね、と言われて頷くと、こちらをご記入くださいと用紙を渡される。
手続きは30秒ほどで終わった。アルバムを受け取った女性は笑顔と真顔の中間くらいの曖昧な表情で私に頭を下げ、「実際にお焚き上げを見られるようでしたら○日にお越しください」と説明した。
管理事務所を出て、「うわ一瞬で終わっちゃった」と言うと、編集さんは「荷物が軽くなってよかったですね」と淡白に祝ってくれた。
■地獄で撮られた写真

自分の身を少しずつ削ってゆくような交際を続けて1年半ほど経ったころ、恋人が突如「ふたりの写真を〇〇さんに撮ってもらいたいんだけど、ついてきてくれるよね」と言った。
有名な写真家による写真館での撮影と聞いて、私はとっさに拒否した。しかし彼は譲らず、「撮る側っていつも自分だけが写真だけに写れないんだよ、その気持ちわかる?」と言う。
彼はカメラマンだった。交際中はほとんど休職していたが、たしかに彼は、よく私の写真を撮った。
写真に写るのが苦手だ、と主張する私を、彼は「撮らないと残らないんだよ」と言ってなかば強引に撮り続けた。いま振り返れば、あれは「俺のことも撮ってくれ」という甘え方の一種だったとも思うが、特に写真に興味のなかった私にはそれがわからなかったのだ。
こちらの拒否も虚しく、「前後不覚になるほど飲酒してから撮られれば緊張しない」という謎のソリューションのもと、私たちは過剰めに酒を飲んだあとに写真館での撮影を終えた。
後日、その写真を大きく引き伸ばして額に入れたアルバムを恋人からプレゼントされたが、実家住まいの私はそれを部屋に飾るわけにもいかず、クローゼットの奥にしまい込んだままで月日が経過する。
■地獄を必死で生き抜いた日々のこと、なかったことにしてもいいや
霊園からの帰りのバスを待っているあいだ、Googleフォトを開いて当時の写真を見返していた。
彼の写真に写る私は、桜の花越しに目を閉じていたり、打ち上げ花火を見上げていたり、万華鏡を覗き込んだりしている。
表情はさまざまだったがすべてどこかぎこちなく、その多くには青白い補正がかけられていて、いま見ると「写真家の恋人」のコントを真剣にやっている感じがしてちょっと面白い。
私は周囲の説得のおかげもあって徐々に正気に戻り、精神的に疲弊する話し合いや手紙のやりとりを何度も繰り返してようやく恋人と別れた。その後、彼にもらった紙の写真はすべて即座に捨てたが、そのアルバムだけは長いあいだ捨てる決心がつかなかった。
どうしてその写真だけとっておいたんですか、と編集さんに聞かれたとき、「あれは一応、有名な写真家が撮ってくれた貴重な写真だしと思って……」とボソボソ答えたが、理由を考えるにつれ、私は当時の自分の写真がゼロ枚になるのがちょっと嫌だったんだろう、という結論に至った。
2年前から写真をスクロールしていくと、友達や夫が撮ってくれた私の姿が少しずつ増えてゆく。最近の写真は酒蔵で酒をしこたま飲んで顔がパンパンになっていたり、旅行先で見つけた猿の顔はめパネルに顔をはめていたりとろくでもないものばかりだったが、そのどれを見ても「ああ、いまの私の顔だな」という感慨があった。
2年前、恋人に抱きすくめられてぎこちなく笑っている私は、いま見るとどうしても自分と同一人物だと思えない。だからこそ、そのころの私の姿が写った写真をこの世から消してしまうことは、あの地獄の2年の思い出とともに当時の私の努力もなかったことになってしまうように思えて、怖かったのだと思う。
しかし、最近の写真に写る自分の呑気さ、ポーズ(ダブルピースとかしている)、笑い方を見るに、「そうだよな、こっちだよな」という気もした。
帰りのバスは、行きほどには揺れなかった。「バスの揺れ方で人生の意味が解かった日曜日」という歌詞があるが、全然意味わかんないよ人生、草野さんどうなってんだよ、と思う。
桜並木を通らないルートでバスは駅を目指していた。
ラブホテルや靴流通センターが続く窓越しの景色を眺めながら、写真を焼いてもらったら、あの2年間、あの地獄を私が必死に生き抜いたこと、別になかったことになってもいいや、と急に思った。
Photo/池田博美










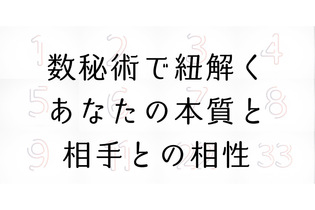










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。