
上手な死と下手な死ーーある医師の死生観
小説家・医師である久坂部羊さんは、これまで数多くの人々の死を見てきました。幾度も看取りをするなかで気づいたのは、上手な死とそうでない死があるということ。どうすれば死を恐れず、上手く死を迎えることができるのでしょうか。

■死は恐ろしいものではない
医師という職業柄、私は一般の人よりは多くの死を見ていると思います。外科医として病院勤務をしていたときは、がんの終末期医療に取り組み、高齢者医療に転じてからは、在宅で多くの患者さんを看取りました。
その経験から言えることは、上手に死ぬ人と下手に死ぬ人がいるということです。
上手に死ぬ人は、心身ともに穏やかに、あまり苦しまずに亡くなります。家族も悲しみはあるものの、ある種の納得と充実感に満たされます。
下手に死ぬ人は、嘆いたり、恐れたり、苦しんだりしつつ、尊厳を失い、心身ともにつらい目に遭いながら亡くなります。残された遺族にも、大きな悔いと悲しみをもたらします。
分かれ目はどこにあるのか。それはひとことで言えば、死を受け入れているか否かのちがいだと思います。
■死を直視すると、死を恐れなくなる
死を受け入れている人は、無闇に病院にかかりませんし、無理に死を遠ざけもしません。それまでの人生に満足し、ときには死を歓迎さえして最期を迎えます。
どうすればそんな心境になれるのか。それは死を直視することだと思います。だれにとっても死は恐ろしく、忌避すべきものと思われるかもしれませんが、それは死から目を背けているからこそ生まれる思い込みにすぎません。
私自身、子どものころは死が恐ろしかったし、死ぬことを思うと居ても立ってもいられないほど動揺したものです。
医師になったばかりのころも、自分が受け持った患者さんが亡くなると、深い絶望と虚無感に襲われました。しかし、何人もの患者さんを看取り、また、周囲の同僚も同じであることを見るうちに、徐々に気持ちが落ち着いてきました。死の本性というか、実態がわかってきたからです。
■長生き=幸せ、とは限らない
当たり前のことですが、死を恐れたり悲しんだりするのは、まだ死んでいない人です。亡くなった本人は何も感じません。
どれほど死を恐れ、嫌がり、嘆いていても、亡くなった人の顔は例外なく無表情です。表情を維持したまま死ぬことはできないからです。そこに私はある種の救いと癒やしがあるように感じます。
何事にもいい面と悪い面があるように、死にも両面があります。死の悪い面は、言うまでもなく、楽しみがなくなることや、悲しい、つらい、怖い、嫌だということですが、死んだらそれらもゼロになります。
死のいい面は、痛みや苦しみ、つらい思いから解放されることです。私のように高齢者医療の現場に長くいると、無闇な長生きがどれほど苦しいかを実感します。
多くの人は、元気なまま長生きしたいと思っているでしょうが、現実はそう甘くはありません。90歳を超えるような高齢になると、たいていの人は身体が弱り、あちこち痛くて、できないことが増え、尿漏れ、便失禁、誤嚥、床ずれ、少し動けば呼吸困難、食べても味はわからず、目も耳も疎くなって、何の楽しみもなく、不眠、めまい、耳鳴り、便秘に悩まされ、寝たきりで、介護なしには生きていけなくなります。
今の日本は医療が進歩したために、望んだとしても簡単には死なせてもらえず、本人にも家族にも過酷な状況を強います。それを目の当たりにすれば、適当なところで死ぬことのありがたさがわかるでしょう。
■私たちは毎晩、死のリハーサルをしている
死に向き合うのは嫌なことかもしれませんが、人間は何事にも慣れますから、そのうち恐怖心も嫌悪感も薄れます。死からいくら目を背けていても、いつかは必ず死ぬのだから、早めに準備しておくほうがいい。今はまだ死のことなんか考えたくないという人を見ると、私はパスカルの言葉を思い出します。
学校の試験と同じく、死に対しても前もって準備しておいたほうがうまくやり過ごせます。試験なら追試や浪人もありますが、死は1回のみ。ぶっつけ本番です。ひどい死に方をしたからといって、やり直しはききません。
上手に死ぬ準備をするためには、いろいろな側面から死を考えることも必要でしょう。たとえば、夜、床について、そのまま死ぬとしたらどうか。もし、眠ったまま死ぬのであれば、恐怖も悲しみもないでしょう。
つまり、死とは目覚めない眠りのようなものなのです。そう考えれば、我々は毎晩、死のリハーサルをしているとも言えます。
自分が消えてしまうことの恐怖や、死んだらどうなるのかという不安も、死んでしまえば霧散します。そう考えると、感情に振りまわされることがいかに無意味かもわかるでしょう。
■「死に時」を考えて生きる勧め
若い人には、自分の〝死に時〟をイメージすることをお勧めします。物事には何でも潮時があるように、死にも死に時があります。とにかく長生きしたいなどと思っていると、前述のような地獄の長生きになりかねません。
私がお勧めする死に時は60歳です。これは何も60歳で死ねというのではなく、自分の人生は60歳ぐらいで終わるものとして生きるということです。そうしておけば、たとえば70歳で死ぬとしても、「10年得した」と思えるでしょう。死に時は80歳などと思っていると、10年損したと嘆かなければなりません。
さらに、80歳を死に時にしていると、50代になってもまだ30年近くあると油断して、時間を無駄にしてしまう可能性もあります。60歳を死に時にしていると、あと10年しかない、こうしてはいられないと、人生に真剣になるでしょう。だから死に時は早めに設定するに限るのです。
死を直視すると、今、死ぬわけではないということもわかってきます。たとえ末期がんでも、今日死ぬわけではない。明日でもない。たぶん1カ月後でもないだろう。自分には時間があるということに気づくのです。
同時に、それは日1日と減っていくことにも気づかされます。そう思うと、今を無駄にできないということが、性根に響くでしょう。下らないことに腹を立てたり、自堕落な生活をしたり、つまらないことを気にして時間を浪費したりすることが、いかにもったいないか。
死に向き合うことが、自分の人生に向き合うことになるというのは、たぶんそういうことでしょう。死を意識して、日1日を無駄にしなければ、その日が来てもある程度は納得して目を閉じられるのではないでしょうか。
実際に自分の死が訪れたとき、私がどう感じるのかはわかりませんが……。
Text/久坂部羊
1955年、大阪府生まれ。小説家・医師。大阪大学医学部卒業。大阪大学医学部付属病院にて外科および麻酔科を研修。その後、大阪府立成人病センターで麻酔科、神戸掖済会病院で一般外科、在外公館で医務官として勤務。2003年『廃用身』で作家デビュー。近著に『告知』(幻冬舎文庫)、『祝葬』(講談社)などがある。
画像/Shutterstock
DRESSでは12月特集「死ぬこと、生きること」と題して、今と未来を大切に生きるために、死について考えてみます。










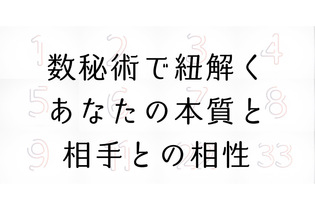










いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。