
死に触れてエクスタシー、すなわち“生”は爆発する
あれほどの感覚を得たのは、後にも先にもあの田舎で死に触れたときだけだった。

――エクスタシーは一瞬の死
この表現を何かの雑誌で見つけた瞬間、14歳の私は痺れてとり憑かれた。今でこそ誰かが洒落めかして書いたのであろう比喩なのだと思えるけれど、読んだのは田舎の暮らしに辟易していた14歳の少女。彼女は“一瞬の死”が閉鎖的な日常をぶち壊し、新しい私としての人生を送らせてくれるのではないかと期待した。
喜び勇んで彼を誘い、セックスに挑むも“死ね”ない。彼に触れられて瞼の裏を真白く染めるいわゆるエクスタシーの体験も、私にとっては一瞬の死などとは形容できない、極めて肩透かしなものだった。
事が済んで、白い下着に付いたわずかな血を見て、私は小さく泣いた。処女喪失の悲しさではない。
「私は一瞬死んで新たな私を始めるはずだったのだ。この現実と」
純粋な好奇心が身勝手に傷ついた瞬間だった。
私はそれからもふたりで、あるいはひとりで、何度も快楽の頂に登った。しかし、そのどれも一瞬の死に値しない、とるに足らないもののように思われた。たとえばとある男性の、過激で横暴なそれに瀕しても、傷つくばかりで“死に”はしない。気持ち良くないわけではなかったが、死と形容できるような、発狂するほどの衝撃はなかった。
――エクスタシーが一瞬の死だなんて大嘘。
肌を合わせるごとに14歳の無垢な期待は摩耗した。肌が擦れ、傷が細かくなるうちに、絶頂と死の結びつきなど考えることもなくなった。
しかし、それから10年後、私は一瞬の死にほど近い、エクスタシーを体験することになる。
ただ、それをエクスタシーと形容して良いのかは私の中の倫理が咎める。それは、セックスでもなく、自慰行為でもなく、死に触れて沸き上がったものだからだ。
■生物の死に触れて、湧き起こった感覚
数年前のある日、始発で国立駅に向かい、田舎暮らしを体験させてくれるという知人を待っていた。知人と言っても顔見知り程度の男性なので、チェックシャツにカーキのチョッキを着たそれらしい人を見つけてホッとする。挨拶もそこそこに車に乗り込むと、その人は田舎暮らしについて機嫌よく話し続けた。ランクルのトランクに積まれた鎌やら何やらの金属がぶつかる音と、車内に漂う血生臭いほのかな獣の匂いが気を散らせた。
鬱蒼と茂る森の中を1時間ほど走っただろうか。突然道が開けて、車が止まった。
「今日はごちそうにするからね。鶏は好きかい?」
「好きです」
「それはよかった。本当に新鮮な鶏は食べたことがないだろうからね」
「何か手伝いますか?」
「うん、もうすぐ手伝ってもらうことがあるから待っててね」
車から降りると、知人は大きな釜に水を入れ、その下に敷いた小枝に火を放ち、腰をかがめて緑の網で覆われた小さな小屋に入っていった。小さなほうの小屋からはコッコッコッコッと小刻みに鶏の鳴き声がする。今から鶏を絞めるのだ。
戻ってきた知人は、右手で鶏の首を掴み、得意げにこう言った。
「これをどう絞めるか知っているかい?」
鶏の絞め方は何かで聞いたことがあった。本当ならば電気などで気絶させてから首を落とすのだが、そうでないときは頭をひと思いに殴打してから首を落とす。痛みを感じない状態で落とすことで、苦しまずに死ねていいのだと教えてくれたような気がする。
目の前にいる鶏は相変わらずコッコッコッコッと小刻みに鳴き、ときどき羽をバタつかせた。
「あぁ、頭を棒で殴るんですよね。聞いたことがあります」
「いやぁ、そんなに大それたことはしないよ。これをこうするのさ」
次の瞬間、乾いた音が辺りを制した。かすかに、しかし確かにパキッという音がして、時が止まった。動けば切れそうな緊張が走り、何が起きているかわからず、血の気がサッと引くのだけがわかった。知人の顔には満面の笑みが照っていた。
「頭を落とすのはこれからだよ。切りやすいように首を捻るのを手伝ってほしい」
そう言って、知人は絞めたばかりの鶏の首を持ち、片手を押し出した。私の手は震え、その震えた右手で鶏を受け取った。できるだけ胴を掴もうと首根っこを掴むと、それより上の頭が心なしかだらりと垂れ、右腕に鳥肌が立った。血を噴くことも暴れることもなかった、質素で地味な死。
棺に入った死者はドライアイスで冷やされて冷気さえ放つのに、温かな鶏の身体はかえって不気味だった。私は今、死に触れている。しかも、ほんの数秒前までは生きていた身体。私の思考は停止した。
「さぁ早く、捻って。釜の湯がもうすぐ沸いちまうよ」
知人に急かされ、我にかえったように私は鶏に向き直った。そうして左手に鶏を持ち替え、右手で首を捻ったとき、私の身体に閃光が走った。
プチプチと千切れる神経の音は振動に変わり、骨を伝って私の腕に感染した。首をひと捻りするたびに、激情が押し寄せてくる。
さっきまで生きていた鶏が死んでいる。
それが実感となり、焦燥感となり、危機感となり、気持ちの高ぶりとなって、まもなく全身を駆け巡った。釜の火を見に行った知人に悟られぬよう、私は唇を噛み、肩をすぼませた。認めたくはないが、その感覚はどこか快楽にも似ていた。
脳内物質の荒波にあらゆるものが押し流され、私は私の中に残されたひとかけらの社会性でこの快楽をなかったことにしようとした。死んだ鶏の首に触れて心地良い気分になっていいわけがない。首を横に振る。瞳を瞬かせる。
私を高揚させているのは、自慰でもない、セックスでもない、まだ温かな鶏の死。そう思うと、血の気が引き、首をひねるたびにつまさきから脳天まで血が逆流した。意識が朦朧とする。もしも私が今死んでいないというのなら、まるで一瞬だけ死んだようだった。
戸惑いを感じながら、背徳感を抱きながら、供給される爆発的なわけのわからぬ感覚にただ身を委ねた。終わりのないフリーフォールのごとく身体を上下する血流だけを感じながら、気絶寸前の数秒間を何度も再生するように、私は鶏の首を捻り続けた。
「そろそろいいよ」
気付けば目の前に知人がいて、不思議そうに私を見つめていた。
「どうした? 顔色が悪いけど。死んだ鶏を触って気持ち悪くなったかい?」
「いえ、別に」
高ぶってしまいましたと言うのは変だと思った。
私が死んだ鶏を触って体調が悪くなったと思ったのか、知人はまた得意になって「都会暮らしは根性がない」などと言い、
「捌くから、それ貸して」
と鶏を指さした。
私はおずおずと鶏を差し出した。知人は鶏を受け取った右手で、首をぎゅうっと握った。
私が窒息しそうだった。
知人は鶏をまな板に横たえて、こちらに一瞥をくれた。
全身が硬直した。
知人は大きな出刃包丁を手に持ち、天高く振り上げた。息を飲んだ。知人が鶏の首の上に包丁を振り下ろした。目の前が真っ白になり、なかったはずの欲望が身体を貫き、めりめりと私の中を押し上げた。
この感情は何、
下半身から頭まで一気に逆流する血液。大声を出さないと気が狂いそうだった。もはや私のものではない身体を持てる限りの理性で立たせて、やっとの思いで鶏に向き直る。首を切り離された白い鶏の首元からはほんの少し血が流れた。まぎれもなく死んだ鶏を見て、私の何かがようやく、冷えていくのを感じた。
■私は“死”に触れることで“生”を爆発させた
あれほどの感覚を得たのは、後にも先にもあの死んだ鶏に触れたときだけ。認めたくはないが、あれはエクスタシーにも近いものだった。
死んだ鶏に触れて興奮したなどと言うのは気が咎める。しかし、もしも綺麗ごとを言うのが許されるならば、あの爆発的な感覚は、死に触れて逆に振り切れた“生”への欲望の副産物なのではないだろうか。
SMでレザースーツを着用するのは、“死”を肌で感じることで性的興奮を高めているからだとするフェティシズムの説がある。“死”を纏いながら享受する快感は、生きる欲望そのものなのではないか、と思う。
大病や大ケガで死を強く意識した後の、セックスの快楽の大きさは異常だったと聞いたこともある。それもまた、死と生とエロスが地続きになっているとは言えるのだと私は思う。
今となっては内容すら朧げな「エクスタシーは一瞬の死」と書かれた作品。もしかしたらあの作品の作者も死を目の当たりにして、自分の中に激しい性欲にも似た生の躍動を感じたのかもしれない……そんなことを考えている間にも、私のえも言われぬ感情は高ぶりを抑えられなくなるのである。
Text/佐々木ののか(@sasakinonoka)










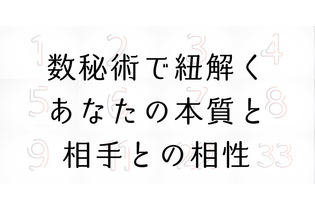










いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。