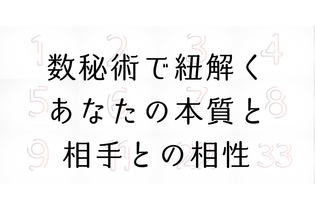【斉藤章佳×中村うさぎ対談】私たちは痛みを抱えて生きている。「依存症」の根底にある”性の問題”
依存症とは、誰もが味わったことのある苦痛が原因となって発症する病です。

目次
「何かに依存する人はもともと意思が弱く、だらしない性格だと見られがちですが、それは偏見です。(中略)仕事がうまくいかない、あるいは大切な人を失う。こうした誰でも経験する出来事が引き金になって、依存症への一歩を踏み出すかもしれないのです。つまり、依存症と絶対に無縁だといい切れる人などこの世にいないということになります」
これは、斉藤章佳(さいとう・あきよし)さんによる日本で初めての痴漢の実態を明らかにした専門書『男が痴漢になる理由』の中に書かれている一節だ。
1月17日新宿、「私たちが依存症になる理由」というテーマのもと、中村うさぎさんと斉藤章佳さんによるトークセッションが行われた。
当日の天候はあいにくの雨だったものの、会場には多くの来場者が集まった。参加者たちは真剣な眼差しでふたりの話に耳を傾け、ときに議論に参加したり、質問をぶつけていく。依存症という病に対して、ここまで感情が入ってしまうのは、誰もがこの問題の原因を胸に抱えているからなのかもしれない。
ここでは、そんな依存症に関するふたりのトークセッションを前編と後編に分けて紹介していく。前編では、私たちが持っている依存症への常識が間違っていること、そしてこの問題が私たちとは無関係でない理由を主なテーマとして取り上げている。
8000文字を超える記事になっているので、ブックマークなどして、ゆっくり読んでいただければ幸いです。
出演者プロフィール
・斉藤章佳さん(精神保健福祉士・社会福祉士/大森榎本クリニック精神保健福祉部長)
・中村うさぎさん(人の本質的な欲望を追求する作家・エッセイスト)

左:斉藤章佳さん 右:中村うさぎさん
中村うさぎさん(以下、中村):斉藤先生は、『男が痴漢になる理由』という本を書かれていて、その中に「痴漢は依存症である」という言葉があるんです。
私は30代のころ買い物依存症だったので、”依存症”のことはすごくわかるんだけれど、まさか痴漢がそのひとつだとは思ってなかった。20代のころは通勤時に痴漢に遭っていて、本当に心の底から痴漢加害者を憎んでいたんですが、「この人たちはなんで、女性の体を触るんだろう」という疑問があったんです。
性欲を抑えられない人が、満員電車の中で女性の体にムラムラしてしまって、そういった痴漢行為に走ると思っていましたが、この本を読んで「この人たちはやめたくてもやめられないんだ」って。そう思ったら、なんか「私の依存症と通じるもの」を感じました。痴漢に限った話ではないですが、“依存症”という病はいろいろなシーンに潜んでいると思うんです。
皆さんの中にも、ちょっと高いバッグを買っちゃった……なんて経験をお持ちの方がいるかと思うんですけど、私の場合、それでは止まらなくなってしまった。そういう日常的なことが依存症になってしまうきっかけとか、その奥にある根本的な原因を斉藤先生からお伺いしたいと思っています。挨拶が長くなってしまってすみません(笑)。
斉藤章佳さん(以下、斉藤):斉藤と申します。どうぞよろしくお願いします。
依存症の臨床に携わってから約20年くらいになります。今日この会場に来る前には、「万引きがやめられない人」つまりクレプトマニア(※)のグループセッションをしてきました。実は、この「万引き」も分類的には、”行為・プロセス依存”と呼ばれるものに該当します。
行為・プロセス依存とは、アルコール依存症や薬物依存症のように物質を体に取り入れるものではなくて、いわゆるその行為やプロセスの中に耽溺していくタイプの依存症のことを言います。私は、これからは物質依存から行為・プロセス依存の時代へと移っていくんじゃないかな、と思っています。
依存症は、誰もが抱えている心の痛みを和らげるために必要なもの
斉藤:依存症の一般的なイメージには、どうしても意思が弱いやだらしない人が、自己破壊的に人生の舞台から転落していき、そして最後は死にいたるという……そんな印象が強いですよね。
ですが、依存症というものは、いわゆるドーパミン優先主義だけでハマっていくものではありません。依存症の本質は、鎮痛剤のように痛みを和らげる。つまり、快楽ではなくて、その人の中に存在するある種の痛みとか苦しみを一時的に和らげて、緩和するという効果があるのです。これをエドワード・J・カンツィアンが提唱した「自己治療仮説」といいます。
その人が抱えている痛みを一瞬でも和らげる――薬物とかアルコールはわかりやすいですよね。これからは、こうしたモノへの依存だけでなく、行為プロセス依存に「自己治療仮説」をどうあてはめていくかというのがポイントになってくると思います。
中村:「自己治療仮説」についてもう少し具体的にお伺いできますか?
斉藤:依存症者は、おそらく無意識のうちに自分たちの抱える困難や苦痛を一時的に緩和するのに役立つ物質を選択し、その結果、依存症に陥る。ここでいう苦痛とは、トラウマなどの過去の記憶だったりします。例えば、生活の中でいうと夫婦関係や友人関係、職場での人間関係の中で、我々はしらふで痛みを感じずに生きるということができません。そういうときに一時的にでも苦痛を和らげてくれるものが薬物やアルコールだったりします。
中村:そこにハマっていくわけですよね。
斉藤:そうです。では、なぜやめられなくなるのかというと、一時的とは言え、痛みを棚上げすることで、生き延びることができるからという、そこには巧妙なサバイバル戦略が含まれています。でも、世間はどうしても「依存症は自分の欲望にだらしない人がなる。だからそこに刑罰を与えれば良いんだ」と認識しています。依存症は、誰でもなる可能性がある病気であり支援やケアを必要とする人なんだということを知ってほしいです。
中村:心の痛みというのは、よくわかります。
人間なら、生活の中で誰でも痛みを感じることがあるじゃないですか。例えば、私の場合ですと、前の夫との離婚。それからスタートさせた不倫相手との交際は不安だらけでした。向こうにはパートナーがいて、土日は当然会えないですし、他にもいろいろ制約があります。それですごい寂しさを感じた。あと、私ライトノベルでデビューしたんですけど、「今は売れているけど、いつまでこの状態が続くのか」とか「次はどうなるかわからない」とか、そういう不安もあったりして、こういった心の苦しみや痛みが買い物依存症に繋がったのかなと。
ただ、「快楽優先じゃない」とのことでしたけど、私はやっぱり買い物依存症のことで一番覚えているのは“気持ち良さ”なんですよ。買ったときの気持ちの高まり……「あれも、これも頂戴!」みたいな。
斉藤:シャネル?
中村:そうです(笑)。
「ここからここまでください」とかって冗談で言われたりするけど、本当にそういう買い方をしていた。でも、家に帰るころにはドーパミンが落ち着いてきて、自分の買ってきた袋を開けるのが怖くなる。そうしてクローゼットの奥にしまい込んで、部屋の隅で三角座りをして、「どうやって支払おう……」と途方に暮れていた。
このとき、やっぱり快感が自分の動機だったように記憶しているんです。それでも快感が原因ではなかったんですかね?
斉藤:絶対に快感が原因ではない、ということはありません。
ドーパミンに耐性ができて、今までやっていた量や回数に慣れてしまって、さらにモノや行為を求めていくということは実際にあります。
ただ、ある瞬間から量を増やしても、それ以上のドーパミンが出なくなります。例えば、ハードドラック(ヘロインやコカイン)にハマっている人が最後にどうなっていくかというと、大麻とか処方薬(抗不安薬)なんかのように比較的軽いドラックに落ち着くケースがあるんです。快楽に溺れていくのなら、より強い薬に手を出し続けそうですが、そうではないようなんです。
やはり、その人の中にある心理的な苦痛というものはずっと続くものなので、(「快楽的な側面」と「心理的苦痛の側面」の)両方からのアプローチが必要なのかなと思いますね。
依存症からの回復のキーワードは《仲間》だけど……

中村:私が買い物依存症だったころは、治療法のひとつに「底尽き理論」というものがありました。これは、依存するだけ依存して、自分が破滅するところまで来たら、人間っていうのは自然に治っていくんだって理論ですね。
私の場合は、それは破産で済むけど、痴漢が依存症であるならば、「気が済むまで女性のカラダを触れ」ってわけにはいかないですよね。
斉藤:これは非常に複雑な問題です。
アルコールにしても、薬物にしても、依存症は自分の人生を破壊してきたものであると同時に、生き抜くための術でもあったわけです。
よく「命よりも大切な酒や薬を、このクリニックに来て奪われた」と受け取る患者さんがいるのですが、その生きがいに代わる別の“何か“を見つけるというのは非常に困難な作業と言えます。この際はっきり言いますと、我々はそれを提供することはできませんし、提供できますよ、みたいなおこがましいことはいえません。
治療や回復の中では、その代替が「仲間との繋がり」なんですよ。
中村:繋がり……? それは同じ依存症を抱えた人同士の?
斉藤:そうです。ただ、これって1カ月やそこらでできるものではなくて、ミーティングやフェローシップ(※)を重ねて何年も何年も経ってから「今まで酒や薬しか信じられなかったけど、今はこんなにたくさんの仲間がいる」という状態になります。
すぐに代替となるものが見つかるわけではない。けれども、依存症の回復モデルとして、仲間との繋がりが、仲間のために力になることが、いわゆる生きがいと言われているものよりも強固なものになるケースをこの目で多く見てきました。だから依存症治療において《仲間》というのは、ひとつの重要なキーワードになりますね。
中村:うーん、私はコミュニケーションが苦手な人とか、人に心を開けない人が、行為依存にハマりやすいのかなって思うんです。私も実際にそうだったからなんですけど、学校のクラスではけっこう派手なグループにいて、友だちが何人もいて……でも、どの友だちにも心を開いていないというか(笑)。そういう表には見えにくいコミュニケーション障害を抱えた人たちが仲間と繋がると言っても、どこまで打ち解けられるのかなって私は疑問に思います。
前に、依存症のグループセミナーみたいな場所に行ったとき、「この人たちと話していて、私にとってプラスになるのかな」と冷淡な目で見てしまった経験があるんですけど、そう感じる人たちもいるじゃないですか。これって依存症に限った話ではなくて、絆を人と作るっていうのが、今の時代はとくに難しいのかなと思っているんです。
多くの死者を生み出した「底尽き理論」による治療モデル
中村:例えば、Twitter(ツイッター)みたいなSNSが日常化していて、みんなものすごく繋がっているように見えているけど、実は全然繋がっていない。繋がったフリが巧妙になっているだけ。
だって、実際はその人の顔も名前も知らないわけじゃない。私は、プロフィールとかをさらけ出してツイッターとかやっているけど、多くの人は普段なにをやっていて、男なのか女なのかもわからない。
そうすると、みんなはあんなに楽しそうに繋がっているのに、なんで私はこんなに孤独なんだって感じたりするでしょ。これだけSNSでやり取りしているけど、この人たち誰ひとりとして私のことわかってない……という気持ちになってくると、顔が見えないだけに閉塞感とか孤独が深まっていくんじゃないかなって思っていて。
孤独から逃れようとしてSNSに手を出したのに、また違った孤独にハマっていくみたいな……。まぁ、SNS依存もこれから問題になってきますよね。

斉藤:《孤独》っていうのも重要なキーワードだと思います。
以前、少しお話させていただいたのですが、TEDトークの有名なジョハン・ハリの動画「「依存症」-間違いだらけの常識」の中でも《孤独》というのがひとつキーワードとして取り上げられています。
彼(スピーカー)は、身内の薬物依存症者をなんとか立ち直らせようと、世界中の専門家に話を聞く旅にでます。どうすれば依存症から回復できるのだろうっていうのを調べにいくんです。
それで、最終的にたどり着いた結論が「アディクション(依存)の反対はコネクション(繋がり)」ということ。今まで、依存症患者は罰せられ、蔑まれ、社会から疎外されてきました。
中村:疎外されてきたというのは?
斉藤:例えば、さきほど「底尽き理論」のお話をされていましたが、アルコール依存症であれば、まずその酒をやめることが最優先だったんです。やめられないのであれば、底を尽くまでもっと本人が困ってから(さまざまなものを失ってから)治療にきてくださいという発想ですね。
中村:はい。
斉藤:たしか1964年の東京オリンピックの前年ぐらいに、国立久里浜病院がアルコール依存症治療の基幹施設として日本で初めて医療でアルコール治療がスタートしたのですが、ここで行われていた治療がまさにこの「底尽き理論」をベースにした久里浜方式です。
極端に言うと「お酒をやめたい人は受け入れます、やめる気のない人は底を尽いてから来てください」みたいな感じです。これはある意味では成功していて、治療への動機付けが高く医療者に対して従順でやる気のある人(自分の依存症に危機感がある人など)が集まった。
しかし一方でこの方法は、たくさんの死者を生み出しました。
つまり、最後までやめる気のない人/やめるきっかけを得られなかった人たち/同じ問題を抱えて、一緒にやめていこうとするコミュニティと繋がれずに、孤独に死んでいった人たちが助からなかったのです。
このように治療動機付けの低い人が、社会や人との繋がりを徐々に断たれていくことこそが「底尽き理論」の弊害でした。
我々も当時、底を尽かせることに熱心になっていた。困ってないなら困らせようと思って突き放したり、放置をしていたんです。それで本人が助けてくださいと言ってきた時だけ手を貸す、というような関係性でした。SOSを出すこと自体が、人に頼るのが下手な病気が依存症なのにそんな対応をしていました。
スタッフ側も「底尽き理論」という考え方を信仰していて、柔軟な個別性を尊重したかかわりを考えず、二者択一的にやめないのは「本人の問題」に集約させて突き放していました。これを直面化技法と当時は言っていましたが、今考えるとこれは、援助者が依存症者をコントロールしようとしてうまくいかなかった挫折感からくる「怒り」をぶつけていたに過ぎない行為だったなと反省しています。
でもここ10年くらいの間で、「今までの依存症治療のあり方は見直さないといけないんじゃないか」といわれるようになってきました。「治療に抵抗を示す患者はいない。そこにいるのは、柔軟性に欠けた治療者がいるだけだ」というM.エリクソンの有名なセリフがありますが、まさにこのような姿勢が依存症に関わるスタッフに足りなかったわけです。
関わりの原点を見直すという視点から、今では「底尽き理論」の必要性はあまり言われなくなりました。
でも、底尽くことで回復する人もたしかにいるので、そこが依存症治療のおもしろさでもあります。今では「底付きは仲間の中で」がキーワードです。
依存症の根底にある性の問題~人はできれば優越感を感じていたい~
中村:恋愛とか人間関係とか、DVもそうだと思うんですけど、そういう関係依存から抜け出せない人もいますよね。
斉藤:そうですね。代表的なのはセックス依存症、それから恋愛依存症、DVもある意味では関係依存の問題ですね。ここにはあらゆる暴力の問題(乳幼児や高齢者への虐待)も含まれます。
私はこうした依存症の根っこには、関係性の問題がある……そして関係依存のさらに奥には「性の問題」があると思っています。
中村:それはなぜですか?
斉藤:私が当時担当していたアルコール依存症の患者さんが断酒3年目のできごとでした。3年やめられるってけっこうすごいことなんです。でもその数日後に、彼は逮捕されたんです。罪名は強制わいせつ。私はそれを聞いたときに、なにかの間違いかなと思いました。すごく真面目で勤勉で、クリニックのプログラムも自助グループ(AA)にも休まず参加していた彼がなぜ、と。
私にとっては衝撃でした。なにがあったんだろうって、(警察や弁護士から)詳しく話を聞いてみると、実は過去に子どもに対する性犯罪を何件か起こしていたんです。その時期を見てみると、断酒をしていたタイミングから行動化していました。
それを知ったとき、お酒をやめただけでは根本的な解決にならないんだってことをある意味、身をもって体験した気がしました。それで「じゃあ、オレはどうすればよかったんだろう」と悩んでいたときに何回も読んだのがアル中のバイブルである『ビッグブック』という本だったんです。
斉藤:この本の中に「私は酒をやめて、本当の自分の問題に気づいた。それは性の問題だった」というくだりがあるんです。ちょうどそのときに、小林薫元死刑囚による奈良市での女児誘拐・殺人事件(※)がありました。
そういうのが重なって、性犯罪の再発防止や、同じ問題で苦しんでいる人たちが繋がれるグループや受け皿が社会内に必要だと思って、今やっている性犯罪加害者の「再発防止プログラム(通称SAG)」をスタートさせたんです。だから、私はこのような体験から依存症の根っこには性の問題が潜んでいると思っています。
中村:その性の問題とは、具体的にどういったものなんですか? 性的に満たされていないということ?
斉藤:そうではないですね。さきほど話に挙げた彼は、幼少期から義理のお兄さんから性的虐待を受けていたんです。彼の中ではそれが外傷体験になっていて、思い出すたびに苦しくなるので、その記憶を酒を飲んで紛らわせていた。彼の中ではまさに「自己治療」だったのです。
お酒を飲んでベロベロになるまで酔っぱらっているときは、あの忌まわしい恐怖の記憶を思い出さずに済む。だから酒の量がどんどん増えていく。それで気づいたらアルコール依存症になっていた。それでやめてみたものの、彼の根っこには生きづらさが残っていて、今度は自分が加害者になった。
彼は勾留されていた警察署でアクリル板越しに「加害行為をすることで過去の自分を許せるようなホッとした安堵感がある」と言っていました。
中村:ホッとした? なぜですか?
斉藤:なぜでしょうね。自分が加害行為を繰り返すことで、彼の中にある恐怖や忌まわしい性的虐待の記憶が上書きされるような、別の意味で癒されるような内的体験があったんじゃないか思います。
中村:もう自分は被害者じゃないと思いたかったんですかね。
斉藤:ここの辺りは解釈が非常に難しいところです。ただ、他者を傷つけることで、自分を癒すということは、彼に限らず人間の中にある普遍的な欲求だと思っています。つまり加害者性ですね。
中村:そうですね。
斉藤:私もそうですけど、弱い者をいじめたりや、誰かよりも優越感に浸りたいとか、マイノリティではなくて大多数の方に所属していたいとか、そういう欲求ってやっぱりこころのどこかにあります。それは否定できない。男性はそれが性の場面で表面化しやすいと思います。私も男性なので、その辺りのことは感覚的にわかるんです。
だから、彼は小さいころから受けていた性的虐待を、自分の性暴力によってバランスをとっていたのかなと思います。もう彼にはそれ以来会っていないですけどね。
中村:今の話を聞いて、いじめとかもそうなのかなと思いました。
いじめって、自分より弱い者を貶める行為や言動によって、優越感や自尊心を保つ行為じゃないですか。逆を言えば、これってものすごくコンプレックスが強いということ。
家族のヒエラルキーの中では、自分が弱いポジションにいるけど、学校には自分よりも弱い立場の人間がいたりする。そういう人を痛めつけたりすることで、自尊心を回復させているのかなって。人間ってやられっぱなしだと本当に生きていけない。やられっぱなしなのは嫌だし、自分より強い人にやり返すのは嫌だから、もっと弱いやつを見つけて、代償行為としてする――これがいじめの構造なのかなって思ったりします。
後半へ続きます→「依存症」とは人にうまく依存できない病
2018年3月2日(金)に本イベントの拡大版が開催されます。興味のある方は以下のリンクをご参照ください。
取材協力:A Day In The Life
新宿二丁目にあるゲイ・ミックス・バー。
http://aday.online/
取材・Text/小林航平