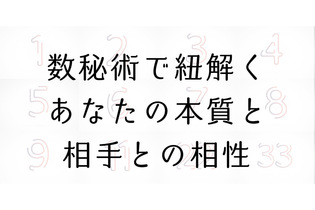『逃げ恥』に見る“男らしさ”の変化とは? ヒットコンテンツで読み解く恋愛観の歴史〈社会学者・高橋幸先生インタビュー〉
『モテキ』『逃げ恥』『君の膵臓をたべたい』――。2010年代以降の恋愛ドラマには、それまでの性別役割から少しずつ脱却していくような価値観の変化が表れています。「ジェンダー平等な恋愛」を研究する高橋幸先生にお話を聞きながら、過去のヒットコンテンツと共に恋愛観の変遷を読み解いていくインタビュー後編。
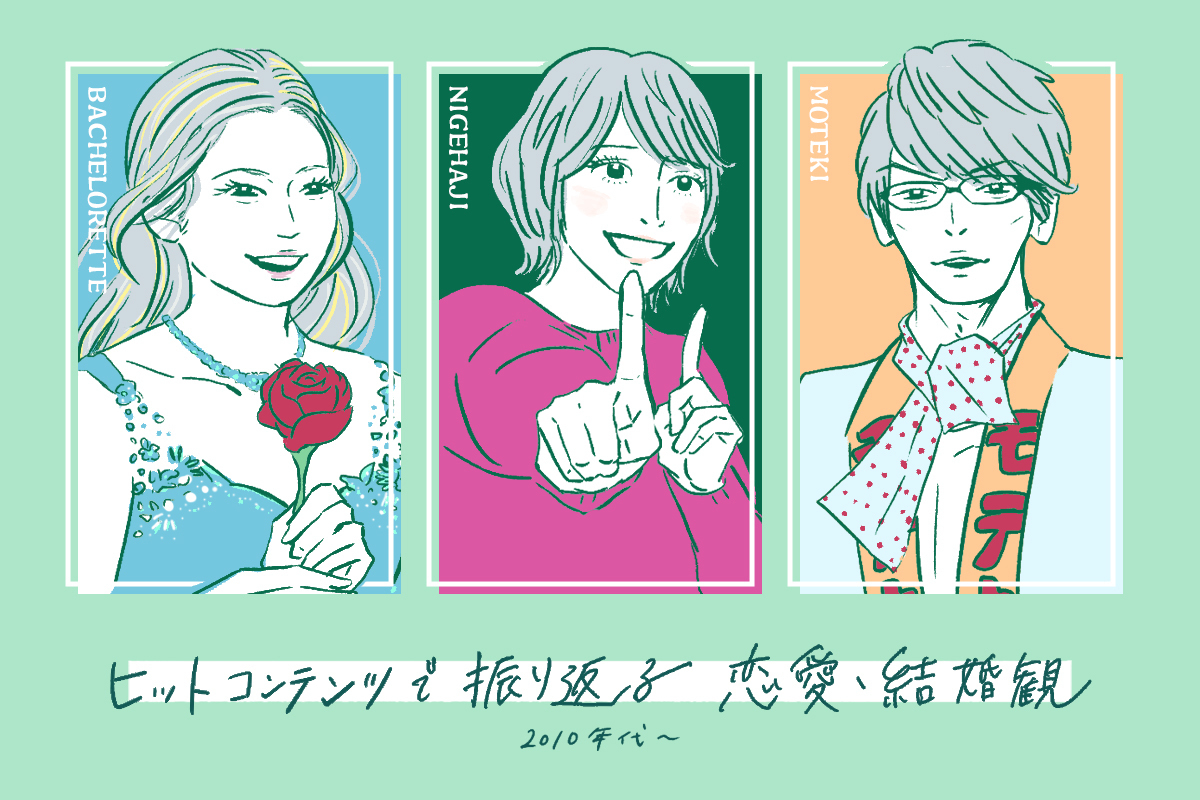
目次
大ヒットドラマ『東京ラブストーリー』の赤名リカに代表されるように、自立した女性像がひとつの理想として描かれてきた1990年代。不景気を背景に「結婚しないと女は幸せになれないの?」という“女性たちの迷い”がコンテンツにも見られるようになった2000年代。
そんな時代を経て、2010年代。恋愛ドラマ・コンテンツの世界では、従来の恋愛観や性別役割を見直す動きが見られるようになっていきます。
「男らしさ」「女らしさ」の扱われ方はどう変化してきたのか。セクシュアリティの描かれ方はどのように変わったのか。
前編に続き、ポストフェミニズム研究が専門で、当時の大衆文化やポップカルチャーを題材に「ジェンダー平等な恋愛とは何か」を分析・研究されている高橋幸先生と共に、2010年代以降のヒットコンテンツと恋愛観の変遷を振り返りながら、令和の恋愛・結婚がどうなっていくのかを考えます。(聞き手:福田フクスケ)
※本記事には『バチェロレッテ・ジャパン シーズン1』の結末に触れる記述があります。
▼前編はこちら
『東ラブ』赤名リカはなぜ支持された? 大ヒットドラマで読み解く恋愛観の歴史〈社会学者・高橋幸先生インタビュー〉
高橋幸先生プロフィール

1983年宮城県生まれ。2014年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。現在、武蔵大学他講師。専門は社会学理論、ジェンダー理論。主著に『フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど』(2020、晃洋書房)がある。
Twitter:@Schnee05
恋愛が共通言語ではなくなっていく2010年代
――さて、いよいよ2010年代ですが、この時期になると視聴者の興味・関心が細分化してテレビ全体の影響力が下がったこともあり、時代を代表するような恋愛ドラマを挙げるのが難しくなっていきます。そんな中、印象的だったのは『モテキ』(2010年)でしょうか。
30歳を目前に控え、ほとんど恋愛経験のないセカンド童貞の藤本幸世(森山未來)に、ある日突然“モテ期”が訪れますが、自分に自信がなく「どうせ俺なんか……」と自己完結するクセのせいで、かえって女性を遠ざけたり傷付けたりしてしまう、という話です。誰とも正式な交際に至らず、恋愛以前の自意識の問題を解決するのに全話を費やすというのが、これまでになかったドラマという印象を受けました。
高橋 草食系男子が「市民権」を得るようになったほか、LGBTQに対する認知度も徐々に高まっていくのが2010年代。これまで当たり前とされていた恋愛のルールや作法が、「本当に当たり前なのか」が問い直されていく始まりを象徴するようなドラマです。
また、趣味が合うことが恋愛のきっかけになるところが、現代っぽいなと思いますね。私は映画版の完成度の高さに感動しているのでそちらに基づいて話しますが、サブカル男子としてのプライドを持つ幸世が、ヒロインのみゆき(長澤まさみ)に恋する理由は「好きな音楽が一緒だから」であり、想いを寄せてくれるるみ子(麻生久美子)に恋することができないのは「音楽の趣味が合わないから」。
決して、男仲間の目から見た一元的な「女のランク」の中でみゆきの方が上だからみゆきが好き、という構図になっていないところが特徴的です。恋愛において重要になってくる魅力が、細分化し、多様化していることが見て取れます。
――これについては、男性から見た女性の魅力が細分化・多様化していると受け取るか、「僕が好きなカルチャーを“わかってる女”だから好き」というサブカル男子特有の厄介なホモソーシャリティと受け取るかで、評価は変わってきそうですね(笑)。
高橋 なるほど、そうかもしれません。それに、今見ると童貞や草食系男子であることを一歩踏み出せない「弱さ」として自虐的に描いていたり、「相手を傷付け自分も傷付きながら成長するのが恋愛だ」というようなハードボイルドな恋愛観を是としていたりするなど、古い価値観もまだ引きずっています。2000年代と2010年代の過渡期にあることを感じますね。
恋愛と結婚の齟齬を浮き彫りにした『逃げ恥』
――恋愛・結婚を扱ったドラマで2010年代を代表する作品といえば、やはり『逃げるは恥だが役に立つ』(2016年)ではないでしょうか。派遣切りとなった主人公・みくり(新垣結衣)と、彼女を家事代行サービスで雇う恋愛経験のない平匡(星野源)が、“雇用主と従業員”という関係のまま契約結婚を結ぶ物語です。
高橋 『逃げ恥』のヒットによって、平匡さんのような男性が世間から好意的・肯定的に受け止められるようになったと感じます。彼は、情熱的なアプローチをして相手の心に踏み込んだり、相手のことを決めつけたりせず、自分の内面と対話して気持ちを冷静に整理し、相手と慎重に丁寧に関係を構築しようとします。
そんな彼の言動は、一昔前ならウジウジしていて「男らしくない」とされてきたものです。『モテキ』の時点でも、まだ「弱さ」として自嘲的に語られていた。ところが『逃げ恥』以降、平匡さん的な言動が、むしろ誠実で信頼に値する“男性的魅力”として受け止められるようになったのは大きな変化です。
――時代に合わせて、またはメディアの影響を受けて、何を性的魅力と感じるかも変わっていくんですね。
高橋 また、「契約結婚」というギミックを多くの視聴者が受け入れ、納得したのも画期的だったと思います。なかなか発展しないふたりの関係を“ムズキュン”というコピーで表すことで恋愛ドラマのときめきを担保しながら、社会的に不安定な女性の立場や、結婚における無償の家事労働などの問題に切り込んでいくバランス感覚が見事でした。
私の個人的な主張としては、今後、恋愛と結婚は切り離されていくべきじゃないかと考えています。かつてのように「恋愛ってこういうものでしょ」というルールを全員で共有できる時代ではなくなりました。人によって恋愛に何を求めるのかはかなりの程度異なっており、恋愛する自由があるのと同様に恋愛しない自由もあって当然。にもかかわらず、恋愛感情というものを根拠にしないと結婚したり家族を作ったりすることができないという現状は、さまざまなセクシュアリティや恋愛観を持つ人に無理を強いていて、暴力的・侵害的です。
――これまで、恋愛というものに価値が置かれすぎていたのかもしれませんね。
高橋 もちろん、恋愛はそれはそれで文化としての価値があります。その文化にコミットしたい人はすればいいですが(そして、私は恋愛社会学という形で一生懸命コミットしているわけですが)、「全員がやらなければいけない」ものではなくなっていくのではないでしょうか。恋愛感情に基づかないパートナー関係を、具体的にどういう形で確立していくかが模索されるべきだと思います。
『セカチュー』と『キミスイ』の10年で変わった恋愛観
――既存のルールやマニュアルに従うのではなく、恋愛感情とは何か、自分の内面を見つめて問い直していくような風潮が2010年代の特徴なのでしょうか。
高橋 そうですね。その傾向は、10代や20代の若い世代にも傾向としてはっきりと表れています。例えば、『君の膵臓をたべたい』(原作2015年・実写映画2017年)は、『セカチュー』と極めてよく似た設定・展開・構造を持つ物語で、人々(特に若い世代)から支持される恋愛観がこの10年の間でどう変わったかを比較するのにとてもいい題材なんです。
『セカチュー』の興行収入は85億円、『キミスイ』は35.2億円で、アニメ映画版や中国での興行収入を合わせても約41億円です。実感としても世間の注目度は『セカチュー』の時の半分くらいかなという感じで、2000年代の純愛ブームの頃のような勢いはありませんでした。しかし、この時期の青春恋愛映画界隈では爆発的にヒットしたと言ってよい作品です。
――『キミスイ』は、人と関わりを持つことが苦手だった主人公の志賀春樹(北村匠海)が、余命わずかのクラスメイト・山内桜良(浜辺美波)と出会い、彼女の「死ぬまでにやりたいこと」を叶えようと一緒に過ごすうちに、心を開きはじめる……というストーリーでした。
高校生カップルの難病もの、ふたりで旅行に行く展開、大人になった主人公が高校時代を回顧する映画版の構成、カセットテープや手紙を使った過去からのメッセージなど、『セカチュー』との共通点が多くあります。
高橋 『セカチュー』と『キミスイ』は、男子のホモソーシャリティのあり方がまったく違うんですよ。『セカチュー』では、主人公の朔太郎は周りの男子にはやされて、クラスのマドンナ的存在である亜紀に告白します。「みんなが言うからあの女はいい女に決まっている」「好きなら告っちゃえよ」「恋愛ってそういうものでしょ」……といった強いヘテロセクシュアル規範に後押しされて行動するんですよね。
一方、『キミスイ』の春樹は友達がほとんどおらず、休み時間もひとりで本を読んでいるようなホモソーシャリティの薄い存在です。「こう振る舞うのが恋愛でしょ」という画一的な恋愛観ではなくて、一歩ずつ丁寧に自分の気持ちと向き合って、少しずつ相手のことを「好き」という気持ちを醸成していきます。
――言われてみればそうですね。
高橋 自分が本当は何を感じているのか、自分の気持ちは今動いているのかをすごく気にして、重要視するんです。実際の恋愛行動を取る前に自分の感情にスポットライトを当てるところが、若い世代の「恋愛」を象徴しているように思いました。ちなみに、主人公がヒロインの桜良に「私ってかわいい?」と聞かれたときに、「クラスで4番目にかわいい」と答えるセリフがあって、いろいろな意味で笑えました。
恋愛市場の女性は“保守化”しているのか?
――私は1983年生まれなのですが、男性がリードして女性をときめかせて口説き落とすのが「男らしい」恋愛のロールプレイだという考えがまだ強固な世代だと思います。今の若い世代は『逃げ恥』の平匡さんのような振る舞いにも共感が集まり、受け入れられているんですね。
高橋 その傾向は女性キャラクターにも変化を与えています。1990年代は『東京ラブストーリー』のリカや『ロングバケーション』の南のように、強くて自立していて自己主張する女性がひとつのロールモデルでした。ところが、2010年代中盤頃からドラマや映画に出てくる10代のヒロイン像が、優しくおしとやかで慎ましくて、言ってしまえば非常に“保守的”な女性像に回帰しているように見えるんです。
例えば、この時期、もっともブレイクした映画として『orange-オレンジ-』(2015年)があります。個人的にも複数の学生さんから「この映画はいい!」という情報を得ました。主人公の女子高生・高宮菜穂(土屋太鳳)のモノローグで進む少女漫画原作の映画で、構図としてはひとりの少年を助けるために頑張る少女の「冒険譚」なのですが、その主人公が、草食系男子に劣らずかなり繊細で、はかなげ。
「今はこんなに弱々しい女性像がウケるの? 大丈夫?」とびっくりしたのを覚えています。びっくりしたのでその後、立て続けに「胸キュン映画」を30本くらい観て分析図式をあれこれ作るという作業をしました。
――それって、若い男の子が求める理想の女の子像が、古い時代に退行しているということですか?
高橋 単純に保守化しているということではなくて、「男女平等」が進んだからこそ、古臭く見える「女らしさ」の価値化が新しい形で回帰しているという状況だと私は見ています。
つまり、女性を対等な「人間」として捉え、女性の側の意向を汲み取りながら誠実な恋愛関係を築こうとする「優しい」男性が、「優しい」女性を求めるようになった。前から女性には「優しさ」や「愛情深さ」といった態度が(男性よりも多く)求められがちだったのですが、男性が「優しく」なるにしたがって、女性にさらなる「優しさ」や「弱さ」が要求されているように見えるんです。
――それってよいことなんでしょうか?
高橋 それがよいことなのか、悪いことなのか、今のところ私には判断ができません。というのも、相手の意を汲んだり、気遣いをしたりする「優しさ」そのものは、別に悪いことではないからです。それは「コミュニケーション力」のような形で、性別を問わず求められるようになっていますし、サービス業中心の社会になればなるほど、気遣いや優しさが評価される傾向は強まります。
ただ、男性よりも“より一層”女性の方が優しくないと恋愛関係になれないというような形で、男女に求められるものの間に「差」が残り続けるとしたら、それはまずいと思います。
――男女どちらも「弱く」「優しく」なっているんですね。
高橋 はい。それから『orange-オレンジ-』や『キミスイ』の主人公たちとちょうど同じ年齢くらいの世代は、男子も女子も恋愛に受け身で消極的。どちらも一歩を踏み出さないから恋愛関係が成立しないというのが、統計からも読み取れる傾向です。
中学生・高校生・大学生のデート経験率、キス経験率、性交経験率はいずれも、2000年代後半以降低下し続けています(※1)。保守化しているというよりも、性や恋愛に慎重になっていると感じます。
なんだかんだ恋愛コンテンツは今後も廃れない
――ただ、一方では『恋はつづくよどこまでも』(2020年)のように、ひたむきで努力家で性格のいい女性が、ドSで俺様な王子キャラの男性に気に入られる……といった古典的なシンデレラストーリーのパターンは、今も若い世代にウケてヒットしていますよね。かつての恋愛規範の刷り込みが残っているのでしょうか? それとも、こういうのって人間の普遍的な欲望なのでしょうか?
高橋 確かに、俺様系王子キャラが人気を集める流れは、脈々とありますよね。『東京ラブストーリー』の「三上」の系譜です。『オオカミ少女と黒王子』 (2016年)や『黒崎くんの言いなりになんてならない』(2017年)も興行収入12億円台なので、青春恋愛映画としてはヒットした部類に入ります。
ジェンダー平等が進む反面、「男性に支配されたい」という女性の欲望が表現されるようになったり、「王子様に見染められて幸せな結婚をしました」というシンデレラストーリーが相変わらず人気を集めたりする現象をどう考えればいいのか? という論点は、ポストフェミニズム論の大御所アンジェラ・マクロビーも指摘している重要なものです(※2)。
――そうなんですね。どういう意見や論調があるんですか?
高橋 ジェンダー平等が進んだからこそ、「支配/服従」や「シンデレラストーリー」といったシチュエーションを女性たちが「プレイ」や「ファンタジー」として楽しめるようになったんだ、という意見があります。他方で、既存の物語がそういうパターンを繰り返し描いてきたから、そのような古い恋愛観やセクシュアリティ観がまだ残ってしまっているのであって、今後さらにジェンダー平等が進めば消えていくのではないかという意見もあります。
私は、そのどちらとも違う立場です。自分ではコントロールできない感情に自分が突き動かされているという感覚を伴うのが、性欲や恋愛感情の特徴です。それは誰かに(もしくはなにものかに)「支配される」感覚と似ている。つまり、「支配される感覚」と「恋愛感情を持つ感覚」は混同されやすい。だから、俺様系王子キャラは人気を保ち続けているのではないかというのが私の仮説なのですが、さてこの仮説をどうやって実証すればいいのかは、まだよくわかりません、すみません(笑)。
――それはすごく興味深い仮説ですし、私も似たようなことを考えたことがあります。恋愛感情には「自分も知らない自分を探し当てられたい」「自分の意志や主体性の外に連れ出されたい」という欲望が含まれていて、それは残念ながら支配や侵害と相性がいいんですよね。ただ、この話は長くなりそうなので、またの機会にゆっくりさせてください(笑)。
高橋 「自分がコントロールできない感情」としての恋愛や性という考え方は、かつて「男の性欲は、自分ではコントロールできない『本能』だから仕方がないんだ」というような言い回しのなかで使われてきたという黒歴史もあるので、かなり慎重に議論していく必要があります。この論点は、またの機会に。
――もうひとつ、若者が恋愛しなくなったとか、草食化していると言われている割に、今もティーンに大人気なのが恋愛リアリティ番組です。ABEMAの『オオカミくんには騙されない』シリーズ(2017年〜)は、「日本の女子中高生の3人にひとりが見ている」(※3)と言われるほどヒットしました。この現象はどう捉えればいいのでしょうか?
高橋 ABEMAの恋愛リアリティショーは、高校生を中心にものすごい勢いで浸透していますね。「本気でやる遊び」として恋愛はやっぱり面白い、という見直しが始まっているのではないかという気がしています。
バブル期に恋愛は「誰もがやる(べき)遊び」になりましたが、2000年代以降の「総オタク化」のなかで、「リアルな人間との恋愛はめんどくさい」という感覚が広がりました。この時期の特徴として、アイドルや2次元キャラクターへの“恋愛にも似た強い親密な感情”が、商品化されつつ多様な形で発展したことは特筆すべき点だと思います。
――かつては「萌え」と呼ばれていたものですね。今では、さらに発展して男女問わない「推し」という概念が生まれたことで、恋愛や性愛とは切り離された独自の感情としてすっかり市民権を得た印象があります。
高橋 そして、2020年代に入った現在、感覚と感情を繊細に研ぎ澄まして「真剣にやる遊び」としての恋愛の面白さが、再発見されているように見えるんです。
もともと恋愛リアリティショーは、恋愛文化を楽しむための良質なマニュアルを提供してきた、という側面があります。それに加えて、『オオカミくんには騙されない』シリーズという同一コンテンツが同年代の人々にこれだけ広がったことによって、新しい世代にとっての新たな「恋愛とはこういうもの」という共通理解が成立しつつあるように見えます。このリアリティショーの大流行の後に、若い世代の実際の恋愛行動がどう変わるのかが、これからの注目点ですね。
ネオリベ的な競争社会を象徴する『バチェラー・ジャパン』
――恋愛リアリティ番組自体は、『ウンナンのホントコ!』内の企画として始まった『未来日記』(2000〜2003年)や、『あいのり』(1999〜2009年)など2000年代から人気でしたが、『TERRACE HOUSE』(2012〜2020年)以降、SNSの力を得てヒットコンテンツになりました。
中でも『バチェラー・ジャパン』シリーズ(2017年〜)は若者だけでなく年長世代からもよく見られている印象があります。ただ、経済力のあるハイスペ男性に女性たちが集まり、選ばれようと競い合うという構図は、時代に逆行しているようにも見えるのですが……。
高橋 なるほど。確かに、一見『テラハ』のほうが参加人数も男女ほぼ同数で対等に見えるので、より男女平等性が高いように見えるというのはわかります。『バチェラー』は「選ぶ男性/選ばれる女性」と性別によって役割が切り分けられているので、一見するととても前時代的なことをやっているように見えるわけですね。
しかし、「女が選び/男が選ばれる」という男女逆転版の『バチェロレッテ・ジャパン』も実現していることを考えれば、『バチェラー』の構図だけを見て男女平等に反すると言うことはできないと思います。
まぁ、今のところ『バチェラー・ジャパン』がシーズン4まで実現したのに、『バチェロレッテ・ジャパン』はシーズン1しか制作されていないことを見ると、まだまだ経済力のある層においては男性が選ぶ権限を握っているんだなということが、改めて明瞭になったわけですが。
――『バチェロレッテ』は、今夏にようやくシーズン2が放送されるようです。その動向にも注目したいと思います。
高橋 お! 楽しみですね。前回の『バチェロレッテ』シーズン1に関しては、男性が「選ばれる側」に置かれた『バチェロレッテ』について、ベンチャー系ビジネスパーソン(男性多め)がSNS上でさまざまな考察をし始め、とうとうNewsPicksの落合陽一さんのチャンネルで『バチェロレッテ』特集が組まれた(※4)という社会現象が、興味深いなと思っていました。
彼らが面白がっていたポイントは、「バチェロレッテ(選ぶ側)である福田萌子さんが結婚相手の男性を選抜していくプロセスを見ていると、起業家に対する投資家のインタビューを見ているような気持ちになる」ということ。結婚相手を選ぶこととビジネスパートナーを選ぶことは案外近いのではないか、という話題で盛り上がっていました。
――なるほど、彼ららしい視点ですね。
高橋 私もそれ自体はけっこう面白い分析視点だと思うのですが、少し気になったのは、彼らがビジネスの用語で『バチェロレッテ』を語り、自分たちが熟知している思考枠組みの中でしか萌子さんの行動を理解しようとしないことで、「選ばれる」側に立つことの居心地の悪さを脇に押しやっているのではないかということです。「男として選ばれる/選ばれない」ということに対する根源的な恐怖感や不安があるのに、そこに関しては見て見ぬふりをしていた感じがするんです。選ばれる側の恐怖感をハンドリングするための方法を、女性文化は発展させてきました。ガールズトークや恋愛トークはそのひとつです。
というわけで、男性たち、特にリベラルな意識を持つ男性たちがいま真剣に語り合うべきなのは、「男として(性的に魅力的なパートナーとして)選ばれるにはどうしたらいいのか?」ということなのではないでしょうか。『バチェロレッテ』を見ながら「選ばれるための戦略」について議論すると、それぞれの恋愛観や人生観も見えてきて、実り豊かなものになりそうです。
――萌子さんを分析的に見るのではなくて、「選ばれる側の当事者」としての男性の声がもっと聞きたい、ということですね。ただ、初めての『バチェロレッテ』だったこともあって、シーズン1は萌子さんの芯のあるキャラクターに注目が集まり、SNSの盛り上がり方もこれまでになく高まった気がします。
高橋 『バチェラー』と『バチェロレッテ』を比較すると、結婚に求めているものの男女差が見えてきて、そこも面白かったです。『バチェロレッテ』の萌子さんのように経済力がある場合、結婚しなくても普通に生きていけるし、むしろ結婚することで大変な思いをすることも多い。そんななかで“あえて”結婚を選択するとすれば、「そのほうが自分の人生がより良くなる」と信じられるときに限られます。
だから萌子さんは、結婚で得られると言われている「愛」とは何なのか? 本当にそれは価値があるのか? どのように価値があるのか? あなたなりの「愛」についての考えを聞かせてと、正面から問い続けるわけです。
――自分や相手の内面を見つめ、恋愛を自分(たち)で再定義しようという意味では、実は『orange-オレンジ-』や『キミスイ』の世代の考えと通じるものがあるかもしれません。
高橋 「これこそが愛だ」と心から納得できない限り結婚に踏み切れない、という萌子さんのスタンスは、彼女のようなスペックを備えているわけではない私たちにとってもけっこう「わかる」ものだったのではないでしょうか。当初、こんなハイスぺ女性に共感できる女性は、日本にはそう多くはないのでは? と思われていましたが、フタを開けてみたら萌子さんへの共感的ツイートが多かったのは、このあたりが関係しているように思います。
バチェラーが理想とする“真実の愛”に納得できる?
――17人にいた候補者を段階的に選抜し、最後のふたりにまで絞りつつそのどちらも選ばなかったという『バチェロレッテ』の結末は、現代の女性があえて結婚を選びとることの難しさを象徴しているようで、印象的でした。
高橋 結局、『バチェロレッテ』に参加した男性たちは「あなたにとっての愛とは何?」という萌子さんの問いかけに答えられるだけの語彙も文法も自分なりの考えも持っていなかった。その結果が、あの結末なのだと思います。
男性陣はそれなりの年齢でいろいろな恋愛経験も積んできているのですから、もっと結婚に求めていることや結婚生活の具体的なビジョンを語り合って萌子さんとすり合わせていくような場面があってもよかったのではないかと思うのですが、そういうシーンは思ったよりも少なかったように思います。
――確かに、今、目の前にいる萌子さんがいかに魅力的か、いかに自分が相応しい男かをプレゼンする男性ばかりで、どういう将来設計で、どういう家庭を築きたいのかというビジョンを語ったり、萌子さんにヒアリングしたりする男性はほとんどいませんでしたね。
高橋 面白い展開だと思ったのは、『バチェロレッテ』に「選ばれる側」で参加していた黄皓(コウコウ)さんが、次に『バチェラー』シーズン4のバチェラー(選ぶ側)として再登場したとき、自分なりの「愛」の定義を明瞭にしてやって来たことです。
「絶対的な味方でいてくれること」というのが、彼の考える「愛」で、一言でいうと黄皓(コウコウ)さんのご両親のような関係のことです。彼のお母様は、お父様が何度事業に失敗してもずっと彼の下を離れず一緒にやってきた。それと同じように、どんなことがあっても自分を見捨てずいつまでも「味方」でいてくれるような人が理想の結婚相手だというのが黄皓さんの考えです。
私は夜中にひとりで「なるほどー! そうきたか!」と叫びつつ(見ていたのが夜中だったので)、でも、それは萌子さんをはじめとする自立した現代の女性にとって、ピンとくる答えではないんじゃないかと、僭越ながら思ってしまいました。ほんと、何様だって話ですが。
――それはどういうことですか?
高橋 お互いが自立した判断力を持つひとりの人間である以上、相手のやっていることを常に支持できるわけではないし、その意味で常に「味方」でいるのは難しいこともあります。
それでも、相手とともに生きる毎日が自分にとって心安らぐ幸せな「良いもの」だと思えるなら、家族関係や愛情関係は続くでしょう。だから、関係を継続することが目的なのであれば、その時々でいま自分や相手が、お互いに何を求めているのかを伝え合い、関係の調整をし続けることが大切になってきます。
――そうですね。
高橋 それに対して、最初から「何があっても絶対的な味方でいてくれ」と要求するのは、女性の自立的な判断力を否定しているようでひっかかるんです。そもそもご両親の世代の愛の形をそのままトレースすると、その古さゆえに、女性の方にしわ寄せがきてしまうという問題もあります。
――古き良き両親の姿をロールモデルにしてしまうと、自然と女性に負担や献身を強いてしまう側面があるということですね。鋭い分析をありがとうございました。
フェミニズムやジェンダー論という視点を加えることで、恋愛コンテンツをより深く、多層的に楽しめることがわかってとても面白かったです。この先、「令和の恋愛コンテンツ」は、果たしてどうなっていくのでしょうか。
高橋 「予想」は苦手分野なのでできませんが、オンライン恋愛や、ロボット(人形)との恋愛...…など、可能性はいろいろ広がっています。「推し」は「恋愛」と重なるところもありつつ、明らかに違う側面もあるので、そのあたりもますます重要になってきますよね。
2022年1月〜3月にNHKで放送していた『恋せぬふたり』は、恋愛関係抜きで家族になろうと、いろいろな試行錯誤と関係調整を丁寧に行っていくドラマで、新しい展開を期待させてくれるものでした。ストーリー構成がすばらしくキャラクターも魅力的なので、みなさん、おすすめです。感覚を研ぎ澄まし、感情に丁寧に向き合うことで切り拓かれていく恋愛文化の新たな境地を楽しみにしましょう!
フクスケさんの確かなドラマの知識と議論の運びのおかげで、いろいろなことを考えることができました。どうもありがとうございました。
※1 『青少年の性行動はどう変わってきたか:全国調査にみる40年間』 2018、ミネルヴァ書房
※2 「詳しくは『フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど――ポストフェミニズムと「女らしさ」のゆくえ』(高橋幸、2020、晃洋書房)および、Angela McRobbie, 2008, The Aftermath of Feminism–Gender, Culture and Social Changeを参照してください」(高橋先生)
※3 日本の女子中高生の3人に1人が視聴する「AbemaTV」のオリジナル恋愛リアリティーショー 人気シリーズ最新作『太陽とオオカミくんには騙されない❤』が初回放送後24時間で130万超の視聴を記録 同シリーズ累計総視聴数は5,200万視聴を突破
※4 【落合陽一】バチェロレッテとリアリティショーの魅惑
Illustration/戸田江美(@530E)