
ニセモノの檸檬を握りしめなければ、生きていくことができなかった
いまこれを読まなければ生きていけない、と思いながら前のめりに本を読んでいた。中学時代に抱いていたそんな想いを、食品サンプルの檸檬に託していた。小説家・磯貝依里さんによるエッセイです。

中学生の頃、糊のゆるんだ制服の紺プリーツスカートのポケットに、檸檬をひとつしのばせていた。
スカートの右ポケットにはリップクリームとあぶらとり紙、それからソックタッチの三点セットが入っていて、檸檬を隠していたのは左側のポケットだった。檸檬はてのひらにおさまるほどのサイズだったけれどそれなりに大きかったから、そんなわたしを遠くから眺めると、きっといつも左下半身だけがポコンと奇妙にふくらんでいたのだと思う。
■騒がしい中学生活の水底で、ひとり本を読んでいた
わたしの通っていた中学校は市の全体を望む山の中腹にあった。山のてっぺんに建つ小学校と山のふもとに建つ小学校のふたつから生徒の入学する中学で、それはちょうど、上下を平行に流れるふたつの小川が合流し、やがて太い河川に結ばれて陽の光を浴びながらゆっくりと遠い海にむかっていく、そんな様子と不思議によく似ていた。
授業中のことはもうあまり憶い出せない。いまもまぶたの裏につよく残っているのはいずれも休み時間や放課後の光景で、たとえば終業チャイム後の購買部。
大勢の生徒が狭いストアの前をはじけるように行き交い、自慢げにフルートを背負った吹奏楽部の女子生徒が楽譜の書き込みに使うラメ入りのカラーペンを買っていけば、それと入れ換わるように体操服の男子生徒たちが膝に巻くためのキネシオテープを買って、団子になって走り去りゆく。あるいは、部活のないだらだらした生徒たちが用もないのに文房具や靴、新しいカッターシャツの見本なんかをさんざん冷やかして下校してゆく。そんな飽和しきった廊下の喧騒とは対照的な、体育館の裏手から立ち昇ってくるカラスノエンドウの真っ青な匂い。自主練のはじまった吹奏楽部のトランペットの鈍い音が、わたしの横を一直線にすり抜けていく。そういうものばかりだった。
先生たちは手のかかる問題児やクラスカーストの高い生徒にだけ注目していたから、適度にまじめでおとなしく、とくに秀でた面もないわたしのような生徒はほとんど認知も相手もされず、クラスメイトからひそかにいじめを受けていた時もまったく気がついてもらえることもなく、でもそれで十分だった。
校内暴力やいじめが日々巻き起こる騒がしい中学生活の水底で、わたしは図書室に毎日入り浸っていた。図書室の薄っすらとしたその暗さはわたしの気持ちを安心させた。図書室では人と人との距離が遠い。わたしのような地味で自閉ぎみの生徒をゆるやかに出迎える、ただそれだけの場所で大好きだった。
さまざまな現代小説を純粋なたのしみとして読みながらわたしは同時に、いちばん奥の書架でぶ厚い埃をかぶっている近代文学全集を一冊ずつ読破していくことをなぜなのか自分に課していて、その近代文学全集のなかで何より魅了されたのが、梶井基次郎の『檸檬』という短篇小説だった。
■梶井基次郎の『檸檬』

《えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧えつけていた》という一文ではじまるその物語は、高校の現代文の教科書にも掲載されているから、記憶しているひとも多いだろうと思う。
終わりの見えない焦燥と嫌悪と憂鬱に取り憑かれた青年、《私》の過ごす日々。友人の家を転々としながら何をするでもなく京都の街を浮浪し、なにげない風景や商店を覗き見ては、ひたすらにそれだけをくりかえす。まだそんなふうに生活が蝕まれていなかった頃に自分の感性をよろこばせていた贅沢な雑貨を置く丸善は、いまの《私》にはもう重苦しい場所であるとしか思えずに、ささやかで見すぼらしいもの、たとえば花火やびいどろ、がらくたや洗濯物だらけの家並みの傾いた裏通りに咲く驚くほど色鮮やかな向日葵やカンナの花に心のやすらぎを覚え、誰も自分のことを知らない遠いどこかへ行って、ただゆっくりと眠りつきたい――、そんなことばかり考えてしまう。
そんな陰鬱な日々をさまよう《私》はある日、寺町の美しい小さな果物屋の店頭で、一顆の檸檬と出逢う。
《私》はその美しい檸檬を握りしめたまま、やがてふらふらとあの憂鬱な丸善へ辿りつく。本屋の平台に積み上げた画集の上にその小さな檸檬爆弾を据えつけて、それが大爆発を起こしてすべてをこっぱみじんにするだろう。そんな想像をあたまに浮かべ、色彩に満ち満ちた京極の通りを微笑みながら下っていく。
■わたしの檸檬を買いに行く
この小説を一読するや完全に魂をもっていかれてしまった中学生のわたしは、地元から二駅先にある百円均一のダイソーで檸檬の食品サンプルを衝動買いした。
ナマの檸檬でなくレプリカを買うという発想がそもそもダサく、また「中学生が檸檬の食品サンプルひとつを買うのはもしかしたらレジのおばさんにやばい奴だと怪しまれるかもしれない」とブドウの食品サンプルも一緒に買って帰るという無駄なムーブを見せたりもしたけれど、とにかくわたしはニセモノの檸檬をぶじに一顆手に入れて、翌日から《私》よろしくいつも制服のスカートのポケットにしのばせるようになった。
すべての明るさやにぎやかさから目を背けて、なんとか街の片隅にしがみついて必死に生きていた《私》のその光景。ほの暗く、見すぼらしく優しくささやかで、静かに尊いそんなものだけが自分の味方であるのだとすがるその感情。それを精緻に描写する、あまりにも鮮やかな文章のつらなり。
鼻をうつ檸檬の匂いそのもののように見事なその小説を、わたしは手に入れたニセモノの檸檬に託し、それをポケットのなかでつよく握りしめる。そんな時、自分は『檸檬』という小説それ自体を握りしめて味方にしているのだと思っていた。
見た目も中身も冴えず、派手なクラスメイトたちから蔑まれるちっぽけな自分の秘密の心のよりどころ。いじめやそれなりの家庭不和で思春期性の鬱病みたいになっていた中学生のわたしは、《私》の心象へ存分に自分を重ねながら、これはわたしの小説なのだとのめり込んだ。
ニセモノの檸檬を握りしめることはつまり、この世界のありとあらゆる小説を握りしめることだった。
『檸檬』だけでなく、中学や高校の頃は、どんな小説でもそこには自分のことが書かれているのだと思って読んでいた。
理不尽さに満ちた中学での日々、いまこれを読まなければわたしは死んでしまうかもしれないとまで思いつめ、前のめりになって本にしがみついていた。感情移入という行為にいっさいの後ろめたさもなく、ただ夢中になって夜を徹して、また授業なんか完全に無視して机の下で本をひろげて読みつづけていた。そうしなければ、子どもと大人のはざまでどうしようもなく憂鬱だったわたしは、生きていくことができなかった。
だからその頃に読んだたくさんの切実な小説を、たぶん一生忘れない。
■ニセモノ檸檬を置き捨てて、新しい街へ
わたしの檸檬はニセモノだから腐ることもなく、中学を、そして高校や大学を卒業し大人になったいまもまだわたしの部屋の棚の上に転がっている。ただの埃をかぶったインテリアみたいになってしまっていて、捨てられなかったのかもしれないし、というより、それを捨てるという発想がそもそもなかったのかもしない。
大人になったわたしは大学で文学の創作を学び、それから読むだけでなく、自分の言葉を小説やエッセイとしてほそぼそと書くようにもなった。あの頃と比べると小説の読み方は随分変わって、熱烈な感情移入をすることも、何かの作品を自分のお守りのように思うこともなくなり、批評的な視点は増えて消化するスピードも速くなったけれど、小説を小説以上の何かだと信じながら読むことをいつのまにかしなくなってしまった。と、久しぶりに棚の上の檸檬を眺めてそう思った。
ニセモノの檸檬のほうがわたしにとってはホンモノの檸檬だったのかもしれない。切実に前のめりになって小説を読んでいた思春期のわたしが、あの黄色いニセモノの紡錘形のなかに詰まっている。あの頃のニセモノの檸檬の気持ちをわたしはいまきちんと憶い出さなくてはいけない。そうしてこの世界のあらゆる言葉と向き合わなければいけない。
この春にわたしは実家を離れてひとり暮らしをする予定だ。
果たしてその時にこのニセモノ檸檬は持っていくのだろうか。きっと持ってはいかないだろう。憂鬱な学生時代を過ごしたこの部屋に、たぶん一生置いておくような気がする。
梶井基次郎が死んだのと同じ31歳になったわたしは、ニセモノ檸檬の転がるこの部屋ごと幼かった自分を捨てて、けれど切実な気持ちだけは握りしめ、それから《私》が丸善をあとにする時のように、色鮮やかな新しい街で暮らしていく。
※《》内引用は『梶井基次郎全集 全一巻』筑摩書房 所収『檸檬』より
Photo/池田博美










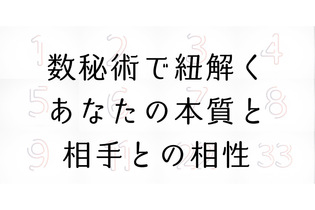










本を読むのが好きです。小説を書いたり、書評を書きます。関西出身在住。