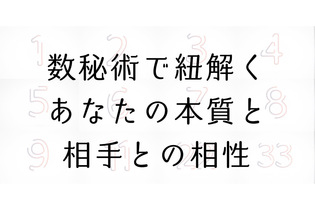結婚相手を〝アイカタ〟って呼ぶのイラっとしない? その本人に直撃してみた。
結婚相手のことを「アイカタ」と呼ぶのを聞いて、ちょっとイラッとした経験はありません? 今回は実際に「アイカタ」と呼んでいる男性にインタビューを行いました。そこでなんと驚愕の事実が発覚します──価値観が180度ひっくりかえるはずですよ。実は「アイカタ」には、すごく、すごく、優しく、真摯な意味がこめられていたのです。

■「アイカタ」ってなんやねん

その日、僕は、イラッとした。
「うちの相方がさあ」
「相方がいうにはなんだけど」
「結局、うちは相方次第でさ……」
アイカタ?
アイカタ?
アイタタ?
ひさしぶりの男友達(2年前に結婚した)との飲み会だった。新婚生活はどうだい、と話をふった。すると彼の話はなにかにつけ「アイカタアイカタアイカタ」だった。結婚相手のことを何度もそう呼んだ。
うん?
僕はビールを飲みながらイラッとしたのだ。
冬の街のなか、帰宅してシャワーを浴びても、その違和感はのこった。なにかの景品でもらったドライヤーの熱風でも吹き飛ばすことはできなかった。
僕はカーテンをあけて夜の窓につぶやいた。
「アイカタってなんやねん……」
■「アイカタ」って聞くと、なんでイラッとするんだろう?

それからというもの3日3晩悩んだ。
結婚相手を「アイカタ」と呼ぶ友人について。なぜイラッとするのか、自分でもわからなかった(あくまで僕個人の感覚です)。しかし思いだすたびにイラッとした。後ろから肩をとんとんされて、ほっぺたをぷにゅってされたときくらいイラッとした。
僕なりに仮説をたてた。
・「結婚している」だけでなく「めっちゃ仲良しなんです!」みたいな関係性の情報をブチこまれてる感じが、いや聞いてないんですけどってなる
・謎の漫才コンビ感
イラッの正体は、このあたりをカクテルした感じだろうと思った。そう考えるといくぶん頭がスッキリした。冬場、暖房でのぼせるくらい暑くなった電車からホームに降り立ったときくらいスッキリした。
4日目、なにかに突き動かされるように、僕はスマホを手にとった。
「なあ」と、彼にLINEを送った。
「おう。どした?」と、友人からすぐに返信がきた。
「取材させてくれ」
「え、意味わかんない。なにを?」
「どうしても聞かなきゃいけないことがあるんだよ」
そして僕と彼の一騎打ちがはじまった。これが世にも名高い平成最後の巌流島の戦いの幕開けだった。
■アイカタ男子との死闘

さる土曜日、僕は、彼を駅近くの雑な喫茶店に呼びだした。
雑なアイスコーヒーを飲んでいると友人(アイカタ男子)は時間通りにやってきた。スーツ姿に立派な紙袋をさげていた。
「結婚式の二次会だったんだよ」と友人はメニューを手にとった。
「2年ごしなんだな」と僕はいった。
友人は顔をあげると、数秒、眉をしかめたあと意味を理解したように笑った。「ちがうよ。俺のじゃない。会社の同期のだ」
しばらく他人のどうでもいい(僕はだいたいのことがどうでもいい)結婚式の二次会の話をした。そのあと、僕は、タイミングをみはからってスナイパーライフルを撃ちこむゴルゴ13ぐらいのピンポイントさで質問をブチこんだ。
「そういえばさ、奥さんのことを、相方っていうよな?」
「え、取材ってそれ?」
「すごく大事なことなんだよ」
僕の真剣な瞳に彼も観念したのだろう。彼は視線をおとして、少なくなったアイスコーヒーのストローをまわした。あたかも何十年ものあいだベテラン刑事でも尻尾をつかめなかった熟年のスリ師が寄る年波にあらがえずついに犯行中に電車のなかで財布をおとしてしまい己の指先をみつめたあと苦笑して年貢の納めどきを痛感したときのようにぽつりぽつりと告白をはじめた。
それは哀しくも美しい愛の挽歌(たぶんエレジー)だった──。
■アイカタの真実

「俺も結婚して2年になる」友人はいった。「結婚相手のことを、どう呼ぶかについて、めちゃくちゃ考えたんだよ。たとえば例をあげるとさ」
【嫁さん】 → 同上
【奥さん】 → 奥においやる(家に閉じこめる)という意味になってしまう。マナー用語としてはOK。でも個人的には気にしてしまう。
【家内】 → 家のなかにいれておけ、というニュアンスになってしまう。
【妻】 → 戸籍上の呼び方だからセーフ。しかし印象として、刺身の〝ツマ〟を連想させて〝添えもの〟というニュアンスになるという説もある。実際は由来を紐とくとそうではないし、公文書も認めるくらいだからいいとも思う。けれど、この呼ばれ方をネガティブに感じる女性もいると感じている。
【名前を呼びすて】 → 公的な場所にふさわしくない。ノロケにきこえかねない。肩書きだけで語りたいときもあるのに──軽い会話の流れで──わざわざ結婚相手の名前を説明するところからになる。
【ピッピ】 → 論外
「よく考えるとさ」友人はいった。「この国で使われる〝結婚相手の呼び方〟って、どれもしっくりこないんだよ。気にしすぎかも知れないけどさ」
「そんなとき大学の先生を思いだしたんだ。ジェンダーを研究してる女性教授だった。その人は40歳くらいで結婚して、相手のことを〝相方〟って呼んでたんだよ」
「彼女いわく本当に使いたいのは〝パートナー〟という呼び方らしい。でも日本では仰々しくなってしまう。気恥ずかしいっていうかさ。だから、その和訳として〝相方〟を使うことにしてたらしい」
「俺はすごくいいなと思ったんだ。対等な、フラットな関係をいいあえる感じがさ。自分がいて、その横に彼女がいて、彼女にとっても横に俺がいて、っていう感じがするだろ?」
「だから俺も〝相方〟って呼んでるんだよ」
友人のガチでリーガルハイの古美門弁護士ばりのロジカルな説明を聞きながら、僕は、ひとことも異議を差し挟むことができなかった。想像以上に考え尽くされた上で「アイカタ」という呼び方があったから。
正直、もっとノープランでいてくれよと思った。
■アイカタで文句あるか?

会計を一円単位まで割り勘にしたあと、僕たちは駅にむかって歩きはじめた。夜はすっかり、やさしい支配者のように広がっていた。恋人のコートのポケットに手をいれて歩くカップルとすれちがった。そういう季節だった。
僕は「ツイッターそろそろ復活しようかな」とかいう友人のどうでもいい話を聞き流しながら、ゆさぶられた価値観について考え続けた。
たしかに相方はイラッとする呼び方かもしれない──彼の説明を聞くとそうでもなくなってきたけれど──ほかに、ふさわしい呼び方が日本語のなかに見当たらないのも問題だった。
そこで僕は気づいた。「妻は夫に従うもの」という価値観が昔にはあったのかもしれない。そのときの呼び方が、いわゆる男女平等の世界にふさわしくなくなってきている──代わりの言葉が発明されないままでいる──ということなのかもしれない、と。
時代は変わる。
それにあわせて新しい幸せの形を作ろうとするように、結婚相手とフェアであろうとする姿勢が〝アイカタ〟にはあった。そのことに僕はなにかを感じた。彼と駅のホームで別れたあと、白い息をはいて、なんとしてもこのことは記事にしないとなと思った。