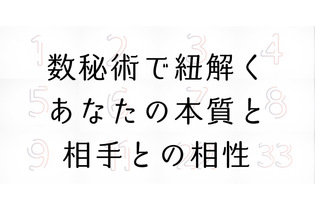私たちは希望を探して出会い続ける【希望をくれる女性の話】
希望をくれる女性に会いたい――日々すり減っていく心に光を灯してくれる人に。そんな想いから始まった、女性の生き方を追う文筆家・芳麗さんによる「希望をくれる女性の話」。第一回目にお会いしたのは、志村季世恵さん。セラピストとして人の痛みや死に触れてきた女性で、ソーシャルエンターテインメント「ダイアログ」の理事も務めています。

■人が心の病を患う理由は、人間関係
日々、たくさんの人に出会っているはずなのに、誰にも出会っていない気がするのはどうしてだろう?
仕事場でよく顔を合わせる人、深夜のコンビニのレジで前に並んでいる人、街ですれ違う人……etc リアルに出会っていても見知らぬ人だし、この先も関わり合うことがないと思える。SNSで言葉を交わすだけの人に心動かされることもあるけれど、目を合わせることもないから不具合が起きたらログアウトすればおしまいの関係だ。
愛だの友情だの、曖昧な概念だからわからないし、それ以前に、好きな人がほとんどいない。自分のことを好きになってくれる人がいない。そんな風に感じる日が多かったのは、思うより心や体が疲れていたからなのかもしれない。
心の病を抱えている人のカウンセリングから終末期のガン患者のターミナルケアまで、長らく人の痛みと死に触れてきたセラピストの季世恵さんの言葉は、柔らかくも重みがある。明日、死ぬかもしれないのは、終末期のガン患者だけではないし、心を病んでいるのは通院中の人だけでない。毎朝、重い足取りで会社に通っている人だって、どこかが壊れているのかもしれない。境界線はいつも曖昧だ。

志村季世恵さん
■暗闇の中では、人と肩が触れたり、ぶつかったりすることすらうれしい

敬愛する年上の女性であり、10年来の友人。志村季世恵さんと約4年ぶりに再会したのは、昨年、浅草橋に移転したばかりのダイアログ・イン・ザ・ダークだ。ここで季世恵さんは仲間とともに、新しい挑戦に向けてますます多忙な日々を過ごしている。
ダイアログ・イン・ザ・ダークはドイツの哲学博士であるアンドレアス・ハイネッケ氏が発案。ヨーロッパで人気を博し現在では、世界41カ国で開催されているソーシャルエンターティメントだ。日常生活のさまざまな事柄を照度ゼロの暗闇の空間で、聴覚や触覚など、視覚以外の感覚を使って体験する。漆黒の暗闇を案内するアテンドは視覚障がい者の方たち。ダークに続き、ダイアログ・イン・サイレンスという音のない世界も開催され、ここでは聴覚障がい者が案内役として活躍している。
世界的規模で展開され、日本でも熱狂的なファンは多いが、まだまだ知る人ぞ知る存在。季世恵さんはダイアログ創設時から、理事と全てのプログラムのクリエイティブを務めている。約10年前、私は当時、外苑前に所在していたダイアログに取材で訪れて、季世恵さんに出会った。
“ダイアログ・イン・ザ・ダーク”とは、直訳すれば、“真っ暗闇の中での対話”。どんなに目を凝らしても見えないほどの深い闇の中に、森や公園や田舎の日本家屋などが設営されていて、参加者はその中を探検する。普段から目を使わない視覚障がい者がアテンドとなり、歩くことすらままならない闇の冒険をリードしてくれる。
暗闇は不思議だ。入った瞬間は恐怖心が襲ってくるのに、前進するたびに安堵に変わる。
目が使えないと、それ以外の感覚が野生の動物のごとく鋭くなる。足元で踏む草の感触や、野鳥の鳴き声、風の匂い……etc. それらに身を浸していると、子どものような遊び心が湧いてくる。参加者がみな小学生か野生の動物に戻ってしまうから、面白い。肩書きや年齢どころか、本名すら必要としない世界で遊ぶ開放感。この瞬間に心を開き助け合う喜び。
視覚障がい者であるアテンドのかっこよさにも痺れる。普段は生きづらそうに見える彼らが暗闇では誰よりも頼もしい百獣の王だ。闇の中でも、まるで全てが見えているかのよう。
ほんの少し会話しただけで、参加者の声と個性と気配を把握して、闇に迷いそうになったときも、すぐに私を見つけてくれる。
――ここは新しい人の魅力に出会い、新しい自分に出会える場所ですよね。

■人が好きだと気づいて、自分のことも好きになれる体験
ダイアログを創設する以前の季世恵さんは、当時のパートナーと設立した治療院「癒しの森」にてカウンセリングを担当していた。訪れる患者さんたちのさまざまな心の病に向き合って、気がつけば、予約は1年待ち、唯一無二のセラピストになっていた。
そんなとき、ダイアログ・イン・ザ・ダークに巡り合った。当時は友人だった、金井真介(現在は、志村真介)さんが、海外のダイアログについての新聞記事を見つけて、「ぜひ日本でもやりたい」と季世恵さんに相談を持ちかけたのだ。
その後、前夫である癒しの森の院長が他界し治療院は閉院。以降彼女はダイアログ・イン・ザ・ダークの中心的存在となり、真介さんを助け常設展示にまで仕上げた。

志村真介さん(写真右)
それならば、私ひとりで多くの患者さんを抱えるよりも、ダイアログでお互いが出会えれば、違った文化も知れるし、人と自分を好きになれるかもしれない。弱い存在だと思われがちな視覚障がい者たちの凄さにも気づいてもらえる。みんな全ては平等だし、助け合えることに気づける。これが世の中だと思ってもらえるかなって。そう考えると、ダイアログと私の出会いは、偶然のようで必然だったのかもしれないね」
ヨーロッパだけでなくアジアでも学校教育の一環としてダイアログを認め、国家で支援している国もあるが、日本はそれに及ばない。
それでも、季世恵さんや真介さんをはじめとするスタッフは、日々、ダイアログとその思想を浸透させるべく、アイデアを絞り、さまざまなプログラムを作っている。
2020年の東京オリンピックを視野に入れながら、昨年から聴覚障がい者をアテンドにすえたエンタテインメント、「ダイアログ・イン・サイレンス」を開催して規模を拡大するなど、新しい挑戦を続けている。
―― 人生も一寸先は闇だしね。
――登山の道すがら、挨拶を交わすような感覚?
季世恵さんは、ダイアログそのもののような人だ。一緒にいると、不思議と五感と心が開かれて、何者でもない子どもに戻れる。無駄な雑念が取り払われ、温かな気持ちで満たされる。
■”人の成長は人との出会いでしか得られない”

私は彼女に出会って間もない、10年前の自分のことを思い出していた。
30代も半ばに差し掛かろうという頃、漠然とした焦燥感に苛まれていた。結婚も出産も仕事も自分なりの答えを出さねばと至極、焦っていたけれど、だからと言って、我が道を軌道修正することも、歩むスピードを変えることもできなかった。明日をもわからぬ恋をして、目の前の仕事にばかり精一杯。何度、つまずいて傷ついても答えが出せない自分は、生産性も計画性もなく、努力不足な人間だと卑下していた。そんな私に、当時の季世恵さんはいった。
あのときは、「でもキリギリスって、冬は飢えて死ぬよね?」と思ったけれど、10年経った今では理解できる。キリギリスのままで年を重ねても、日々、ご飯はますます美味しく、心動くことに遭遇して、大切な人たちがいる。
これでいい。肩の力を抜いてそう思えるようになったのは、きっと季世恵さんとの出会いがあったから。あの頃、互いに多忙な日々の合間を縫って、子どものように遊んだ。
都心の森のような公園で目隠しをして鬼ごっこしたり、夏には山頂のお寺に行って和尚さんに禅の食事の作法である食禅を学んだ。中目黒の桜吹雪の中でイタリアンを食べながら、語り合った夜もあった。季世恵さんにもらった時間や言葉のかけらは、時が過ぎ去っても心を支え、今の自分を作っている。

■おはようとおやすみが言えるってすごいし、幸せなことだと思うんだ。
季世恵さんは4年前、ダイアログの代表であり、長年の同志でもある真介さんと結婚した。
ずっと、真介さんは季世恵さんのことが大好きでたまらなかったし、パートナーであることには変わらなかったのだけれど。ある日、突然に真介さんが大きな病に倒れたのを機に、入籍した。「真ちゃんは、今、元気だけど、いつ倒れるかわからなくもあって。だからね、結婚して家族になりたかったの」と季世恵さんはいう。
――真介さんと結婚してから何か変わった?
――どんな風に変わって行くの?

いつか終わりを迎えても、終わらない関係があるならば、それはどれほど大きなものになっていくだろう。出会いがあれば、別れがある。だけど、別れはあっても、心の中にともに過ごした記憶は続いていく。それは、きっと夫婦や家族に限らない。
『おはよう』とか『おやすみ』という言葉の本質もそこにあると思うの。今日も出会えた家族や友達に『おはよう』したら、『おやすみ』でまたリセットする。私ね、命の終わりを見てきて、永遠はないことを知っているから、おはようとおやすみが言えるってすごいし、幸せなことだと思うんだ。たとえ、家族でも一期一会。おやすみは、また明日も会えるといいねだし、おはようは、出会えてうれしいって言う気持ちで言っているの」
もうすぐ開催される、ダイアログ・イン・サイレンスの準備に追われて、ますます睡眠時間が削られているはずなのに、今日も季世恵さんは穏やかで楽しそうな空気をまとっている。

「今日はまた新しい芳麗ちゃんに出会った気がする。何だか幸せそうでうれしい。きっと、あの頃より、自分のことを好きになれたんじゃないかなぁ」
別れ際に季世恵さんは今朝、庭で摘んだというジャスミンの花で作った花冠をくれた。いつの日か、大好きな香りだと彼女に話した記憶が蘇ってきた。
帰り道ですれ違った、小柄なおばあさんに『暑いですね』と挨拶してみたら、『暑いねぇ』と返してくれた。その笑顔を見て、季世恵さんの気配を思い出す。また、出会えますようにと願いながら、私は毎日、見知らぬ誰かに、初めての自分に出会い続ける。
取材・Text/芳麗
Photo/池田博美