「美人じゃないからロッカーに生卵を入れられる」と思っていたころのこと
小さいころに受けたこころない言葉が、今でも呪いとなって意識を縛りつける――もしも、これをコンプレックスと呼ぶのであれば、多くの人がそんな呪縛に苦しんでいるのかもしれない。

10代のとき、同級生に「整形したい」が口癖の友人がいた。
彼女は目も二重で鼻もくっきりと高く、整った顔立ちをしていたが、エラが張っているのが許せないのだと言った。
彼女は普段、校則を守って一切の化粧をしていなかったが、休みの日に私服で集まると、化粧や髪型のおかげでその華やかな目鼻立ちは目立った。待ち合わせの時間に少し遅れてきたときに、その理由を「さっき二回もしつこいナンパされちゃって」と語っていたこともある。
そんな彼女が事あるごとに言う「あー整形したい」に、当時の私は「チェッ」みたいな気分でいた。もっと言葉を選ばずに言うと、「美人だろ、うるせえな」と思っていた。美人な彼女の口から整形、という言葉が出るたびに、あなたに整形なんかされたら私はどんな顔して生きていけばいいんだ、と憂鬱な気持ちになった。
自分は美人ではない、と気づいたのは小学生のときで、そのきっかけは母の友人たちからかけられる「お母さんに全然似てないね」という言葉だった。母は若いころ、校内にファンクラブがあったり、モデルのバイトをしていたこともあるような誰しもが認める美人だった。その話を周囲からよく聞かされていた私が「美人な母にまったく似ていない自分」というシンプルな情報から「自分は美人ではない」というシンプルな結論を導き出したのは、至極当然のことだった。
美人ではないという自負は、10代を迎えるとすぐに強いコンプレックスになった。もともと病的に自意識が過剰なことに加え、成長期でやや太り、肌も荒れていた中学生の私は、電車の窓に自分の姿が映るたび毎朝飽きずに「うわあ化け物だ」と思ったし、駅ですれ違ったカップルがこちらを見ただけで「死ねブスって思われた、無理だ、死のう」と本気で思った。
通っていた中学・高校は女子校で、顔の美醜がヒエラルキーを決めるような文化では決してなかった。なかったはずなのに、私は勝手に「醜いから馬鹿にされている」と思い込んだ。同級生にいじめられて自分のロッカーに生卵が入っていたときも、「美人ではないから生卵を入れられるんだ」と思った。端的に言って、10代は地獄だった。
■子どものころに受けた言葉が、今も律儀に私を落ち込ませる
大人になってから、改めて自分の容姿について考えてみたことがある。
私は容姿に強いコンプレックスを抱き続けてきたけれど、じゃあ、実際に自分の顔のどこが嫌いなのだろう? と自問自答してみたのだ。
すると不思議なことに、“特別嫌いなパーツ”はなかった。当然、二重幅が狭すぎるだとか、鼻と口の距離が長いだとか、歳のわりにほうれい線が目立つだとか、“そこそこ気になるパーツ”はあるのだが、嫌で嫌で仕方なく、可能ならいますぐに別の部品と交換したい、みたいなパーツは別になかった。
じゃあ、どうしてこんなに「私は美しくない」という意識に悩まされているのだろう。
答えは明確で、幼いころ、「お母さんに似てないね」と言われ続けたからだ。こんな言葉をかけられ、自分は不細工なのだと自分から思い込んだせいで、その意識がいまだに自分のなかから消えてくれないからだ。
幼少期や思春期に受けた自分に対する評価というのは、大人になってからも驚くほど残り続け、尾を引き続ける。
周囲を見渡してみれば、子どものころに親から頻繁に言われた「可愛げのない子」という言葉がコンプレックスになって、「自分には愛嬌がない」と最近まで思い込み続けていた友人がいたり、高校生のときに付き合った最初の恋人にかけられた「お前がもうちょっと可愛かったらなあ」という言葉に苦しめられて化粧マニアになり、コスメカウンターで美容部員として働くようになった知人もいる。
後者の例のように、コンプレックスがなにかを始める原動力になるような素晴らしいケースもあるのだけれど、基本的にはコンプレックスを抱き続けることは辛く、しんどい。
そう。コンプレックスを持ち続けるというのは、それだけでもう、すごく労力のいることなのだ。
試しに周囲に「コンプレックスってある?」と聞いてみると、半分くらいの人が「10代のときは〇〇で悩んでいたけれど……」と昔の話をする。いまもコンプレックスがあると言う人も、その多くはそこそこ折り合いがつけられている(ように感じる)。大人になってからも「自分の容姿は醜い」と毎日律儀に落ち込み、苛立っている自分のようなケースは、ある種やはり病的なのだとも思う。
■「自分のことを愛せない人は、他人からも愛されない」は嘘だと知った
コンプレックスについての文章を、と今回原稿を依頼していただいたとき、すこし困った。
私にはその解消法は書けないし、むしろ解消法なんて死ぬほど見聞きして自分なりに考えてきたけれど、やっぱり自分のことを醜いと思う意識からは逃げられないことがわかっていたからだ。
どんな自己啓発本を読んでも「まずは自分で自分の顔を好きになってあげましょう」と書いてあるし、「自分のことを愛せない人は、他人からも愛されない」的言説も100万回くらい耳にしてきた。けれど、どうしたって私は自分の顔を好きになれない。
コンプレックスの原因が幼少期にあるとわかっていたって、メイクをするようになって周囲から多少容姿を褒めてもらう機会ができたからって、それは変わらない。
だからこそ、大人になってからもコンプレックスを手放せず、コンプレックスにとらわれている人の気持ちはよくわかる。実際に美人だろうがそうでなかろうが、愛嬌があろうがなかろうが、「私は不細工」「私は可愛くない」と強く思い込み、どれほど歳を重ね、経験を積み重ねてきても、その呪いから逃れられない人の気持ちが。
ただ、私が(ほんのすこしだけ)そのコンプレックスの荷を軽くしたのは23歳のときで、当時付き合っていた恋人に「私は不細工なので写真を撮らないでほしい」と言ったときのことだった。彼の「いや、可愛いじゃん」と私の「不細工だから」で押し問答になり、最終的に彼が怒って、大声で「それは俺の主観だろう! 俺とお前は他人だろうが」と言った。
その瞬間、「そうか」とハッとした。自分が自分のことをいくら醜いと思い込もうが、他人はそう思わないこともあるのだ、と突如気づいたのだった。自分を愛せない人は他人から愛されない、なんて言葉も嘘だとわかった。だって、自分以外の人間はすべて自分と美意識も物の感じ方も違う「他人」なのだから。
そのときから、「もしかすると私が感じている『私は醜い』も、他人からしたらそうでもないのかもしれない」とようやく思えるようになった。
私はたぶん、いつまでかはわからないけれど、これから先も「私は醜い」と向き合い続けるだろう。けれど、その「私が醜い」が、もしかしたら(他人から見ると)間違っているかもしれない、という可能性だけは、常に頭のなかから消さないように努力し続けようと思っている。
この前フェイスブックを見ていたら、「整形したい」が口癖だった友人が、結婚したという投稿をしていた。ドレス姿の彼女は変わらず目鼻立ちが華やかで、彼女があれほど気にしていたエラは、たしかに多少は張っているようにも見えたけれど、そんなことどうでもよくなるくらい、やはり美しかった。「整形してねえじゃないかよ」と心のなかでつぶやいて、自分と彼女の容姿の差に落ち込み、その夜はそのまま寝てしまった。










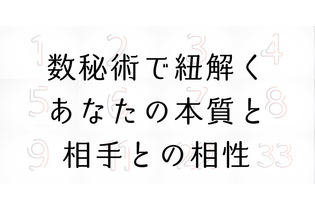










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。