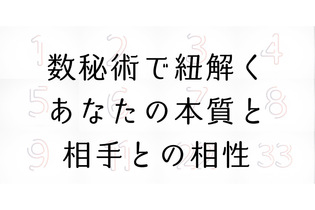「私たち」という幻想
人を群れに囲い込んでラベリングするような女性誌の時代は終わり。私たちって言わない女性たちが欲しがるものを提言してほしい。

「私たちってさ」って言いあう友達、どれぐらいいます?
高校生の頃、同じ制服を着て同じ教室に毎日集まる女の子たちは「私たち」だと思っていた。私たち、恵まれているよね。私たち、ちょっと特別な女の子だよね。私たち、何にだってなれるんだ。みんな同じ。だから、スカート丈一つで「私たち」の中の棲み分けが出来た。
だけど大学に上がってバラバラになったら、「私たち」は幻想だってことに薄々気づいた。恋愛観だとか、所属する場所だとか、何だかズレてくる。就職活動の時期になると、本当に人脈に恵まれた子や、実力があって優秀な子はやすやすと就職を決めた。あのときようやく、あれ?私たち、学校では平等だってことにされてたけど、はじめから全然違ってたんじゃないか! と、遅まきながら気がついたものだ。
企業に入ってからは、同期が「私たち」になった。新人研修時代には「私たち、こんな目にあって大変だよね」って一緒に泣いて頑張った。けど、いざ仕事が始まってみると、ほんとに残酷なぐらい、私たちは一緒じゃないってことがよくわかった。需要が違う。評価が違う。置かれた場所でどんどん洗練されて行く女の子たちは、もう誰一人「私たち」なんて思わなくなった。
母親になったとき、私は「私たち」って言われることを警戒した。ママ友っていう関係にどうしても違和感があったから。同じ時期に子どもを産んだ友人や、近所で同じ年頃の子どもを持っている人との付き合いもしたけれど、幼稚園受験をきっかけに言動がおかしくなったり、小学校受験をきっかけに被害妄想になったり、本当に人が変わったようになるのを見てしまった。子ども越しの関係しか結べない人たちの、脆弱さゆえのむき出しの攻撃性に辟易した。
海外に住むようになって、日本人駐在員社会の「私たち」との接点も出てきた。日本人駐在員の娘として海外生活を送った私は、母がそれでどれほど苦しんだか、よく知っている。世間の狭さという点では、日本にいるときの何十倍も密度の濃い人間関係を、正確に言うと上下関係を、生きなくてはならないのが駐在員だ。私は企業の転勤命令で海外に引っ越したわけではないので、彼らの言う「私たち」ではない。だから、距離を置いている。
もちろん、私にも数は少ないけど友達はいる。環境はあまり似ていない。私は既婚女性で子どもがいて片働きで、海外に住んで日本で働いているけれど、友達は独身だったり、子どもがいなかったり、女装していたり、仕事が全然違ったり、仕事をしていなかったり、異性だったりする。
そして彼らは「私たちってさ」とは言わない。
雑誌が売れない時代だと言う。たぶん、この「私たちってさ」が作り手に見えにくくなっているのだと思う。たとえ同じ世代だってファッションもお財布事情も結婚観も人それぞれだし。けど、「私たち」は、なくなったわけじゃないと思う。
互いに密かに値踏みして同盟関係を結ぶような「私たちってさー」じゃなく、
全然違うんだけどなんか気が合うんだよね、という「共感を感じる間柄」というのは確かにある。それはトレンドとしては現れにくいのかもしれないけれど、敢えて言ってみれば「それぞれに好きなものを見つけて一緒に生きて行ける人たち」というのは確かにいるのだ。
かまびすしい「私たちってさー」の声を横目に、黙ってスタスタ歩き回っているそういう人たち、結構いる気がしません? 人を群れに囲い込んでラベリングすることで商売を成立させてきた女性誌が、「私たち」って言わない女性が手に取りたくなるような提言をしたら、もっと世の中が面白くなるのになあ、なんて思う。