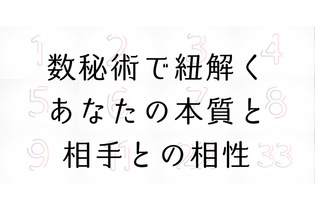「自分らしく」を求めた夫婦の悲劇【結婚は、本から学ぶ#5】
読書を通じて愛と結婚について考える連載の第5回目は、「家族の終わりに」という米作家による小説について書きました。題名からも予想がつくように、ちょっとした行き違いから破局への道をたどる若い夫婦を描いたこの小説。繰り返される日常の出来事や、夫婦の細かな心の動きが丁寧に書かれており、文学作品としての評判も高いストーリーです。

目次
小説「家族の終わりに」との出会い
今回とりあげる作品は『家族の終わりに』という小説。
この本の原書は「レボリューショナリー・ロード」という題名で、アメリカの小説家リチャード・イェーツによって書かれ、高い評価を得た作品です。
私がまだアメリカに住んでいたときに、長距離ドライブのためにオーディオブックを借りようと図書館に行き何気なく手にしたのが、この本を知ったきっかけ。
その後、この小説が映画化され、あの『タイタニック』で恋人同士を演じたレオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレットが、10年ぶりに夫婦の役で共演した作品として話題になりました。
日本では「レボリューショナリー・ロード/燃え尽きるまで」という題名で公開されましたが、このふたりの共演に惹かれて、あらすじをよく知らずに映画を観た人も多かったようで、ネット上の映画の感想には「結婚は怖い」「家族をテーマにしたホラー映画だ」などというコメントも見られました。
今回、結婚のひとつの形として、ぜひこの小説に出てくる夫婦を取り上げたいと思い、あらためて『家族の終わりに』というタイトルの日本語版を読んでみました。
『家族の終わりに』書籍情報
『家族の終わりに』あらすじの紹介
舞台は1950年代のアメリカ。郊外に家を買い、ふたりの子どもを育てる若い夫婦のフランク(夫)とエイプリル(妻)は、はたから見れば絵にかいたような幸せを手に入れたカップル。ですが、内面に鬱々としたものを感じながら毎日を生きています。
物語は、「想像できるかぎりいちばん退屈な仕事」に就いているフランクが、昔は俳優志望だった妻の出演する地元の劇団が主宰したお芝居を観に行くところから始まります。
お芝居は散々な出来で、帰り道にふたりは大げんかをするのですが、その前後で、ふたりの出会いや、それまでの結婚生活がどんなものだったかが語られていきます。
死ぬほど退屈な仕事と、同じくらい退屈な郊外での生活。
冒頭のお芝居の件からしばらく経ったとき、エイプリルは「思い切ってパリに移住してやり直さない?」と夫に提案します。自分が働いて生活費を稼ぐので、フランクは本当にやりたいことをじっくり見極めればいい、と。
エイプリルの熱気にフランクも次第にその気になり、計画を進めるのですが、予想外にもエイプリルが再び妊娠。
後半は、宙に浮いたフランス行きや、子どもを産むのかどうかということを巡って対立する夫婦の姿が描かれ、ストーリーは一気に結末へと向かっていきます。
「普通の生活」か「意味を感じられる人生」か
このストーリーでは、フランクもエイプリルも、現在の生活では得られない「何か」を渇望しています。
死ぬほど退屈でも、一応きちんとした仕事があり、ふたりの子どもたちがいて、郊外に買った家に住んでいる……というだけでは満足できないふたり。フランクは職場で浮気をして気を紛らわせようしますが、心は満たされません。
一方、エイプリルも、「何かしら意味のあることができるはず」と思っていたのに、若くして妊娠し、郊外での退屈な生活に縛られていると感じています。
フランス行きを決めてからは、生きる目的を思い出したかのように活気を取り戻し、夫婦仲も良くなりますが、妊娠が発覚してからはふたたび絶え間なく喧嘩をするようになってしまいます。
中でも印象に残っているのはフランクが「本当は自分も子どもが欲しくなかった」と回想するシーン。
「(妻が妊娠中絶をしようとするのを説得してやめさせた)あの瞬間以降、自分の人生のすべてがほんとうは望んでいないことの連続になったのではないか?」と自問するフランク。
そして、彼は
”自分が頼りになること”を証明するために、死ぬほど退屈な仕事に就いた。
”健全できちんとしていること”を証明するために、高すぎる気取ったアパートに移った。
”ひとりめの子どもが間違いではなかったこと”を証明するためだけにふたり目をつくった。
”自分でもそのくらいはできる”と証明するために郊外に家を買った。
……と、自分の人生を批判的に振り返っています。
フランクが根底ではこんな気持ちを抱えて生きているからか、たびたび出てくるふたりの喧嘩のシーンは本当に痛々しく、読者をやりきれない気持ちにします。
海外移住は逃げの手段?
ストーリーの中で描かれるフランス行きのアイデアは、退屈な現実から抜け出す手段としての海外移住にほかなりません。フランス行きを子どもたちに話しているシーンがあるのですが、フランクもエイプリルも、どことなくリアリティのない、夢物語を語っているかのような印象を受けました。
結婚するということは、自分ひとりだけの人生ではなくなること。子どもがいればなおさらです。「自分がやりたいから」というだけで物事が進むとは期待しないほうが良いでしょう。
実際に、ストーリーの中でも、一時はフランス行き計画をきっかけに仲良くなるふたりですが、ひとたびその計画がうまくいかなくなると、あっという間に関係が悪化していきます。
この本を読んでいた当時、私もいつかアメリカでの生活をいったん終わらせて、日本に移住したいと思っていた時期があったのですが、「いずれ日本への移住を試みるにしても、夫への提案の仕方には十分な準備や工夫が必要そうだ」ということを、この小説から教えてもらいました。
繰り返される平凡な日常に耐える結婚生活
お互いが自分の人生に不満を感じており、夫婦の関係もあまりうまくいっていないとき、その突破口として海外移住をしようと思う人はほとんどいないかもしれません。そういった意味では、この小説は、共感を呼ぶような構成になっていないと言えます。
ですが、描かれる人間模様や、お互いが考えていることと、ふたりの間で交わされる言葉で伝わることのギャップは非常にリアルで、おそらく長く間交際をしているパートナーがいる人にとっては、身につまされることも多いのではないかと思います。
結婚はゴールではありません。その後も生活は続いていきます。繰り返される日常生活の凡庸さに耐えていくのが結婚生活だと多くの人が認識したら、それでも結婚しようと思う人は少なくなってしまうでしょうか。ささやかな身の回りの出来事に幸せを感じられる人だけが、結婚に向いていると言えるのでしょうか。
私は、生きている限り、人はどのようにでも変わる可能性があり、夫婦のあり方も変わっていくと思っています。その変化がいつもプラスの方向にいくとは限らないでしょう。
でも、もともとは赤の他人だった人と深い関係を築いて、ずっとひとりでいたら得られかったかもしれない”大きな感情の揺れ”を体験する、それこそが、結婚生活の醍醐味のひとつなのではないかと思います。
すでに結婚して、数年が過ぎていて、行き詰まりを感じている人が読むと「自分たちの夫婦のあり方もそう悪くない」と思えるかもしれません。
また、結婚する前か、あるいは結婚したばかりという人が読むと、「こうならないためにはどうしたらよいのか」と考えるきっかけになるでしょう。
文学作品としての評価も高く、随所に心に響く台詞や表現があるので、読み物としても楽しめる小説です。