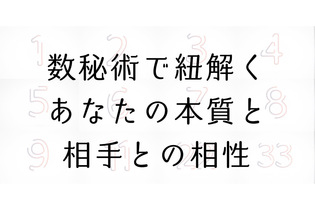繁殖期間だけつがうキツネやロビンそのほか多くの種と同じように、ひとの一対一の絆も、もともと扶養を必要とする子供ひとりを育てる期間だけ、つまりつぎの子供をはらまないかぎり、最初の四年だけ続くように進化したのである。
『愛はなぜ終わるのか』(ヘレン・E・フィッシャー著・草思社刊)より
3年目の浮気には理由があった! 私たちに定められた愛の期限
世間を賑わす浮気や不倫。ダメだとわかりつつ手を出してしまう人が後を絶たないことを見ると、現代の結婚観にこそ問題があるのかもしれない。今回は「3年で愛が終わる」という説について、生物学的な観点で掘り下げていく。

■3年目の浮気が原因? 離婚のピークは結婚2~4年目
「3年目の浮気ぐらい 大目にみろよ」
多くの人が耳にしたことがあるだろうこの一節は、1982年(昭和57年)にリリースされたヒロシ&キーボーのデビュー曲『3年目の浮気』の歌詞である。この曲がヒットしたのはコミカルなデュエットソングという点だけでなく、結婚3年目に浮気に至る気持ちがわかってしまう人が多くいたからではないだろうか?
実際に結婚後約3年程度で離婚に至る夫婦は多い。

『愛はなぜ終わるのか』(ヘレン・E・フィッシャー著・草思社刊)P107より
国連人口統計年鑑によると、1947~1989年の期間における、世界62の国、地域、民族グループが離婚した年月について、さまざまな社会で多くの人が結婚2~4年目に離婚しており、そのピークは結婚後4年目になっている。
「恋愛の期限は3年」なんてこともよく言われているが、今回は生物学的な観点でこの愛の期限について考えていきたい。
■一夫一妻制をとるのは哺乳類の約3%⁉

まず愛の期限について検討していくうえで、現代の世の中で一般的となっている一夫一妻制というスタイルについて生物学的に考えていこう。
人類学者のヘレン・E・フィッシャーが執筆した『愛はなぜ終わるのか』によると、自然界で一夫一妻制という形をとる生物は稀で、哺乳類に限るとわずか3%だという。
一夫一妻制をとるキツネや鳥類は、無力で未成熟、そして一定期間親の庇護が必要な子供を産む。そのため、子供が小さいうちは、メスがつきっきりで面倒を見なくてはならない。なので、生き延びるための餌を得ようとして、オスとパートナー関係を結び一夫一妻という形を取る。
しかし、この一夫一妻という関係性は子供が育つまでの繁殖シーズンのみで、これが終わると関係性を解消する。つまり、一夫一妻といっても生涯添い遂げるわけではないのだ。
これは人類の祖先にも言える話だと、ヘレン・E・フィッシャーは言う。
私たちの祖先は移動生活をしていた。移動生活では、オスがハーレムを作れるほどに多くの資源を確保し守ることは困難であった。また、繁殖に最適の地を独占することも難しかった。そのため、オスはひとりのメスといっしょに動き回り、発情期にほかのオスから保護し、子を育てるのを助けるという一夫一妻を取っていた。そして、キツネや鳥類と同じく、人類の祖先も子育ての期間だけつがいになったのだろう。
■一夫一妻制の必要性は、子育て期間のみ?
では、人類の子育て期間というのはどれくらいなのだろうか?
京都大学大学院の「理学研究科 自然人類学研究室」の研究によると、伝統的な狩猟・採集民族であるサンたちは、授乳期間が今でも3~4年と長期に渡ることから、出産間隔(子供を産んでから次の子を産むまで)も同じくらいの年月を必要とする、と言われている(これは、授乳によって排卵が抑制されていると推測されるため)。
この事実から人類学者のジェーン・ランカスターらは、4年という出産間隔は、過去の長い進化の間にできたパターンなのではないかと考えている。
この人類の出産間隔である4年は、なんと現代における離婚のピークである結婚4年目と一致する。
この4年という子育てサイクルに関して、ヘレン・E・フィッシャーは以下のような考えを示している。
子供が乳離れするまで配偶関係を続け、逐次的一夫一妻を選んだものたちが残る率が圧倒的に高かったのだろう。ひとの繁殖のサイクルによってできあがった、七年めの浮気ならぬ四年めの浮気は、生物学的現象のひとつなのかもしれない。
『愛はなぜ終わるのか』(ヘレン・E・フィッシャー著・草思社刊)より
つまり、一夫一妻というパートナーシップを結ぶ必要がある子育て期間が終了することによって、3~4年目の浮気が起こりやすいのではないか、ということである。
今は時代も変わっているし、夫婦がペアになって子育てしなくてはいけない期間だってもっと長いようにも思う。しかし、人類の祖先が種として生き延びるために行った生存戦略が、現代の私たちにも引き継がれているとすると、なんだか神秘的にも思えてくる。
【出典元】
ヘレン・E・フィッシャー著、吉田利子訳(1993年)『愛はなぜ終わるのか』 株式会社草思社.
【参考文献】
京都大学大学院 理学研究科 自然人類学研究室 日本人類学会進化人類学分科会ニュースレター 2014/10
http://anthro.zool.kyoto-u.ac.jp/evo_anth/evo_anth/sym1410/sym1410.pdf