
レーダーホーゼン、あるいは人を恋に落とすひと言について
人が発するなにげないひと言には時々、一瞬でその人の倫理観や審美眼を白日の下に晒してしまうようなおそろしい力が宿ることがある。何よりも怖いのは、その言葉を発しているとき、当人にだけはそのひと言が持つ効力が決して自覚できないということだ。きっと今のあなたも。

村上春樹の初期の短編に「レーダーホーゼン」という話がある。(私も読むまで知らなかったのだけれど、)レーダーホーゼンとはドイツの民族衣装のひとつで、肩紐のついた皮製の半ズボンのことだ。
ある女性がドイツをひとりで旅している。彼女はドイツ土産として夫に頼まれていたレーダーホーゼンを買いに専門店まで足を伸ばすが、その店はオーダーメイドのシステムをとっていて、履く本人が店まで来なければ売れないと追い返されてしまう。
仕方なく、夫に似た体型のドイツ人男性を店に連れていって採寸をしてもらっていると、彼女は突然「自分は夫を憎んでいる」と自覚する。そして、帰国したらすぐに離婚しようと決意する──というのがおおまかなあらすじ。
私はこの話がけっこう好きで、村上春樹の短編でおすすめはないかと人に聞かれるとしばしば「レーダーホーゼン」を挙げる。あらすじを伝えたときの反応は「怖い」か「あ、なんかわかる……」にざっくりと二分される。
「あ、なんかわかる……」の人たちにはそのまま、レーダーホーゼンのようなできごとを実際に体験したことがないかを聞くようにしている。つまり、それ自体には一見なんの意味もない(ように思える)ものがきっかけになって、自分の気持ちや他者との関係が決定的に変化してしまったできごとについて。
■「この枝豆めっちゃまずい」
ある男友だちは、枝豆がきっかけで恋に落ちたことがあるという。
大学時代、福引きかなにかで夏の花火大会のチケットが2枚当たってしまって、特定の恋人や花火に誘えそうな友だちのいなかった彼は、SNSを通じて当時よくやりとりをしていた女性に声をかける。彼女は驚きつつもその誘いを快諾してくれて、ふたりで花火を見にいくことになった。
浴衣を着てきた彼女を見て華やかで可愛らしいとは思ったけれど、恋愛感情はまったく抱かなかった、と彼は言う。その日は朝から小雨が降っていて、湿気と人の多さにうんざりしたふたりはどちらも言葉少なだったらしく、花火が終わるころにはなんとなく気まずい雰囲気さえ流れていた。
けれど、せっかくだからごはんだけ食べていきましょうか、という話になって適当に入ったチェーンの居酒屋で、彼は突如恋に落ちてしまう。お通しに運ばれてきた枝豆をひと口食べるなり、彼女が「うわっ」と顔をしかめて「この枝豆めっちゃまずい」と言ったのだ。
初対面の女の人に枝豆めっちゃまずいって言われたら好きになっちゃわん? と友だちに言われたとき、正直、いやなっちゃわんよと思った。が、彼のツボはわからなくても、その気持ちはよくわかる。私自身、大学の掲示板の横を歩いていたとき、そこに貼られた英語の案内プリントを見て「ぜんぜん読めねえけど“ホームワーク”の意味はわかる!」と叫んだ人のことを、その瞬間に好きになったことがあったから。
■インターネット・ミームの元彼
もちろん反対に、あるひと言が引き金になって相手のことを大嫌いになってしまった、という話もある。
Kという女友だちは、当時付き合っていた恋人の言葉遣いに漠然と不満を抱いていたという。具体的には、何を見ても「エモい」「ヤバい」を連呼したり、インターネット・ミームをそのまま口に出したりするのがなんとなくいやだった。けれど、まあ別れるほどのことでもないし、と気にしないようにしていた。
しかし彼女が友だちのカップルと4人でドライブに行った日、恋人の口から決定的なひと言が出てしまう。友だちカップルの彼氏のほうが、ふざけて「〇〇ちゃん(自分の彼女)好きンゴ!」と叫んだのを聞いたKの恋人が、かぶせるように「ンゴ!!」と叫んだのだ。
その瞬間もうぜんぶ駄目だった、とKは言う。彼女いわく、友だちの彼氏が最初に口に出したなんJ語は、照れ隠しの意味もあっただろうし可愛らしいと思えた。けれど、わざわざそれを繰り返して叫ぶつまらなさ、主体性のなさ、よりによって「ンゴ」だけを局地的に切り取るセンス、すべてが彼女にとっての我慢の限界を超えていた。そのドライブのあとすぐに、彼女は恋人と別れてしまった。
この話をKから最初に聞いたとき(失礼を承知で言うと私は爆笑してしまったのだけど)、彼女が理不尽だとは微塵も思わなかった。冒頭の「レーダーホーゼン」の主人公の女性にとって、夫と同じ体型の人が目の前で採寸をされている様子が憎しみを自覚する引き金になったのと同じように、おそらくそのできごとが起こるずっと前から、相手に対する些細な違和感や嫌悪感はもともと彼女(たち)のなかにあったのだ。
Kが恋人に「エモい」と連呼されるたびに漠然と感じていた不快さを、「レーダーホーゼン」の彼女はたぶん、自分のために土産を買ってきてくれと夫から命じられたときにも感じていたのだろうと想像する。
人が発するなにげないひと言には時々、一瞬でその人の倫理観や審美眼を白日の下に晒してしまうようなおそろしい力が宿ることがある。何よりも怖いのは、その言葉を発しているとき、当人にだけはそのひと言が持つ効力が決して自覚できないということだ。
無自覚なひと言は本当に驚くほど軽やかに人を恋に落としたり、はたまた別れを決定づけたりしてしまう。
■地雷を踏み抜いた2文字
もちろん、自分自身がその「ひと言」の当事者にならないとは限らない。
何年か前、知人とふたりでちょっといいレストランでディナーをしたことがある。その人と会うのは2回目だったが、デートと言えばデートだしそうでないと言えばそうでないですよね、みたいな微妙な空気が場を漂っていた。けれど、食事もお酒も美味しくて、会話もけっこう弾んでいたように思う。
相手のグラスが空いたとき、私はなんの気なしに尋ねた。「つぎ、泡とかどうですか?」
その瞬間、相手がほんとうに一瞬だけ、見下すように口角を上げたのが見えた。
「シホさん、スパークリングのこと『泡』って呼ぶ人なのけっこう意外です」と彼は半笑いで言い、そのまま何事もなかったかのように食事は続いた。けれど、その2文字が彼のなんらかの地雷を踏み抜いてしまったのはあきらかだった。頭が真っ白になった。
私にはもう、そのあとの会話の記憶がほとんどない。彼とは結局、それから2週間くらいで会えなくなってしまった。










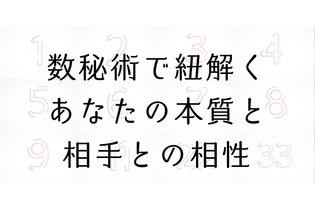










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。