
「どうしてあなたは強くなろうとしないのですか?」
悩んでいる人、加害を受けている人に「もっと、こうすればいいのに!(よかったのに!)」なんて言葉をかけたことはありませんか? 素朴で、優しい提案や疑問だとしても、その言葉は時として、人を追い詰める刃に変わります。そんな感覚を実際に抱いたことがあるというエッセイスト・生湯葉シホさん。そのお話しを綴っていただきました。

何年かぶりに髪を染めたら、似合わなかった色の服が似合うようになった。フェイスラインと髪の内側全体に入れてもらったゴールドは、思っていたよりもずっと目立つ。人に会う機会の減ったいま、自分の顔を鏡や写真でまじまじと見ることも少なくなったけれど、シャンプーをするとき、仕事中に落ちてきた髪をかき上げるとき、あ、金髪、と思う。ふだん忘れているぶん、うれしさは想像を小さく裏切るかたちで不意にやってくる。
人混みのなかを歩いているとき、ぶつかられそうになる前にすっと道を譲られる日が増えたことにはしばらくして気づいた。知人に話すと、「よかった。黒髪だとどうしてもなめられるから……」と喜んでくれる。彼女も子どもを産んだばかりのとき、髪を明るいピンクベージュに染めていた。金似合ってるよ、と笑ってくれる彼女のことをやさしいと思った。同時に、黒髪で小柄の人間が誰にもぶつかられず人混みを歩く、それだけのことが難しいだなんてどう考えたっておかしいじゃないかと、泣きそうなほどの怒りが湧いてくる。
■好きだっつってるだろうがよ
「僕はミュージシャンを目指してるんでしょうか?」
むかし、人にそう聞かれたことが忘れられない。
たまたま入った喫茶店の奥で、ピアノを弾いていた人だった。彼はそこで何曲か有名なJ-POPを演奏し、常連客から拍手を受けていた。店主のはからいで、週末だけそこで小規模なコンサートを開いているという。ふだんは調理場担当のアルバイトだけれど演奏のある日だけフロアに出てくるんです、演奏が好きで、と言う彼に、いっしょにいた私の友人が、「じゃあミュージシャン志望なんですか」と聞いた。すると彼は一瞬、あきらかに困ったような、呆気にとられたような顔をして、「どうなんだろう……僕はミュージシャンを目指してるんでしょうか?」と私を見た。それは責めるようなトーンではなかったけれど、責められてもおかしくないようなことを言った、とすぐに気づいた。
私たちはしどろもどろになってしまって、聞かれてもいない曲の感想をべらべらとしゃべり、すぐに店を出た。帰り道、「迂闊だった」と友人が言った。彼の年齢を聞き、アルバイトをしながらピアノを弾いているという境遇を聞いて、失礼なことを言ってしまったと。すぐにそう言える友人のことが誇らしく、まぶしくもあった。ミュージシャン志望なんですか。その言葉は友人が言わなければ、隣に座っていた私が口にしていても、なんらおかしくはなかった。
そのすこし前に読んだ作家の本のなかにあった、「ライトノベルが好きなせいで学校でいじめられている」という読者からの悩み相談を思い出す。「僕はむかしから海外文学ばかり読んでいたけど、それでいじめられることなんてなかった。あなたも海外文学を読んでみたら?」という作家の回答に、私の腸は煮えくりかえっていた。ライトノベルが好きだっつってるだろうがよ。読者を勝手に憑依させ、怒りを代弁するかのように頭のなかでそう唱えていた自分の声が、友人と別れてひとりになった途端、信用できなくなった。なぜ彼を勝手に、“目指している人”に仕立てあげていたんだろう? 演奏が好きだっつってるだろうがよ。
■「引き上げようとする力」の強引さ

もうすこし寝ていたいのに布団を無理やり剥がされていた、子どものころの日曜日の朝を思いだす。起きなさい、いい天気だよと言われるたび、鬱陶しくてたまらなかった。それがやさしさなのはもちろんわかっている。けれど、休みの日にただひとりで眠っていたいというささやかな願望を、起きたほうがいいに決まっているでしょう、と否定されるたびに苦しかった。くりかえすけれど、まちがいなく善意からの言葉なのだ。それでも、引き上げようとする力はときどき強すぎて、こちらに口をはさむ隙すら与えてくれないことがある。
金髪にしたくなったから金髪にした。けれどこれまでは、黒髪でいたかったから黒髪でいたのだった。派手な髪色は自衛になるよ、と人から言われたりSNSで目にしたりするたびに、きっとそうだろうな、と思いながらもそうしなかったのは、染めるための経済的な余裕もなかったし、なにより、黒髪で着たい服がたくさんあったからだった。
「金髪にしたらレジで順番を抜かされなくなったし、人にぶつかられなくなったんですよ!」と嬉々として言い、周囲が祝福してくれるのは気持ちいい。なんらかの強さを身につけたような気にもなる。けれど、私は自分が同じことを黒髪の友人にさえあまりにも無邪気に言ってしまいそうで、それがたまらなく怖いのだ。震えながら渡り終えた揺れる橋をふりかえって、「早くきなよ!」と向こう岸の人たちに明るく言い放つような暴力性が、すくなくとも私のなかには確実に眠っている。
ここが戦場でないのなら、丸腰でいることを誰も非難しないはずなのに、と思う。自分のありたい自分が頭から足の指先までまるまると武装した姿であっても、反対にどんなかたちの武器も持たない姿であったとしても、ほんとうは誰にも口を出す権利なんてないはずなのだ。ただ、自分の思う自分のありたい姿からなにも足したり引いたりせず、そのままで歩いていたいというだけなのに。「私はそうした」という経験、あるいは「私はそれを手に入れた」という感覚が「どうしてあなたはそうしないのですか?」という素朴でおそろしい疑問に反転するまでの距離は、たぶん、想像しているよりずっと短い。
おおげさな、と自分のことを笑いそうにもなる。けれどそのたびに、あのときの喫茶店の彼の目を思い出さずにはいられない。僕は、ミュージシャンを目指してるんでしょうか?










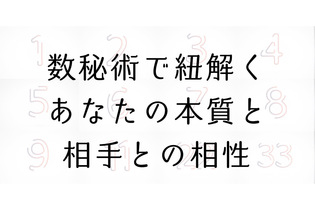










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。