私がかつてあきらめてしまったビブラート
「私の怠惰が、ずっと好きだったバイオリンを嫌いにした――」。好きでい続けられること、変わらず仲良しでいられることは、当たり前のことなのだろうか。その裏には目に見えないさまざまな努力が積み重なっているのではないか。文筆家・生湯葉シホによる怠ることと続けることについてのエッセイです。

教室の扉を開けるときはいつも音を立てないようにしていた。そうっと入っていくと、半分開いた障子のむこうで、先生が前屈みになってバイオリンを弾いているのが見える。先生がレッスンを担当する水曜日はいつも教室じゅうが暑かった。それは「東京人は寒さに強くて意味がわかんねえ」が口癖の先生がちょっと信じられないくらい暖房の温度を上げていたからというのもあるけれど、なによりパガニーニを弾く彼が発する熱気、のようなものが凄まじかったからだ。ひとりでいるときの先生は銃を連射するみたいにバイオリンを弾いた。気づかれないようにその様子を見ていると、どこかでようやく「うおっびっくりした」と顔を上げる。毎回それを合図にレッスンがはじまった。
そのころの私はバイオリンのレッスンに通うのが憂鬱だった。幼稚園から習っていた教室長の先生が家庭の事情で水曜日に来られなくなり、先生が替わったばかりだったのだ。新しい担当となったその 先生は若く、口は悪いけれどやさしいのは話せばすぐにわかった。ただ、45分のレッスンのうち、30分くらいをこまごまとした基礎練習にあてる。私にはそれが退屈でしかたなかった。
波立てるように音の高さを揺らす、ビブラートという奏法がある。先生は私に「一見ビブラートができてるっぽいんだけど、それはビブラートじゃない」と繰りかえし注意した。でもこれでずっとやってきちゃったんです、と私が反論すると、「記憶消して」と無茶を言う。私は指先だけで弦を震わせているけれど、腕全体で揺らすようにしないと、いつかもっと難しい曲を弾くようになったときに立ち行かなくなる──というのが先生の言い分だった。
子どもの私はそれをまるきり無視して、自己流のビブラートをつづけていた。だって現に弾けているし、なんの問題もないと思った。するとしばらくして先生の言ったとおりのことが起きる。発表会用の難しい曲を練習することになったときに、曲のテンポに指が置いていかれるようになってしまったのだ。ビブラートのやりかたを矯正しなかったからだ、と自分でもわかったけれど、それを一からやり直すような情熱は私にはなく、曲はうまく弾けずじまいだった。
あるときからなんとなくバイオリンが楽しくなくなり、大学生になって勉強とバイトが忙しいから、とそれらしいことを親に言って教室をやめてしまった。しかたないね、と親も先生も納得してくれたけれど、そんなのは嘘だったことを自分はよく知っている。あれは単に私の怠惰だった。私の怠惰が、ずっと好きだったバイオリンを嫌いにした。
■「気づいたら今日になっていたんです」
気づいたら今日になっていた、という表現に出会うことがある。仕事で人にインタビューをしているとときどき耳にする言葉だ。「無心で漫画を描き続けてきて、気づいたら今日になっていたというか……」「目の前の仕事に四苦八苦しながらやってきて、なんか、いつの間にかこんなに経ってたんです」。ちがった分野のプロフェッショナルが口をそろえてそう言うことが、この仕事をはじめたばかりのときは不思議だった。もちろん、現状維持は死とばかりに、出世魚のように姿を変えながら歳を重ねてきたと語る人もなかにはいらっしゃる。けれど、「転機は」とか「印象に残っているエピソードは」とか、いかにも取材記事のフックになりそうな質問をしたときに、「正直に言うと……」という前置きのあとで語られる「気づいたら今日になっていた」には、謙遜とはどうも思えない飄々とした重みがあった。
「ずーっと枝やら土やらいじってて飽きません? ってよく聞かれるんですけどね」。整った日本庭園を前に、むかし話をお聞きした造園家のかたがこう言ったことがある。
「木とか草とかって、放っておいたらものすごい茂るんですよ。ものすごい茂ってる草を想像してください……しました? あのね、その10倍は茂ります。変化ってなにか手を加えるから起こることだって思うでしょ。ちがうんですよ、なにもしなくてもどんどん勝手に変わるんです、自然って。だからそれを“維持”しようと思ったら、ちょっとずつちょっとずつ手を加えなきゃいけない。その手間みたいなものが、みなさんから見たらおんなじに思える景色をつくってるんです」
彼はさも当たり前みたいな顔でそう言ったのだけれど、私は、手に持っていたICレコーダーを握りしめて停止させてしまったほど衝撃を受けた。いつも同じ帽子を被っていることを人に指摘された友人が、「自分ちの犬の面倒みてて『あ~もう育てんの飽きたなあ』って思わなくないすか?」と言いかえすシーンを見たことがあるのを思い出す。「まあ飽きないですよこの仕事は」と目の前の人に言われ、どんな言葉で相槌を打てばいいのかわからなかった。自分にはこの言葉に応える資格がまだない、とも思った。
■「もろくない人間関係なんてこの世界にあんのかよ」
なんら長続きするものを持ち得なかった私が唯一、歳を重ねるなかで(ほんとうにすこしずつだけれど)わかってきたのが、人と人との関係もたぶん同じなのだろうということだ。なにもしなくてもずっと仲良し、なんて都合のいいことは起こらない。自分にとってそう感じる関係があるとしたら、おそらくそれは相手が継続のための努力をしているのだ、自分には見えないところで。血縁や約束は決して永遠を保証しない。
大好きな小説、『ナイルパーチの女子会』(柚木麻子)のなかにこんな台詞がある。
古くからの女友達との良好な関係を維持することだけに人生の情熱を注いでいる真織という女性が、女同士の友情なんてもろいものだと馬鹿にする夫に「お前は満たされていないのだ」と言われ、吐き捨てるように叫ぶ台詞だ。私はこの言葉を読みかえすたび、思わず立ち上がって真織に拍手を送りたくなってしまう。
女友達や職場の同僚たちに見せる明るい顔の裏で冷酷さも隠し持つ、決して褒められたキャラクターではない真織。けれど、彼女が地元の女友達を自分の結婚式に招待するのをなにより楽しみにしていて、そのために座席表や引き出物にまでこまかく気を配っているという途方もない労力に、夫は気づかないのだ。旅行に行くたびに職場へのお土産を買ってきては、気の利いたメッセージをひと言添えて給湯室に置く真織。
燃えつづける火の下には、その火を絶やさないために、人知れず油を注ぎ足す人がいつもいる。これが努力ではなかったらなんなんだと、『ナイルパーチの女子会』を読むたびに泣きそうになる。

■お気に入りの靴を履き続ける努力をしているか?
ある映画の特典映像で、愛とはどのようなものだと思いますか? と尋ねられた制作陣のひとりが、こんな答えかたをしていたのも覚えている。「お気に入りの靴を修理してまた履くよりも、新しいのを買うほうがずっと安上がりですよね。でも、それでもお気に入りのを履き続けたいと思いませんか?」
思います、と心のなかで返事するとき、先生が弾いていたあの美しいパガニーニを思い出す。私が陰からこっそり見ていた先生は、いつも汗だくで腕を震わせていた。およそ先生らしくない先生の、獣みたいなこわい顔。南国のようなあの第2レッスン室から聴こえてくる、私がかつてあきらめてしまったビブラート。











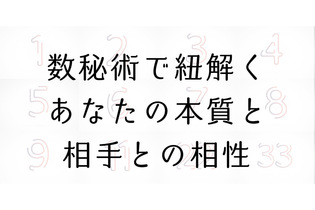










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。