
自転車のうしろから手を離さないでいること
誰かの孤独を救おうなんておこがましいかもしれない。ひとりで絶望や悲哀を抱える人のそばにいることは難しいのかもしれない。けれど、その一歩手前のワンシーンにだけでも居合わせることができたら。文筆家・生湯葉シホによる誰かの不安に“居合わせる”ことについて綴ったエッセイです。

フリーランスになる前、ライターとして何年かアルバイトをしていた会社では、各チームの上長が月ごとにチーム目標を立てるという決まりがあった。Webメディアの記事制作を主な業務とするその会社では、新規顧客の獲得や高いPVが見込めるコンテンツをつくることが目標として設定されることが多かったのだけれど、ある月に、同じ編集チームの先輩がふしぎな目標を立てたことがある。
「これはチームで達成してほしいというより、僕がみなさんに対して伝えておきたい目標なんだけど……」と先輩は前置きしたうえで、「居合わせる」と言った。8人ほどのチームメンバーが全員きょとんとした顔になったのを見た彼は、「みなさんには萎縮せずにいろんなチャレンジをしてほしい。僕はそれがうまくいこうがいくまいが、必ず“居合わせる”。だからできる限りみなさんもそうあってほしい」というようなことを、ゆっくりと時間をかけて、全員の顔を見ながらつぶやいた。それからはずかしそうに「以上です、解散」と言った。
ずいぶん前に働いていた会社のたったひと月のできごとだから、私たちのチームがその目標をどんなふうに受け止めたのか、そして“居合わせる”というあまりにも抽象的な目標がどのくらい達成されたのかは、正直に言ってあまりおぼえていない。けれど、なんかへんな目標だったなあと当時を振りかえるたび、仕事で困ったことが起きると必ずその先輩が一緒に悩んでくれたこと、そして、まとまりのないチームだったわりに彼がチームメンバーからとても慕われていたことを思い出し、なつかしい気持ちになる。電話に出るのがすごく下手なひとで、彼が電話対応をしているシーンにたまたま出くわすことがあると、がんばれ、と近くで密かに応援せずにはいられなかった。ほかのチームメンバーも、たぶんだけれど同じだったんじゃないかと思う。
■「話を聞いてくれるだけでいいんだ」
ついさいきん、担当編集のOさんと雑談していたら、『きのう何食べた?』(よしながふみ作)を読んだばかりだと言われてうれしくなった。2019年にテレビドラマ化もされて話題になった同書はまちがいなく、自分の人生のなかでいちばん多く読みかえした漫画のひとつだ。弁護士の筧史朗(シロさん)と美容師の矢吹賢二(ケンジ)のふたり暮らしを、主にシロさんがつくる食事や、家族や職場の同僚といったふたりを囲む人々とのコミュニケーションを中心に描いている。
「シロさんのお父さんが癌の手術で入院することになったときに、シロさんがケンジに『父親の事で何かあった時 話聞いてもらってもいいかな』『話を聞いてくれるだけでいいんだ』って言うシーンあるじゃないですか。あれ、すごくいいなと思って……」とOさんに言われ、うんうんと何度もうなずいてしまった。
背景をすこし説明すると、このエピソード(15話)の時点でシロさんとケンジは共に40代前半。人当たりがよく、温和でおしゃべり好きなケンジに対し、シロさんは几帳面で理屈っぽく、やや短気な性格でもある。連載初期のシロさんは特に、友だちのなにげない愚痴をダラダラと家で喋るケンジに対して、「じゃあ結局どうしたいんだよ!」と怒るようなタイプだった。半泣きのケンジに「ただ話を聞いて欲しかっただけだもん……」と言われたシロさんは、「またやっちまった」と内心ハッとする。シロさんはこういうとき、はっきりとはケンジに謝れない。ただ、些細なことでケンジとぶつかるたびに、自分の合理的であるがゆえの短絡さがケンジを追い詰めてしまうケースがあること、そして、ケンジのおおらかさにじつは憧れてもいること──などが示唆される。
職場の同僚たちにもカミングアウトをしているケンジに対し、シロさんは世間から「ゲイっぽく」見られることをなによりも嫌がるタイプだ。ひとりっ子のシロさんにとって、自分の境遇や生活について嘘をつかずに話をすることのできる相手は、ケンジを除けばごく限られた数名しかいない。そしておそらく、弁護士という職業的性格が、「話をする/聞く」という行為を問題解決に至るための手段として捉える彼の考え方に拍車をかけている。シロさんにとって「友だちの行動にちょっとだけ違和感を覚えたんだけど、でも、基本的にいい子ではあって……」というケンジのどっちつかずな愚痴は「結局どうしたいんだよ!」に回収されてしまうし、「このごはんまたつくってね」というリクエストは「冷凍しといたからそれ食べろ」という的はずれな応答で解決されてしまう。
けれど15話では、そんなシロさんがただ「話を聞いてくれる」という行為に価値を見出し、その欲求をわざわざ言葉にする姿が描かれる。このシーンを美しいと私が思うのは、シロさんがパートナーであるケンジを信頼して弱さを見せる姿が初めて公にされたからというのはもちろん、彼が“会話は問題解決のためにするもの”という(多くは社会のなかで男性に降りかかる)暗黙の要請を振りはらい、自主的にその役を降りた瞬間が描かれているからだ。
シロさんはおそらく、コミュニケーションが目的地への一本道をずんずん進んでいくようなやりとりだけで成り立っていないことを頭ではわかっていたはずだ。ここで彼が言った「話を聞いてくれるだけでいいんだ」という台詞はいわば「どこに通じているかわからない道を一緒にうろうろしてほしい」というお願いで、その相方にケンジを選んだという宣言でもある。実際に“話を聞く”段になると、ケンジは「大丈夫?」とか「どうしたの?」ではなく、ただ「シロさん」と名前を呼んで会話の襷を相手に完全に受け渡すのだけれど、その塩梅も抜群にいい。
このエピソードの一連のコミュニケーションを見るたび、シロさん、ほんとケンジに出会えてよかったね……という気持ちが極まり、いつも涙ぐんでしまう。信頼している人が目の前にいるだけで救われる思いがあること、そして、人と一緒に過ごす時間だけが人を変えていくということを、こんなにも鮮やかに描いたシーンはほかに知らない。
■なぜか後輪から手を離さなかった父

同じような気持ちを私が初めて現実世界において明瞭に感じたのは、記憶している限り、小学生のときのことだ。家の近くの荒川土手で補助輪を外した自転車に乗る練習をしているとき、運動が人一倍できない私の自転車の後輪を支えてくれていた父は、(これを人に言うと驚かれるのだが)いちどもその手を離さなかった。
いま思えば、ああいうのってこっそりどこかで親が手を離し、「いまひとりで乗れてるよ!」と後方から叫んで子どもに成功体験を積ませるのがセオリー(?)なんじゃないか、と笑ってしまいそうになる。けれど、親子そろって臆病な父と私はオロオロしながら自転車にしがみつきつづけ、県境を越えていつの間にか板橋区から埼玉県に入ってしまうばかりで、何日経っても練習は上達しなかった。結局私は小学生のあいだに自転車に乗れるようにはならなかったのだけれど、あのとき感じた“自転車のうしろをたしかに持たれている”感覚だけは、大人になっても体に残った。
母に言わせれば「親ばかすぎる」という父のあの謎の併走に私は感謝しているし、大げさかもしれないけれど、私が大人になってからもパートナーや信頼する友だちに自転車のうしろを持ってもらうようなこと、言い換えるなら、ただ一緒にいてもらう、話を聞いてもらうということをあまり遠慮しない性格でいられているのは、あの経験があったからかもしれないと思う。同時に、たとえば『なに食べ』の初期のシロさんのように、それをしたくてもなかなかできない人がいることも感覚としてわかるから、かつて先輩が掲げた“居合わせる”を、自分の指針として胸のなかに置いてみたりもする。
いや、自分の不安には自分ひとりで向き合うしかないじゃないか、ただ誰かにいてもらうなんて気休め以外の何物でもないじゃないか──と思う人もいるかもしれない。残酷だけれど、それはおそらくまちがいない。悲しむこと、怒ること、償うことの極地はすべて、言葉を失う苦しみだと思う。どんな言葉も伝わらず、伝えようとする気力も失い、言葉の無力さを痛感するようなとき、つまりひとりでは到底抱えきれない荷物をひとりで背負わされるような状況にこそ、人は絶望する。そして、おそらくどんな人もいずれ、どこかしらの地点で、その孤独にさらされるときがくる。
矛盾しているように聞こえるかもしれないけれど、だからこそ他者が要るのだ。孤独の渦中にいる人の心をほんのすこしでも温められる可能性があるのは、自分以外の誰かが自分といてくれたときの記憶だけなのだと思う。だからせめて、孤独がやってくる前のワンシーンにだけでも私は居合わせたいと思うし、あなたにも居合わせてほしい、と思うのだ。










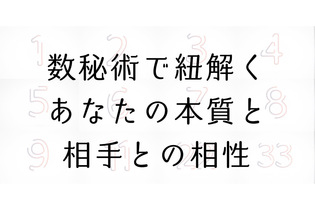










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。