
ずっと「母の料理」が正解だと思ってた
母親の作る料理にとらわれて、 “手間ひまをかけた美しくておいしい食事”を家庭料理のゴールに置いていたという生湯葉シホさん。そんな彼女がすこし自由に料理を楽しめるようになったきっかけを綴ってくれました。きっと、それぞれの料理に楽しさは宿るし、それぞれの食事においしさは詰まっている。

なにかを炒めたり煮込んだりしているとき、鍋の底をじっと見ている。あまりにじっと見るものだから「なにかいるの」とギョッとされることもあるけれど、ただ火にかけられた食材を見ているだけだ。場から離れてほかの作業をする、ということが私にはできない。複数の工程を同じ時間軸に存在させるのが苦手で、油断して洗い物でもはじめようものなら鍋を焦がしてしまう。だからそういうことはぜんぶあきらめて、菜箸を時折差し入れながら、ただ見守る。
油を吸った茄子をとり出し、すこし固くなりかけているように見える豚肉もとり出し、残った野菜をまたじっと見る。見られている野菜もちょっといやかもしれないと気の毒になるくらい見る。むかし、賽の河原で石を積む人をひたすらに監視しつづけては頃合いを見てそれを崩し、また監視するという作業をループする鬼の話をなにかで読んだことがあるけれど、たぶん私にはああいう係は向いているだろうなと思う。
ひとつの料理が完成したらその鍋を遠いところに置き、また別の鍋で同じような作業をくりかえす。同時にお湯を沸かしておけばよかったな、と一瞬だけ反省するけれど、工程が進んでゆくにつれ綺麗さっぱり忘れていく。ぜんぶ終わる頃には最初のほうに作った料理が冷めきってしまうので、おかずは多くても2、3品が限界。おおよそ毎日こんなふうにして、私の夕飯はできあがる。
■「偽の土井先生」の声が頭から離れなかった時期のこと
20代のはじめくらいまで、人にキッチンに入られるのがとにかくいやだった。隠れて機を織るツルのように「絶対に入ってこないで」と念押ししてドアを閉めきってからじゃないと、料理ができなかった。
作業の一つひとつ、つまり煮たり焼いたり味つけをしたりがそこまで不得手というわけではなかったと思う。ただ当時からとにかくマルチタスクが苦手だったから、手際の悪さを友だちや家族に見られるのが苦痛だった。加えて、実家暮らしだったその頃は日常的に料理をしていなかったこともあって自分の作るものに自信がなく、人に料理を出すときは常に長ったらしい言い訳をしていた。ちょっと失敗したと感じるときは「レンジ使ってみたんだけどやっぱりちゃんと茹でないとだめだね……」などと一方的に反省点を口走り、まあいつもどおりの味だな、と感じているときでさえ「薄いとか濃いとかある……?」と神妙な顔で相手に聞いていた。ひと口目を食べるときに仏頂面じゃなかったことって、たぶんないんじゃないかと思う。
結婚・離婚を経験し、昨年の春に人生初のひとり暮らしをはじめてからは、自炊をするにあたって料理家の土井善晴さんによる和食アプリのレシピを参考にするようになった。誰にも見られずにひとりで作ってひとりで食べる料理は思いのほか気楽で、ああ、私は思っていたより料理が嫌いじゃないのかもしれないな……と最初は思った。土井先生自らが料理のポイントを教えてくれるアプリの動画の穏やかな口調も、料理へのプレッシャーを軽減してくれるようでとても心地よかった。
しかし、様子がおかしくなってきたのは夏だった。動画をくり返し見たおかげで、その頃には土井先生による料理のポイントがほとんど頭に入っていたのだけれど、材料を切ったり混ぜたりしているとき、「とうもろこしいいですねえ、この時期が旬やからねえ」といったいつものやさしい声に混じって、「あ~なんだかえらい小さめに切りはるなあ」とか「その豆腐もう水切りしてはる? ずいぶん長いことそこに置いてますけど」という幻の声が自分の頭のなかにだけ聞こえるようになってきていた。
ど、土井先生……? と心がざわつく。でも、こわくなってアプリを確認すると、(本当の)土井先生はいつだってやさしい。むしろ「種なんかとりたい人だけとったらよろしいわ」とか、常にこちらがホッとするようなことを言ってくれているのだった。私はそれを確かめるたびに土井先生に一瞬抱いてしまった猜疑心を解き、なんでこんなこと考えちゃうんだ、と泣きそうな気持ちになった。けれど困ったことにこの「偽の土井先生」現象はしばらくつづき、私を困惑させた。
■ずっと「母の料理」が家庭料理のゴールだと思っていた
そのとき私に聞こえていたのが母の声──というより母の言葉だったのだと気づいたのは、ごく最近のことだ。
母は料理が得意だ。実家で彼女が作ってくれていた料理は、魚をまるまる使ったアクアパッツァとか、自家製ソースの煮込みハンバーグとか、野菜を何種も盛り合わせた彩りのいいサラダだとか、いま振り返るとちょっと驚愕してしまうほど手の込んだものだった。昔から夕飯のたびに感激して「ほんとうにおいしいねえ」と伝えてきたし、母も母で「我ながらそうなのよねえ」と平然と答えていた。あれ、ありがたかったなあと思う気持ちはいまもまったく変わらない。
ただ、母には私がする料理に口を出さずにはいられないところがあって、その言い方がけっこうきついのは、いつもしんどかった。「なんでそんな包丁の持ち方するの?」とか、「盛りつけるセンスないねえ」と言われるたび、もともとあまり強くない自尊心がジリジリと削られていくのを感じていた。大人になったいまは、自分にも他者にも厳しい母の性格をそういうものとして受け入れられるようになったし、心配の裏返しできついこと言っちゃう人なんだよな、というのもわかってきた。けれどやっぱり、母に自分の料理の仕方を否定され続ける経験はつらかったし、そのつらさから逃れようと、母が指南する「正しい料理の仕方」をインストールしなければいけないと強迫的になっていた側面が私にはあるのだと思う。自分にとって「母の料理」はいつしか、目指すべき家庭料理のゴールのようになっていた。
そう気づいたきっかけはふたつある。ひとつは、いまのパートナーがうちでときどき料理を作ってくれるようになったこと。彼が料理にはまった入り口は料理YouTuberの動画らしく、レシピ動画が更新されるたびに「カレーうどん食べたい人いる?」などと言いながらキッチンに立つ(私は食べたい人としておとなしく待っている)。料理の様子をたまにうしろから覗いてみると、時折スマホを確認しながらもおおむね自由に、鼻歌とか歌いながら材料を切っていて、ああいいなあと思う。そうやってのびのび料理したほうが絶対楽しいよな、私もそうなりたいなあと、彼を見ていたらごく自然に思うようになった。
それからもうひとつは、ある料理家さんと仕事でご一緒したときのこと。話のなかで、「世間にはこんなにもたくさんの時短レシピや冷凍食品も溢れているのに、私たちは手間のかかっていない料理のことをどうしていまだに卑下しちゃうんですかね?」と自分自身の悩みが半分混じった質問をしたら、その方が「手間ひまをかけた料理は当然おいしいけど、そうじゃない料理にもまた別のシンプルなおいしさがあるってことを実感できていないんでしょうね。いま食べているものをおいしいと感じる力が足りないんだと思う」とさらりとおっしゃった。そのとき、ほんとうにそうだ、と正面から殴られたような気持ちになった。
思い返してみれば、母が教えてくれたレストランみたいな料理を起点に、それを息苦しく感じて適当にアレンジして作るようになったパスタとか、バレンタインデーの前夜に半日かけて作ったザッハトルテとか、なにもかもが面倒になってわかめと塩だけで作ってみた雑炊とか、私は私なりにいろいろ料理を試してきたじゃないかという記憶が波のように押し寄せてくる。そのなかで、ちょっとこれは手間に見合わないから二度と作らないだろうなと感じる料理や、面倒だけどたまには作って食べたいなと感じる料理、人にはちょっと出しづらいけど私はまあ好きだなと感じる料理もあったことを思い巡らせ、その日のコンディションに応じて自由なルートを選べばいいんじゃないか、とはっと気づいた。

結果、私はカルガモの親子が車道を横断するときのようなスピード感で夕飯を作るようになって今日に至る。こんなに時間かけないほうがいいのかなあとうっすら思いつつも、自分にとってちょうどいい味と量をこしらえようと思ったら私の料理はこのくらいかかるのだ、と徐々に開き直れるようにもなってきた。人がいるときは手伝ってもらうので、だいたい半分くらいの時間でできるということもわかってきた。
ついこのあいだ、ワクチン接種の副反応で何日も起き上がれず困っていたら、母が車で10分ほどの実家から作った料理を持ってきてくれた。お礼を言って母を見送ったその日の夜、ありがたさと申し訳なさのなかでタッパーをあけると、生ハムやらシャインマスカットやらが美しく並び、ミントの葉が飾られたサラダが入っていた。こんなの自分で作れるわけないだろうさすがに、私はなんでこれをずっとゴールだと思ってたんだよ、と思わず笑ってしまう。同時に、私の卑屈さが勝手に生み出した土井善晴の幻を思い出し、土井先生ほんとうにごめんね、と謝りたくなる。
母の料理は当然のようにとてもおいしくて、「すごいねえ」と何度もLINEをした。母からは「そうなのよ」と返事がくる。母の料理を食べさせてもらえることは私にとって変わらず幸せな体験だけれど、母のような料理を作りたいとはもう思わなくなった。この豪華なサラダを食べ終わったら自分でまた2時間くらいかけてなにか作らなきゃなのか、面倒だなあ……という思いが一瞬頭をよぎる。けれど、面倒であることは仕方ないとして、私は自分で作る味噌汁やら餡かけ野菜炒めやらの味がけっこう好きなのだ、いまは。そう思えるようになってから、料理をしているときに誰の声が聞こえてくることもなくなった。










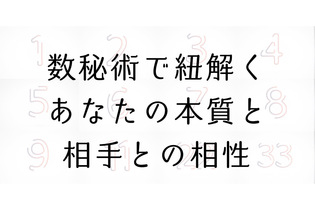










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。