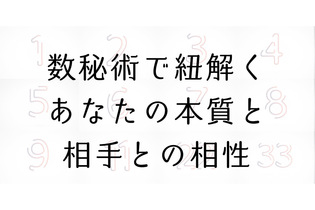「良さを言葉にできるということは、置き換え可能であること」
10連休のリレーエッセイ企画「忘れ得ぬあの人の言葉」。かつて好きだった人から受け取った、忘れられない言葉の想い出を振り返ります。今宵は、ミスiD2019文芸賞でモデル・ライターのいとうさんが綴る、“片思いなのか両思いなのかよくわからない間柄”だった人から言われたひとこと。

何かの良さを言葉にできるということは、それが何かしらに置き換え可能であると認めることだ。
例えば、私はフライドポテトが好きだけど、それは「しょっぱくて」「簡単に食べられて」「ジューシー」だからだ。なるほど、だからその3つの要素さえ揃っていれば、別にフライドポテトじゃなくても私はきっとその食べ物を好きになる。
だから安易に良さを言葉にできるということは、すなわちその存在が唯一無二であることを否定していることになる。
そして、私は、この言葉をとある人に2回言われたことがある。
■あの映画はちょっと言葉には変えがたいから

もう3年前のことになる。その人に初めて出会ったとき、ぼんやりとあァ、「人あたりが良さそうな顔」をしているなあ、と思ったのを記憶している。笑うと目尻にシワがよってくしゃくしゃっと人懐っこい笑顔になる。あーこういう人を人気者というのか……。
そんなことを考えながらふとガラス窓を見やると、猫背、真っ黒で重い前髪、引っ込み思案……ぼっち要素詰め合わせパックのような特徴を揃えて教室に隅にいるだらしない女の子が映っていた。あー違うなんか違う。彼は私とは縁遠い世界線の人だった。
しかし、現実は面白いもので、ひょんなことから実はお互い異常なまでの根暗で、それを人前で器用にしまえるか否かの違いだったことがわかり、次第に言葉を交わすようになった。好きな音楽も趣味も違うけど、言葉が好きなことは共通していた。私は小林賢太郎のシニカルな言い回しを紹介して、彼からはカタカナばかりでよくわからない建築家の名言を教えてもらった。言葉が好きな彼が好きだった。
初めて会ってから半年くらい経って、彼とはよく一緒にいるようになった。どこかに出かけるでもなく、ふたりで遊ぶときはもっぱら映画を観ることが多かった。
まだサブスクリプションなんて言葉も知らなくて、Netflixなんてハイパー快適なサービスもそこまで流行ってなかったから、近くのTSUTAYAで気になる映画をふたりで選んで、ベッドと机と本棚と洗濯物で6割を占めているワンルームのきったない部屋で、どちらからともなくノートパソコンにDVDをかけるのだ。
ちょうど23時くらいの夜と深夜の間。安いチューハイを片手に引っ掛けながら、14年製のMacBookのガサついた音響の中で、ちょっと青白い小さな画面を凝視して2時間をぼんやり過ごした。
映画を観ている時間には私が勝手に敷いた暗黙のルールがあった。それは「決して映画の間は喋らない・干渉しない」こと。
私にとって映画は現実からの逃避であり、この2時間だけは普段暗くて惨めな自分という存在について考えなくてもいい時間だからだ。2時間は私だけの時間。私の大切な幸福の時間。それを彼に話したことはないけれど、彼からも話しかけられたことはないし、触れられることもなかった。2時間の間でお互いの缶チューハイはあまり減ることがなかった。
もうひとつの暗黙のルールは、映画を観た後に何がよかったか、どこが微妙だったかを語り合うこと。私たちが観る映画は、御曹司の全米国民的ヒーローが活躍して「はい、俺らに立ち向かうやつ全員敵、結! 滅!」みたいなわかりやすい話じゃなくて、どことなく陰鬱で勧善懲悪がはっきりと分かれていない葛藤と怠惰と暴力と執着の面倒くさいヒューマンドラマばかりだった。だから、語り合うことはたくさんあった。私は、映画の直後の興奮と若干の冷静さとの間で語られる彼の持論が本当に好きだった。
そんな中、一度だけ映画を観ても彼の口から感想が出てこなかったことがある。
いつもどこか俯瞰して自分の感情を分析できる人だから、前代未聞の事態に私も彼自身もちょっと驚いていた。時間が経ってもう~~~ん、としか唸れない状態でもどこか彼は満足そうだった。彼の言葉が出てこないので、私はこれ見よがしに持論を展開したが、それを聞いても彼は不服そうに、ふーん、と言ったのみだった。
その態度にイライラして私が不貞腐れていると、彼は言った。「なんかうまく言えないんだよな……。言葉じゃ表せられないんだ、何かの良さを言葉にできるということは、それが置き換え可能であることと一緒だから。あの映画は他の作品とは違ってちょっと言葉には変えがたいから」。
その瞬間、これ見よがしに感想を語っていた自分がひどく陳腐に見えて恥ずかしくなった。
これが1回目。
■私のどこが好き?

それから3カ月くらいの時間が経った。私の片思いなのか両思いなのか、よくわからない間柄だった。
でも遠いような近いような彼の隣は居心地がよく、あいかわらず私の知らない言葉を教えてくれた。建築の模型を見ながら、何やら難しい単語と誰かの思想を口にしていた。いつも、気がつけば彼は隣にいて、気がつけば私はひとりに戻っていた。
そんな面倒な関係なんて告白さえしてしまえば、どうにかなるものなのに、残念ながら当時の私はそんな勇気を出せるほど面の皮が厚い人間じゃなく、彼からの返信がこないかずっとLINEを開いたり閉じたりして、ため息をついて、また10秒後に開いたり閉じたりしていた。あァ……なんともガキらしいアオハル……。
当時の私はわざわざ好きな人に振られるリスクを背負うよりはこの居心地の良い関係を続けていくことを選んだのだ。聞かない私が悪いし、仲のいい友達でいいじゃない!
だけど、いつものようにふたりでダラダラとチューハイを飲んでゴールデンウィークの生ぬるい風に当たりながら散歩をしていたとき、突然本当に突然、半歩前を歩く彼を見て今までよしなにやり過ごしていた感情が、言葉が、込み上がってきたのである。なんと前振りも何もない、突拍子もない衝動。
カンカンッ、金槌がなって私の脳内法廷が開廷される。
あいつに私のこと好き? って聞きたいの? いやいやいやそんなの聞いたら関係破綻じゃない? いや、あんただって聞きたいでしょ? 私は好きなの、異国語みたいな知らない言葉を教えてくれるのも、タバコ吸うときに見える長いまつ毛も笑ったときのくしゃくしゃな顔も全部好きなの! でもそんな野暮なこと聞いてどうするの、あんたはこのリスキーなことを背負える器じゃないでしょ!
「え? どしたのいきなり」
気がつくと目の前に彼が立って怪訝そうに私を見ていた。さっきまで白熱していた脳内法廷は一気に閉廷し、目の前に半笑いの彼の顔が見える。「付き合ってもないのにどこが好きなんて聞く?」
なんてこと! どうやら私は彼に「私のどこが好き?」と口走っていたようである。あの、えっと、と私が状況確認にしどろもどろになっている間に彼はちょっと考えて、言葉を続けた。
「うーん……うまく言えないんだよな……。よくわかんなくて……。その良さを言葉にできるということは、その要素さえ満たしてしまえば、置き換え可能じゃん?」
そういった彼は、照れ臭そうに缶チューハイを少し飲んで、また私の半歩先を歩きだした。なんとなく私もそれについていった。私は褒められたのか褒められてないのか釈然としなかったけれど、とりあえずこの恥ずかしさを溶かしてしまいたかった。私はぬるくなった缶チューハイを勢いよく飲んだ。
えーと、これが2回目。

……これで私の話はおしまい。
彼は今でもお会いする。あいかわらず、私は小林賢太郎のコントを見せつけ、彼は外国語のような建築家のウンチクを話してくれる。時々映画も見るし、昼から酒を引っ掛けたりもする。
私たちは未だにずっとぼんやりとして曖昧な関係で、言葉にできない時間を過ごしている。
Photo/奈辺