
「非常に言いにくいが、お前、鼻毛が出てるよ」
10連休のリレーエッセイ企画「忘れ得ぬあの人の言葉」。かつて好きだった人から受け取った、忘れられない言葉の想い出を振り返ります。20代の頃に付き合っていた、愛していた男が一度だけ、私の鼻毛を切ってくれたことがあるという大木亜希子さん。そんな彼との別れ、親友の言葉から私が手にした大切な“薬”の話。

20代のある時期、一度、ひとりの男性と深く関わった経験がある。
それまでも手痛い恋愛や地味な恋愛、私からの一方的な憧れゆえ点火して“秒速終了”した「恋愛のようなもの」も経験してきた。
しかし、そのときだけはちょっと趣が違った。
一応、私たちは深く向き合い、きちんと「交際」という形をとっていた。
■あんな恋愛をするなんて、夢にも思わなかったけど
その人は、スタイリストをしていた。
当時の私は日々芸能の仕事に勤しんでみたり、バイトに励んでみたり、とにかくモラトリアムな期間を過ごす真っ最中。
ちょこちょこと「恋愛のようなもの」は繰り返してはいたが、毎回こっぴどく失敗しては、やさぐれていた。
「恋愛偏差値」という時代錯誤な言葉を使うつもりもないが、私は恋の始め方も終わらせ方も下手で、どうしようもなくこじらせており、「人との交際の仕方」も実のところ理解していなかった。
だから、あんなにでかい恋愛が自分の身に降り掛かってくるとは、夢にも思わなかった。
■明るいことだけが、ふたりの間にはあった
彼は私と同じ年齢でいつも愛想が悪く、ブスッとしている男だった。
私が行きつけのバーでひとり飲んでいるとき、彼もよくひとりで来店していたが、互いに面倒なので話しかけることもなかった。
しかし、何度か来店するうち、イヤでも遭遇するようになり、結果的にどちらからともなく話しかけるようになると急速に仲は深まる。
決して口数の多い男ではないがグルメで、安くて旨い店をよく知っており、意外なことに気が合った。
そこからふたりは多くの定食屋へご飯を食べに行くようになり、気が付いたら付き合っていた。
彼はスタイリストという職業柄、新しく手に入れたおしゃれなスカートを私に穿かせてみては、オモチャのカメラでよく私の横顔を撮った。
旅先でも道端でも、本当に彼は私の横顔を飽きることなく撮る。
次第に照れた私が全力で変顔するようになると、普段はポーカーフェイスな彼がプッと吹き出して笑うようになった。
次第に少しずつふたりの関係に信頼が増していくことが、私はうれしかった。
常に彼の笑顔が見たくて、「どうしたら笑わせられるか」と真剣に考えていた。
季節は春。そして、私の心も春だった。
ふたりの未来には、明るいことしか起こり得なかった。
■男が私の鼻毛を切った日
夏。
箸が転んでもおかしい年頃の悪ガキのように、イタズラし合っては笑い転げる私たち。
世間から見れば彼はただのブサイクだろうが、その寡黙な顔が愛おしそうに見つめてくれるだけで私の人生は万々歳の絶好調で、ベストコンディションだった。
あるとき、ふたりで海に行った帰り道、彼が助手席の私に顔を向けてきた。
キスをしてくるのかと思い慎ましく目を閉じると、
「非常に言いにくいが、お前、鼻毛が出てるよ」
と、彼は大真面目な顔で言ってきた。
こちらは“乙女心”からマスカラをたっぷりと塗りたくり、瞳を閉じて完璧な演出をしているというのに、彼は一切なびかずに鼻毛を指摘してきたのだ。
私がショックのあまりうろたえていると、
「ちょっと待ってろ」
そう言って彼は道の脇に停車し、仕事用のバッグからソーイングセットを取り出して、丁寧に糸切りハサミで私の鼻毛を切ってくれた。
年頃の女がポカンとした表情を浮かべ、注意深く男に鼻毛を切られている姿は、事情を知らない人からみれば滑稽だったに違いない。
ハサミを握る彼の眼差しも、まるで“オペの最中の医者”のように真剣で、そこには微塵の色気も感じられなかった。
私は淑やかに瞳を閉じた3分前の自分を恥じ、黙ってアホ面を彼に顔を差すしかなかった。
その距離は10センチに満たず、キスをしようと思えばできる距離なのに、しないふたりは、まるで少年同士のようだった。
しかし、そんな屈辱さえ私は面白くなってしまった。
そして彼もそのシュールな状況に耐えられなくなったのか、いよいよ盛大に吹き出した。
「このハサミ、もう仕事で使えねぇよ」
彼は呆れていたが、なぜか顔は愉快そうだった。
私はそこで初めて、恋とはいつも当事者以外からしてみるとみっともなくて恥ずかしくて、だけど“愛おしいもの”であることを知った。
彼といるといつも心に温かいものが溢れ出し、それが心地よく胸に響いた。
神様。どうかお願いだから、こんなアホな時間がずっと続きますように。
私は、切に願った。
■別れを前に、記憶の海に溺れかけて
秋。
別れは突然やってきた。
あるときから互いに束縛が増え、さらに彼の優しさに甘えた私が傲慢な態度を取り始めると、次第に関係に亀裂が入るようになった。
私は、ずっと一緒にいられることを前提とした「和解案」を掲示してみたが、彼が納得することはなかった。
そしてありふれた恋の終わりのように、私たちも互いに連絡を遮断するようになる。
少しの期間を経て連絡をとってみたりもするが、また同じようなことで揉め、別れは不可避な状態になった。
私は、今生では彼に会えなくなったこと、もしくは会えたとしても、もうそのときは“他人”として顔を合わせなくてはいけなくなった事実に狼狽した。
静かにメンタルは崩壊していき、私は毎晩、親友の綾子に泣きながら電話をするようになる。
そこで私は、「初めて人を好きになったの」とか「一緒にいると世界で一番幸せだったの」など、ポエムがかった恥ずかしい言葉を吐露しまくった。
そして、「あの時もしも私が彼にもっと優しく接していれば……」とか「今から時間が戻らないだろうか」と、真剣にタイムワープ方法を綾子に相談した。
端的に言って、ちょっと気がふれていたのである。
ミシェル・ゴンドリー監督の映画『エターナル・サンシャイン』は、別れた恋人との思い出を消去したいと願う主人公が、ある博士により「記憶除去手術」を受ける物語だが、当時の私はその映画を永遠に観ては深い闇に落ちていった。
彼との記憶を消し去りたいが、一方で愛おしい思い出の数々が薄れていくことが恐怖で、もはや「記憶の海」に溺れかけていた。
このまま「ふたりの思い出」が処理できないくらいならば、いっそのこと早くほかの男に鞍替えして、“あんな男”のことなど忘れてしまいたい。
しかし一向に忘れられず、むしろ彼と一緒に入ったカフェの前を通るたびに楽しかった記憶がフラッシュバックする。
「あれ以上に好きな男が現れることはもうないだろう」と悟ると、それだけでもう、ゆるやかに死にたかった。
■「恋愛において“もしもあの時”はあり得ない」
冬。
未だ泣きわめく私に、最初は同情してくれていた綾子が、ある日キレた。
とうとう私に愛想を尽かして、ピシャッと一言、電話口でこう言ったのだ。
「ねぇ。よく聞いて。恋愛において、『もしもあの時』はあり得ないんだよ」
続けて彼女は、こう言った。
「人は常にそのとき最善の選択をして生きてんの。だから『もしもあの時』っていうのはナシ!」
と、断言したのだ。
その瞬間、周囲の喧騒が止まったように、脳内にその言葉だけが響き渡った。
あれ……? そうか。私が今、猛烈に執着している「もしもあの時」は、あり得ない出来事なのか。
上手くいかない恋愛ではあったが、それでもふたりは最善を尽くそうと努力して、そのベストな結果がこれなのか。
もしかして私ができる彼への最後の“始末のつけ方”は、現実を受け止めることなのではないか。
まるで頭を叩かれたかのように、私は長い眠りから目を覚ました。
彼女の言葉がなければ、私は今でも「未練おばけ」になっていたと思う。
そこからは静かに現実を受け入れ、再び恋愛市場に戻ることができた。
■辛い夜を乗り越えさせてくれた言葉
一度好きになった男にあげてしまった恋心は、いつだって自分の元に返ってきにくい。
さらに失恋直後の脳内は、“楽しかった時代”を毎回残酷なほどに映し出してきて、現実に強く反発してくる。
そのたびに、狂いそうになる。
しかし哀しいけれど綾子の言う通り、「もしもあの時」という世界は、もうどこにも存在しないものなのだ。
その意味を痛感した私は、以前よりも少しだけ強くなれた。
その後も辛い夜が何度もあったが、私はそのたびにこの「もしもあの時はあり得ない」という言葉を心の引き出しから取り出し、特効薬として処方した。
そして、何度目かの春、私はまた、ほかの男を好きになることができた。
■別れはいつも突然。だから、後悔したくない
「恋はしたほうがいいよ」
と人はよく言うけれど、私はそうは思わない。
恋とはいつも自分の感情が激しく揺さぶられ、ほかのことが手につかなくなり、落ち込むことも多いからリスクがありすぎる。
しかし私は今日も、「人を好きになる偶然の確率」を信じてみたい。
なぜなら、いつでも別れは突然やってくるから。
だからこそもったいぶらず、日々「愛の言葉」を好きな男には囁きまくり、後悔しない生き方を選びたい。
それと、今日もどこかで生きているであろう、彼。
私の横顔を写した写真は、できれば消さず、思い出として良かったら残しておいてください。
いえ、やっぱり消してください。どうかお元気で。
Text/大木亜希子
東京都在住。フリーライター/タレント。2005年、ドラマ『野ブタ。をプロデュース』で女優デビュー。数々のドラマ・映画に出演後、2010年、秋元康氏プロデュースSDN48として活動開始。その後、タレント活動と平行しライター業を開始。Webの取材記事をメインに活動し、2015年、NEWSY(しらべぇ編集部)に入社。PR記事作成(企画~編集)を担当する。2018年、フリーライターとして独立。2019年5月23日、アイドルのセカンドキャリアに迫った自身初の著書『アイドル、やめました。AKB48のセカンドキャリア』(宝島社)が発売予定。Twitter:@akiko_twins note:https://note.mu/a_chan
写真撮影/佐野円香










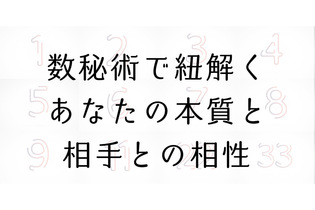










いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。