
「あなたの思うように俺が感じなくても、そのことを責めないでくれ」
10連休のリレーエッセイ企画「忘れ得ぬあの人の言葉」。かつて好きだった人から受け取った、忘れられない言葉の想い出を振り返ります。今宵は、会社員兼ブロガーのはせ おやさいさんが、離婚へと進む道の途中で言われた忘れられないひとことを綴ります。

■「お嫁さん」にただ憧れていた
ありふれた話であるが、わたしは一度離婚を経験している。
相手は9歳年上の作曲家で、優しく繊細な人だった。結婚を決めた理由はたくさんあったが、離婚を決める理由もたくさんあった。それはもう大きなものから小さなものまで。数々の理由を総合すると、「わたしが幼かったから」と言い換えられるかもしれない。
30歳を過ぎてからの初婚なので、「幼い」という年齢でもなかったのだが、他にうまい言いようがない。結婚という言葉にただ憧れ、「お嫁さん」に夢を見ていた自分に、気が付けなかった。
いや、もしかしたら自分でも、自分の「お嫁さん」願望に薄々気付いていたかもしれない。が、前夫はおそらく「お嫁さん」を受け入れるタイプの男性ではなかった。
彼が見ていたわたしは、仕事が好きで自立心が強く、公私を問わず忙しく、充実して過ごす女性だった。そういう女性となら、お互いが自分のペースを守りながら結婚生活が過ごせると思ったのだろう。
事実、わたしにそういう一面はあったが、結婚観については違っていた。
頼もしい会社員の父と、それに守られている専業主婦の母。自分の両親をロールモデルに、「愛されるお嫁さん」になるのを、心のどこかで夢見ていたのだ。
彼が見ていた自立して働く自分も、わたしが夢見ていた結婚観も、どちらもわたし自身だったことに変わりはない。しかし、そのふたつは致命的にズレており、本来であればそのズレについてお互いで話し合う必要があった。
だが、恋人として付き合い始めて早々にプロポーズされ、わたしは舞い上がった。結果、相手と一緒にいたいあまり「お嫁さん」に憧れている自分から目をそらし、「古い結婚の慣習にとらわれない自分」であろうとした。ちぐはぐである。
そんな状況でも、だましだまし結婚生活を続けることはできたかもしれない。が、間欠泉のように、たびたびわたしの不満は爆発した。
双方が自立した関係を求める元夫と、「お嫁さん」としての庇護を求めているわたしの結婚生活は、ズレの連発だった。与えられすぎる自由に、わたしが不安を感じるようになったのだ。相手からしてみれば、言動不一致で、さぞ混乱しただろう。
お互い歩み寄りも試みたが、根本的な解決はみられなかった。当然の話だ。わたし自身が、自分の本当の願望から目を背けていたのだから。
そうしてわたしの初めての結婚は破綻した。
■すべては「自分のため」だった
年齢差もあったし、相手は二度目の結婚で、わたしより冷静で達観している部分があり、そのことに完全に甘えていた。
甘えていた、というのはつまり「自分のことばかり考え、優先し、わがままを言っていた」ということなのだが、当時は相手に愛されるため、あれこれと尽くしていたつもりだった。相手のことを、深く愛していると思っていた。
いま冷静になると理解できるが、「『自分が』愛されるため、相手に尽くす」という行動自体、とても幼稚なものだったと思う。前夫はそうではなかった。自分自身のことはさておき、まずわたしのことを理解しようとし、尊重しようとしてくれた。
わたしが心身の不調を訴え、会社を逃げるように辞めたときも、結婚早々、仕事も家事もできず、ただ臥せっていた時期も、じっとそばにいて、見守ってくれた。
それにもっと早く気付くべきであったが、できなかった。「わたしが」「わたしが」ばかりで、なぜ相手が自分の言うことをもっと理解して、実践してくれないのだろう、と思っていた。わたしを愛しているなら、もっとこうしてよ、ああしてよ、と不満ばかり感じていた。
離婚を決意するまで、気が遠くなるような回数の言い争いをした。後悔してもし足りないほど、本当に酷いことを言ったと思う。
「こんな結婚、しないほうがマシだった」
「あんなに尽くしたのに、理解してくれないなんて、がっかりした」
口数が少なく、穏やかな性格だった前夫も声を荒げる回数が増え、あるとき、こんなことを言われた。
「あなたの思うように俺が感じなくても、そのことを責めないでくれ」
わたしは弁が立つタイプで、口喧嘩をして相手を言い負かすことも多かったが、このときは二の句が継げないほどの衝撃を受けた。
この頃のわたしは、プレゼントや食事の献立、報せたいニュース、サプライズなど、「こうしたら喜ぶだろうな」と思って準備したものに対して、前夫が期待した通りのリアクションを取らなかったとき、心底がっかりした表情をしていたそうだ。
前述したが、当時のわたしは「『自分が』愛されるために相手に尽くしていた」ので、「相手を喜ばせるためにこうしよう」という思いが「こうしたら喜んでくれるに違いない」と、おかしな方向へ向かっていた。
つまり、わたしの行動は「『自分が』相手から愛されているか」の「確認」が目的であり、相手のためを思っての行動ではなかった、ということになる。
指摘されるまで、まるで自覚できていなかった。そう言われて、虚をつかれたようにわたしは黙り込んでしまった。わたしが「相手への愛だ」と思ってしていた行動は、『相手のため』ではなく、『自分のため』だったのだ。それを当の本人から指摘されたのが本当に惨めで、恥ずかしかった。
わたしの中に、「結婚したら一心同体」「夫婦とはこうあるべき」というような幻想があったのかもしれない。「相手を自分の思うようにコントロールしたい」という傲慢さもあったと思う。「わたしがここまでしたんだから、喜んでよ」という主張は、まるで子どものようだった。
父親に喜んでほしくて、母親の真似をしいろいろと世話を焼いていた子ども時代を思い出した。わたしはあの頃から、まったく成長していなかった。相手に愛されている確認をするため、「父を愛している母」の行動を、盲目的にただ真似していたのだ。
そうすれば、わたしも愛されると勘違いしていた。わたしの両親と、わたしがいま作ろうとしている夫婦の形が違っていることにも気付かず、目の前に実在する、自分の夫の感情を無視してまで。
ほどなくして、前夫とは離婚することになった。死ぬほどの言い争いが、憎しみに着火する前に離れたい、と思ったからだった。
とはいえ、言い争いで得るものも多かった。前夫は本当にわたしのことをよく見つめていてくれたと思う。離婚へ進む道を猛スピードで走りながら、「ああ、この人は本当にわたしを愛していてくれたのかもしれない」と思う瞬間もあった。それほどまでに、夫の指摘は的確で、痛く、つらいものだったし、ありがたかった。
だが、もう間に合わなかった。当時のわたしは情けないほどに幼かったし、夫婦というパートナーシップを構築するには、怠惰だった。口さえ開けていれば餌が放り込まれると思っているヒナと同じで、自分から努力するということを、よくわかっていなかったのだ。
離婚届を提出するのに先立ち、お互いの住居を分けた。飼い猫と一緒に狭いアパートに転居し、荷解きも済んでいない部屋の中でひとり素足で立っていると、自分のつま先が、冷たく痛かった。
この冷たさを忘れないぞ、と思った。
両親のもとでもない、夫のもとでもない、誰のもとでもない、わたししかいないこの場所から、自分の両足で立ち、今度こそ、誰かを本当に愛して、大切にしたいと思った。
■わたしたちは、別々の人間なのだから
その後のことは割愛するが、二度目の結婚をし、娘をもうけた今でも、前夫の言葉をたびたび思い出す。家族であっても、夫婦であっても、わたしたちは別々の人間で、別々の感情がある。別々の人間が出会い、歩み寄って関係を作るから、夫婦というのは面白いのだ。
そこには努力も伴うだろう。自分の価値観を見直す作業も必要だろう。だが、それが苦にならないのが愛なのだ、と思った。
もちろん自分の行動で相手が喜べば、それはうれしい。でも、もし相手が喜ばなくたって、それでもいい。わたしは自分がしたいから、自分がうれしいからいいのだ、ということしかしない、と決めた。それが「相手を尊重し、愛すること」だと思うからだ。
ありがたいことに、今の結婚はおおむねうまくいっていると思う。それは、我ながら少しずつでも成長できてきたからというのもあるが、夫の性質によるところも大きい。
夫は自然と「自分がしたいから行動する」を選べる人だ。「俺がしたいから、そうしてる」という行動は、わたしに安堵と喜びをもたらしてくれる。同じように、わたしも夫にしたいと思う。そして生まれてきた娘にも。
娘はわたしと血はつながっているが、彼女もまた別の人間だ。まだ0歳で、自我が芽生えてくるにはもう少しかかる。
彼女の命を守り、育てていくのは言うほど簡単なことではないと日々実感している。だが、今はわたしがいないと生きていけない娘も、いつか自分の両足で立ち、わたしの手を離れるときが必ず来る。
自分で見たものや聞いたものを吸収し、わたしとはまったく違う価値観を持つ可能性だってあるのだ。そのときに、わたしは自分の一部が切り離されるような寂しさを感じるだろう。
それでも、わたしはその寂しさを喜び、娘の感情を尊重したいと思う。
娘とわたしは、別々の人間なのだから。
Photo/ぽんず(@yuriponzuu)










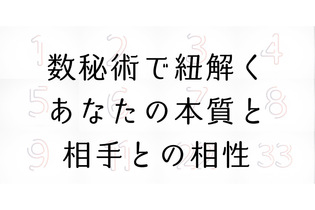










会社員兼ブロガー。はてな(id:hase0831)を中心に活動。仕事はWeb業界のベンチャーをうろうろしています。