
私が思う、通いたくなるバーのたったひとつの条件
誰にも邪魔されず、酒を飲みながらカウンターで本を読めるバーがあればいいと思う。つらい仕事が終わったあとに、ひとりで足を運べるバーがあればいいと思う。ひとりで酒を飲むのはこんなに楽しい。エッセイスト・生湯葉シホが送る、等身大の酒飲みエッセイ。

知らない人と話すのが苦手なくせに、ひとりでバーに行くのは昔から好きだ。
バーで女がひとり飲み、と言うと出会いを求めていると思われることも稀にあるのだけど、独身だった頃も結婚した現在も特にそういう目的ではなく、「ひと言も話しかけないでください」というオーラをバチバチに出しながらカウンターで酒を舐めていることが多い。
初めてバーで酒を飲んだのは、20歳になってすぐのことだったと覚えている。
「渋谷 バー 入りやすい」と検索して見つけた店に入った。円山町のラブホテルのど真ん中にあるバーだったので、入り口の扉を押すまでにいくらか勇気は必要だったけれど、入ってみるとずっと店のスピーカーから爆音でメタリカが流れていて緊張はしなかった(あとから聞いたら、その日は幸か不幸か「メタルオンリー」的なイベントの日だったらしい)。
メタリカのせいでバーテンダーになかなか注文が通らなくて、店主がずっとカウンターから身を乗り出すようにして客のオーダーを聞いていた。いま思い返すとあの爆音のなかでショートグラスに注がれたカクテルをちびちびと飲んでいたのはけっこうシュールだったが、「バー、意外と怖くないじゃん」と思うようになったきっかけがあの日だったのは間違いない。
■テーブルの灯りを見つめながら、ひとりでぼんやり飲む
その日から5~6年の年月をかけて、通学ルートや仕事場の近くを中心に、お気に入りの店を少しずつ増やしていった。
たまに「インターフォンを押して入ってください」という店や一見さんには入り口の開け方がわからないようになっている店があってオロオロしたが、回数を重ねていくと自然と慣れて、「ア、ひとりです……入れてください……」と小さい声で言えるようになった。
店に入ると、だいたい決まってジンフィズかギムレットを頼んで、テーブルの上のキャンドルとかカウンターのうしろの調度品なんかを見つめながらぼんやりと飲む。
女ひとりでカウンターに座っているとバーテンダーが気を遣って話しかけてくれることも多いけれど、バーテンさんというのは「黙って飲ませてくれ」側の人間をすぐに見分けてくれるケースが圧倒的なので、大抵の場合はこちらのリアクションを見てスッと引いてくれる。
同じように、仮に話しかけてくるお客さんがいても、その人があんまり饒舌だったりすると、こちらを見てやんわりと制してくれるのでありがたい。
バーというのはただの店ではなく、お客さんと店主によって創られる場だから、「できればお客さん同士で楽しく交流してね」という空気があるバーはその店なりの哲学でその空気をつくっているのだ(と、思う)。
だから、たまにそういう店に入ってしまうと「あ、自分が読み間違えたな」と思うだけで、その場はその場で楽しく会話をして帰ることが多い。そういう試行錯誤を繰り返しながら、喋らないことを許してくれる空気があって、できればジンの種類も多い店をちまちまと探す。
■バーテンダーの機転と、ブルームーンのふたつの意味
喋らない、と散々書いたけれど、大学生の頃、初めて自分が行きつけにしたバーでは、私は例外的によく喋った。
そこは女性と男性のバーテンダーふたりで切り盛りしている店で、カラオケスナックや風俗店が入った雑居ビルの奥にひっそりとあった。
2階なのに、カウンターで飲んでいるとなんだか地下にいるような気分になる変なバーで、たまに友だちも連れて行ったけれど、ひとりで行くことのほうが圧倒的に多かった。
ふたりのバーテンさんは若き酒飲みを気にかけてくれて、酒にまつわることをあれこれ私に教えてくれた。初めてウイスキーを飲んだのもその店で、ラフロイグの独特の匂いに驚いていたら「正露丸の味がするでしょう」と男性の店主に微笑まれたのを昨日のことのように覚えている。
メニューごとのアルコール度数の強弱や、泡が綺麗に立つビールの注ぎ方、スマートなオーダーの仕方……などなど、バーで酒を飲むための基礎演習のようなことは、ほぼすべてその店で習ったと言ってもいい。
なかでも、店主が教えてくれたことで忘れられないのが“カクテル言葉”だった。
「カクテルにも花言葉みたいにカクテル言葉があるんだよ、たとえばオールドパルは『思いを叶えて』」と教えられた。
そのときは「ロマンチックだけどそれ聞くと頼みづらくなっちゃいますよ」というようなことを言ったような気がする。
ある晩、その店で飲んでいて、酔った男性客に馴れ馴れしく手を握られたことがあった。男性客とはもともと顔見知りではあったので、店主も、すぐに制するべきか窺っているような視線を時折こちらに向けてくれていた。
どうしたらいいものか迷っていたそのとき、ふと、店主に教えてもらった“カクテル言葉”が頭をよぎって「ブルームーンください」とオーダーした。店主はすぐにカクテルを作り、こちらがお手洗いに立ったタイミングで男性客と席を離してくれた。
数年に一度しか起こらない珍しい天文現象の名前を冠したブルームーンというカクテルには、真反対のふたつの意味があって、ひとつは「滅多に遭遇できないような幸福な恋」、もうひとつは「拒絶」。店主はそう教えてくれていたのだった。
あの晩、こちらの様子を見て「拒絶」パターンと判断し紳士的な対応をしてくれた店主には、いまでも感謝している。残念ながら、その店は閉店してしまって、いまはもうないのだけれど。
■訃報を聞いて、真夜中に訪れた京都のバー
何度も足を運んだ店の思い出は当然尽きない。一方で、一度訪れただけなのに、記憶のなかで忘れられない存在感を放っている店もある。
昨年の夏、仕事で京都に一泊する機会があった。せっかくだからと京都の友人に声をかけ、夜、ふたりでおでんが名物の居酒屋に入った。
畳敷きの席で膝を抱えながら互いの近況などを話し、2時間ほどで、ちょっとお手洗い行ってくるねと席を立った。戻ってくると、座っていた彼がこちらを見上げて、「ねえ、さくらももこが死んだ」と言った。
呆然として、「ウッ」みたいな間抜けな声が漏れた。そうか、癌だったんだ、知らなかったねと二言三言しゃべって、そのまま店を出て先斗町で飲んだ。いいバーを見つけて、店を出るとき、彼に「デートで使ってもいいけど、この店は私が見つけたことは忘れないでくれよ」みたいな余計なことを言ったような気もする。
深夜だったので、ホテルまで送ってもらった。手を振って彼と別れて、「いま友だちの〇〇と飲んでたよ」と夫にLINEをしたあと、メイクを落とそうとユニットバスの洗面台に向き合う。
そのとき唐突に、「飲み足りないな」と思った。もう十分酒は飲んでいたから飲み足りないなんてことはあるはずないのだけれど、こみ上げてくる気持ちをとにかく酒でごまかしたいという日はたまにあって、それがその日だった。
ホテルのすぐ近くに小さいバーを見つけて、ネットの情報も見ずに入った。まだやってますか、と聞くと「いいですよ」と女性のバーテンダーが立ち上がって、奥に案内してくれた。
外観から想像したよりも小さい店だった。カウンターのうしろの狭い棚のなかにアブサンの瓶を見つけて、強めのアブサンくださいと注文する。
目の前に出された薄い水色のアブサンをちびちび飲んでいたら、これ飲める方に久々にお会いしましたよ、嬉しいですとバーテンダーに微笑まれた。
いくつかの和やかな会話を交わしたあと、彼女がすこし迷ったように、「失礼だったらすみません、お姉さんなにかありましたか」と言った。
別に言う気はなかったのに、「さくらさんが亡くなられたんですよね」という言葉が自分から出てきて驚いた。
口にした途端にその事実がリアリティを持って目の前に迫ってきて、幼稚園の頃、コジコジの「飛べないし泳げもしない半魚鳥の次郎くん」というキャラクターがツボに入ってしまってずっと笑い転げていた日があったことを突如思い出し、じわじわと泣けてきた。
アブサンを舐めながら泣いている私に、バーテンダーの彼女はそれから一度も声をかけなかった。
代わりに、コジコジのアニメのエンディングテーマだった電気グルーヴの「ポケットカウボーイ」を小さな音で店のスピーカーから流してくれて、私のほうを見ないようにしてくれていた。ピコピコしたその音を聴きながら、体に入れたアルコールで自分の感情の波が凪いでいくのをひたすら待った。
……そんな夜だったから、また京都に行ったとしても恥ずかしくてあのバーにはもう行けない。けれど、自分の頭のなかの「名店」のリストに、ひっそりと名前だけは書き入れている。
■私が思う、いいバーのたったひとつの条件
自分にとって「いいバー」というものがあるとしたら、それは元気がないときでも足を運べる店だな、と思う。
私は1年のうちの3分の1くらいは元気がない状態で過ごしているので、そのバーに合わせてテンションを整える、という必要がある店はちょっと苦痛だ。わりと元気なときに行ってもそうでないときに行っても、いい意味で「そちらのコンディションなんかいちいち気にしていないですよ」という顔をしてくれる店がいい。
そして、そういう店には例外なく私のような(気分にムラがあり、人間よりも酒が好きな)客が集まる。
ひとりで飲んで楽しいの? と聞かれることもあるけれど、店のBGMで気になった曲をSpotifyに取り込んだり、カウンターの隣に並んだカップルの会話にそれとなく耳を傾けたりしていると、驚くほどあっという間に時間が過ぎてしまう。それに、(カウンターで読書をされることを嫌がる店もなかにはあるけれど、)おいしい酒を飲みながら本を読むのは至福の時間だ。
カクテルで満ちたショートグラスの表面にそっと唇をつけるときはいつも、気に入ったワンピースを試着して鏡に向かい合うときのような、えも言われぬ胸の高鳴りを感じる。
子どもの頃、海水浴に行った日の夜は、ベッドに入っていても満ちては引いていく波のリズムが体の奥に残っているのを感じて、よく海の夢を見た記憶がある。
いいバーで酒を飲んだ日も、その店の空気が家に帰ってからも喉の奥に薄暗く残っていて、心地のいい気分で眠ることができるような気がするのだ。
そんな言い訳を用意して、今晩もいそいそとどこかのバーで酒を飲む。
Illust/兎村彩野(@to2kaku)










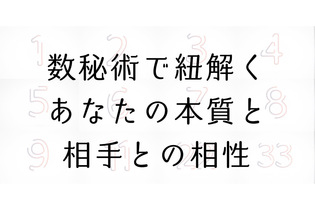










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。