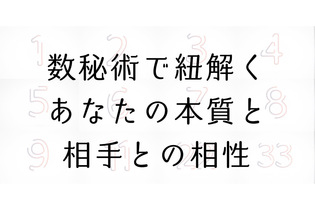小説を書いたのは母への復讐。作家・内田春菊、書くことによって楽になることもある
人に対して憎しみや怒りがなければ、それは良いことだけど、現実問題そうもいかない。心の奥底から湧き上がるその感情をどうすればいいのか。作家・内田春菊さんは「書いたり、話したりしたほうがいい」と話します。

ここのところ、母と娘のこじれた関係が取り上げられる機会が増えてきました。
“毒親”という概念が知れ渡ると同時に、「親を憎んでもいい/許さなくてもいい」という認識も広まり、気持ちが楽になった人も多くいると思います。
ただ、それだからといって、これまで親から受けてきた傷のすべてが、何事もなかったように回復するわけではありません。 依然として「それでも親なのだから、許すべき」といった、無神経な部外者からの圧力もあり、本当の意味で毒母から自由になることは、なかなか難しいケースも。
そこで今回、“毒母”という概念が生まれる以前の1993年、実母の了解のもと、養父に犯され続けていた壮絶な過去を描き、世間に大きなショックを与えた自伝的小説『ファザーファッカー』の著者であり、今年の11月に同じテーマを母親側の視点から描いた『ダンシング・マザー』を上梓した内田春菊さんに、“毒母”についてのお話をお聞きしました。

内田春菊(ウチダ シュンギク) さん。漫画家、小説家、俳優、歌手。1959年長崎県生まれ。1984年に漫画家デビュー。1994年『私たちは繁殖している』『ファザーファッカー』でBunkamuraドゥマゴ文学賞受賞。その他の作品に『南くんの恋人』『あなたも奔放な女と呼ばれよう』など。私生活では4人の子どもの母親(夫はいない)。
■時代や社会の仕組みから、暴力をふるっていた両親
――ベストセラーとなり、直木賞候補ともなった『ファザーファッカー』から25年経った今年、母親側の目線から描いた『ダンシング・マザー』という作品を出されたわけですが、執筆している最中は、どんな心境だったのでしょうか。
『ファザーファッカー』の時よりは、全然楽。『ファザーファッカー』は、読み返したら泣いちゃって、続きが書けなくて、完成するまでに何年もかかっちゃったんです。だけど『ダンシング・マザー』は、時間が取れたら書き進めてっていう感じでした。
それに担当の編集者の方が知らない間に、母親への怒りを込めてしまっている部分を、すごく綺麗に取り除いてくれたんです。
「小骨、全部取りました。そのまま食べられます」くらいの形にしてくれた。わたしの母は自分が悪人であるという自覚がないので、作風がそういった仕上がりになって良かったと思います。
――養父が娘に性暴力をふるうことを黙認するって、ものすごく酷いことなのに、悪人だって意識がなかった。
当時の女性って、とにかく男の人にボカスカ殴られますからね。特に母が生まれ育った九州は、男尊女卑があって、荒っぽい風土でもあります。現に実父も義父も母を殴っていました。だからわたしも、「男の人は女を殴る」というのが当たり前の環境で育ってきているんです。
――たしかに少し前までは、家庭内ではもちろん学校なんかでも、体罰が横行していました。
わたしも付き合ってきた男性にはけっこう殴られてきました。もちろん全員が暴力をふるうわけではなかったですけど。それでも精神的なDVやハラスメントはふんだんに受けてきたので、えらい目には遭った感じがしています。
最後に付き合っていたボーイフレンドには、二年以上「別れよう」って言っていたんです。セックスを拒まれた続けたこともあったし。
でも、別れてくれない。それで別れ話を切り出すと、相手が頑張って(セックスを)するんですよ。そうされると、言いづらくなって、別れるのに時間がかかってしまった。
――そもそも、セックスレスもハラスメントだったりしますよね。
そう。セックスレスはハラスメントです。セックスって、男の人がプライドを満たすための行為でもあると思っていて。最初のうちは男性のプライドが満たされているけれど、だんだんとそうじゃなくなっていき、その結果セックスレスになってしまう。
――セックスレスも含め、そういったハラスメントをする傾向のある男性を選んでしまうのって、ご両親の影響もあると思いますか?
あると思います。これまで3回結婚しましたが、殴られなかったのは、最後の離婚をした後に付き合った人、ふたりくらいです。それでも精神的なDVやハラスメントはふんだんにあった。
でも、両親の影響というよりも、男の人ってプライドが傷つくと、暴力をふるいますよ。男の人っていうまとめ方も乱暴だと思いますけど、よく口で負けると、手が出るとかっていうじゃないですか。
手が出る時は、その人が相当傷ついているともとれる。殴られたシーンを思い返すと、どうにかして「俺の方が上だ」という立場を、取り戻すためだったなって。とても迷惑な話なんですけど。
――「傷ついているから、暴力をふるう」ってことを前提においた場合、愛人の娘に性的暴力をふるった義父は、何に傷ついていたと思われますか。
やっぱり、彼の兄と父親が東大で、自分が家では一番ダメな子だったってことじゃないですか。彼の中にある心の傷を回復させるために、一番自分の言うことを聞かなそうな愛人の娘を支配したかったんじゃないかなって。
――そうした義父の行為を黙認されていた母についてはどう思われていますか?
母はいろんな意味で、わたしに嫉妬しすぎていた。わたしにも才能があって美しい娘がふたりいるんですけど、娘たちを育てている今だからこそ「どんだけ嫉妬してたんだよ」って改めて思います。

母と娘は違う人間です。でも、わたしの母は娘が自分と違う人間だと思えない……つまり、「自分が作ってやったモノ」と考えていた。だからこそ、「わたしのモノなのに、わたしよりも優れていて」という嫉妬の念を抱いていたんだと思います。
たとえば、わたしの母は「女の子は高校なんていかなくてもいい」みたいな時代の人だった。だから、「勉強さえしていれば(もっといい人生が送れたはずなのに)」と思っていたのかもしれない。
――個人の責任ではなく、社会的な背景からそうやって生きていくしかなかった。そこから時代が変わり、自分が選べなかった人生を送る娘に対して嫉妬を持っていた。
わたしもそういう時代に育っていたら、彼女のような感情を抱いていたかもしれないです。「なんでわたしばっかり馬鹿みたいな目に遭って、チッ」って。
――思春期にどんどんとスタイルがよくなっていく娘を見て「わたしだって、あなたを生む前はスタイルがよかったのに」って考えてしまうとか。
『ハハな人たち』(角川文庫)に収録されている原田宗典さんと中島梓さんの対談の中に、どこかの娘さんがまだ小さいのに、「『わたしのほうが、(お母さんよりも)若いもーん』って言った」って話が出てくるんです。それを読んで「うわっ、すげぇな」って思いました。だって、そんなあたりまえのこと言われてもねぇ。
――けれども、当の母親に「女性は若い方が価値がある」みたいな意識があると、その娘の一言に刺激されてしまいますよね。
「女はひとつでも若いほうがいい」って思っている人が父親(パートナー)だったりするとそうなりやすいんじゃない。パートナーの価値観的なセンスがとても大切だと思います。
■「子どもが小さいと『この子は自分のものだ』って勘違いしやすいんですよね」
――「毒親」に育てられてきた内田さんにも今はお子さんがいらっしゃいます。壮絶な体験を親という存在から受けてきたかと思いますが、子どもを産むことに対して葛藤のようなものはありませんでしたか?
バースオアダイ(Birth or Die)でしたね。生むかゼロかしかなかった。ひとりだと大変なことになると思っていて、産むならたくさん産んで、自分の毒を分散させようって思想がありました。
――毒を分散、ですか。
そう。わたしが毒親になりだしたら、集まって「えらいことになったよ、どうする?」ってお互いに相談できるような環境を作りたくて。ふたりは必須かなって思っていたけど、運よく4人産めました。
――実際に子どもたちが内田さんのことに関して相談するシーンはありましたか?
うん、時々ありましたね。やっぱりお酒を飲むと、おかしくなる。すると向こうで「母ちゃんがまともな時に、また話をしよう」って話していたり。もうお酒をやめたので、そういうことはなくなりましたけど。
――機能不全な家庭で育つと、どうやって育児をすればいいのかわからなくて、不安だって話もよく聞きます。
わたしも育て方がわからなかった。だから手探りでしたよ。幸い、生き物を飼っていたのでそこから子育てについて学んだことは多々あります。
以前、飼っていた猫が子どもを産んだとき、寒かったのでお産ボックスの近くで毛布をかぶってずっと見守っていたのですが、わりと感動して。動物の育児って極めてシンプルじゃないですか。その真似をすればいいんじゃないかなって。
――育児で、これはしないとかって決めていたことはありますか?
息子のちんこを舐めないとか。
――えっ! 舐める人、いるんですか?
けっこういるらしいですよ。わたし、「もう舐めた?」って聞かれたことあるもん。でも、子どもが女の子のケースでもそういうのがあるのよ。「最初の男は俺にしとこう」っていって、舐めた父親の話もいっぱい聞きました。

――それも自分と子どもの区別がついてない例のひとつですよね。でも、「娘のおむつ替えの時にパパが覗き込んでくる」とか「お風呂で娘の身体を素手で洗うけど、注意ができない」って話は、何度か耳にしたことがあります。
「もう舐めた?」っていうのは、とある女性に聞かれたんですけど、「わたしなんて、もう両方とも、口に入れてむにゅむにゅってしちゃった」なんて仰っていて。
その話を聞いて、どうしていいかわからなくて。やっぱり子どもが小さいと「この子は自分のものだ」って勘違いしやすいんですよね。可愛いし、もう無防備で、お風呂上りはホカホカだし、魔が差す気持ちも多少がわかるけど、でもそれはやっちゃいけない。けど、やる人はけっこういるって話です。
■母への復讐として、小説を書いた

――結局のところ、親が子どもを「自分のコントロール下にある、自分の好きにしていい存在」と思っているところが、 “虐待”といわれる行為の原因になるように思えます。最後に『ダンシング・マザー』のヒロイン・静子は、家出という形で家を出ますが、毒親からはそうやって、逃げるしかないんですかね。
毒親からは距離をとったほうが良いとは思います。夏休みが明けて二学期になると、休みの間に家を出て、親とすったもんだした同級生の噂が伝わってくるんですよ。それを聞いて「その手があったか!」と思い、わたしが家出したのが16歳になりたてのころ。
――今はどういう状態なのでしょうか。
お父様方(実父・養父)は、もうお亡くなりになってると思います。希望的観測ですけど(笑)。
でも母は生きてると思いますね。そして元気なんじゃないかな。うちの家系は長寿系なんですよ。
ただ、わたしも、そうなんですけどストレスに弱いらしくて。ストレスで癌になったんだなって(※)。
――ちょっとお聞きしただけではありますが、ストレスの大きい時期があった人生だと思います。
母も癌くらいにはなっているかもですけど、そうだとしたら、わたしが金を出すんじゃないかって、妹が連絡してきそうな気がするんですよね。絶対ガードしていきたい。
――すべてのエピソードが壮絶なんですが、こうしてお話していると、その悲壮感みたいなものがあまりないのがすごく不思議です。突き抜けているというと、失礼かもしれませんが。
時々、そこで昔のことを思い出すと「わたし、可哀想だったな」って思う。でも、娘も息子も、わたしに優しいんですよ。だから、「なぜわたしの母はこうできなかったんだろう」って疑問に思うこともあります。
作家の吉本ばななちゃんは、「時代のせいとかって言っちゃだめ」って言ってくれて。「よくもそういうところから逃げ出して、素晴らしいものを書いたね」って。

もともと『ファザーファッカー』を小説として書いたのは、小説として出したほうが母への復讐になるからと思ったからです。母は漫画というものをクソミソにけなしていて、彼女が小説家になりたがっているのもわかっていたので。
――書くことによって、ある意味、乗り越えた部分があるのかもしれないですね。書いていて、癒されるってこともありますか?
書いてる時は、やっぱり楽しいんですよ。なので、とくかくみなさんも書いたり話したりしたほうが絶対にいいと思いますね。
――傷を持っている人は、それを言語化することでなにかを乗り越えて、楽になることもある。
そうそう。作品を作る効果っていうのは実証されているらしいんです。池谷裕二さんという脳研究者の方がツイッターで、自分が読んだ面白い論文を紹介しているんですが、その中にありましたよ。どんな作品でも出したほうがいい。出す意味があるっていうの。
――それでは最後に、毒母やDV男性に苦しめられた経験があったり、つらい思いをしている女性になにかメッセージをお願いします。
自分のことを責めるのは本当に避けたほうがいいです。「わたしに何か原因があるんだ」とかも、思わないほうがいいですね。絶対に悪くないから。向こうがダメなの。まずはそういうふうに、切り替えないと。わたしも、向こうが悪いっていうふうに切り替わって、親の問題に視点を移動したことで、『ダンシング・マザー』を書けたのかもしれない。

取材・Text/大泉りか(@ame_rika)
Photo/飯本貴子(@tako_i)