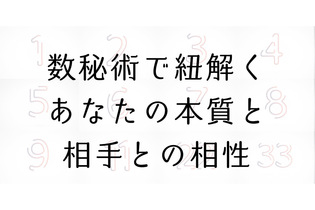最後の1ページを開き、私は今日も浮遊する。世界を柔らかく崩壊させる漫画
ストーリーは人生を支えてくれる。と同時に、危険なものでもあるような気がする。
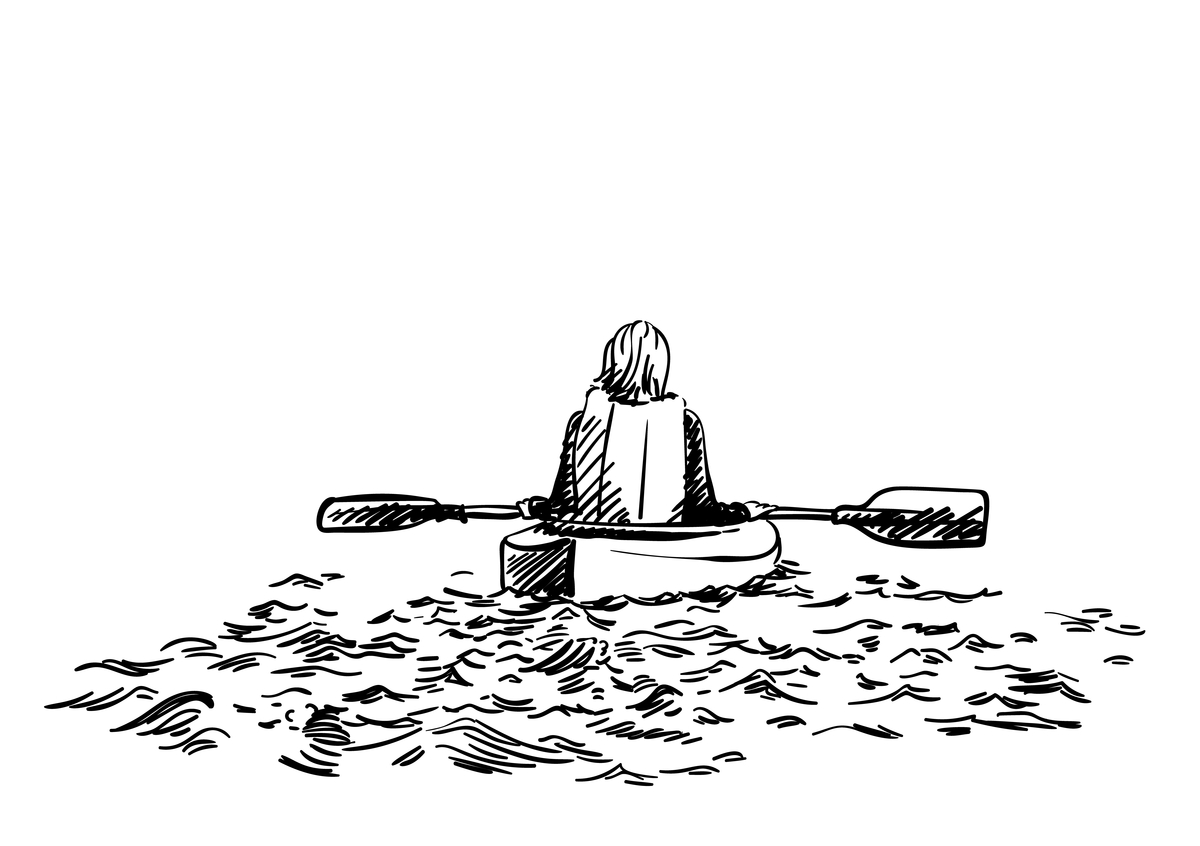
毎日の何気ない暮らしにもストーリーは宿る。
例えば、岐阜県でイラストレーターをしている人。
神奈川県でメーカーの営業所に勤めている人。
広島県でお土産コーナーの販売員をしている人。
埼玉県で銀行員をしている人。
山口県で製薬工場勤務の人。
それぞれに宿るストーリーは人生に愛しさをもたらしてくれる。目の前の世界を意味のあるものにしてくれる。
一方で、この「人生に託している意味」は、自分の手の中にのみ視線を集中させ、他の視座から人生を見つめることを忘れさせてしまう危うさも持ち合わせているのではないかと私はずっと心配している。
この世界に生まれたのなら、この世界で、この舞台装置で生きるしかない。
知っている高さの空を飛び、知っている深さの海を泳ぐしかない。
生活に満ちる人生のストーリーに飲み込まれそうになったとき、私は決まって、ますむら・ひろし先生の『コスモス楽園記』を手に取る。
■晴ればれと明るい様子で描かれる死の気配『コスモス楽園記』

『コスモス楽園記』/©ますむら ひろし/扶桑社
――物語はTV番組製作会社の若手スタッフ 藤田光介青年が、ロバスという謎の島に足を踏み入れるところから始まる。
南太平洋に位置するロバス島は1950年代に核実験と植物細胞実験が行われ、誰も近寄ることのなくなった無人島だ。
光介は人気番組『秘島探検シリーズ』の下調べのため、危険を顧みず単身で上陸したのだった。
絵になりそうなショットを探して歩き回る光介の眼前に、突然町が現れる。驚くべきは無人と思われていた島にコロニーが存在していたことだけではない。町には二足歩行し、なぜか日本語を話す猫たちが「普通に」暮らしていたのだ。
声をかけてきた猫「文太」に案内され、光介は奇妙な猫の町に留まることになる。
ますむら・ひろし先生といえば『アタゴオル』シリーズが有名だ。
これまた二足歩行の猫ヒデヨシが傍若無人な振る舞いで事件を起こしまくる物語である(1990年代後半、ヒデヨシが矢野顕子さんの音楽とともにハウス食品「シチューミクス」のCMに登場したことを覚えている人も多いと思う。懐かしすぎる)。
『コスモス楽園記』と『アタゴオル』シリーズは、両者とも二足歩行で日本語を話す猫が登場したり、連載時期も前後していたりと混同されやすいが、世界観は少し異なる。
『アタゴオル』が架空の森を舞台にしたファンタジー作品であるのに対し、『コスモス楽園記』は現実世界をベースにしている。
連載当時の時間軸に沿った新聞が登場したり、ロバスが無人島になった由来として化学実験の歴史が語られたりと、やけに生々しい。
なにより、死の気配が隠しきれずに漂っているのだ。
それも、晴ればれと明るい調子で。
猫はかわいい。光介と一番初めに出会い、その後相棒的存在になる「文太」はでっぷりと太って愛嬌があるし、その他の住人(住猫)とも比較的円滑にコミュニケーションを取ることができる。
にもかかわらず、あっけらかんとした不穏さが空気中にしれっと混ざっている。
猫たちは島の外に人間の世界が広がっていることを知っていて、意図的に自分たちの生活を守ろうとする。
文太は島に来たばかりの光介に「オキアミジュースおごっちゃる」なんてにこやかに言っておきながら、「一度上陸した人間が帰れるわけないよォ」とさらっとぶっちゃける。
光介のシャツを盗んで海に流し、死んだように見せかけて捜索隊が来ないように工作までする。
これ以上はネタバレになるので伏せるが、猫たちの出自についても物騒な設定がどんどん明らかにされていく。
これだけ書くと「まんまとストーリーの奥深くへ取り込まれているじゃないか、どうやってストーリーから開放されるんだ」と思われるかもしれないが、この漫画は各話の最後に必ず、概念がめちゃくちゃになるページが存在する。
■私は私のストーリーから逃れる方法を知らなかった

『コスモス楽園記』1巻 その3 「ムーンライト・キネマ」より/©ますむら ひろし/扶桑社
機械仕掛けのベッドで眠った光介の夢を、猫たちが映画のように上映し鑑賞するお話のラストシーンだ。
『コスモス楽園記』では総じて、一見平穏な(非日常の中の)日常から物語が始まる。
非日常の中の日常の中で、ちょっとした非日常が起こる。
生活と地続きの世界でイレギュラーな事件が起こり、光介や文太たちが手元の秘密を暴こうと視点を寄せていくと、最後の1ページで突然視座がぐんと上がり、世界のルールがやわらかく崩壊する。
作られたストーリーに引き込んでいくくせに、最後にその枠組みをぱっと瓦解させるのだ。ずるい。
以前ブラック企業で働いていたとき、朝まで資料を作り続け、とりあえずメールで提出して、全身から異臭を放ちながら風呂に入るためだけに帰宅し、ビシャビシャの髪もそのままにうっかりこの漫画を読み始めて号泣したことを覚えている。
私は私のストーリーから逃れる方法を知らなかった。
というか、ストーリーを無力化したり、放棄したり、再構築できるのだという発想がなかった。
明るいことばかりではない生活の、なんてことのない日常の話をしているように見せかけて、最後のページでほんのり丸みを帯びた地平線が見えるほど勢いよく浮遊する。
これまで従ってきたストーリーの「確からしさ」の脆さ、魂の身軽さ、残された不可解な余白の自由さを目の当たりにする。
それは「1から10までの範囲内で考え事をするように」と言われて一生懸命1、2、3…と数えているところへ、なんの前触れもなく京とか、垓とか、丈などの途方もない単位を並べて見せられたような心地だった。
■人生のストーリーはどんな見方をしてもいいのだ
漫画は全5巻。
最終話まで、結局猫たちが何なのかはわからない。
彼らの正体は中盤で明らかにされるが、善性を持つ者なのか、それとももっとプリミティブで曖昧な存在なのかはっきり理解できないまま、日常がまだまだ続いていくことを示唆しながら物語は終わる。
きっと島ではこれからも次々に不可思議なことが起きるのだろう。
そのたびに猫たちは「ああ、あれ? あれは〇〇に決まってるだろうよ」とこともなげに言う。
だが、どう考えても「こと」はありまくる。
使っている言語が同じだから意思疎通ができているように見えるけど、実は似た言葉遣いでまったく異なる話をしているのかもしれないという気さえする。だけどこれは1989年のロバス島に限らず、いつでもどこでも私たちの世界で起こっていることなのかもしれない。
非日常の中の日常が少しグラグラしながらも保たれている中、章の終わりごとにパラダイムシフトは起き続け、ストーリーをどこから見てもいいのだということを示し続ける。
最後の1ページを開き、私は今日も浮遊する。
Text/はらだ有彩
DRESSでは9月特集「今夜は、漫画を抱きしめて」と題して、漫画から素敵な影響を受けた人々が、作品の魅力を綴るコラムやインタビューをお届けしていきます。