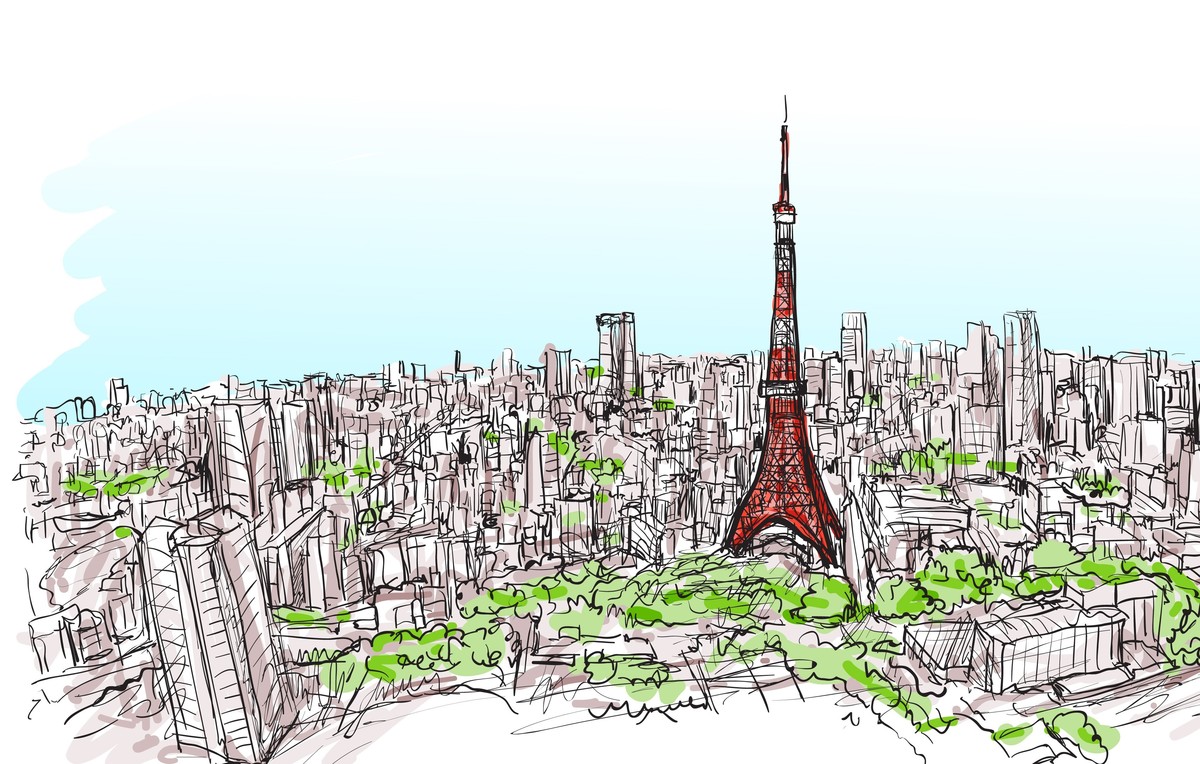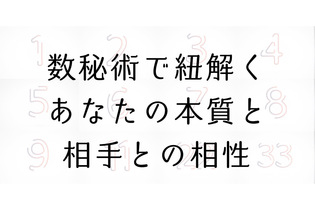無知は強みだし、行動が全て。東京はやりたいことをやって受け入れてくれる街
東京はあなたにとってどんな街ですか? 8月特集「東京の君へ」では、東京を舞台に活動を広げる”表現者”たちに、上京にまつわるエピソードをご紹介。もしもこの街でチャンスを掴みたいとき、私たちはどうすれば良いのでしょうか――。今回はそんな答えの見えない質問に、ヒントをくれるひとりの男性にお話しを伺いました。

カメラマンとして20 年以上も広告・雑誌・CM映像制作の第一線で活躍しながら、自らの作品も精力的に発表し続けている。一方、映画監督としても、『白河夜船』などの作品で高い評価を得る若木信吾さん。
若木さんは、独自のルートとストーリーを辿って上京します。「もともと東京に憧れはなかった」と語る彼は、なぜ、いかにして東京へとたどり着いたのか――。
クリエイター志望者はもちろん、東京で夢を叶えたい人も必読です。

■東京に憧れなんてなかった
――若木さんは静岡県・浜松市出身だそうですが、上京はいつ頃だったんですか?
――上京する年齢としては、決して早くはないですね。
選択肢が少ないなと思っていたときに同世代の間で留学ブームが始まったんです。浜松の書店にも留学ジャーナルみたいな雑誌が並ぶようになって。それを読み込んでいるうちに、『こんな選択肢もあるのか』と。正直、東京に憧れはありませんでした。高校時代、ブルース・ウェーバーの写真展を観に行くために上京したりしていたけれど、人が多いなぁ……という印象くらいしかなくて。
憧れていた写真家もリチャード・アヴェドンとか海外の人ばかりだったから、『アメリカの大学に行く!』という選択肢は、思いついた瞬間から揺るぎないものになりました」


若木さんはニューヨーク州ロチェスター工科大学写真学科で学び、’94年に卒業。卒業後も帰国する意思はなく、ニューヨークを拠点に活躍するトップカメラマンを夢見て、同大学同期の友達とともにマンハッタンで部屋を借りて共同生活を営みながら、バイトと営業に明け暮れる日々を送るようになったという。

■ニューヨークで無名でも、東京ではいきなりスター⁉
夢見る貧乏時代は数年続いたが、それでも、東京に帰るつもりはなかった。
それを見て営業してみようと思いついて、片っぱしから電話をかけて会いに行ったんです。自分の撮影した作品を1冊のブックにして、それを持って売り込みに回った。ニューヨークでは当たり前のやり方だけど、90年代の日本では珍しかったみたいで。多くの人が面白がってくれて、『一緒にご飯でも食べよう』と言ってくれたり、仕事をくれたりもしたんです」

ニューヨークではアジア人の無名カメラマンがどれだけ売り込みに回っても、滅多に仕事にありつけないどころか、まるで石ころのように扱われることも日常茶飯事だった。
当時の若木氏にとって、東京のクリエイティブ界隈の大人たちの対応は、まるで別世界の温かく大らかなものに感じられたという。
そのあたりから、東京でもカメラマンの仕事で呼ばれるようになったんです。やってみようと思った理由は、生きるため。東京で数カ月仕事をすれば、しばらくはニューヨークで生活できるお金も稼げましたから。それに、東京で仕事を始めたら、ニューヨークの雑誌から『日本人の目線で東京を撮ってきて欲しい』なんて依頼も来るようになって。そのとき、ほとんど初めて“東京”を撮る目線で眺めてみたんですけど、完全に外国人目線である自分に気づきました」

――外国人目線で東京を見ていた?
東京にはなじみが全くなかったからというのもありますし。当時の僕はニューヨークの写真やアートやファッションに心を持っていかれていたから、東京の人やカルチャーに違和感があった。何を見ても『エキゾチックトーキョー!』という感じ(笑)。
何を撮ったら面白い東京なのかよくわからなくて。知人に映画『トパーズ』(村上龍監督,高岡早紀主演)に出ていた、SMの女王様を紹介してもらって、SMの衣装で渋谷センター街に立ってもらって撮影したりしてましたね(笑)」
――それは、外国人観光客が喜びそうなノリですね(笑)。
同時期に最初のマネージャーとも出会い、東京でも事務所に入りました。それが渋谷の桜ヶ丘。出版社ロッキング・オンがある街でもあって。『ROCKIN'ON』にポートフォリオを持って行ったときに、『Beastie Boysが来日するんだよね』という話を聞いた。すごく好きだったから、『撮りたいです! 彼らはオレしか撮れないと思います!』って強気のプレゼンをして。
いきなり表紙を撮影させてもらったんですけど、それがいちばん最初の『ROCKIN'ON』の仕事になりました」

いきなり表紙撮影とは驚きだが、それも若木氏のセンスと実力と行動力のなせる技かと尋ねると、「運もあったと思う」と述懐する。
■無知は強みだし、行動が全て
日米を行き来して、3年近くが経過。
相変わらず、ニューヨークでは月に1~2本の撮影の仕事も、東京に来れば引く手数多の売れっ子カメラマンに。
“ニューヨークからやってきた、ちょっと生意気な若手カメラマン”は各所で話題を呼び、雑誌の表紙やモード誌のファッション撮影、SMAPをはじめとする日本のトップアーティストのCDジャケット、一流企業の広告撮影など、大きな仕事が次々に舞い込むようになった。

トントン拍子で売れっ子カメラマンになってから、東京から引き寄せられるように上京。さぞや、初めから充実した楽しい東京ライフだろうと思いきや、「ニューヨーク在住のときみたいに貧乏はしなかったけど、うまくいかない部分とか葛藤はありましたよ」と若木さん。
僕は僕でオールドスタイルのニューヨークを引っ張ってきているから、全然感覚が合わない。たとえば、当時の東京では、猫も杓子も白い壁をバックに人物を撮影しろと言われた。平面に撮るっていう、いわば、浮世絵スタイル。同時代のニューヨークでは、奥行きのある設定や場所を選んで撮る、3Dスタイルが主流だった。
当時は人一倍、オレオレな若者だったから反発心も強くて。こちらは、VOGUEとかIDとか世界のモード誌のイメージを描いて撮っているのに、雑誌のデザインでまったく別物になってショックを受けるなんて日常茶飯事。今思えば、日本の雑誌にはそれぞれのカラーや役割があるし、東京は東京のスタイルでやったほうが良いことも理解できるんですけど、当時は受け入れられなかったです」

当時の若木さんは、若きクリエイターの中でも突出して尖っていた。反抗心をむき出しにして、数多く撮影した写真の中からベストなものを選ぶ広告の仕事ですらも「1枚しか撮らない」など自分のスタイルを貫き通した。
――なるほど。

あれから、約20年。
その間、ずっと写真家・映画監督として東京の最前線で活躍しながら、プライベートでは、結婚して子どもも生まれた。東京は若木さんにとって仕事をするだけ場所から、生きる場所にもなった。
――20年近く暮らして、東京に対する見方や想いは変わりましたか?
孤立しているからこそ、いろんなことを柔軟にやれる街だし、可能性も広がる。それこそ、ニューヨークではファッションはファッション、ポートレートはポートレートとカメラマンでも住みわけがくっきりできていて。各分野の層も厚いし、レベルも高いから、入り込みづらいし、上のレベルに上がりにくいんです。でも、東京ではもっと何でもありというか、意思と行動力さえあれば、自由にジャンルを超えて撮りたいものが撮れる。
クリエイターはもちろん、セルフプロデュース次第でやりたいことをやって受け入れてもらえる場所だなと。今は東京のブランド力も高まっているし、SNSで個人でも世界にも発信でできるから、より可能性は広がったんじゃないかなぁ」

――この街で若き日の若木さんのようにチャンスを掴むにはどうしたらいいでしょう?
普通は失敗したくないから、先にその場のルールやマニュアルを学ぼうとするけれど。そうすると、二の足を踏んでしまうこともあるし、個性が失われることもあると思うんです。無知は強みだし、行動が全て。僕が東京で最初から自由に挑戦できたのは、ニューヨークでも行動し続けて、図々しさを手に入れたからだと思いますし。それから、『どうせ失敗するよ』と人から止められることほどやったほうが良いと思います」
――と言いますと?
今年は、カメラマンなのに、絵本を作ったりしているんですけど、それも反対されたことですから。つまり、人の評価よりも、自分の好きなことやりたいことを信じるということ。それを行動に移すことが、生きる上での変わらない基本かなと思います」

取材・Text/芳麗
Photo/池田博美
DRESSでは8月特集「東京の君へ」と題して、夢や希望を持って上京し、東京で活躍する「表現者」たちの“東京物語”をお届けしていきます。