生きる意味を見失った街で手にした、光。人気脚本家はいかに挫折を乗り越えたのか
夢や希望に満ち溢れる街、東京。しかし、光があれば陰があるように、この街で“挫折”を味わう人も少なくない。脚本家として第一線で活躍し続ける橋部敦子さんも、挫折感に打ちひしがれる日々を送ったひとり。観る者の心を揺さぶるドラマを生み出しながらも、人知れず苦悩した日々。何度転んでも立ち上がってきた橋部さんの東京物語とは。

幼い頃の私は、コンプレックスばかりを抱えていました。自分に自信が持てない、言いたいことをうまく伝えられない……。そんなもどかしさを抱えながら、周囲の顔色を窺い、同調し、流されるままに生きていました。
地元である名古屋からの上京を決意したのも、そんな自分を変えたいという一心からでした。東京に出てきたのは、18歳の頃。短大進学という名目で、新しい環境に飛び込んだのです。
そこで出合ったのが、「ダンス」でした。
当時、東京でダンサーをしている叔母がいたこともあって、たまたまそのレッスンに参加することになったのです。もともと体を動かすことは好きでしたし、ダンスも運動のひとつとして捉えていたのですが、実際に踊ってみると全然違いました。
ダンスは、全身を使う表現方法。それに気づいた私は、あっという間にダンスの世界にのめり込んでいったのです。
けれど、20歳の頃、一度地元に帰ることになりました。短大を卒業したら地元で就職をする、と両親に約束をしていたからです。それでも私はダンサーになるために、3年経ったら必ず東京に戻ってこようと思っていました。

橋部敦子さん
愛知県名古屋市出身。1993年、第6回フジテレビヤングシナリオ大賞にて佳作を受賞。1996年、『SMAPのがんばりましょう「NAKED BANANAS」』にて脚本家デビュー。主な代表作に『僕の生きる道』『僕と彼女と彼女の生きる道』『僕の歩く道』など。10月より、新作オリジナルドラマ『僕らは奇跡でできている』が放送予定。
地元に帰った私は、野村證券に就職しました。当時は景気も良くて、新入社員でも驚くようなボーナスをもらえる時代。両親も喜んでいました。けれど、心の中にあった「ダンサーになる」という決意が揺らぐことはありませんでした。
その結果、私は両親にも相談せず、2年半で退職することに。もちろん、両親は大激怒です。その上、ダンサーという夢を理解してもらえるはずもなく、「東京に行くなら、二度と戻ってくるな」と勘当されてしまいました。それでも、夢を捨てることはできなかった。
それまで、世間がよしとするレールに乗って生きてきた私にとって、ダンスというのは初めて見つかったやりたいこと。やらずに後悔するくらいならば、どうなったって構わないから突き進んでみようと思っていたのです。
■やっと見つけた夢が打ち砕かれた瞬間
なにもかもを捨てて2度目の上京をしたのが、23歳の頃。池尻大橋にある風呂なしのアパートを借りて、新たなスタートを切りました。
お金はなかったものの、アルバイトをしながらダンスのレッスンに没頭する日々は、非常に充実していたことを覚えています。
そんな生活を2年ほど続けるうちに、地方のショーレストランや都内のキャバクラのショータイムなどにダンサーとして呼ばれるようになりました。少しずつ夢に近づけている――そんな実感を持てるようになったある日のことでした。
いつものレッスン中に、膝に激痛が走ったのです。病院でレントゲンを撮ってみると、どうやら膝の骨がすり減っているとのこと。医師からは「まるで老人の膝のよう。このまま踊り続けるのは無理です」と宣告されました。
もう踊ることができない。その事実は、私をひどく打ちのめしました。実家に戻るわけにもいかず、かといって東京での目的も失ってしまった。私は、ただただ絶望感に包まれていました。
もはや生きる意味すら見失ってしまった。これからどうしよう。そんな風に思っていたとき、身近な人が小劇団を立ち上げることになり、参加することにしました。
正直、歌や演技がしたかったわけではないのですが、何もすることがなかった私は、とにかく目の前のことにすがりつくことにしたのです。
■運命を変えた、シナリオコンクール受賞

脚本と出合ったのは、その劇団に入ってからのことでした。舞台を公演することになり、私が脚本を書くことになったのです。けれど、それまで脚本の勉強をしてこなかった人間に、ちゃんとしたものが書けるはずありません。
そこで私は、どうせやるならば勉強しようと思いたち、表参道にある「シナリオ・センター」の門を叩いたのです。
何も知らない状態で飛び込んだ、脚本の世界。それはとても魅力的なものでした。脚本ならば、自分を表現できるかもしれない。25歳でダンスに代わる新しい夢を見つけた私は、あっという間に“書くこと”にのめり込んでいきました。
そして、シナリオ・センターに通い始め、半年が過ぎる頃、いつものように教室に行くと、他の生徒さんが誰も来ていなかったのです。講師に理由を訊いてみると、「みんな、『フジテレビヤングシナリオ大賞』への応募作を書くために休んでいるんだよ」と。
そんなコンクールの存在も知らなかった私は、「なんですか、それ」といろいろ尋ね、応募することを決意しました。ただし、その〆切は2週間後。とてもじゃないけど、時間がありません。
それでも私は勢いだけを頼りに書き上げ、なんとか〆切に間に合わせることができました。それが、佳作に入選し、私の脚本家への道が開かれることになったのです。
受賞の連絡を受けた日のことは、いまだに忘れられません。その頃、脚本家になりたいとは思っていたものの、生活が苦しく、そろそろ頭を下げて実家に戻ろうと考えていたのです。いよいよ大家さんに退去の連絡をしようと思っていた日のことでした。
アルバイトから帰ってみると、留守電が入っていたのです。メッセージを再生してみると、まさかのフジテレビから。それで折り返したところ、私の作品が佳作に選ばれたと告げられたのです。
賞金は50万円。当時、10万円あれば1カ月は生活できましたから、これで5カ月は生き延びられると(笑)。新たに東京にいる意味もできたので、私はそのまま東京でやっていこうと決意し直しました。
■決して平坦ではない、光を手にするまでの道のり

けれど、コンクールで受賞したからといって、すぐにプロになれるわけではありません。デビューに向けて企画を出しても、うんともすんとも言われず……。
コンクールで私の作品を推してくださったプロデューサーの計らいもあり、プロの脚本家の打ち合わせに参加しながら勉強するという日々が続きました。
その頃、よく通っていたのが池尻大橋にある銭湯「文化浴泉」です。風呂なしのアパートに住んでいたこともあって、毎日のように通っては、湯船に浸かりながらボーッとするのがリフレッシュになっていました。
でもあるとき、考え事が多すぎて、ぼんやりしながらずっとシャワーを浴びていたら、横にいた人に怒られちゃって。「お湯がもったいないでしょ!」って(笑)。あの頃、すごく疲れていたのだと思います。
そんな日々が2年ほど続き、ようやくチャンスが巡ってきました。深夜ドラマの脚本を担当することになったのです。それが『SMAPのがんばりましょう「NAKED BANANAS」』という作品。
わずか5分半の12回連続モノという特殊な深夜ドラマでしたが、これが私のデビュー作になりました。放送は毎回チェックしていましたし、なにより、スタッフロールに私の名前が表示されていることが嬉しかった。「脚本家になれたんだな……」とすごく感動したことを覚えています。
とはいえ、その後も脚本家として生計が立てられるようになるまでは時間がかかりました。本当に脚本のお仕事だけで食べていけるようになったのは、30歳の頃。97年に放送された『月の輝く夜だから』で、初めてひとりで連ドラを任されることになったのです。
けれど、その間には何度も悔しい想いをすることがありました。プロデューサーから、「脚本家に向いていないよ」と言われたこともあります。96年には、大先輩である野沢尚さんが6話まで書かれた『おいしい関係』の7話以降を書かせていただきました。
書き終えた後、監督から「野沢さんとの決定的な違いは、脚本に色気があるかどうかだよ」と厳しくも温かい言葉をいただいたことも。そのときは、色気って何なのか、まったく意味がわかりませんでしたが、ずっとその言葉が心に残っていました。
そして、03年放送の『僕の生きる道』で、自分なりの答えが見つかりました。色気とは、“世界観”があるかどうかなのではないか。この作品を書いたときに、初めて自分の世界観に出合えた感覚がありました。
ちょうど、自分の代わりなんていくらでもいるという危機感を持っていた頃だったので、前に進めた感じがして、とても嬉しかったです。
■“挫折”は、ただの通過点でしかない
東京という街は、自分を活かしきることができる、素敵な場所だと思っています。そう思えるようになったのは、未知の世界にも臆することなく飛び込んできたからかな……。私はあまり深く考えずに行動するタイプなのですが、それが良かったのかもしれないと思います。
脚本を書くことにハマったときも、10年もあればプロになれるだろうと楽観視していました。でも、そこで「いや、簡単になれるものではないでしょう」と考え込んでしまっていたら、きっと二の足を踏んでいたと思うのです。
もちろん、途中途中で、何度も挫折感を味わいました。大好きなダンスが踊れなくなったことも、プロデューサーから「脚本家に向いていない」と言われたことも、当時の私からすれば非常にショックな出来事。でも、そういった挫折は“通過点”でしかないと思うのです。
そして、必要な出来事だったとも言えます。踊れなくなったから脚本家になろうと思ったし、「向いていない」と言われたから、それでもなりたいと強く思う自分自身を確認できたのです。
実は、目の前の最悪な出来事には、望む未来につながる光が隠れているのかもしれない。そんなふうに見てみてはどうでしょうか。
Text/五十嵐 大
Photo/タカハシアキラ
DRESSでは8月特集「東京の君へ」と題して、夢や希望を持って上京し、東京で活躍する「表現者」たちの“東京物語”をお届けしていきます。

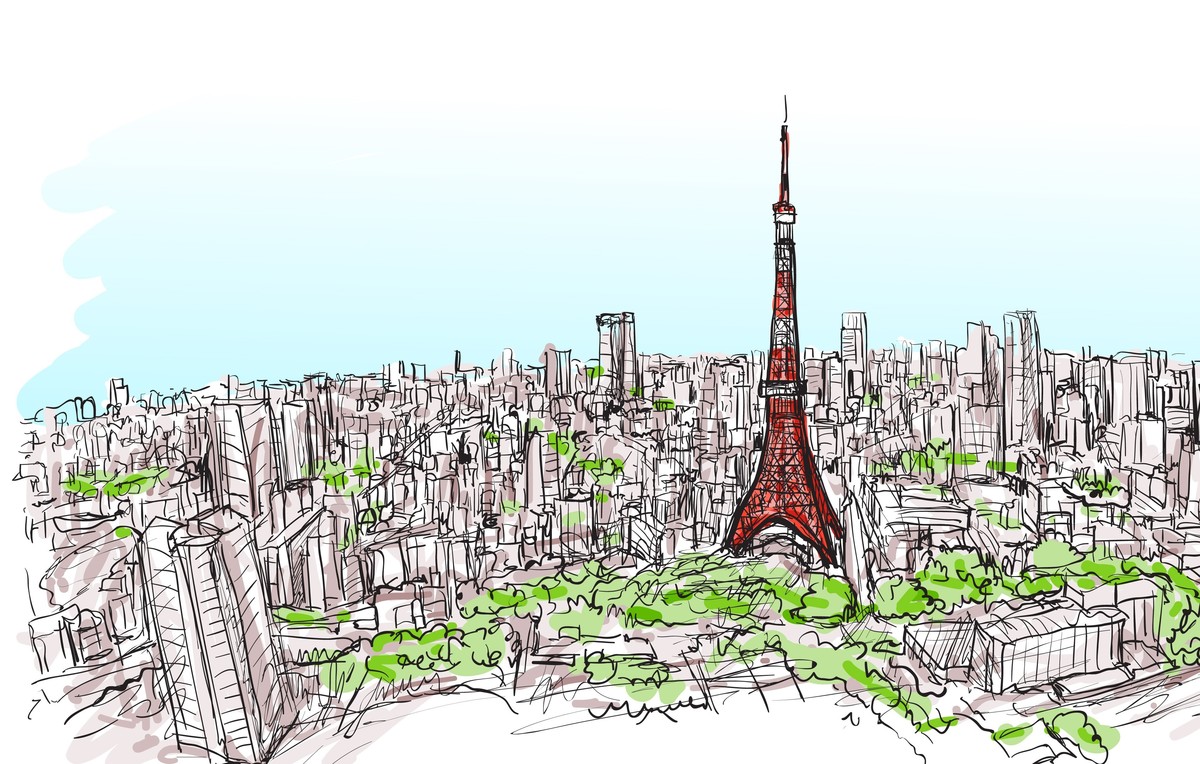









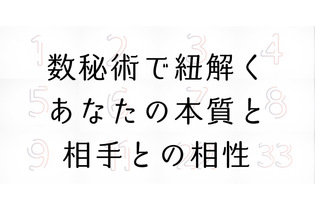










いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。