ぜんぶポルノグラフィティのせいだ 【偏屈女のやっかいな日々】
作品やパフォーマンスに触れて、そのアーティストを好きになることがある。大好き過ぎて、その人たちのことならいくらでも語ることができるようになる。周りから見れば、暑苦しいかもしれない。けど、きっとそういう出会いが、人生を死ぬほど楽しくしてくれる。生湯葉シホさんのそんな出会いは、中学一年の春、地元のイオンで生まれました。

SEが途切れ、客電が消えると、観客は一斉に立ち上がる。
前列の人たちが始めた手拍子が、水紋のように会場中に広がっていく。
ステージを覆う幕が落ち、悲鳴に近い歓声が上がる。
1万4千人が見つめる先で、赤いライトに照らされたボーカルが歌い出す。
あの日の1曲目の最初のフレーズは、「情熱は変わんないぜ」だった。ボーカルの声はライブから13年が経ったいまでも、驚くほど鮮明に耳の奥に焼きついている。
■“お茶の間”的ロックバンド、ポルノグラフィティ
ポルノグラフィティというバンドを追いかけ始めて14年になる。
と人に言うと、たいてい「ポルノ? 昔よく聞いてたよ」と言われる。「アゲハ蝶とか中学のときめちゃめちゃ聞いたなあ、懐かしいなー」と言われるケースも多い(こちらはいまだにアゲハ蝶を週4くらいでめちゃめちゃ聞いているので、ノスタルジーに寄り添えず申し訳ないなと思う)。
2人組なのでデュオとかユニットと呼ばれることも多いのだけれど、ポルノグラフィティはロックバンドだ。
彼らはベーシストがメンバーにいた3人体制の時代(1999~2004年)に、誰もが知るようなヒットソングを連発している。
しかし、その楽曲の飛び抜けたキャッチーさや、看板となるようなシングル曲の作曲をメンバーではなくプロデューサーが行うという初期の制作スタイルのせいもあり、世間からも音楽業界からも、なかなか“ロックバンド”として評価されてこなかった。
メンバー本人たちのキャラクターもそうだけれど、よくも悪くも“お茶の間”的なアーティストなのだ。
しかし2008年ごろからはシングル曲の作曲もメンバーが行うという方向に舵を切り始め、いまではすべての曲の作詞作曲をボーカルの岡野昭仁とギターの新藤晴一が行っている。
ポルノがすごいのは、ラテン、ロック、ポップス、ファンクといった当初からの音楽ジャンルの幅が、作曲者がふたりになっても決して狭まらなかったことだ。
デビュー当初はコンポーザー(作曲者)が多かったことで担保できていた楽曲の多様さを、彼らはいつしかたったふたりで完璧に自分たちのものにしてしまった。
進化し続けるポルノというバンドは間違いなくいまがいちばん面白くて……みたいな話は、このまま続けると3万字くらいになってしまうのでそろそろ切り上げる(もしこれを読んでポルノに興味が湧いた方がいたら、アルバムを年代別にぜんぶ貸すのでTwitter宛てにDMください)。
今回はポルノというバンドの魅力は一旦横に置いておいて、私がこのバンドを好きになったことで、人生のあらゆることが変わってしまった話をしたい。
■好きという気持ちが冷めてしまうことがなによりも怖い
「彼らが好きだ」と気づいたのは、中学1年生の春、地元のイオンの中の新星堂で流れていたライブDVDを見たときだった。
2005年前後、2枚組のベストアルバムが大ヒットし、テレビCMなどにも出演していたポルノにはちょっとしたブームがきていた。
CDショップに行けばどこかしらに特集コーナーができており、ライブ映像や過去のシングルのPVが流れているというのもざらだった。
学校のない土曜日、幼なじみとなんの気なしに新星堂に入ったときも、やはりそこにはポルノのコーナーがあり、サウダージのライブ映像が流れていた。
幼なじみがそのモニターの前で立ち止まり、「やっぱ昭仁のほうがカッコいいよね」と何度もボーカルの名前を呼ぶので(当時、昭仁はアイドルのような人気があった)、ひねくれている私は「ギターのほうがカッコいいじゃん」と反論して言い合いになった記憶がある。
意地になってギタリストのほうをじっと見ていたら、いつの間にか本当に彼のことがカッコよく思えてきてしまってドキッとした。
「あれ?」と思いボーカルに目を移したら、彼もやはりカッコよかった。そこで初めて、私は演奏する彼らの姿がすごく好きだということに気づいた。
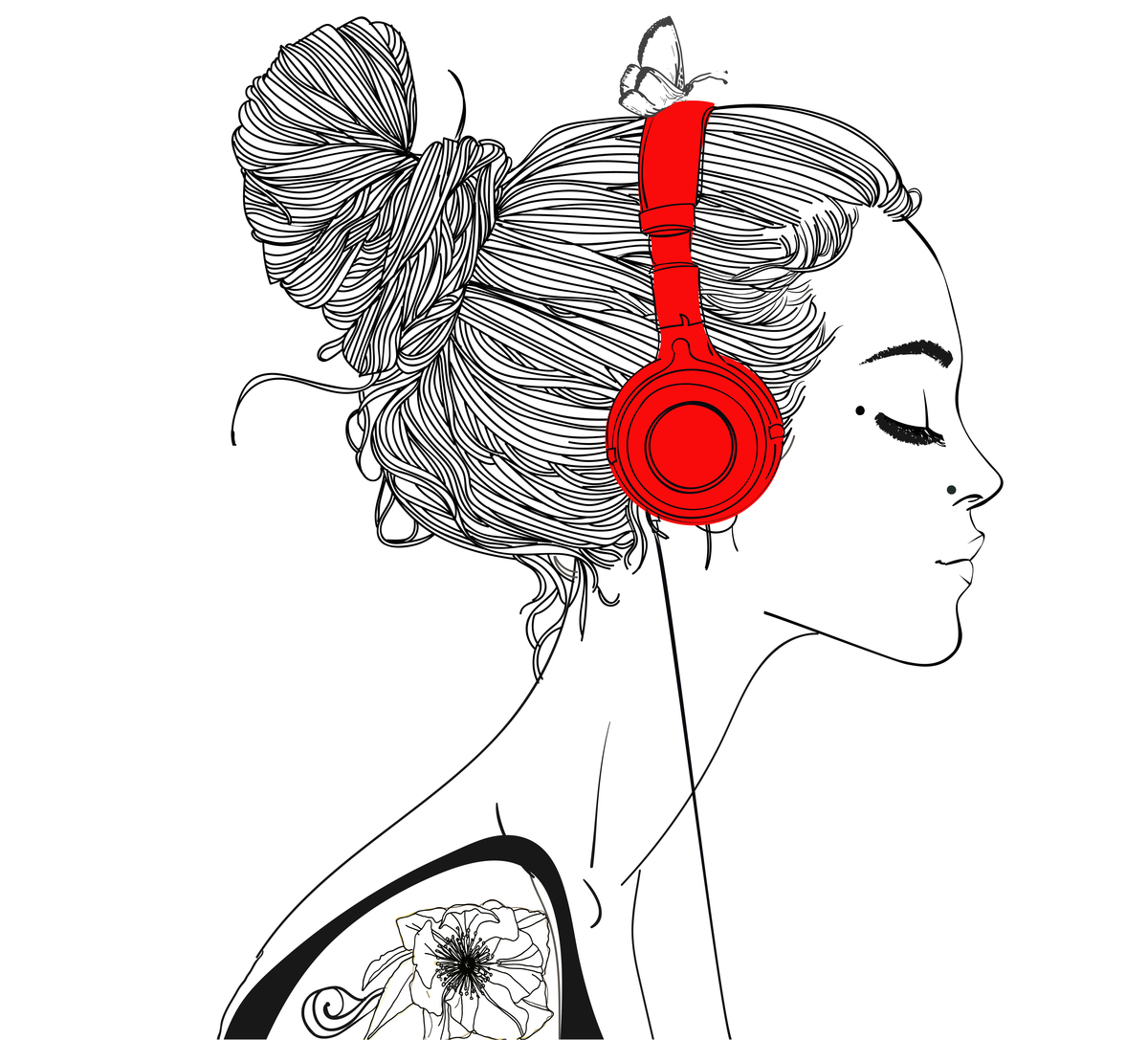
あれよあれよという間にファンになり、CDを買うようになった。ファンクラブにも入り、冬には初めての日本武道館のライブにも行った。
そのころにはもう、生活のすべてがポルノグラフィティ一色なのだった。通学時も授業中もiPodでポルノを聞き、歌詞を下敷きにびっしり書き込み、月曜日の夜にはギタリストのラジオを聞く。冗談でもなんでもなく、「サーモグラフィー」という言葉ですら「ポルノグラフィティ」に聞こえた。
中学では友達が少なかった。というより、ざっくり言うといじめられていたのだけれど、授業中に頭の上から消しゴムのカスが降ってきたり、移動教室で決まって自分の椅子だけなかったりしても、ポルノを聞いていれば平気だった。
当時、文章を書き始めたばかりの私は、なにを思ったのか1冊のノートの左ページにポルノの歌詞を、右ページに自分の詩を書くという気味の悪いルールを決めていた。
ポルノの歌詞は、情緒的で美しい。ノートが文字で埋まっていくにつれ、自分の書くものとポルノの歌詞の出来のあまりの差に落ち込むようになり、歌詞サイトに載っているJ-popの歌詞をあいうえお順に1日1組ずつ書き写すという妙なことをするようにもなった。
ポルノのことが好きすぎて、常になにかをしていないと、好きだというエネルギーが体のキャパシティを超えて突然叫び出したりしてしまいそうだった。そんな気持ちになったのは人生で初めてのことだったので、毎日戸惑い、泣き、信じられないくらい長い時間眠った。
当時の日記には、「この好きという気持ちがいつか冷めてしまうことがなによりも怖い」と書いてある。
このときの怖さはさすがにもう覚えていないけれど、たぶん本心だったと思う。
■私の何パーセントかは、いまでもあの日の横浜スタジアムにいる
そのまま順調にポルノグラフィティオタクとして成長した私は、ボーカルとギタリストの結婚という打撃(ショックすぎて期末テストを白紙で出した)も乗り越え、大学生になった。
4年生の夏になんとなく就活をし始めたとき、同級生たちの大半はもう就職先を決めていた。私はなんの方針も目標もなく、就活エージェントに登録して薦められた2社だけにエントリーをしていた。
同じころ、横浜スタジアムでポルノグラフィティの15周年を祝う2日間のライブがあった。
スタジアムの3万人の観客の中で見るふたりはいつもより小さく、しかしいつもと同じように輝いていた。ライブの終盤、観客が声を合わせて「15周年おめでとう!」と叫ぶと、ボーカルが、それよりも大きいんじゃないかと錯覚するような声で「これからもよろしく!!」と叫び返した。
その瞬間、不意に、ここは自分のホームだという感覚がせり上がってきて泣いてしまった。帰属意識や仲間意識がもともと薄く、なにかに所属するのがどうしても好きになれない自分が、ひとつのバンドを愛し応援し続けてきた人たちの中にいると“ホーム”を感じるというのは新しい発見だった。
その日の帰り、就職なんてちっともしたがっていない自分に気づき、「いつか物書きになりたい、それまでの道のりはなんでもいいや」と考えた。そして、すぐに就活をやめてしまった。
私はいまでもあの日、2014年9月の横浜スタジアムをときどき夢に見る。私は確実に、自分の心と体のうちの何パーセントかを、あの日の横浜スタジアムに残したまま今日を生きている。
■ひとつのバンドを10年以上愛し続けて気づいたこと
ポルノグラフィティにまつわるエピソードを書こうとすると、あまりも数が多すぎて書ききれないことばかりだ。私の進路や大きな決断にまつわるほとんどすべてが、ポルノグラフィティのせいなのだ。
でももうひとつだけ、自分のこれまでの中でポルノに関わるとても大きな出来事があったとしたら、それは今年の春にした結婚だった。
正直に言うと、私は人生で一度も結婚したいと思ったことがなかったし、自分が結婚なんてできるわけない、という気がずっとしていた。
過去に付き合っていた人と別れた理由はきまってこちら側の情がなくなってしまうからで、一度冷めてしまえば相手のことを名前ごと忘れてしまえるような自分はあまりに薄情だと思っていた。
だから、好きな人と今年初めて一緒に暮らし始めたときも、はじめはすこし不安だった。
突然、ふっと夢から覚めるように、好きという気持ちがなくなってしまったらどうしよう──。
そんな気持ちを打ち消したのは、「いや、だって私ポルノのこと14年も好きじゃん」という自負だった。
ひとつのバンドを10年以上も愛し続けることは、(こちらが勝手にやっていることとは言え)簡単なことではなかった。メンバーが結婚しても、ダサい上に高いライブグッズが出ても、この曲はちょっとと思う曲がリリースされても、そのたびに「やっぱり好きだ」という気持ちを確認し、手放さないという勇気が必要だった。
愛の手入れのような作業を繰り返しているうちにいつしか、私にとってのポルノグラフィティは生活になり、自分の一部になった。だからたぶん、いま好きな人のこともそうやって愛していけばいいのだと気づいたとき、私は初めて結婚してみようと思えた。
■ホームがたったひとつでもあれば、人生は楽しくなる
あの日、イオンの新星堂で流れていたライブ映像がもしも他のアーティストだったら、私はいまごろポルノグラフィティじゃない別のバンドを熱烈に応援していたのかもしれない、と思うことがある。
おそらく私は先天的なオタク気質なので、なんらかのきっかけさえあれば、いまは見向きもしていない別のアーティストを追いかけて北海道から沖縄まで駆けずり回っていた可能性は大きい。
けれど、「ポルノ」と胸にでかでかと印刷されたダサいライブTシャツを着込み、スタジアムの座席から身を乗り出すようにして音楽を浴びている瞬間だけは、いまこの時間にここ以外の場所にいる人生なんて絶対にありえなかったのだ、と思う。
バンドに限らず、人でも趣味でもなんでもいいのかもしれないけれど、「ここが私のホームだ」と思えるような場所がひとつでもあれば、それだけで人生は死ぬほど楽しい。
いま私は今年の秋に広島で開催されるライブに向けて、急いで現地のホテルを探しているところだ。










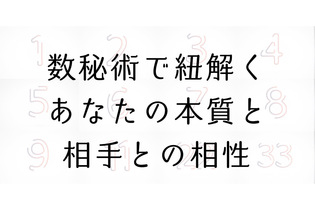










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。